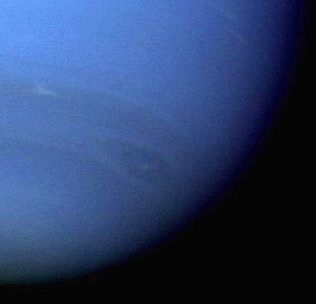小さいときからSFが大好きで、そればかり読んでいました.
大きくなったら哲学書ばかり読んでいます.
SF好きは哲学が好き.
SFもスターウォーズより、マトリックスが好きです.
ソウルメイト(中編 2014-06-30)
ラット・オン ー 不履行 ー(中編2013-11-07)
一太郎からの手紙(短編2012-07-09)
深夜勤務 (短編 2011-05-09)
恋する青年と娘の会話(戯曲 2011-4-20)
KIRAMEKU-SORA(短編 2009-9-19)
デパートにて(短編 2009-8-24)
下宿(短編 2009-8-18)
夏の夜(短編 2009-7-25)
ディープパープル(短編)
最終戦争(超短編)
過去への旅(超短編)
溶ける男(短編、未発表)
昭和一代女(短編、未発表)
仮想手術(短編、未発表)
時間が止まった日(短編,未発表)
知能強化装置(中編,発表,推薦賞)
親友(短編,未発表)
やさしい気持ち(短編,発表,推薦賞)
野獣の国(短編,未発表)
|
外の景色がまわってみえる.真っ白い切り立った山が、真っ黒な空が順番に現れる.コントロールを失って、車はスピンをはじめた.目の前にガードレールが迫る.その先はなにもない.そして、車はガードレールを突き破って、20m下の海へとダイブした. すべてがスローモーションのようにゆっくり動き始めた.もっと運転に気をつければ良かったとか、もしかしたら下に落ちても死なないかもと思った.外は夜だから暗いはずなのになんだか明るいのは雪明かりのせいかもしれない. ** Jとは僕がちょうど高校卒業直後から付き合い始めた。Jは色白で身長は平均より少しだけ高かった.髪の毛は茶色だったが、柔らかくまとまらないせいか、いつも後ろに三つ編みにしていた.学生時代の気分が抜けきれず服装は地味だった.太っているのを気にして、ゆったりしたジーンズとTシャツを身につけていることが多かった.近視が強くて銀縁のめがねをかけていたが、後になってコンタクトに変えたら雰囲気が都会的になった. そのころ、僕はまだ就職先が決まらなくて、小中学生に相手の学習塾を手伝っていた。その塾は、G町の中央にあった.経営者がやり手との噂でここ以外にも、市内に5つの塾を経営していた. 「待った?」 「いいえ、そんなに待たなかったわ。」 僕は塾に向かう途中で、Jと待ち合わせをした。たいてい夕方の5時頃である.その場所は、徐々に市街地化が進んでいる新興住宅地である.まだ家の建っていない更地と、青々と茂る田畑がまだらになっている.Jのアパートが近くのため、ここを選んだのだった.夕方は帰宅する学生と会社員で人通りが多い.そんな所では落ち着かないから、僕たちは少し離れたあぜ道に移動した. 「ごめん、出がけに電話がかかってきたから。」と僕.本当は忘れ物をして引き返したのに、Jに嫌われたくなくて、つまらない嘘をついてしまった。 「はい、これ。夕食まだなんでしょ?」渡された袋の中には、お菓子が2つ入っていると言う。お菓子2つにしては大きな袋のように思った。Jの顔を見ると、笑ってこちらを見ている。 「一緒に食べましょう。」そう言われた。 目の前には青々と茂った稲穂が風に吹かれてざわざわしている。夕日が徐々に低くなり、蒸し暑さも少し和らいだように思えた。Jがくれたのは、かき氷だった。中心に少しだけクリームがのっかている.しかし時間が経っていたので、溶けかけていた。何となく気まずくて、黙って食べているのは悪いかなと思ったけれど、何も思いつかないから、やっぱり黙っていた.。 別れ際に、「塾の仕事が終わったら、また逢えるかな?」と聞いた。 Jは明るく「うん。」と返してくれた。 返事を聞いた後で、塾でくたくたに疲れていることを考えたら、ちょっとだけ後悔した。それでもJのうれしそうな顔を見たら、やめたとは言えなくなってしまった。 「じゃあ、あとで。」と僕が言う. Jが見送る中、バイクに乗って塾へ向かった。Jと話したら、これから塾で起こりそうな嫌なことは忘れてしまった。 塾の前には既に多くの小中学生が集まっていた。正面に大きなガラスのドアがあり、僕は鍵を使って開けた.かなり古びた感じのドアは開閉のたびにキイキイ音がする.一斉に、生徒たちが決められた部屋へと移動する.僕が仕事する部屋は入り口から2番目で、今夜は中学2年生の数学を担当することになっている.講義が始まるまで少し時間があったので、僕は仲間はずれの子供のように、部屋の隅で生徒の様子をぼんやりと眺めていた。子供っていうのは、なぜこんなに元気で、つまらないことで笑えるのか不思議な気がした。しばらくしたら塾の講師が現れ、一気に部屋の中は静かに張り詰めた空気に満たされた。 講師は30代の長身のやせた男だ.神経質そうな顔は周りの生徒たちに余裕を与えなかった.講義が始まった.僕はプリントを配ったり、黒板を消したり、講師のサポートをする. 「先週の続きは、えー、M君だったかな?」 一番前の席に座っていた生徒が青白い顔をしてうつむいた。どうやら準備をしていなかったようだ。 講師は顔をしかめると、威圧するような声で言った.「この問題を解いてみなさい。」 Mはやっぱりうつむいたまま返事をしない。 「どうしたんだ。今週は君から始まることを知っているだろ?しかたがないな.それでは隣の君がかわりに解きなさい.」 急に名前を呼ばれた生徒ははちょっと驚いた顔をしたが、すぐに前に進むと、すらすらと問題を解き始めた。うつむいていたMはようやく顔を上げたが、少しだけ泣き顔に見えた。 後で聞いた話では、昨日、他の生徒とけんかをして、予習をするのを忘れてしまったらしい。けんかで興奮して、勉強どころじゃなかったのだろう。けんかの相手はS町の運送会社の社長の息子である.社長の息子といっても小さな会社だからそれほど裕福な家庭ではない.むしろ大会社に勤めるサラリーマンの子供の方が身なりは立派で贅沢である.言葉遣いも上品ではなく、口癖の「俺」を連発している.しかし、口が上手で、活発な性格は人気がある.そいつはけんかをしたことさえも忘れているかのようにけろりとして、教室にいた。 Mは普段から大人しくて、僕は一緒に他の生徒たちを騒いでいる所を見たことがなかった。父親は近所で土建業を経営している。川のそばにある大きな家がMの住まいである。家の前には、玄関が見えないくらいの砂山があり、数台のダンプカーやブルドーザーがその横に並んでいる。長男だから、たぶん跡継ぎを期待されているのであろう。よく母親が講義の様子を見に来る。塾に通っているのに成績が上がらないからだ.母親の様子からは会社の羽振りが良いのがわかる.ブランドのバッグを持ち、派手な白と黒のワンピースを着ていた。化粧も上手で、歳よりも若く見えた。講師室で講師と深刻な様子で話していルのを聞いた限りでは、口調は優しく上品だった。 「ええ、学校から帰ったら、私がいくら言っても漫画を見たりゲームばかりしています.宿題は寝る間際までしないです。」 「勉強の習慣がついていないようです。勉強をしない頭がいい子より、勉強の習慣がある子の方が成績は良いですよ。つまり、ウサギとカメのたとえ話と同じです.今の成績では希望される高校は難しいと思います.」僕の前ではしかめっ面の気むずかしい講師は、親の前では明敏で饒舌だった. 希望校に進学は無理だと聞いて母親はすっかり元気を無くしてしまい、その日は息子と話すこともなく帰っていった。息子のほうは母親の姿に気がついていたので、当然声をかけてくれると思っていたから、すっかり落胆してしまった。 壁の時計を見ると午後8時になろうとしていた.ようやく今日の仕事も終わると思い、僕はうっかりあくびをしてしまった.熱弁をふるっている講師には気づかれなかったようだ.窓の外には住宅地の中に残る水田が広がっていた.蛙の鳴き声が以外に大きいのに気がつく。「きょうはここまで.」講師が言うと、子供たちは帰り支度を始め、一気に教室は賑やかになった。僕の仕事は続く.小さなモップで教室の掃除をした.黒板もぞうきんできれいにした.すべてが終わると、講師室に顔を出した.あのしかめっ面の講師は机の上のパソコンをにらみながら生徒の成績を分析していた. 「お先に失礼します.」僕が挨拶をすると、講師は疲れた様子で「ああ.」と返事をしたが、パソコンのモニターから目を離さなかった.しかし、何かを思い出したらしい.急に頭を上げると、 「そうだ.明日のプリント準備は君がやってくれ.私にはまだ仕事があるからね.」 「はい、もちろんです.」と僕は答えた. 「無謀な運転が父兄たちに目撃されると、この塾の評判にも影響するからねえ.とにかく気をつけることに越したことはない.どこでだれが見ているかしれないからね.」 銀縁のめがねの奥から、神経質そうな眼が動く.神経質な人は目が落ち着かないのだ.常に細かく動いて相手を観察しようとする.相手から視線を外すことをおそれるのだ.勉強の虫め.この塾で自分のコピーを作ろうとしている.ミスをするなと常に注意されれば、だれだって神経質になるか反抗的になる.僕はこいつの常に逆をやってやろうと考えた.だから車の間をすり抜けることもあるし、スピードを出すこともある.そうじゃなきゃ、バイクに乗る楽しみがないというものだ. あいつのせいで時間を無駄にした.約束に時間は過ぎている.僕は走って自転車置き場へと向かった.バイクにまたがると、ようやく仕事が終わったことが実感できた。スターターボタンを押して、思いっきりエンジンを吹かすとタイヤをスリップさせながら発進させた.塾からJとの約束の場所までは2Kmも離れていない.きっと5分くらいで着くに違いない.午後8時に逢う約束だったが、待ち合わせ場所に着いた時には残念ながら10分ほど過ぎていた.Jはまだ来ていなかった。勝手にJが待ちこがれて先に居ると期待したが、これを独りよがりというのだろう.なんだか自分が滑稽に思えてわら愛がこみ上げてきた.昔から僕は勝手に物語を作ってその中の主人公になっている.現実とのギャップを埋めるために、僕にはこんな夢想が必要なのだと後になって理解するまで、他人から見れば、変わった人間だと思われたに違いない.ちょっと人物観察をすればわかるのに、優しくしてくれたとか、明るい性格に思えたとか、少しだけ美人と言うだけで、僕はその人が好きになり、自分の頭の中でどんどん理想化していく.そして理想と現実のギャップに直面すると、2人の関係は破綻するわけだ.理想を求めていた青春時代が、中年になると人間には理想は永遠に達成できないことがわかり始めた.ドストエフスキーが言うように破天荒さが人間の本来の姿だとわかったときには、ずいぶん落ち込むものである. いつ来るかわからない人を待つのは長く感じる。30分ほど経っただろうか、Jは歩いて現れた。 「遅いじゃないか。」と僕は言いかけたが、口から出たのは 「夜に出てくるのは迷惑じゃなかった?」 何という自己欺瞞。そう思いながら、心の中では、Jが「ごめんなさい。」としきりに謝ってくれることを期待している。でも、帰ってきた言葉は違った。 「時々、貴方が遅くなることがあるから、それに合わせて。」 無償の愛がほしかった。失望が言葉を塞いだ。 しかし、感情は別のことで復讐しようとしていた。 身体を強く抱き寄せ、荒々しくJの身体を愛撫した。 Jは身体を硬くし、手から逃れようと、身体を捻った。 若い頃の僕は、体に触れていやがる女は、自分を嫌っていると思った。でも実際は、手を握ったぐらいでいやがる女は、男を値踏みしているのでは無いだろうか?この男は体を許すに値するのだろうか、でも男の機嫌を損ねたらまずいから、とりあえず上手くかわそうとしているのだろう。概してそんな女は、頭がよくて、人生で失敗することはない。自分のように些細なことに悩んで、付き合うことに畏怖を覚えるのに比べたら、何と世慣れているのだろう。体力でおとるぶん、損得勘定は女の方が長けている.それがわからなかった頃には、女に対して引け目を感じ、劣等感に苛まれる。しかも、若さ故に、強がってみたり、ある時には欲情に流されて本当の理想を見失ってしまう。 ある夜、塾が遅くなって、Jに連絡の取れないまま、待ち合わせをすっぽかしてしまった。さぞ怒っていると思いながら約束の場所に行ってみたが、果たして女は居なかった。僕は意気消沈して自分の下宿に戻った.しかしその夜は12時過ぎになってもまんじりともしない.僕はJの住むアパートに出かけてみることにした。 Jの住むアパートは待ち合わせた場所からそれ程離れていない。大通りをしばらく進むと、住宅地が始まるがその最初の交差点を左に折れ、100mほど進むと先に木造のこじんまりしたアパートが見える。しかし、このアパートは男子禁制である.正面から入るのは気が引けたので、裏に回ってみた.裏はぬかるんだ荒れ地である.そこに踏み込むのを躊躇した.しかしくるぶしまで泥だらけになりながら、僕はJの部屋を探した。彼女の部屋は2階の一番奥である。部屋の電気は消えていた。僕はその窓に向かって小さな石を投げた。1個目は外れた.何度か試すうちにカチンと音がした。窓からJが顔を出した。 僕はJの姿を見られたことで幸せを感じ、窓の下から大きく手探りを振った。「待っていて.」とJが言う.しばらくすると、Jは薄いピンクの柔らかそうなジャージを着て現れた.部屋着であろうか。いつもと違う服装に、僕はドギマギした. 「塾が遅れてしまって、30分過ぎにここに着いたのだけれど。」 Jは黙っていた。 待っていられなくて帰ってしまったことが申し訳ないのかと思い、僕の方から声をかけた. 「これから15分待って来なかったら帰って良いよ。」と言った. 「30分待っても、来なかったら帰る。」とJが言った. 昔から、僕は家族や他人との会話で沈黙が怖くて、相手の気持ちを知りたくて、自らおどけてみたり、自分から挑発してみたり、人との付き合いは緊張の連続だった。3年前に生まれ育ったF県からこの都会に出てきたばかりのとき、僕は冷たくてずるい考えをおし隠した言い方を賢いなあと勘違いしたり、田舎者の正直な反応をかっこわるいと思っていたりした時期があった。だから人とつきあうには、世渡りが上手なスノッブじゃないとだめだ.なんて考えていた. Jとの会話は続く.「貴方の投げた石で、ガラスにヒビが入ったわよ...でも、大家さんには上手く言っておくから大丈夫だと思うわ。」Jは平然として言った. そんなふてぶてしさも彼女は備えていたが、反面、彼女の強さを心地よく感じる自分も存在した.しかし、気の強さもある時には、思ってもいない感情を生み出すこともある. 「はい、これ貴方の洗濯物。」 Jから手渡された紙袋には、僕の洗濯物と小さな石けんが入っていた。 「結婚している訳じゃないのだから.」 Jは鋭い口調で言った。 彼女はたぶんこう続けたかったのだろう。 『結婚している訳じゃないのだから、(洗濯を頼むなんて図々しい人)。』 それを聞いた時、近頃、彼女とうまくいっていると思っていた自信が消え失せた.今考えればそれほど僕のことが好きじゃないのだろう。 それでもJとの関係は続いた.どちらかと言えば僕が無理して続けたがっていた.いつも僕はなんとか時間に遅れないように努力した.最初の頃はJが待っていてくれることが多かったが、最近では僕が待つことが多くなった.この間は、Jから体調が悪いからと塾に電話があった.期待が大きかった分、落胆も大きかった.そんな日に限って塾が時間通りに終わったので、Jのいない待ち合わせ場所に行ってみたりした.風景はいつもと同じだったが、この場所は一人でいるととても静かだと気がついた. 翌日は仕事が休みだった.僕はベッドに寝ころびながら、天井を眺めていた.天井には雨漏りのシミがいくつか並んでいる.それを結びつけたらJの顔に見えてどきっとする.なぜ急に逢えなくなるのか?僕に飽きてきたからか?それとも他の男が出来たのか? ずいぶん迷ったけれど、勇気を出してこの疑問をJにぶつけてみることにした.つまらないことを質問すると、Jのことだから怒り出すかもしれないし、もしかしたらこれがきっかけで、仲が悪くなるかもしれないなあと何度も逡巡した結果である. ほとんど振られた気持ちでJに電話をした. 電話のJはいつもと同じ口調だった.つまりそれほどうれしそうじゃないってことさ. 「昨日は逢えなくて残念だったよ.体の具合はどうなの?」 「え、体?」 Jは逢えない理由を忘れているようだった. 「そうそう、急に吐き気がして、最近私の方もパートの仕事が忙しくて、疲れているのかもしれない.この間は店長とけんかしちゃってね.」 奔放な性格のJは、好きになったら相手の都合も考えないでプレゼントをくれたり、デートに誘ったりするが、少しでも気持ちがさめるとあからさまにわかる. 「次はいつ逢えるかな?」 「そうね、仕事が忙しくてしばらく逢えそうにないわ.」 僕の心の中に、落胆と憎しみがこみ上げてきた。 「今までは、君の方から都合を聞いてきたのに、何で逢えないの?」 「だって都合が悪いから、仕方ないじゃない.もう少し待ってちょうだい.」 僕の自己愛はJの愛を疑っている.だから、Jにしつこくする.しつこくするのは嫌いなのに.本当はJのことを愛していないのかもしれない. 「だったらもういいよ.ウソばかりついている.」 「ウソだなんて.そんなひどいことを言うと相手がどれだけ傷つくかわかっているの?」 「君の都合ばかり並べて、少しも時間を作ってくれないなんて、君の気持ちを疑ってしまうのは当然のことだろう.」 「だから少し待ってと言っているじゃない.永遠とは言っていないわ...」 僕の場合、大抵はこんな風にして関係は終わりを迎える.破壊的になって、関係をリセットしようとする.でも、本当は関係を壊すのじゃなくて、最初からやり直そうとしているだけなんだ.僕は破壊と混沌を好む.それによって自由が得られるからだ.そして、再び創造するのだ. すると電話の向こうのJの声質が変わった。「なんだか気分が悪いの.これくらいにしてちょうだい.」それで電話は切れた。 受話器を置いて、部屋の窓から外を見たら、いつの間にか雨が降り出していた。薄暗い霧雨が窓の隙間から中に入ってくるような気がした。僕は冷蔵庫から、飲みかけの紙パックの日本酒を取り出すと、少し飲んでみた。酒なんてちっとも楽にならないなあ、と思い、残りを一気に飲み干した。飲み慣れないお酒で気分が悪くなった.もっと悪くなって、病気になればいいとおもった. 僕はあることがダメになると、不安に耐えられなくなり、関係のないことまで破壊して、孤独で惨めだと自分を追い詰めようとする.そしてそんなときには、ある一種の快感を得るのである. Jとの仲がうまくいっていた頃の話をしよう。その話を聞いたら僕とJの何が悪かったのかわかるかもしれない. いつもの場所で、Jを拾うと、オートバイの後ろに乗せて近くの食堂へ行く.お互い貧乏と言うことは知っていたから、それほど高級な所へ連れて行かなくても文句は言われないし、それでも僕の一週間分の食費はこの夜で消える.なじみの食堂はショッピングセンターの中にある.バイクを止め、僕とJは明るい電飾に照らされた入り口へ向かう。入り口の自動ドアが安っぽい音で開いた.同時にBGMと騒音があふれ出した。中は買い物客であふれていた.めざす食堂の入り口には造花の観葉植物の鉢が置いてある。おしゃれなカフェを気取ろうとしているが、間口が狭いせいで地味に見える。小さなガラスのドアを開けると、カウンター席が6席とボックス席が2つある.夕食時間には遅いため、カウンター席には中年の男が一人だけだった.主人が注文された料理をカウンター越しに男の客に渡した。僕は主人の親指が皿の中に入っているのが気になった. 僕たちは隅のボックス席に座った。 「えーと、今日のおすすめはチキンカレーらしいね。」 「鳥はくさいから苦手なの。」 「じゃあ、ビーフカレーにしようか.」 「肉がたくさん入っていると、気持ち悪いわ.」 Jは相変わらず僕の前では遠慮がない.聞いた話では他人には優しいらしいが、我慢しすぎて突然ヒステリーを起こすこともあるそうだ.この場合、それよりはましかなと思った. この店はカレー専門店と言うことでカレーのメニューばかりだ.ようやくJをなだめて注文が決まった。僕はなんだか一仕事終えた気分になり、おもわずあくびが出そうになった。何とかそれをかみ殺し、僕は近況などを話して聞かせた。「塾の仕事も慣れてきたから、今度は自分で塾を経営しようかと思っている。」 「大学も出ていないのに、人に教えられるの?」年があまり離れていないせいかJはまるで母親のようにはなす.子供のように心配されるのは好きだが、あれこれ指示されるのはもうゴメンである.僕は子供じゃない君の前では主役でありたいのだ. 「相手は小学生や中学生だから、勉強はそんなに難しいことじゃないよ。それよりも、一緒に学校での悩みを聞いてあげられるお兄さんのみたいなほうが人気があるんだ。今だって、生徒の中には他の先生には聞けないけれど僕には何でも聞いてくる子がたくさんいるよ。年が近いせいもあると思うけど.」 「ふーん、そうなの。でも、塾を経営するって場所を借りたり、人を雇ったり、結構お金が必要でしょ?」 「まあ、何とかなるって。」 僕はお金より目標が大事だと思っていた。 「へい、お待ち.」注文した料理が僕たちのボックス席に運ばれてきた.つい主人の手元を見てしまうが、彼女の前だから気にしないふりをした.Jはエビカレーを注文していた.僕の注文はルーの上に角切りの生野菜がのったカレーである。 空腹だったので、僕たちは何もしゃべらずに食べていた。ようやく人心地が付ついたところで、 「どう、おいしい?」 「ええ.まあまあね.」 「大学生向けだから、ボリュームがあるんだろ?」 「そうね.でもわたしには多すぎるみたい.」 「じゃあ、僕が残りをもらおうかな?」 僕は大抵2人前注文するから、ホームカレーの次には何を食べようか考えていたところだった. 「今週さ.日曜日だけど空いている?有峰湖までツーリングに行こうかと思っているんだ.」 「今週の日曜日は友達と予定があるし...それに....」 「え、それに?」 「それに、バイクの後ろに乗るのって、不良っぽいからあまり好きじゃないの.」 「そうだったの.じゃあ今まで我慢していたの?」 「本当はバイクで迎えに来られるのも苦手かな.」 「じゃあ、今度は車を借りてくるから、それなら良いだろ?」 「ええ、それなら.」 Jの横顔は子供っぽいことに気がついた.鼻が上を向いて、眼が大きい.いつも笑っていてくれるといいのにと僕は思った. 国道に沿って南へ行くと、J川に架かるA橋がある.その橋のたもとを堤防に沿って下流に向かって行くと道が狭くなり突き当たりになる.その脇に広い空き地があって、たくさんの車が止めてある.そこが親戚のおじさんが勤めている自動車工場だ.おじさんは営業で不在らしい.もうすぐ帰ってくるから中で待っていたらと受付のおばさんに言われた.受付にはソファーと小さなテーブルがあり、それとくしゃくしゃになった車雑誌を並べた本棚があった.その中の一冊を手に取り、茶色のビニールレザーのソファーに座った.おばさんが気を利かしてお茶を入れてくれた. 「最近はちゃんと働いているの?お父さんがうちに来て、あいつは家では何も話さないから何をしているかわからないと心配していたわよ.」 「うん、働いているよ.アルバイトだけどね.塾で手伝いをしている.」 「だったらいいの.あなただけが家でぶらぶらしていると居心地が悪いだろうと思って、気になっていたの.」 「家でぶらぶらなんかしていられないよ.そんなところを見つかったら、たくさん用事を言いつけられるから.」 「まあ、大変ねえ.」 おばさんは口で言うほど心配していないようで、はははと笑いながら、カウンターの向こうへ戻った.僕としてはその方が気楽で良かった. 30分位すると、おじさんが戻ってきた.相変わらず黒い顔で、いわゆる営業焼けというところだ.顔がつやつやと光っている.ワックスでもかけたみたいだ. 「よう、元気か?」 「ああ、なんとか.」 「なんだ、若い者がしょうがないなあ.」黒い顔がにこにこしている. 「昨日頼まれた車だけど準備しておいたぞ.新しい車じゃないが、営業で使っている車だ.この間車検が済んだばかりだから、大丈夫だぞ.店の前に置いてあるから見てみな.ところで何に使うんだ?デートか?」 「そんなんじゃないよ.」 「そうか、とにかく事故に気をつけてな.おまえの父さんは顔には出さないけれど、神経質だから、もし車を貸したことがわかると、俺が怒られる.」 父の性格は知ってはいたけど、他人から言われると、気が滅入る.これからも長男として同じ家に住むのである.それでも車を貸してくれるおじさんがいることは僕を理解してくれる人がいると言うことだ.世の中にいる様々な人を選別しないと、いつまでも子供のように片っ端から信じていたら、精神がおかしくなってしまう. 僕はありがとうと言い残して、外へ出た.そこには白いバンがあった.僕は初めて車を買ってもらった若者のように、早速シートに座って、室内の雰囲気を感じてみた.飾り気がないのは営業用だから仕方がない. 「まあ、一度ここら辺を走ってみろよ.」 おじさんの声が聞こえたが、僕は返事もせずにすぐに出発した. Jを乗せてみたいから、車をちょっと早めに借りて、練習しようと僕は考えた.バイクしか乗ったことがない僕には、車はとても大きく感じる.意識していないと、いつの間にか道路の中央を走っている.なんとかぶつけることもなく近所を一周できた. 「くれぐれも気をつけて運転しろよ.」そう言って、 「これ.たばこで臭いだろう.いいにおいがするぞ.」と緑の液体が入ったの芳香剤を手渡された.しかし、帰宅途中でたばこと芳香剤がまじったにおいをかいでいたら、気分が悪くなり吐いてしまった. 2日後の木曜日、いつもの待ち合わせ場所にいつもより15分早く着いた.Jはまだ来ていない.僕はラジオをつけた.むかし、夏によく聞いた4人のバンドの歌が流れている. きみのこころにとどけたいよ 過ぎていく夏の夕暮れを見ながら、僕はチョットだけ感傷的になった。燃えさかる夏の暑さに少しだけ秋を感じて寂しい気持ちになった. 遠くに白のパンツに水色のトレーナーを着た女が見えた.Jだ.でも僕に気がつかないみたいだ.外へ出て手を振った. 「やあ、こんばんは.」 「なあに、これ、買ったの?」 「まさか、借りたのさ.」 「へえ、仕事に使う車みたい.」 「まあ、そんなところさ.」 Jはあまりうれしそうには見えなかった。つきあう期間が長くなるほど、相手の感情が伝わるようになり、かえって神経を使う.それでも、思いなおして僕は言った. 「ちょっと、これからドライブでもしない?」 Jは困ったという顔をして 「でも、あまり遅くなると大家さんがうるさいの.」 「大丈夫、10時までには戻るからさ.」 「ええ、それなら良いわ.」 女は助手席に座ると、なんだか落ち着かない様子で僕を見る. ここに来る前に灰皿は掃除したけれど、所々にタバコの焼けこげがあり、室内が汚れているが気になるようだ. 僕は車を走らせた.ギアがマニュアルだから何速かわからず緊張する.Jはじっと前を見ている.時折、助手席側の窓を見るけれど、僕を見ようとはしない.ここから5,6Kmのところに、K山という標高300mくらいの山があり、頂上には公園があり、デートスポットになっている.次の緩いカーブを越えると頂上だ.僕はちらりと女を見た.やはり黙って前を見ている.出発してから、一言もしゃべらない. 「どうしたの?気分が悪いの?」 沈黙があった. 「どうして、デートにこんな車に乗ってくるの?だって、色もそうだけど、形からして仕事用でしょ!それに室内だって、汚いわ.こんなところをだれかに見られたらかっこ悪いじゃない.」 意外な言葉に僕は驚いた.そういわれて車内をみるとフロアーマットは泥が付いている.でもそれ以外はシンプルだけど、どこも悪くないように思えた.僕はJの怒る理由が理解できなかった. 僕たちは再び無言のままだった. やがて頂上が近づいてきた.木が植えてない山頂は、夕日がよく見える.西側の駐車場は、それを見たい車であふれていた.ほとんどカップルにちがいない.反対方向に駐車する車は他の目的があるのだろう. 車がきれいに一台おきに並んでいる.僕はそれを見て何となくおかしくなった.人は秩序が大好きである.ただし、平和が保たれている限りだが.やがて夕日が沈んで、少しずつ帰る車が増えてきた.僕たちの車の周りには一台もいなくなった. 「夕日が沈むと、今度は夜景がきれいだよ.」 僕には精一杯にキザなセリフだったが、 Jは少し機嫌を直したように見えた.僕はJの肩を抱いた.Jは少しふるえていたような気がしたが、そうじゃなかったかもしれない.「いや.」とJは小さく言った.僕はかまわずJの体を引き寄せた.街の明かりが一つ二つと増えてきた. ** 「高校しか出ていないやつに、たいした仕事はない.」塾の上司から言われたことがある.夏休みが終わる頃から徐々に居づらくなり、11月に僕は首になった.だれにも負けないくらい子供たちに好かれていたつもりだった.しかし、親からの投書で高卒者から教わるのはいやだという意見があったらしい.子供の意見よりも、親の意見が重要なのだろう.それからしばらくして、学歴で嫌みを言われたのでこちらからやめてやった. 何の話のついでか忘れたけれど、家の食事の時に僕の仕事が話題になった. 「塾の仕事は辞めたよ.今は無職さ.」 母は心配して、 「今度、お母さんの知っている人に仕事がないか聞いてみるから、また働いてみたら?」と言う. 僕が無職で家にずっといられちゃ困るのかもしれない. 父は黙って、日本酒を飲んでいる.僕のことが心配でも、どう対処して良いかわからないみたいに見えた。 「これから職安に行って、探してみるから、心配しないで.」とつい両親の気持ちを先読みしてしまう.しばらくのんびりしたかったのに、自分にノルマを与えてしまった。 僕の仕事の話はそれっきり誰も話さなくなった.両親ももう大人だから、自分のことは自分でするだろうと考えているみたいだ.友人のKの家では、昇進や仕事のことをうるさく聞いてきたり、指示したりする親らしい.それでいて、過保護ときているからまるで金で出来た檻の中で飼われているみたいだ.それに比べると僕の家は良い環境かもしれない.父の酒の量が増えるのが気になるけど... JとはK山で夜景を見たのが最後だった.それからしばらくして僕はJに別れを切り出した.好きじゃないのがあからさまなJの態度に耐えられなくなった.つまり鈍感な僕でも、最近のJとの会話から冷え切った関係がわかる.断る理由は忙しいからと、それとなく嫌いになったことを気づかせようとしているようだ.全くJってやつは頭がいい.自分からは決して嫌いになったとは言わない.それに比べて僕ときたら、うちの番犬より交渉能力がない.わんわんほえるだけだ. Jとの最後の電話を切ったとき、あれほど悲しさと悔しさで涙が止まらなかったのに、1週間後、僕はまたJに電話をしようとした.敗者復活?そんなことを気持ちよりも、僕の何が気に入らなかったのか聞きたかった.けれどもどうせ本心は明かしてくれないだろう.結局、連絡を取ることは無かった. それから5年くらい後の話だけど、近所の本屋の前でJとすれ違った.たぶんJかな?記憶の中の顔と違っているように思ったが、とてもびっくりした顔をして走り去ったのをみて確信した.一途な僕と別れたことが後ろめたいのかもしれない.それともそんなに嫌われていたのかとも思った.少しくらい話してもかまわないだろう. ** 近所のKは小学校からの幼なじみである.小さな町だから遊び相手も少ないから、よく彼の家へ尋ねていった.しかし、男同志だから、それほど会話が弾むわけでもなく、勝手にコミックを読んで、ただ同じ部屋にいるだけという状況だ.Kの部屋には機械油のような臭いが漂っている.Kは手先が器用で、親も裕福だから、何に使うのかわからない機械が部屋中にあふれている.いつだったか、おもしろいものを見せてやると言って、僕たちは2階へ上がった.4畳半くらいの和室の中央には、ベニヤの分厚い板が万力にはさんで置かれていた.Kは部屋の机の上にある銃のようなものを取り上げて、僕に自慢そうに見せた. 「どうだい、モデルガンだけど、実際に弾を撃てるぞ.」 黒光りのするそれは確かに銃そのものだった.初めて見る銃におそれと興味があったので、Kの話に聞き入った. 「今のところ、自作の弾だから威力はそれほど無いけどさ.ちょっと撃ってみようか.」 僕はうなずいた. 「耳をふさいだ方がいいよ.」 Kが劇鉄を起こしゆっくりと引き金を引いた. パァーン 火薬の臭いが部屋に広がった.それと耳の奥でキーンと言う音が残った. 青い煙は銃の先から立ち上っている.ベニヤ板を見ると、穴は空いているが、貫通はしていなかった.それでも本物の銃を見て僕は興奮した.触っても良いかとKに聞いた. Kは黙って、僕に銃を手渡した.ずっしりとした感覚が手に伝わった.銃の形は西部劇で出てくるリボルバータイプだ.銃身が長くて、かっこいいなと思った. 「撃ってみたいな.」 Kに頼んだ. 「さっきの弾で最後だよ.弾を作るのが結構大変だから.この銃に使える6mmの薬莢はなかなか手に入らないんだ.自衛隊の演習地から拾ってくる奴がいて、それを買う.また、火薬を詰めたら撃たしてやるよ.」 僕はKを尊敬の目で見た.銃を作れるなんて僕には出来ないと思った.その部屋には真っ白な模型のボートが置いてあり、それも設計から製作までK一人でやったらしい.近くに寄ると燃料のアルコールと火薬の臭いがした. Kは中学の途中からほとんど学校に出席していない.しかし、会社を経営している父親は家を空けることが多いから、不登校には気がつかない.仕事のことしか頭にないから、たまに一緒になる食事も話題は仕事のことである. 「取引先から、無理難題を言われたので、腹が立って帰ってきた.大企業だからと言ってあんな若造になめられた口をきかれて黙っていられるか.」 「社長自ら時間外手当ももらわずに、がんばっているぞと社員に言ったら、社長もちゃんと給料もらえばとぬかしやがった.こっちがどれだけ苦労してるかわかっていない.」 ほとんどは、会社の愚痴であり、自分のストレスの吐け口を家族にしている弱い男である.短気な性格でやがて経営がうまくいかなくなり、社長が交代となるのは先のことである. Kに対して跡継ぎに対する期待が大きいに違いない.学校での成績も良かったらしいが、なぜ学校に通わなくなったのかKは言わなかった.でも、ほとんど家にいない父親は、教育は母親に任せきりである.仕事の不満をKにぶつけることもあり、いつしかKは全く父親とは口をきかなくなった.Kの上には先妻との間に出来た姉が3人いるが、すでに成人して家を離れている.もう一人実の兄がいるが、全く耳が聞こえない.だから話すことも出来ず父親は跡継ぎとは考えていない. Kの母親は僕が遊びに来ると、お菓子や飲み物を次々と出して迎えてくれる.Kがいないときに母親が僕に教えてくれたのだけど、Kは家でほとんどしゃべらない.でも、僕がいるととても明朗に話すらしくて、それがうれしくてたまらないとKの母親がそっと教えてくれた.だから、Kの母親は僕が遊びに来ると、時々お菓子を携えて部屋にやってくる. 「大きくなったら、飛行機の操縦士になりたいな.」Kが話す. 「また夢みたいなことを言って.」Kの母が楽しそうに言う. 「本で調べたら、セスナの免許は200万くらいで取れるし、中古のセスナなら500万で買えるよ.」 Kの母親はにこにこしながら聞いていた. 僕にしたら夢のような大金だけど、この一家にとってはそれほどじゃないのかと思った. いつしか夕方になり、テーブルの上にはお菓子の山が出来上がっていた. 後日、母親からKが家を出て、東京へ行ってしまったことを聞いた.とても寂しそうな声が印象的だった.僕に何も言わないなんて、衝動的に家出をしたのだろうか?父親とけんかをして出て行ったのかもしれない.僕は、人の別れは突然来るものだとそのとき感じた.子供の頃に一緒に遊んだ友達も、大人になればそれぞれ違う道を進み、一生会うこともないのだ.Kとはそれっきり会うことは無かった. ** 母に買い物を頼まれてM町ショッピングセンターに行った.店内を歩き回っているうちに、咽が渇いてきた.それで、おいしいと評判の生ジュースを味わってみようと考えた.お店は一階にある. 「何がおすすめなの?」 「そうですね.今の時期ですとキウイがよく出ています.」カウンターの中から、若い女の子が答える. 「じゃあ、それ.」 僕は、カウンターから少し離れたテーブル席に座って、女の子の動きをぼんやり見ていた.女の子は皮がむかれたキウイを冷蔵庫から取り出すと、手際よくシロップと水を混ぜてジューサーに入れた.その子がジュースを運んできた. 「お待たせしました.350円になります.」 僕が代金を払おうとすると、その女の子は微笑みながら顔をじっと見ている. やけに愛想のいい子だと思った. 「もしかしたら、先生じゃないの?」女の子が言う. 「忘れたの?塾で先生に習っていたEよ.」 僕はまったく思い出せなかった.たぶん顔も変わっているだろうし、化粧もしているからわからないのかもしれない.知り合いだからと、カネをせびられたこともある.しかし、相手が若い女だから、それほど警戒することはないだろう. 「覚えていないみたいね.まあ、いいわ.もう2年前だから忘れても仕方ないか.」 若い女はいつのまにかため口になっている.僕は彼女の勢いに圧倒されて、彼女の話を聞くしかなかった. 「クラス分けのテストがあったでしょ?あのとき先生が、そっと指さして教えてくれたじゃない.アレすごく助かったの.だって、下のクラスに落ちる所だったから.私は下のクラスでも良いのだけれど、親がうるさくてね.わかるでしょ?」 「ああ、そういえばそうだった.」 ようやく僕は思いだした.とてもまじめな生徒で、僕の下手な授業でも、真剣な顔でノートを取っていた子だ.こうしてみると、この子に笑顔があるのが不思議なくらいだ.笑顔だったから気がつかなかったのかもしれない.僕はその女の顔を見ながら、教室での出来事を思い出そうとした. まあるい小さな顔が、こちらを見ている.子供は大人と違って、視線に遠慮がないから、こちらが視線を外すまでじっと見ている.僕がにこっと笑うとあわてて下を向く.たぶん答がわからないのだろうと思って、その子の机に近づいた.最後の文章問題で詰まっているようだ. 答の番号を指した.その子は突然現れた僕の指に驚いた様子だった.しかし、すぐに番号を答案用紙に書いた.全員に答を教えたい気持ちに僕はとらわれた.しかし、そんなことをすれば、すぐに上司から注意が来て、運が悪ければ解雇だ.なにしろ、学校とは人と差をつけるための場所だ.全員が賢くなったら、存在する意味がない.だから学校の準備をする塾も同じことをやっている.なんて、堅苦しいことも考えたけれど、単にその子がかわいそうに見えただけで、それほど深いことを考える僕じゃない. その女の子と個人的に話したこともないし、印象も無いから忘れかけていた. 「ようやく思い出したよ.ここでアルバイトをしているの?」 「うん、土曜日と日曜日だけどね.」 「高校へ進学したの?」 「進学したけど、一年でやめちゃった.」 「ふーん、そうか.学校は嫌いか?」 「学校も、友達もみんな嫌い.」 僕ははっとした.まるで頬をぶたれたように感じた.塾での仕事はそりゃお金を稼ぐためだけど、少しは人のためになるかと思っていた.でも、無理して人間を飼い慣らして、進みたくもない方向へ押し込め、生きたくない人生へ向かう手助けをしてきたとその時感じた.人のためになるって難しいなあとつくづく思った. なんだか気まずい雰囲気だった.それから後はジュースの味が無くなってしまい、半分くらい残して、僕はその店を後にした.その子に後ろめたさを感じた僕は、罪滅ぼしのつもりで次の日曜日にまた尋ねてみようと思った.その子の力になりたいという思いと、それが出来たら自分の気持ちが収まるような気がした. 次の日曜日、もう一度Eの勤めるお店に行った.彼女はいなかった.そこで仕事をしている人に尋ねてみることにした. 「お客さん、何にするの?」カウンターにいた小太りの中年の女の人が無愛想に聞いてきた.白いエプロンのポケットのところがうす黒く汚れている.清潔じゃない奴は食品を販売する資格はない.心の中でこの女に話しかけた.ごくりと僕は唾液を飲み込み、心を静めようとした. 「あの、Eさんいますか?」 「きょうは、体調が悪くて休んでいるよ.注文は?」 「いえ、注文は別に...」 「注文はないのね.」仕事をじゃまされて不機嫌そうに言い放った. 女が見たとおりの意地悪な人だったので、僕は少しだけおかしくなった. 小雨の中、僕は雨よけのジャンパーを着て、オートバイに跨るともう一度ショッピングセンターへ向かった.雨脚が徐々に強くなり、道路が黒光りし始めた.次のカーブを曲がると、ショッピングセンターである.交差点では下水工事をしていた.道を掘り返して下水管を埋めたようだが、舗装はまた後日するのであろう、茶色の鉄板がその上に敷かれていた.車が、急に脇道から現れた.僕はその車を避けようと軽く右へハンドルを取りながらブレーキをかけた.鉄板の上で、バイクの後輪がロックした.と同時に、後輪は左の方へスリップした.僕はバイクを立て直そうと、今度は左へハンドルを切って体を傾ける.今度は右へタイヤがスリップする.それを何度か繰り返しているうちに僕は対向車線へと飛び出していた.大きなダンプカーが目の前にあった.なんてことだ.全くついていない日だ.僕はどうすることが出来なくて、ダンプカーの正面にぶつかった.激しい痛みがあるかと思ったら、全く痛みがないんだ.死ぬ時はこんなものか. ドンドンドン. ドンドンドン. ドンドンドン. 遠くの方で大きな音がする.体を動かそうとするが、ちっとも動かない. 外で誰かが呼んでいる声がする. 「Tさん...、Tさん...、Tさん...」 ぼんやりした頭が徐々にはっきりしてくる. 「Tさん、電話だよ.」 頭がひどく痛い.日本酒が飲み慣れていないせいだ.日本酒、ワイン、ビールという醸造酒ときたら、飲み始めはおいしいけれど、あとからひどいしっぺ返しがくる.2面性があるところは政治家と一緒だ. ようやく、体を起こして、よろよろと廊下の共同電話へと歩いた. 受話器を取ると聞き覚えのある声だった. 「昨日はごめんなさい.何か私に用事だったの?」 「近くまで行ったので、話でもしようかと思ってね.ところで良くここの電話番号がわかったね.」「へへ、実は塾へ電話をして、聞いたの.生徒の保護者と思わせて、先生にお礼を伝えたいと嘘をついちゃった.先生、塾、やめたの?」 「ああ、やめたんじゃなくて、クビになったんだ.」 「またテストの答を教えてばれちゃった?」うれしそうにEは笑った. 「そんなんじゃないよ.」先生と呼ばれていたのに、今では友達みたいだ.普通は怒るところだろうけど、僕はなんだかうれしくなってきた. 「アルバイト以外には何かやっているか?」 「家にひきこもっているよ.たまに買い物や映画を見に外出するけどね.」 「親がうるさいだろう?」 「うん、うるさいよ.学校へ行くか、ちゃんとした仕事をしろってさ.」 「ふーん、それで言うことを聞いて、仕事をしているわけだ.」 「あんなの仕事じゃない.小遣い稼ぎと、親へのエクスキューズよ.」 「じゃあ、良かったら僕と一緒に仕事を始めないか?」 「うん、なんだかおもしろそう.でさ、どんな仕事なの?」 「それは今、考えているところさ.」 「なんだ、はははは、おかしい.何の仕事か決まっていないのに、人を誘うなんて.やっぱり先生はおもしろいよ.」 「そんなに笑うなよ.これでも毎日毎日、悩んでいるんだぜ.君も少しは考えてくれ.」 「うん、わかったよ.私たちがやる仕事ね.何が良いかな?えーと、すぐには思いつかないなあ.」「今度、会う時までの宿題だ.」 「えー、なんか学校みたい.でも、学校の宿題みたいに嫌じゃないわ.不思議ねえ.」 無職同志、通じ合うところがあるのかなと思った.それより2人ともマジメに学校に行っていないおかげで、いわゆる大人の常識を知らないかもしれない.でも僕はいちおう毎日学校へ行っていたんだ.朝起きるのが苦手でいつも遅刻していたけどね.学校に着く頃は給食の時間だから、授業を受けるのは5時間目になってしまう.こんな僕が卒業できるかのかなと思っていたら、中学は卒業できた.でも高校は単位が足らなくて中退になった.母親はそんな僕でも怠け者とは考えないし、無理に朝から学校へ行かせることもしなかった.だから、学校は全然嫌いじゃなかった.友達もいたし、時にはいじめられっ子をいじめっ子から守るために、一緒に下校したり、人とは違うことをするのが好きだった.そいつとは今でも僕のことを慕ってくれる.でもそいつは大人になっても相変わらずいじめられっ子だけどね. 小さな部屋は段ボールの荷物でいっぱいである. 「今からお届けしますね.」 部屋の隅にある大きな段ボール箱からビニールの包みを取り出した.Eは背が低いから、商品を持つと前が見えなくなくなり、ふらついている. 「これから、一丁目のAさんへ配達に行ってくるわ.」 「うん、気をつけて.悪いけど、帰りにYさんのトイレットペーパーを買ってきて.」 「わかったわ.」 Eの後ろ姿を見送った.腰のあたりがしっかりしている.すっかり大人の女の姿だ.僕はもやもや変な気分になったので、領収書をまとめることにした.「くそっ、この領収書ってやつは、何でみんな同じに出来ないのだろう.」領収書を日付け順に並べようとしたが、途中でやめた.結局、形が不揃いだから針に刺して置くしかない. 僕たちが始めた仕事は、客から注文をもらい、それをお店で購入して、配達する.始めてから1年になるが、徐々に注文が増えきた.それで今度はEに配達用の原付を買うことにした.それから重いものを配達するため車を購入した.車を使うようになったら、客から「おっ!車を買ったの?」と言われる.景気がいいなんて思われたくないし、本当に中古車だから「古い中古車です.」と答えた.後で考えたら、少し気にしすぎたかもしれない. その晩は、仕事が遅くなり、2人が事務所兼倉庫に戻ったのは10時過ぎだった. Eが汗にぬれたグレーのTシャツの袖をまくっていた.顔にも汗が滴っている. 「客が不在で困ったわ.仕方がないから、隣の住人に預かってもらうことにしたの.先生はどうだった?」 「こっちも、渋滞していたから、いつもより時間がかかったよ.明日から地区の祭りらしいから、今日はその前夜祭みたい.」 「途中で、お弁当を買ったけれど、一緒に食べる?」 「いいねえ.もうお腹がすいて倒れそうだよ.」 Eは、僕の顔を見て笑った. 「倒れそうだなんて大げさねえ.だったら、これくらいじゃあ足らないかもしれないわ.何か買ってきましょうか?」 「いいよ.これで十分さ.足らなければ、明日まで取っておく.」 「ふふふ、取って置くなんて、なんか変.」 僕はEの買ってきてくれた、惣菜弁当を食べた.お腹が減っているせいかとってもおいしかった.僕はほとんど会話することもなく先に食べてしまった. またEが笑いながら 「本当にお腹がすいていたのね.私のも食べる?」 「いいの?じゃあ、もらうね.」 半分ほど残ったEの弁当をまた僕は一気に平らげてしまった. 「今度の仕事は順調ね.」 「ああ順調だ.」 「これからどんどん忙しくなるのかしら?」 「ああどんどん忙しくなるよ.」 「これ以上忙しくなったら、こうして先生とゆっくりと話も出来ないわね.」 「そうだね.だったら人を雇おうか?」 「でも、そうなると2人きりと言うわけにはいかないわね.」 「そうだね.でもたまには2人だけの時があるかもしれないよ.」 「うん.そうだね.」 僕たちはそれっきり黙ってしまった. 遠くに犬の鳴き声が聞こえる.その後は深い静けさがただよった. いつかEに尋ねようと考えていたことが頭の中に浮かんだ. 「ねえ、Eちゃん.」 Eは満足そうな顔をしていた.食後は誰でもそうさ.幸せな気持ちになれる. 「君は霊の存在を信じる?」 「先生は急に変なことを聞くのね.そうね...霊はいると思うわよ.私には守護霊がいるの.その霊がいつも私のことを守ってくれているのを感じるの.」 「どんなときにEちゃんを守ってくれるの?」 「この間、運転していたら後ろから追突されたの.」 「それじゃあ、守護霊がいないんじゃないの?」 「ちがうの、最後まで聞いてよ.私の車のマフラーが破れていたところにぶつかって、ぶつかってきた人に修理してもらったの.ラッキーでしょう? 「おばけがでてきた.」 「ちがうったら、車にひかれそうになったの.」Eはまじめそうに答えた.僕がふざけても気にならないほど信じているようだ. それから死んだらどうなるかなと聞きたかったけれど、もう遅いから話さなかった. この世に生まれた理由を知りたくて、僕はいろいろと漂流している.新しい仕事もはじめたら、何か少しでも自分の目的が見えてくるかなと思った.僕の魂はそれを知っているはずだ.若いときからずいぶんと危険なことや自ら体を傷めることもやってみたが.魂は何も教えてくれない.この世でひとりぼっちにされた気分だ. それから僕は失敗してもそれほど落ち込まない.この世での修行のために何か得るものがあると思っているからだ. それでも、いやなことはたくさんある. この間、客が、注文した商品が違うから返金しろと言われた.注文を受ける時にはノートに書いて間違えないように気をつけているのに、よく似た名前の商品があるものだ. 「名人の作る納得サラダ」と「職人の作った納得サラダ」という冷凍食品. それほど味が違うとは思わないけどね.どちらもサラダには違いがない. 仕方がないから、返金して、商品は事務所の冷蔵庫行きである. 僕たちの夜食がまた増えた.先月は黒字かと思ったら、今月は赤字になりそうである. 「今月の給料だけど、少し待ってくれない?」と僕. 「うん、それはいいけど、大丈夫なの?」とE. 「いつも赤字ってわけじゃないから、心配するなって.」 「わたし、働きに出ようかな?」 「今だって、十分に働いているさ.」 「そうじゃなくて、空いている時間に他で働こうと思うの.空いているのは夜くらいだけど、探せば、何かありそうよね.」 「働きになんて行くなよ...なんとか来月は黒字にするよ.」 「ええ、期待しているわ.」僕には切実さが欠けているらしい.Eはケラケラと笑った. 口コミで注文は徐々に増えているが、その割には利益が出てこない.たぶん商品の安いからだ.もっと高額な商品の注文を取らないと... 「おはようー.」事務所に僕の声が響いた. 返事がない. いつも僕より早く来ているEがいない. 1週間前から、Eは時々遅刻するようになった.夜中にパートでホテルの清掃に行っている.時間通りに終われば遅刻はしないけれど、何かトラブルがあると、間に合わないと言っていた. 今日もトラブルらしい.. 9時過ぎ、事務所のドアが勢いよく開いた.ようやくEが出勤してきた.僕は朝一番の注文をもらって、事務所に戻ったところだ. 「おはよう、きょうもトラブルなの?」 「そうなの、ラブホテルの清掃は頭を使わないから楽だろうと考えていたのに大きな誤算だったわ.ホテルは2人で使うものじゃない?」 朝にする話にしては刺激が強い.僕はにやけながら「普通そうだね.」と答えた. 「それを4人で使ったみたいなの.大きな声でカラオケを歌ったり、騒いだりしているから、おかしいと思ってIさんが様子を探りに行ったの.小窓からのぞくと間違いなく2組の男女がいると言うの.社長から、3人以上泊まったら追加料金をもらえときつくいわれているし.もし見逃したら、すごく怒られるから、Iさんは必死になってシャッターを閉めて出られないようにしたの.」 「うんうん.それから.」おもしろいことになりそうだと僕は期待した. * * * 「おい!なんでシャッターが閉まっているんだ.」茶髪の背の低い男が部屋の下の車庫から戻ってきて.小太りの若い男に言った.小太りの男は体格がいいのを強調するように、体にぴったりのTシャツを着ていた.半袖から刺青が見えていた. 「おかしいな?部屋のボタンでさっき開けたぞ.」 黒いタイツを履いた超ミニの女は、ソファーでタバコを吸いながら男たちのやりとりを見ている. もう一人の長い髪を金髪にした女は上下とも黒のジャージを着て、ベッドの上で携帯をいじっている.今起きている出来事には関心がない. 「ねえ、何をトラブっているわけ?」超ミニの女がイライラしている. ぶつぶつ文句を言いながら、背の低い男がフロントへ電話をかけた. 「あのさ、シャッターが降りていて出られないだけど...え?何、料金が不足している?表示された分はちゃんと払ったよ...3人以上で利用しているから、さらに6000円追加料金を払えって?...ちょっと待ってくれる?」 「おいCちゃん.なんだかさ、追加料金を払えと言っているけどどうする?」 小太りの男が、めんどうくさそうな顔をした. 「料金が高くなるってどこにも書いていないぞ.そんなもの払えないって言え!」 背の低い男が電話に向かって繰り返した. 「払わないなら、それでも良いけど、帰ってくれってさ.」 「なんだよそれ、なんか俺たちが料金を踏み倒したみたいで、そっちが謝れと言ってやれ.」小太りの男はさっきの酎ハイが飲んで、気が大きくなっているようだ. にやにやしながら背の低い男が、強い口調で息巻いている. 「むこうは謝っているよ.」 「電話じゃあ気に入らないな、直接謝ってもらわないとなあ.」 小太りの男は、ソファーに腰を下ろすと、ミニスカートの女の腰をなで始めた. 女はいやがったが、男が怖くて抵抗できずにいた. しばらくすると、ホテルの従業員だという若い女が現れた. 女はこんなホテルにしては洗練されていた. 「こちらの手違いで申し訳ありません.追加料金は結構ですので、どうぞお引き取りください.」 「なんだ、こっちは被害者だぞ.こころが傷ついてつらいんだよ.もう少しましな謝り方があるだろう.」相変わらず女の腰に手を回しながら、引き寄せようとしている.従業員の女はキッと見返して「どうしてもお引き取り願えないなら、警察を呼ばせてもらいます.」と言う. 「なーに、呼べるものなら呼んでみろ!」 連れの女たちが騒ぎ出した. 超ミニの女が「えー、いいからもう帰ろうよ.」と甘えた声を出した. 「黙ってろ!金を払わずに逃げたなんて思われたら、男のメンツが立たないだろ.」大声で小太りの男は再び怒り出した. 「じゃあ、電話します.」従業員は引きあげた. やがて遠くからサイレンの音が聞こえてきた. 威勢の良かった男女4人は何となくシンとしてしまった. 「なんだよ.悪いのはあっちの方だし.俺たちは何も悪いことをしていないのだから、堂々としていればいいよ.」と背の低い男が言うと小太りの男は近くにあったゴミ箱を思い切り蹴飛ばした. 足音とともに大勢の声がこちらへ近づいてきた.部屋の前で止まる. ドンドンとドアがノックされた. 「あのー、○○署だけど、少し話を聞かせてくれるかな?」 目深に制帽をかぶった体格の良い警官を先頭に4人の警官がそこにいた. さらにその後ろには、ホテルの従業員が隠れるようにして立っていた. 「退去しないようだけど、そういう事をするとまずいよ.」警官は優しく話し出した. 「ホテルの方に責任があるから謝ってほしいといっているだけで、出ていかないわけじゃあない.」と小太りの男が憤慨しながら言う. 「そのことについてはホテルの落ち度だから、追加料金はいらないと言っているから.」 「だったら俺たちが何で悪者扱いされるのか納得いかないね.」 「まあ、そういわずにここは黙って帰ってくれないか.」 「ちっ、もう2度とここは使わないからな.」悪態をつきながら、客たちは渋々帰り支度を始めた. * * * 「それでさ.Iさんが声を震わせて言うのよ.『どうしよう.追加料金がもらえなかったことが社長にばれたら、すごく怒られるわ.』てね.だから私は言ってやったの.黙っていればわからないって.」 僕は客たちが暴れて、警官と乱闘になることを期待していたが、普通の不良ならその程度かもしれない. 「それよりも、Iさんが社長に報告するって聞かないの.お金を取れなかったことを私のせいにして、自分は良く思われたいみたい.それで私はカチンと来ちゃって、朝からずっとむしゃくしゃしているってわけ.」 「私のせいにしたいのならどうぞ勝手にしてくださいと言ってやったわ.でも、また同じ事が起こるわ.」 * * * 「何度もご説明しているように、3人以上のご利用は追加料金が必要でございます.どうぞお願いいしたします.」 優しい口調で、D男は一生懸命電話で説明した. 「だから、そういうことはあらかじめ言ってもらわないと困るな.追加料金が必要なら、このホテルには入らなかったよ.」 それから何度も客との間でやりとりが行われたが、結果は同じだった. いまは夜中の2時である.この時間に社長を起こすと機嫌が悪い.さんざん迷ったが、D男はついに意を決して社長に連絡を取った. 「あのー、社長、夜分済みません.実は料金を払わない客がいて困っています.」 「なにい、料金を払わせるのがおまえの仕事だろう.何をのんびりやっているんだ.」舌が回っていないのは、かなり酒を飲んでいるのだろう. 「い、いや、社長.何度もご説明しているのですが、ご理解できないようでして、はい.済みません.」 「おまえ、説明したと言っているが、払ってもらえないなら、説明したことにならないだろ.それでも脳みそあるのか?」 「あ、いや、済みません.どうにもならなくて、どうしたら良いでしょうか?」 「もういい、俺が直接説明してやる.どいつもこいつも...」 汗を拭きながらD男は受話器をそっと置いた. 「社長が来るってさ」D男は同僚のM子の顔を見た. M子は肩をすくめながらも、黙って洗濯物を畳んでいた. 社長は近くで経営するラブホテルに住んでいる.5分もしないうちに黒塗りのベンツが現れた.タックの入った黒いズボンにベージュのポロシャツを着た太った中年の男が降り立った.顔はゴルフ焼けだろうか、浅黒くシワが目だった.不機嫌そうに事務所のドアを開けた. 「おい、D!料金の説明の出来ないのか!頭悪いな.」部屋に入るなり怒鳴りだした.D男はまだ部屋の客と何度目かの電話中であった. 「はい、そのようなことにはなっていませんので、はい、えー、少しお待ちください.」D男は社長を見つけ、電話を替わってほしいと目配せをした. 社長はその電話を受け取ると、すごい剣幕で怒鳴りだした. 「おい、料金を払わないとどうなるかわかっているんだろうな.タダではここから出られないんだよ.ここのバックには○○組があるんだ.今から、そこへ相談に行くけど良いな?」 やくざのような脅しで客は折れたようだ. しかし、社長の怒りは収まらなかった.「D、おまえは大学を出ているくせに、こんな事も出来ないのか?頭悪いな.」 社長の怒号にもD男は下を向いて黙っているだけであった.「全く、どいつもこいつも脳みそあるのか?」 ちょうどその時、部屋からの電話が鳴った. M子が電話を取る. 「はい、フロントです.はい、ピザを一つですね.わかりました.」 しかし、M子は冷凍ピザの保存場所がわからず、事務所の中を行ったり来たりし始めた. 「おい、何をしているんだ.」社長の顔が赤黒く変わった. 「はい、お客さんからピザの注文を受けたのですが、どこにあるのかわからなくて...」 「ピザなら、冷蔵庫の中にあるに決まっているだろ.ここに勤めて長いくせになにやっているんだ.」 社長は立ち上がると冷蔵庫のドアを開け、中から冷凍ピザを取りだした. 「これくらいもわからないのか?」 そう言って、M子へピザを投げつけた. M子はそれをうまく受け取れず、足下に落ちた. 「おまえ、脳みそあるのか?」 M子は黙っていたが、下に落ちたピザを拾い上げ、レンジの中へ入れた. M子は気持ちが抑えられなくなり、やがて泣き始めた. 社長は言い過ぎたと思ったのか、何かぶつぶつと言いながらその場からいなくなった. 社長がいなくなると、D男はM子に「大丈夫?僕もよく怒られるから.」そう言って、弱々しく笑った. M子はまだしゃべられる状態ではなく、うなずくだけだった. * * * ある日、深夜、Eが仕事をしていると社長からホテルに電話あった.ネットで準備中の部屋がいつまで経っても空き室にならないのに我慢できなくなったらしい.きょうは連休の初日である.きっとホテルには入れない客たちがまわりで待機しているのだろう.ネットで空き室表示があれば、すぐに車で乗り付けるはずである.しかし、Eがいくらがんばっても、一晩で7〜8部屋までしか掃除することは出来なかった.そのことを社長に伝えたら、「そうじなんて、見えているところだけきれいにすればいいだろう.そんなのはこの業界では常識だ.バスタオルで風呂を掃除すればいいし、コップもそれで拭けばいい.」 雪が降る季節になっても、Eはそんな話をしていた.きっとそれで心収まるのだろうと思って、僕は黙って聞いていた.でも、そんな職場の社長や意地悪な同僚に我慢できなくなり、ある時、Eに話した. 「そんなに大変なら、やめれば?」Eはちょっと僕の方を見ると、まじめな顔をしていった. 「ううん、今の仕事は気に入っているの.だって、ここの仕事の差し支えにならない真夜中の仕事だし、これでも掃除ってとってもいい運動になるの.最近、運動不足で体が重かったけれど、今じゃ、ほら、楽に階段も上れるようになったわ.ほらみて少し細くなったでしょ.」 Eは自慢そうに僕の目の前でスカートのすそをたくし上げた.スタイルのいい足が目の前にあられた. 「それはそうだけど.」 僕は自分の心に問いかけた.本当はEのことを心配しているのか?単に不満を聞きたくないだけなのか? どちらにしても、今の仕事はEにはふさわしくないと思った.僕のひいき目かもしれないけれど、Eは学生の時から良くできる生徒だった.しかし、まじめで正直な性格は他人とうまく合わせられないことが多かった.だから高校を中退してしまったのだろう.僕は陰のある人を見ると助けてあげたくなる.僕と同じものがその人の中に見えるからだ. Eは今の仕事もすぐに慣れて、どんなふうに宣伝しているのかわからないけれど、注文もたくさん取ってきてくれる.客の受けもいいようだ.だけど男の客からの誘惑があるのを聞いた時には、おもしろくなかった. 「わたしも行く先々で声をかけられるのは嫌なの.正直に言えば、男の人はあまり好きじゃないの.」 女とは声をかけられるとうれしいのかと思っていたが、そうじゃない女もいるのだと初めて知った.好きでもない男に口説かれて、虚栄心を刺激されるだろうけど、そんな女に引っかかった男はとんでもなく不幸だ. 「先生は違うよ.」とEがまじめな顔をして言う. 「男って、必ず下心があるから嫌なの.下心のない男の人は滅多にいないわ.仕事を始めた最初の頃は私も子どもだったから、いろいろと気を遣ってなんて優しい客だろうと思っていたけれど、その次にあった時に食事に誘うの.この人もそうだと思ったら、がっくり来てしまうわ.」 Eは本当に怒っているように見えた. 僕はEの顔をじっと見つめながら、10年後、20年後の成長を想像してみた.さらに人間として強く優しくなっているだろう.僕が最初に見たまじめだけど折れそうな弱さとは見違えるほどに. 「何を考えているの?」Eが僕にたずねる. 僕の頭の中の優しい顔が、いつの間にか、芯の強いEに戻っていた. 「そろそろ眠くなってきたから帰るね.それから、明日の配達は直接行くことにするよ.」 僕は、翌日配達する商品を車に載せるために事務所の外へ出た.一面真っ白になっていた.12月の初旬に雪が降ることはこの地方ではそれほどまれではない.僕のアパートから事務所まで約10Km位である. それほど雪は深くなさそうだ.それに、タイヤを交換する気力は残っていない. 荷物は15分ほどでセリカに積み終えた.Eに挨拶を言おうと思い、もう一度事務所に戻った. 「じゃあ、行くね.良ければ事務所で泊まってもいいよ.たいしたものはないけれど、好きなものがあったら勝手に食べていいよ.」 「ありがとう.でも、もう遅いから食べないで寝るわ.太るからね.」 「じゃあ、また.」 「ええ明日ね.気をつけて.」 道路は空いていた.気温が下がっているため、跳ね上げられた雪は煙のように舞い上がり、音もなく車は走る.まるでおとぎの世界にいるようだ. いつもは国道を通るけれど、今夜は海岸沿いの道で帰ることにした.海岸の近くは、海風が強いから、雪が積もらない.そう思った僕は国道に入らず、海へ向かった.だんだんと街灯がまばらになり、暗闇が広がる.たぶん周りは畑らしい.その次の交差点を右折すると、少しずつ道が登りになって、やがて海岸に沿う道にでた.粉雪が舞っているが、道路には雪は積もっていないようだ.緩やかなカーブがヘッドライトに浮かび上がった.いつもは楽に曲がれる場所なのに、きょうは雪が吹きだまりになっていた.あっという間に後輪が滑り出すと同時に、ゆっくりと車は回転し始めた.そして、車はガードレールをつき破って海へとダイブした.たいていの車は、前の方が重いのであり、海につっこむときも前の方か落ちる.そして、海までの距離が長いほど、下向きになってしまう.20m下なら、ほぼ真っ逆さまに海へ落ちることになる.車はすぐには沈まない.トランクからぶくぶくと泡を出しながら少しずつ沈んでいく. *** 予感がしたのかもしれない.君を残して急にぼくがいなくなったら、君はどんなに悲しむだろうと心配している.ぼくときみの共通の友達がいたら、そいつに君のことをよろしくと頼むのだけれど、そんな懇意な友達はいなかったね.だから、少しでもきみの悲しみを減らすことが出来たらと思って、この手紙を残した.事務所の引き出しにしまっておいたから、ぼくの遺品を整理したらすぐに気がつくと思っている. きみがこの手紙を読んでいると言うことは、たぶん僕はもう存在していないのだろう.僕たちの仕事は、始まったばかりだ.だから十分にきみと話すことが出来なかったと思う.カップルの中にはお互い好きだけど傷つけ合うだけの関係もある.また、好きだとか恋愛を超えてお互いに必要な関係もあるだろう.きみとの関係はそのどれにも当てはまらない.だって、恋人のような会話だけで、恋愛の最終的な行為もしていないしね. いま、若くしてこの世から去っても、長生きしても年功以外何も持っていない年寄りよりはましかもしれない.僕にとっては何を成し遂げたかではなく、何を成し遂げようとしたかが重要だ. 若くて美しいときにはいろいろと親切にしてくれる人が現れると思うけど、本当に君を愛してくれるかどうかは、君が長生きして、人間を見極めなくてはならない.教育は十分ではなかったけれど、きみにはバイタリティーがある.毅然とした心がある.それさえあれば、どこへ出ても必ず成功をおさめるよ. いつか事務所できみがうたた寝をしているのを見たことがある.とてもあどけなくてびっくりするほどだった.働いているときとはちがってね.あどけない顔を見ていると仕事や人生の悩みがこの人には無いのだろうかとにくらしく思ってしまうほどだ.不思議なことに長生きすると人間のいやな部分が透けるように見えてくる.そのことで君の素直さがだんだん無くなるのは残念だけど.では、いつもそばに. ぼくの親愛なるEへ (おわり) |
|
「それじゃあ、この実験の結果はそのまま信じろって言うのかい。」 ハムステッド研究所の主任研究員のロバート・プラントは助手のリンダ・ホイルに少し怒ったように言った。 「でも、結果を信じるのが、科学者でしょう?信じないなら、弁護士にでも転職したら?」 長年プラントの元で働いているホイルは、少しも譲らない。 「わかったよ。このことはジョーンズ 所長に相談してから、考えよう。だけど、君は頑固だねえ。人の進化でそんなことがあるはずがないじゃないか。」 独り言のように話しながら、プラント研究員は、自分のデスクに戻っていった。 「『信じられないことでも、他に可能性がなければ、それが真実である』て、あの有名なシャーロックホームズも言っていたわ。」冗談を言いながら、気分転換をしたホイルは、無断でその研究を進めてみることにした。 暗い夜の空に光る点があった。その点は徐々に大きくなると共に点滅を繰り返して、信じられない速さで、地面に激突した。焼けこげるにおいと、赤いきらめきが10秒ほど続くと、大きな地響きと天が割れん程の轟音を発した。だが、ここはゴーストタウンが点々と広がるテキサス州である。この落下に気がつく人は、誰もいなかった。何かが落ちてきたように思われたその場所には、地表の土壌は吹き飛び地下の岩盤が溶けてドロドロに変化していた。クレーターのみで何も残っていないように見えた、その時、落下地点の中心部の溶岩が少し盛り上がって来たように見えた。それがみるみる大きくなってきた。そして、中央に小さな黒いひび割れが出来上がると、何かが徐々に現れ始めた。最初は暗闇に混じって、黒くなめらかな表面を持つ、とがった角のような物が現れ、それに続いてオレンジ色の人間の大きさの【塊】が出現した。その塊は周囲の土や草などの有機物質を引きつけ、表面に付着させていった。 老化の遺伝子はテロメアと呼ばれる。DNAの末端にある小さな遺伝子であるが、これが短くなると、もうそれ以上細胞分裂が出来なくなり、細胞は老化を始める。人のテロメアは他のほ乳類より長大であるが、それでも限界がある。しかし、それを乗り越えれば、莫大な富と不老不死を手に入れることが出来るとあって、多くの研究者が、この老化の解明に、熱中していた。研究とはある峠を越えれば、後は放っておいても自然に結論が導かれる物であるが、そこまで達するのが、一苦労である。単細胞や構造の簡単な線虫などでは成功する実験でも、人に置き換えるとなると、非常に難しいし、ここアメリカでは遺伝子の組み換えや操作に関しては自由であるが、彼の地の日本では大臣の許可が必要らしい。それが良いことか悪いことかは別にして、アメリカの方が遺伝子操作については、遙かに進歩していた。 リンダ・ホイルの実験とは、静電気を使って、ほ乳類のテロメア以外の遺伝子の影響を抑えてから、テロメアが長くする酵素を使うというものだった。静電気がかかると、なぜだか、DNAの修復機能が押さえられて、簡単に遺伝子の操作が可能になるであった。線虫を使った実験ではすでに2年も生きている。通常は3週間で寿命を迎えるはずが、2年も生きている。おかげで、通常の大きさは1mm程度の大きさが、10mmくらいに成長している。1リットルほどの透明な培養液の中でたくさんうごめくそれは、あまり気持ちの良い生物ではなかった。身体が小さな時は、はっきりしなかった目が今では黒く2つの点となり、存在を明らかにしていた。 「まだまだ、大きくなりそうね。」 リンダ・ホイルは、光に照らされた保温機の中を、まぶしそうに眺めながらつぶやいた。 「大きくなるだけじゃなくて、進化しているように見えるわ。次は、人間で試してみたいけど、そのためには、被験者を捜さなくては。人間では、制限遺伝子があるから、線虫のように無限に大きくなることは無いと思うけど、できれば、寿命の短い人が良いわ。」 彼女の手元には、ワクシニアウイルス(テロメラーゼ)と手書きされた注射液があった。 * * * 白塗りの古い壁を抜けると、あまり手入れされていない生け垣が続いていた。更に進むと、たくさんの平屋の建物が続いていた。その中で、ひときわ古そうな木造の家には、今年で80歳になるジョン・ボーナムは一人で住んでいた。白塗りの壁は所々穴が開き、応急的に板が乱雑に釘で打ち付けられている。ジョン・ボーナムはここのデッキで、椅子に座り、ぼんやりと外を眺めていた。家の中で電話のベルが鳴る。大儀そうに立ち上がると、やせこけたその身体は自分の体重を支えるのもつらそうで、長い年月が彼の背中は丸くし、手も前にぶら下がるようになった。歩くときはバランスをとるために、手を後ろへ回し、ペンギンのように小刻みに歩いた。あまりに時間がかかったので、電話のベルは、もう少しのところで鳴りやんだ。 「やれやれ、また診療所の看護婦からかな?どうせ、生きているかどうかの確認だろう。」 そう独り言を言っている所に、また電話のベルが鳴り出した。 ジョン・ボーナムは受話器をとった。 「もしもし...」 聞き覚えのある看護婦の声ではなかった。 「私、この地区を担当している保健婦ですが、インフルエンザ予防注射の案内が届いていると思いますが、ご準備はよろしいでしょうか?」 何か一方的な話しぶりに、少し反感を持ったが、そこは久しぶりに聞く、若い女性の声だったので、つい話に合わせてしまった。 「いや、案内は届いていないけど、予防注射をするのかい?」 「はい、ジョン・ボーナム様は先日、診療所に来られなかったので、よろしければこれから家におじゃまして、予防注射をしたいと思います。」 「ああ、ワシはかまわないよ。」 短い話だったが、疲れたようだ。よろよろとソファーに戻り、座り込むと寝息を立てて深い眠りについた。 何時間経ったのだろう。目を開けると、夕日が窓から差し込んでいる。散らかった部屋がこの世とは思われないくらいすべての物が赤く染まっていた。 「やれやれ、いつまでこんな生活が続くのだろう。こんな身体じゃあ、家の中を歩くだけでも息切れがするわい.いっそのことこの世からお別れしたいものだ。」 人にはモゴモゴとしか聞こえないようなか細い声しかでなかった.きょうも1日の半分以上寝ているが疲れがとれないようだ.目の前にある古いテレビでは若いアナウンサーが今日の出来事を早口で話している.この状況ではたとえ宇宙から怪物がやってきても興味がわきそうになかった.もう一度、老人は目を閉じた. ** 次の信号を曲がれば、目的の家である。脇道から、急に自転車に乗った子どもが飛び出してきた。大きなタイヤのこすれる音が響き渡った。リンダ・ホイルが運転するSUVはその直前で停止した。子どもは何事も無かったように通りすぎていった。しかし、勢いで彼女のバッグはシートから車内の床へ落ちてしまった。 「大変!」 あわててバッグの中のアンプルを確認すると、ガラスが割れて中から茶色の液体がアンプルの回りに付着している。リンダ・ホイルはあわててで、アンプルの口をテープで蓋をした。 「もう少しで、あの家に着けるというのに、どうしましょう。でもこれくらいあれば量は足りるかしら?」 夕日に照らされた家の前に黒い車が止まる。リンダ・ホイルは白衣に着替え、家の中へと消えた。 「こんにちは。さっき電話をした保健婦ですが、ジョン・ボーナムさんはいらっしゃいますか?」 奥の方でかすれて弱々しい老人の声が聞こえた。 「ここにはジョン・ボーナム以外は住んでいないよ。」 老人らしいひねくれた返事だった。 「すみません。私、この地区は初めてですので、お顔を知らなくてごめんなさいね。保健婦のウィルソンと言います。」 リンダ・ホイルは嘘を言った。 「さあ、それじゃ、インフルエンザの予防注射をしますね。」 声の明るさが、不自然だったが、この男には医療に勤める人の習性だと思っていた。 リンダはバックから、先が破損しているアンプルを取り出し、男に見えないように、注射器に詰めた。 終始笑顔を見せながら、男の腕にそれは注射された。男は一瞬、痛そうな顔をしたが、やがて元のぼんやりとした顔つきに戻った。 「1週間後にまた様子を伺いますね。」 予防注射の後に様子をうかがいに来ることなんて考えられないが、男には、そんなことを考える能力はなかった。ただ、予定が出来て、良い暇つぶしだと思っただけだった。 * * * オレンジのヒト型の物体は、徐々に形を際だたせていった。いまや背丈は3メートル以上の大きさになり、周囲に吸着された有機体は、人の肌のようにも見える物質に変化していた。そしてまるで人間のように歩き出した。 ドロドロとしたまるで溶けかかったアイスクリームのような物体から、はっきりとした人間のようなモノになった.いやそれは人間そっくりの形であった.大きさが5mあることを除いて.その大きな人間は、通りにぶつかると、周りを見渡した.目は赤く光り、ネコのようだった.暗いところでもよく見えるようだ.肌は灰色で滑らかな感じに鈍く光っていた.髪はなく、その顔つきは無表情で、冷酷な感じがした.建物の影に隠れると、一人の若い女が歩いて、こちらにやってくる.夜も遅くなるとここベルプレイン通り(テキサス州)は寂しくなる.その女は、携帯電話に夢中のようだった.大きな声で嬌声を上げながら、ゆっくりと大男の方へ近づいていった.周りは暗く、大男の体は建物の色にとけ込んでいた.やがて街灯に照らされた灰色の大きな足に気がつくと、ゆっくりと頭を持ち上げた.大男の赤く光る目を見ると同時に、叫びとも悲鳴ともわからないような「あっ!」と短い声を上げて、今歩いてきた方へ急いで引き返した. 女は懸命に走っているが、足が気持ちに追いつかない.「はあ、はあ.」後ろを見たら、追いつかれそうな気がして振り向くことも出来ない.ようやく次のビルの角で曲がって一息つくことにした.息が切れる.足も痛んできた.手を膝について下を向いてやっと呼吸している感じだ.ふと周りが暗くなったような気がした.恐怖でアドレナリンが大量に女の血液の中にあふれた.動悸がする.胸が苦しい.そう思ったとたん気が遠くなり、その場に座り込んだ.薄れていく意識の中で、大男の手が首に触るのを感じた.「さあ、これで楽になるだろう.」女の頭の中で誰かがしゃべった.黒いベールが目の前にかかり、女は灰色の男に押しつぶされているように見えた.そして暗闇. * * * 「ほう、これはどうしたことだろう.」ジョン・ボーナムはうれしそうに歩いていた.「こいつは驚いた.膝も腰も全然痛く無いじゃないか.今までは玄関の階段を上るのでさえ、膝がきしんでいたのになあ.これなら杖もいらないくらいだ.」傍らの車いすを部屋の隅へ押しやると、どっかとソファーに座り、若い頃のようにテーブルに足をのせて、テレビを見る.手には、赤ワインの瓶を握っている.つい最近まで、好きな酒も年のせいか、味が薄いし、アルコールのにおいばかりが鼻につく.ところが、あのインフルエンザの予防注射を打ってから、酒に酔わなくなったようだ.酔わないというより、酒に強くなっている.気持ちよく酔えるのだ.若返った気がして、鏡を見る回数が増えた.しかし、残念ながら、顔のしわの数は減らなかった.鏡の中にはいつもと同じ見覚えのある顔だ.「これで、顔も若返ったならば、死んだばあさんには悪いが、街に出かけて若い子とあそびたくなりそうだ.なんだかじっとしているのが惜しいほど、体に力がみなぎっている.近所のマイクに尋ねてオレの体の調子の良いことを見せつけてやろう.きっと、たまげるぞ.」 ジョンの家からマイクの家までアメリカのことだから、近所と言っても優に4kmは離れている.若い時だったら、納屋にあるトラックをすっ飛ばして行くところだが、目が悪くなり、運転は控えていた.だから、マイクが尋ねてくるのを待つしかなかった.しかし、今のジョンは昔のジョンとは違った.なんだか4kmくらいは歩けそうな気がしたのである.まあ、やってみようと考えた.舗装されていない道を歩くのは、気を抜いたら足をくじきそうである.膝も痛むような気がした.それでもジョンは歩き続けた.思っていたより膝も腰も痛くならなかった.次の丘を超えたらマイクの家が見えるはずだ.そう思ったら、ジョンはいつの間にか、かけ出していた.そう、若い頃のように息を弾ませながら、しっかりとした足取りで、一気に丘を駆け上った. 家のベランダに置かれた椅子にマイクが腰掛けているのが見えた.そのまま走って、マイクの家の前へと滑り込んだ.マイクはジョンだとはわからずに、「はあ、どなたさんだい?こんなとしよりのところに用があると言ったら、役所くらいかのう.まさか近所のジョンはこんなに元気じゃないはずだしなあ.」 そう言いながら、息の上がっている男をじっと見た.「ジョンに似ているが、ジョンのはずはない.あいつはもう歩けないくらいよぼよぼだからなあ.」 「おいおい、マイク、よぼよぼとはひどいな.おれだよ.幼なじみのジョンだよ.」 マイクはびっくりして椅子から転げそうになった.顔は変わらないが、背筋が伸びているせいで、マイクが知っているジョンよりとても大きく見えたのである.いや、実際にジョンは大きくなっていた.家に入ろうとしたら、頭を入り口の上にぶつけてしまったのである. 「マイク、家が小さくなっていないか?」ジョンは言った. * * * 夜の研究所は、普通の会社とは違って、人が多い.しかし、夜の3時ともなればさすがにほとんど人影はない.研究所は4つの棟が四角に並び、中央には円形のプールがあり、そこは夜でも街灯が光っていた.リンダは、今日の研究を終えて、このまま研究所に泊まろうか自宅に帰ろうか迷っていた.明日は研究の合間なので、その気になれば休んでも問題はないのである.リンダの部屋は、北棟の2階にある.実験室のある東棟からは歩くと5分くらいである.リンダは眠い目をこすりながら、北棟へ向かった.渡り廊下を通るときにふと空を見た.新月で外は真っ暗だったが、星がきれいに見えた. 「とても静かな夜ね.」 ふと見た円形のプールが街灯に照らされて青く浮かび上がっていた.しかし、今夜はいつもと違ってすっきりとした色には思えなかった. 「疲れたのかしら?早く部屋にもどって休まないと.」 部屋に着くと、カーテンが動いているのに気がついた.窓が開いていると思って、鍵をかけようとカーテンを開けた.そこには灰色の大きな顔があった.あまりに驚いたリンダは声を出すことさえも出来ずに後ずさりをする.人間の顔ではなかった.その大きさは1m以上、赤い目はしっかりとこちらを見ている.ここは2階なのだ.リンダは気がついた.何という大きさなのだろう.その怪物は手を伸ばして、窓を破った.大きな音とガラスの割れる破片が、リンダを現実に戻した.素早く振り向くと部屋のドアに向かって走り出した.怪物は体の半分以上が部屋に入り込んでいた.リンダを捕まえようと大きく腕を伸ばす.リンダは腰が抜けて動けない.這ってドアへ向かう.怪物は部屋に入れても立ち上がることが出来なくて、同じように部屋の中を這ってリンダの方へ向かってくる.ハイハイ競争である.何度も手を伸ばすが、そのたびにかろうじて避けることが出来た.怪物の手が勢い余って、部屋の壁を突き破った.リンダはようやく立ち上がることが出来て、その崩れた壁の穴から脱出することが出来た. 廊下を走る.走り続けた.怪物が這いながら、それでも速さは人の駆け足くらいである.ガタンガタンとモノが壊れる音がしながら、リンダの後ろから迫ってくる.階段室に着いた. 「このまま階段を下りて、屋外に出ると、怪物にきっと追いつかれるわ.」 裏をかいて上へ向かうことにした.階段で時間を稼いで、何とか建物の南にある駐車場までたどり着くプランを練った. 「アレとの距離は音の様子からすると100mも無いわ.距離をもっと広げるにはやり過ごすしかないわ.」そう思ったリンダは、廊下の突き当たりにある洗面所に駆け込んだ.一番奥の部屋に滑り込み、息を整えた. ズシン.空気がびりびりとふるえる.廊下と天井の壁を次々と破壊して怪物が近づいてくる.振動と音が最大になった.リンダは震える手を耳に押し当てて耐え続けた.幸運なことにそれは洗面所の前を通り過ぎた.徐々に音が小さくなっていった.突然、振動と音が一瞬静まった.何も聞こえない闇の世界.リンダは心細さで、泣き出しそうになった.3年前まで付き合っていた研究所の副主任と別れてから、ずっと一人である.話し相手は仕事場の同僚だけである.家族はオハイオ州の田舎にいるが、こちらから連絡することはない.副主任とは不倫だったがそれなりに楽しい毎日だったと思い出すことがある.今一番楽しいことは、家で飼っているペルシャ猫の相手と、研究だけである. * * * ある日、リンダは製薬会社の依頼で精子の遺伝子解析を行っている時に、偶然、人間を不死にする酵素を発見したのだ.もし、依頼とは違う研究をしていることが会社にバレルと、研究費はたちまち引き上げられるのでこの研究は秘密で行わなければならない.製薬会社は精子の優劣を判定して、優れた精子のみを選別して受精させることを目的としていたのだが、リンダは優生であることが何を持って優生なのかもともと疑問を持っていた.人間の近視的な発想から、IQ、顔やスタイル、運動能力、健康などのパラメーターから自由に選べるようになるらしい.生命誕生から神が行ってきた選別を人間が行おうとしているのである.このプロジェクトにはアメリカの政府機関も絡んでいるらしく、100億ドル以上の予算が出ている. 「そういえば、黒いスーツ姿の男が目につくわね.」テクニシャンのケリーが言った.研究者は大抵、ジーンズにT-シャツなのでスーツを着て、髪をきれいにそろえているとかなり目立つ.主任研究員のロバート・プラントはその窓口になっているため、対応にはとても気を遣っているように見えた.常に愛想良く、黒服の男に対して研究の進ちょく状況を報告していた. 途中からジョーンズ所長が加わった. 「大丈夫ですよ.私たちに任せてください.今年中には完成すると考えてもらってかまいません.」 黒服の男は、表情を変えることもなく 「そうですか.よろしくお願いしますよ.」と低い声で話した. 「失礼かもしれないが、私たちの予算を他に流用していると言うことはないだろうね.」 鋭い目がさらに細めてロバート・プラント主任研究員を見た. 「私たちの計画は国が推し進めている最重要課題だからね.だから贅沢な研究費を出しているのであって、それを流用なんてしたら、君が首になるだけでは済まないよ.研究所がつぶれることになるよ.」 「は、はい.もちろんわかっています.情報は逐一そちらへ報告していますから、どうぞご心配なく.」 政府はアメリカをもっと競争力のある国にするために、優生技術の開発が進めている.その最先端技術が精子の選別である.表向きは「この薬を使えば、あなたの精子から最も優秀な精子を選別しますよ.」と耳あたりの良い宣伝でこの薬品を性交後に、パートナーの膣に入れる.そしてその薬品が最も優秀な精子のみを選び、それ以外の精子を不活性化(動けなくする)するのである.しかし、実はその薬品の中に遺伝子を組み換えるウイルスが含まれていて、劣った遺伝子を組み換えてくれるのである.原理だけを聞けば、なるほどと思わせるかもしれないが、短期間での成果しか考慮していないため、遺伝子の変化が人間の進化にどのように影響してきたのか、未だにわかっていないことをすっ飛ばしているのだ.単純に言えば、賢くてハンサムや美人で病気をしない国民が増えるのだろう. そんな疑問を持ちながらリンダは研究を続けたが、偶然にラットの遺伝子の中で不老につながる酵素を発見した.正常のラットでもその酵素は少量ながら、オスの体内に持っている.ラットとはいわゆるハツカネズミであり、一般的にオスの方が長生きである.リンダはそのオスにしか存在しない酵素を発見し、濃縮することに成功した.普通のメスは半年から1年ほどの寿命であるが、この酵素で処理されたオスは5年以上も長生きをする.しかし、5年後にはハツカネズミとは思えないほど巨大になり、毛の色は白から茶色へと変化する.徐々に凶暴化し、他のラットに対して攻撃的になっていた. 「ふーん、人間も長生きすると体が大きくなるのかしら.すべての細胞で不死化が起こるのなら、すべての細胞がずっと成長を続けるわけだから、そうかもしれないわ.年を取ると骨が萎縮して小さくなったように見えるけど、場所によってはずっと成長し続けるところもあるわね.たとえば軟骨は萎縮することがないから、常に成長して、老人は鼻や耳や喉が大きくなるのはそのせいだしね.これが、すべての細胞に起こるならば、脳さえも成長し続けることになるわ.」 脳が成長を続けることはいずれ究極の脳が出来上がることになる.線虫の場合、それは目であった.人間の場合は...? 一番最後に発達した場所は、新皮質.そこは人間らしさの要と言える想像力、高度の視力、聴力になった.高度な視力とは映画を見られる能力である.下等な動物では、コマ送りのようにしか見えない.それでは、究極の視力とは... ジョンはマイクの家を後にしていた.精気のない老人と話してもつまらないだけだった.話題と言えば、病気と年金、そして孫の話である.話に飽きたジョンは、町に買い物をするからと、車を借りることにした. 「まったく、おいらには興味のない話だったな.おいらには子供も孫もいないし、年金なんて心配しても増えるものじゃないからなあ.それに、最近は病気をしなくなったなあ.」 ガシャン 大きな音を立てて、一台のトラックが中央分離帯を乗り上げて、目の前に現れた. 飛び出した子供をよけようとして、中央分離帯を越えてしまったのだ. 一瞬の出来事なのに、ジョンにはとても長く感じられた.いま、
ジョンの車へ向かっているトラックがどんなコースで通過するのか見えるのだ.まるで予言者が未来を見るように.このままハンドルでトラックを避けないでブレーキだけ踏めばいいことがわかった.ジョンは余裕を持って、そのように実行し、何事もなくそこを通り過ぎた. 「ふー、驚いたね.でも、未来が見えるなんておいらの目はどうかしちゃったのかな?まあ、見えない訳じゃないから、眼科で見てもらうこともないかな.」 ジョンのおんぼろ車をビュンビュンとたくさんの車が追い越していく.しかし、それが急にゆっくり走り出した.いや車は時速80km以上で走っているのだが、ジョンの目にはゆっくり映るのだ.さらに、影のようにその車がこれから進む方向が見えるのだ.方向指示器をあげる前から、その車の曲がる方向がわかり、車が止まる前から、止まる位置が見える.変な感じだった.ジョンはその人の心で思っていることがわかるわけではないが、どのように動くのかが見えるのだ. やがて目の前に小さなドライブインが見えた.デニーズの食堂と書いてある.最近、ジョンは無性に腹が減るのである.目の前のドアをゆっくりと開けるとギーと大きな音がした.一斉にこちらを見る客たち.ジョンは少しも臆することなく、カウンターに向かった.一つ小さな咳をすると店員がやってきた.「へい、旦那、何にする?」 「そうだな、ステーキとキャベツのチリソース炒め.すべて大盛りで頼む.」 「飲み物は何にするかい?」 「じゃあ、ポートワインだ.」 食事が運ばれてくるやいなや、ジョンは空腹をやっつけるために、味わうのも惜しんでひたすら口へ運んだ.ようやく空腹が収まったのは、追加の鳥のもも肉を平らげた頃である. 「へへへ、旦那、よほどお腹がすいていたようだね.」 「ああ、そのようだな.あと、この店のおすすめはあるかい.」 「おすすめはあるけど、見たところ旦那は初めての客だし、ちょっと先払いしてもらえないかな?今までのの食事分でも50ドルは超えているぜ.」 「じゃあ、今日はこれで帰るよ.」 「へい毎度あり.全部で52ドルになるよ.でもまあ初めての客は大事にしないと..な.50ドルにしておくよ.」 「悪いな.持ち合わせがないんだ.付けにしておいてくれ.」 「旦那、ここは初めてだろ.付けは効かないよ.」 「おい!」店員が少し語気を強めた. 「黙っていないで、金を払いな.」 ジョンは其れには答えず、店から出ようとした.店員がどこかへ電話をしている.「もしもし、保安官事務所ですか?ええ...無銭飲食をした野郎がいるんですが....はい....よろしくお願いします.」 店員はジョンの前に立ちはだかり、肩をつかんだ.「もうすぐ、保安官が来るぞ.おとなしく代金を払うか、それとも豚箱にはいるか、自分で決めな.」 「だから付けにしろと頼んでいるだろう.」ジョンは店員の手を払いのけた. 店員は相手が老人だと思い、見くびっていた.ジョンは店員のあごに軽く一発お見舞いした.店員は勢いで後ろへ倒れそうになる.店員はみるみる顔を赤くして、殴りかかってきた.店員の背はジョンと同じくらい、体重も同じだ.違うのは、年齢が30代ということである.しかし、今のジョンには振りかざした店員の拳が影となってゆっくりと向かうのが見える.少し、右へ体をずらすと店員は勢い余って、ジョンの後ろへと飛んでいった.店の中の5,6人の客たちは、ワイワイ騒ぎ出し、おもしろいとばかりジョンと店員を取り囲んだ.ますます店員はエキサイトし、近くにあったシャベルを手にした.そして、ジョンの頭に向かってシャベルを振り上げた.振り下ろされる時、誰もがジョンの無惨な姿を想像した.額から血を流して、地面にゆっくりと倒れる老人.しかし、ジョンは振り下ろされたシャベルを楽々と避け、店員の左耳のあたりにカウンターの一撃を加えた.よろめいた店員は思わずシャベルを手放した.ジョンはそれを取り上げると、反対に店員に向かってシャベルを振り下ろそうとした. バーン.大きな音が店の中に響き渡る. 銃声であった.火薬のにおいが店内に広がった. 「よーし、そこまでだ.おい、おまえ、そのシャベルを捨てろ.おとなしくしないと、今度は空砲じゃすまないぞ.」小太りの保安官と助手がそこにいた.助手がジョンの方にやってきて、シャベルを取り上げる.ジョンは驚いた顔を見せおとなしくなった.しかし、おとなしかったのもそこまでだった.出入り口は保安官がいるから、使えない.ジョンは従業員の出入り口に向かって走り出した.後ろで大声がする.「止まれ、止まらないと...撃つ.」と言うが早いか、保安官はジョンの足に向かって発砲した.はずれた.もう一発撃つ.またはずれる.おかしい.こんなに当たらないのは初めてだ.もう一度ねらいを付けて、撃った.ジョンはすでにそこにはいなかった. 保安官たちはジョンの後を追って、勝手口から店の裏庭に出た.店の裏はゴミ置き場で、廃車された車や、収集されずに残ったゴミであふれていた.その奥には小さな物置小屋がある.ジョンが走っている気配がないため、どこかに隠れているに違いない.そう考えた助手と保安官は慎重にその納屋に拳銃を構えながら近づいていった.表の戸は閉まらずに、風に吹かれてがたがたと振動していた.中へはいる.窓からの日差しだけではほとんど室内の様子はわからない. 「おい、車からライトをもってこい.」保安官が助手に向かっていった.保安官は一旦納屋の外に出た.納屋の出入り口は一つしかない.地面には入り口には足跡は一つしかなく、出て行った足跡はない.「やつは必ず、ここに隠れているはずだ.きっと捕まえてやる.」普段の運動不足があるのかもしれない.この小太りの保安官は息がまだ整わず、ハンカチで顔を拭いていた. その時、遠くで何かが倒れる音がした.助手がライトを手にして戻ってきた.急いで納屋の中へと入る.ライトを照らすと果たしてジョンが床に倒れていた.ライトでその顔を照らすと顔は死んでいるかのように白かった.「こいつ、こんなに大男だったか?」保安官が言った. * * ズシン、ズシン.一旦小さくなりかけた音が、また大きくなり始めた.「こちらへ、引き返している.」リンダは自分の心臓が高鳴るのがわかった.緊張を恐怖によるアドレナリンが分泌されはじめた.怪物はリンダの隠れている婦人用洗面室の入り口を破壊しはじめた.グシャ!入り口に一番近い個室が壊された.ジャー!水道水の噴き出す音がする.そして次の個室.そして次...ガシャン!最後の個室も怪物のハンマーのような腕で壊された.あふれ出した水道水で床はすっかりぬれていた. ドキドキ... リンダは隣の個室が壊された時に覚悟を決めた.どうせたたきつぶされて殺されるのなら、出て行って怪物の隙をねらって逃げようと思ったのだ.そして飛び出そうとした瞬間に、またあたりが静かになった.ズシン!.ズシン..ズシン...やがて怪物の音が小さくなっていった.そいつの腐ったようなにおいを残して.そう、リンダが隠れたのは、一番奥の掃除用具置きのロッカーだったのだ.まさかこんな小さな部屋に人間がいるとは思わなかったに違いない. 「ようやく、去ったようね.でも油断が出来ない.私を追いかけるやり方を観察すると、結構高度な知性を持っている気がするわ.」洗面室は怪物に天井を壊されたせいで、蛍光灯が点滅を繰り返し、非常用の緑のライトがリンダの横顔を照らしていた. 「ここで休んでいる暇は無いわ.深夜とはいえまだ、何人かの研究員が残っているはずよ.早く正面入り口の警備員に知らせて、警察を呼んでもらわなくちゃ.」リンダは切り傷や打ち身で痛む足を引きずりながら、隣の部屋の電話を取った.電話の回線はつながっているようだ. 直接警察に連絡したいが、研究室の電話は外線にはつながらないのである.何度かけ直しても、警備室は出なかった. リーン...リーン.規則正しい電話の呼び出し音が警備室に響いた.しかし、人の気配はない.血が床に流れている.警備員は怪物につぶされていた.その手には拳銃を持ち、硝煙が立ち上っていた. リーン...リーン.「おかしいわね.どうしたのかしら?こうなったら、やはり自分で連絡を取るしかないわ.携帯を手に入れるには自室へ戻らないと.」リンダは用心深く、廊下に出ると耳を澄ました.遠くで悲鳴が聞こえたような気がした.リンダは再び恐怖で緊張した.がれきに注意しながら、少しずつ前に進む.足が痛む.骨折したのかもしれない.エドワード研究室.「まあいいわ.ここに何かあるかも.」リンダは打ち破られた壁の穴からその研究室に入った.暗い部屋で何かを探すのは難しい.「非常用の懐中電灯がドアの近くにあるはずだわ.」そう考えて手探りで前に進む.足で柔らかいものを踏んだ気がした.はっとして、手で触れようとすると人が倒れていた.暗くて誰かわからない.体つきから女性のようだった.体が温かい.どうやら死んではいないようだ. 「ちょっと、起きて、目を覚ましてちょうだい.」リンダはその女の体を揺すった.そのとき再び怪物の動きが止まり、静寂が訪れた.リンダは気がついた.もしかしたら怪物は、音を探っているのだと.そしてその音を聴く能力は極めて高いと言うことが. 再び、建物を震わせる音が近づいてくる.リンダはとっさに机の上にある電話機を取り、どこかへ電話をする.リーン...リーン...遠くの方で電話の呼び出し音が鳴る.怪物はその電話が鳴り続けている部屋に向かって方向を変えた.ガシャン、メリメリ...部屋のドアが壊される音がした.リンダは受話器をあげたまま、部屋の中を探しようやく目当てのガムテープを見つけた.それで足首を固定するためだ.立ち上がって、歩いてみた.何とか痛みは我慢できるようになった.怪物が気を取られている間にと思って部屋の外に出ようとした.そのとき、呼び出し音が止まってしまった.怪物に壊されたようだ.あたりに再び静寂が訪れた.リンダはもう一度さっきとは別の部屋に電話をかけた.再び呼び出し音が響き渡る.それに合わせて怪物の動き出す音が聞こえた. リンダは思わず笑いそうになり、口を押さえた.「バカなモンスターね.」心の中でささやいた.怪物が架空の獲物を求めて暴れている間に、リンダは廊下へ飛び出し、階段室へと向かった.ここの階段室は吹きさらしである.リンダは外の空気を吸い、少し開放された気分になった.駐車場まであと100m. *** 薄暗い部屋で、目を覚ます.頭がぼんやりしている.はっきりと目が見えてきた.白い天井が見える.しかし、体は全く動かない.どうやらベルトのようなモノでベッドに縛られているらしい.ジョンは渾身の力を込めた.しかし、このベルトは外れそうになかった.ふと横を見た.点滴で何か白い液体がジョンの体の中に注がれていた.それ以外にも、体にはいろいろな線がつながれているのに気がついた.壁には出入り口が一つだけである.それ以外には小さな窓があるが、外の景色は見えない.たぶん監視用だろう.少しでもジョンの体が動くたびに、近くにある小さなランプが青から赤に変わる.この部屋で動く物体を検知しているようである.しばらくすると、ガチャンと重そうな音がして厚いドアが開いた.5,6人ほどの白衣を着た男が入ってきた.ジョンを動物だと思っているように、誰も「ご機嫌いかが?」なんて挨拶をする人はいなかった.ただ、器械の数値を見たり、くくりつけているベルトの点検をしていた.ジョンはふざけた男たちだとは思ったが、自分の置かれた立場も理解できた.「こいつらはおいらのことを実験用のモルモットと思っているらしい.」 一人の男がジョンの近くにやってきた.「不自由な思いをさせて悪いが、もう少しの辛抱だからな.それが済んだら楽にしてあげよう.」その男は心が凍り付くような薄笑いを浮かべた.こうしている間にもジョンの体は変化を続けた.すでにここに来てから、体は10cm以上大きくなり、やがて拘束用のベルトもきつくなってきた.白衣の男が、ジョンのベッドから離れるように伝えた.ブウーン.器械のうなり音が大きくなり、その男が、何かスイッチを押した.突然のショックがジョンを襲った.一瞬で意識が遠くなり、そして深い暗闇へと続いた.次の瞬間に目の前が明るくなった時ジョンは生まれ変わったような気分だった.しかしそれもつかの間、体の自由がきかないことが意識されると、ジョンは現実に戻ったのである. 「やはり、5000ジュールでは効果は無いようです.」 「そうか、次は1万ジュールまで上げてみてくれ.」 「しかし、それでは、組織の一部が壊死するかもしれません.」 「ふん、それも仕方がないだろう.死ななければ良いんだよ.」 「今度、開発されたOPTIMを使ってはみては?ジョーンズ所長.」 「それは良いかもしれないね.とにかく、不死化するのは確認できたが、不死化が止められないのも困るわけだ.彼も実験動物としてはなく、何か意味を持って生まれてきたのだから、人の役に立たなくてはならないのだよ.」 「常に大きく成り続けるというのはどういうことでしょう?所長.」 「植物が生存している限り成長し続けるのと似ているととらえれば、彼は先祖返りしているのかもしれない.テロメアとは植物から動物に変化した時に現れた遺伝子だろう.もしくは子宮内で起こる現象と同じかもしれない.子宮内では動物の成長の99.9%が起こっている.つまり生まれた時はほとんど完成状態に近いといえる.」 突然、アラームが鳴り出した. 「何のアラームだ.」所長がうるさそうに叫ぶ. 「モーションセンサーのようです.」 「何を言っている.部屋には動くものは何もいないぞ.」 研究員たちはぎょっとした.部屋には何もいないのである.いや見えないのかもしれない. 「機械の故障じゃないのか?」 研究員ロバートがふとジョンが寝ているベッドをみた. 「所長、ジョンがいません.」 「そ、そんなはずは...」 研究員が驚いて目をさらにして、部屋をくまなく見た.しかし、白い部屋には何も無いのである. 「おかしいぞ、いないはずがないんだ.」所長の声は引きつっていた. 「ハロセンガスを投入しろ!」 シューという透明なガスが部屋一杯に広がった.いや目には見えないから、広がったはずである. 「ガス濃度をモニターしろ!」 「今のところ、10ppmです.」 「よし、さらに100ppmまで増量だ.」 ガスの注入音以外は観察室からは何も聞こえない.みんな少しの音も聞き逃さないように気をつけている. 「モーションセンサーはどうだ.まだ反応があるか?」 「いえ、今のところありません.」 「目で見えないというのはどういうことだ.」所長は研究所の所員の手前、威厳を保ちたいが不安がそれを押しつぶそうとする. 「プラント君、武装した警備員と一緒に中に入って確かめてくれ.それから、赤外線カメラを持って行った方が良い.」 プラントの心臓は高鳴り、今にも倒れそうな気分だったが、何とか立ち上がり、警備員を2人前に立たせた.開閉スイッチを入れると、重い銀色のドアをゆっくりと開いた.白い部屋の明かりが、観察室の中に広がっていく、一瞬、その明かりが暗くなった気がしたが、誰も気にしなかった. 人間の神経細胞は1秒間に100回が興奮できる限界である.情報はどんなに頑張っても1/100秒おきにしか脳へ送れない.つまり100分の1秒以内に起こることについては、感じることができないのだ.もし、ある物体がそれ以上の周期で振動していたり、動くことが出来れば人間の目で見ることは出来ない. 「おかしいですね.さっきまでモーションセンサーに反応があったのですが...」 手に持てるくらいの大きさの器械を前にかざしながら、プラントはつぶやいた.と同時に、後ろの方でエレベーターのドアが開いた.誰も乗っていないエレベーターがそこにあった.やがて、ドアが閉じると上へと向かった. 「しまった.エレベーターの中に誰かいるぞ.早く上に連絡して、やつを捕まえろ.」所長は叫んだ. らちがあかないと思ったのか所長は自ら電話を取ると話した. 「1階の警備主任を呼べ.私だ.ジョーンズだ.よし...準備してあったあれをエレベーターの中に噴射しろ.中に誰も乗っていないように見えるが、かまわないから空になるまで全部噴射しろ.なに、死んでもかまわん.外に出られて手が付けられなくなるよりはましだ.責任は私が取る.」 *** 1階のエレベーター前 20人以上の屈強な男たちが、その周りを取り囲んでいる.一列目には火炎放射器のような筒を持った男たちが腰を低くして待ちかまえている.一番外側にはサブマシンガンを持った男まで準備されていた. エレベータのドアが開く.中には何も乗っていなかった.しかし、命令通り一斉に5つの筒の先から白色の...ガスが噴射された.一気に当たりの気温は氷点下まで低下し、エレベータ内は凍り付いた.それでもひるむことなく、噴射し続けた.当たりは真っ白になり、ほんの先の視界も失われてしまった. 「おい、何か見えるか?」警備主任のハロルドが言った. 「いや、何も見えません.」噴射を行ったエドワードが答えた. 「え、ちょっと待ってください.何かが見えます.」 灰色の2mくらいの固まりが、床に転がっているようだ.よく見ると小刻みに震えている.更に白い霧が晴れるとそれはジョンだった.さっき地下の研究室で見た時よりも、ずいぶん小さくなったように見えた.筋肉隆々の体が今では普通の人間のように見えた. 「おいおい、これのどこが怪物だって言うんだい.ジョーンズ所長は大げさだなあ.」 主任のハロルドは安心したのか朗々と話した. 次にジョンを見たのは、元の地下の拘束室だった. 「おい、おまえら、俺をモルモットにするのはやめろ.実験動物だってもっと大事にされるぞ.動物愛護団体へ訴えてやる.」 暴れるジョンをもっと強力な金属の拘束具が縛り付けていた. ジョンは裸なので、すべての体の様子が観察室から見ることが出来た.なぜか彼は勃起していた. 「くそっ、こんな目に合わせやがって.おいらはもうだめだ.もう死ぬんだ.その前に子供がほしかった.何も残せずにこの世を去るなんて耐えられない.」 しかし、ジョンにはすでに3人の子供と、8人の孫がいたのである. ** 駐車場まで後100m... リンダは走った.普通に走れば20秒もあればたどり着く距離なのに...すでに、足も腰も痛めて思いっきり走れない.それに加えて、恐怖で腰に力が入らないのである. 突然、目の前に黒い影が飛び出した.あっと言うまもなく、リンダは道の脇の芝生へと倒れ込んでしまった.何が起こったのかと、気を取り直してその黒い影を見ると、警備員のジミー・ペイジだった.ペイジは拳銃を上に向かって発射した.その先には、あの大きな怪物がいて、まさにリンダに飛びかかろうとしていた.弾丸は怪物の腹部に当たった.グオーという叫び声を上げて、怪物はお腹を手で押さえた.人間と同じ赤い血が流れていた.しかし、怪物の怒りは激しくなった.今度はページに向かって走り出した.もう一度拳銃を撃った.今度は肩と胸に当たった.しかし、怪物はひるまず、ペイジをその大きな手で横へ吹き飛ばした.ペイジは止めてあった車のフロントガラスに激しくぶつかった.ウッという短い叫びの後、動かなくなった. 再び怪物はリンダに向かって歩き始めた.リンダは逃げようとするまもなく怪物に捕まった.そして、ショックで気を失ってしまった. 「ここはどこなの?」リンダは暗闇の中で目を覚ました.怪物はそばにはいないようだ.起き上がって、窓のそばへ行こうと歩き出したとき、何かを踏んだ気がした.「痛い!」女の声がした.よく見ると顔は埃で汚れているが、若い女のようだ.リンダと同じくらい元気そうに見えた. 「あなたは誰なの?」女が聞いた. 「わたしはリンダ、リンダ・ホイルよ.」 「アンドレア・コリンズよ.よろしく.」 「他にも、ここには誰かいるの?」 「いいえ、今のところ私たちだけみたい.」 「わたしがここに連れてこられたときは、もう殺されると思っていたけど、アレがあなたをまた連れてきたのを見たら、殺すつもりはないみたい.とても大事そうに扱っていたわ.暗くて見えなかったけれど、アレはあなたに何かをしていたみたい.」 それを聞いてリンダは思わず身震いがした.急いで体中を調べてみた.すべての体は動くみたいだし、痛いところもない.しかし、下腹部に違和感を感じた.黒のスラックスと下着が無かったのである. 「あなたも下着が脱がされていたの?アンドレア」 「アンでいいわ.そうなのわたしも下着が無くなっていたの.でも、どこにも痛みがないから、アレは何をしたのか心配になるわ.」 よく目をこらすと、下着とスラックスは埃まみれの床に見つけた.それを穿くと再び窓際へ向かった.今は何時くらいだろう.月の傾き方を見ると明け方近くか?あの騒動からまだ1時間しか経過していない.ヤツもすぐそばにいるに違いない.迂闊に外に出ればすぐに見つかるに違いない. リンダは、窓を音を立てないでゆっくりと開けた.月明かりが、部屋の奥へと差し込む.その光をたどって奥を見ると、崩れかけた壁と全く呈をなしていないドアがあった.アレはここから出入りしているようだ.窓から見るとここは3階だ.目の前に舗装された道路と歩道があるが、穴だらけである.向かいのビルやその隣になる家も明かりは見えない.街灯も付いていない. 「誰か人はいないのかしら.」ここから見渡す景色は、どこまでも暗闇だけだ.不思議なことに虫の声が今夜は聞こえない. アレの気配もない.リンダは部屋の中を忙しく歩き回った.やがてカーテンとシーツを見つけると、それを手際よくロープに加工した.窓際に近づくとそれを手すりに結びつけ、下へ垂らした.何とか2階のベランダに届くようだ.アンもそれに続いた.2階から下の歩道へはそのまま降りることが出来た. アレは近くにはいないようだ.2人は足音を立てずにそっと向かいのビルの影に隠れた.監禁されていたビルの3階は、所々窓が割れて、外壁も一部が崩れていた.1階は食料品店だったようだが、バリケードのように冷蔵庫や壊れた机やいすが放置してある. 「北に向かえば、国道に出るみたい.」リンダを先頭にして、足音を立てずに歩いた.2階建ての民家を過ぎると、レストランらしい平屋の建物があり、その入り口が激しく壊れていた.そのまま通り過ぎれば良かったが、リンダは研究者らしく好奇心が恐怖に勝ったようだ. 「よしましょうよ.こんな所へ入るのは.」アンが強く反対した. 「ちょっとだけだから、もしかしたら、役に立つものがあるかもしれないから.」とリンダが振り返って説得しようとした.月はずいぶん高いところにある.うっすらとアンの白い服が浮かび上がる.するとアンの青白い顔がかたまった. 「あれは何?」アンが言う. 「え」と後ろを振り返るリンダ. そこにはアレがいた.顔をこちらに向けて、こちらをじっと見つめていた. アレとの間には5mもない. リンダは頭が真っ白になった. エピローグ 「父親になった気分はどうだい.」ブライアンが、助手席に乗っているデニスをからかう. 「こればっかりはなってみないとわからないぜ.政府が配っているシンデレラという薬を使ったおかげで、とても良い子が生まれたよ.なんと言っても、必ず健康で頭の良い子が生まれるのだから安心だよ.」 「俺の姉貴もその薬で、確か3人の子どもを生んだけど、確かにみんな優秀でハンサムなんだ.俺たちの頃より、更に洗練されているような気がするけど.」 「ああ、毎年改良されて新製品が出てくるから、そうなるよな.」 前方に白い建物が見えてきた.右に緩やかなカーブしている道路の先にあるのが、エド・サリバン産婦人科病院である.車を降りると、ブライアンとデニスは妻のグレースに会いに第3病棟へ向かって歩き始めた. 50年前のあの2つの事件は国民の記憶からすっかり忘れ去られた.政府もほとんどそのことについては報道しないようにマスコミへ圧力を加えたと言う噂もあった.報じられているのは、インフルエンザワクチンの副作用で、脳に障害を起こした老人が死亡したという話と、ハムステッド研究所でテロがあって、研究職員のリンダ・ホイルが重症を負ったと言う事件である. ジョンは拘束されて、体が弱ってしまい、そのまま死んでしまった.地球外の生物も、原因不明だが、体が弱り発見された時には死んでいた. リンダとアンはその後軍の病院へ隔離され、詳細な検査を受けた.その結果、地球外生物のDNAが卵子に混じっていたようだが、細胞分裂を起こすには至らなかった.そしてアレのDNAは人間のものによく似ていた. 政府が開発した遺伝子改善剤はその後大きな副作用が見つかった.遺伝子を最適化して不老不死に近くなると、体が大きくなり、いろいろな特殊能力を発揮しはじめるが、脳がそれについて行けない.やがて大脳の抑制が無くなり、本能で行動するようになる.つまり人間から動物へと逆戻りする.政府はそれを防ぐ方法として、人間に強力なストレスを与え、更にテロメア分解酵素を定期的に注射することで解決した. 「子どもが健康になって、予防接種をしなくても良くなったのは良いけど、また違う注射をしなくちゃだめだなんて、なんかおかしくないか?」デニスがエレベーターの中でブライアンに話しかけた. 「それから、強力なストレスが必要だと言うことで、体罰が認められるようになったけれど、これって100年前に戻っていないか?」 「でも、ストレスを与え続けないと、まずいことになるらしいよ.」 「まずいことって何だい.」 「噂では、伸長がどんどん伸びて、暴れ出すらしいよ.反対に体が弱ると、子孫を増やしたくなるらしいねえ.植物でも栄養が良くて自分が成長している時には、実や種を作らないけれど、剪定されたり、幹を縛られると実を付けると言うじゃないか.それと同じみたいだ.」 「そう言えば、人間にも当てはまるんじゃないかな?親が自分の限界がわかると子どもに期待をかけるからな.」 「俺も、疲れた時の方がアレが元気だ.」 優生化政策はほとんどの人々には受け入れられたが、それに反対する集団もいくつか見られた.そのサブカルチャーをリリパット(小人)と呼ばれていた.彼らは遺伝子改善剤を拒否し、昔のままの生活を続けた.遺伝子の改良を受けた人たち(オプティマ)とは、外見、体力や知力が劣るため共存は出来ない.そのため都市部の周辺に、居留地区として政府が認めた場所にだけ住むことを許された.オプティマの寿命は理論上は永遠であるが、注射によって抑制され100-120年である.また病気は消滅し、死亡原因の1位は老衰であり、2位は自殺、続いて殺人、事故死だ.時々、定期的な注射を拒否して、巨大化して凶暴になるオプティマが現れ事件になった. 「地球外でも遺伝子の最適化を行なわれ、逃げ出したやつが地球をめざしたのかもしれないなあ.」とブライアンが独り言のようにつぶやく. 「1234号室.ここが妻の病室だ.」 個室の銀色の扉を開けると、顔の整った利口そうな赤ちゃんを抱いた美人の女がいた. |
|||
|
初めまして。みんなは、オイラのことを全然知らないと思うけど、これからゆっくり説明するから聞いておくれ。つまらないとか、途中で嫌になったら、止めてもいいよ。 生まれは、今でも昔の風習が色濃く残っている田舎だ。家の周りは一面の田んぼと、ちっちゃな川がぐねぐねとその中を走っている。人は住んでいるのかって?もちろんいるさ。ここいら一帯には、二種類の人間しか住んでいねえ。オイラの一家とそれ以外の一家だ。違うところは、オイラの一家は大人だけじゃなく子供も働いているんだ。とうちゃんは「わが家は税金をたくさん払わなくちゃいけないから、大変なんだ。贅沢するな。節約しろ!」といつも言っていた。オイラの家はたくさん土地を持っているし、それを人に貸したりもしている。土地や家を借りている人が地代を持ってくるけど、それでも金に困っているとその時は信じていたね。 ある日曜日、休日は農作業か、庭の草むしりがオイラの仕事だ。どうしても休みがほしくて、サボって家の手伝いをしないで部屋にいたら、とうちゃんが怒鳴り声を上げながら、やってきた。オイラは怖くて、ちょうど茶の間にいたばあちゃんの後ろに隠れたけれど、その日は一日中しつこく文句を言われた。かあちゃんはそれを見ていたけれど、一度も助けてくれたことはなかったなあ。唯一、オイラの見方になってくれたのは、ばあちゃんだった。とうちゃんも、ばあちゃんの前ではオイラを痛めつけないから、とても心が安らいだね。かあちゃんはちょっとでもオイラの肩を持つと、とうちゃんから「お前はどっちの味方なんだ。」と叱られ、それ以上何も言えなくなるんだ。もし、ばあちゃんが居なかったら、オイラはロボットのように育って、人に対して感情を持てず、冷酷な政治家(社会的に適応すれば)や犯罪者(適応しなければ)になっていたかも知れない。条件付きでしか、自分は愛されていないと思っていたから、勉強ができて、家の仕事をしないと、この家では大事にされないと思ったよ。だから、認められようと頑張った。従順で成績がよければ、家の長男として、ちやほやされるんだ。簡単に言えば、憎ったらしい馬鹿はいらないってことさ。 かあちゃんは、近くの役場に勤めていたんだ。朝食の準備と洗濯がかあちゃんの仕事だ。いつも忙しそうにしている。ある日、オイラのシャツを部屋に脱ぎっぱなしにしておいたら、突然、とんでもなく怒られたことがある。「こんなに行儀の悪い子は、この家の子じゃないよ。」てね。オイラはびっくりして、固まってしまった。こんな風だから、この家では、オイラの感情よりも、効率や秩序が大事だったのさ。オイラにしたら小さなことで叱られるから驚いたんだ。意外なことで大人たちを怒らすから、いつもオイラはストレス満タン。でも、洗濯物は洗濯カゴに入れることにした。まあ、これでオイラも少しは大人になったというわけだ。 オイラには2歳年下の妹がいたんだ.頭が良くてオイラとカルタをするといつもオイラより速く札を取るんだ.なぜそんなに時も覚えていないのに,札を速くとれるのか聞いたことがあった.絵を見れば分かると言われた.オイラは覚え始めた字でカルタの札を探していたから,妹には追いつけなかったってわけさ.でも,オイラが5歳の時,突然病気で死んじまった.それ以来,家族のオイラに対する態度が変わったんだ.ほしくもないおもちゃをたくさん買ってくれたり,急に大事にされるようになったんだ.でも,それも長くは続かなかったね.その3年後に次の子が生まれたんだ.でもその3年間はとても幸せだったような気がする.でも,次の子が生まれたら前に逆戻りだ.家の仕事を次々とやらされて,遊ぶ暇もなくなったね.でも,家族の一員だから,不平や不満を心の中に持つようなら,オイラが悪いんだと思っていた.いつも自分ばかり責めていたから,親の許可を得ないと何にも出来ない子供になっていたんだ.かあちゃんは,とうちゃんやこの家の不満をオイラにぶつけてくる.機嫌が悪いと,足音がうるさいだけでも怒られた.それ以外の時はオイラの面倒をよく見てくれたけれど,精神的には不安定だから,オイラの心も不安だったよ.次に生まれた妹は,かあちゃんにとっては自分の心を何でも打ち明けられるいい話し相手だったみたいだ.つまり,かあちゃんのかあちゃんてわけさ. いまでもとうちゃんのまえでは、悪ぶって、仏頂面をして、わざと利己的なことを言ったりするけど、足は震えているんだ。それは、自分の中の、自分がいなくなってしまいそうになるからさ。とうちゃんはオイラが意見を言う度に意志をくじこうとばかりする。それくらいして当然なほど、とうちゃんはオイラとは比べものにならないくらい立派な人なんだろうと思いたいんだ。オイラの頭がおかしくなって、馬鹿なこと口走らないしまわないかぎり、オイラの意見を聞いてくれそうにない雰囲気があったなあ。その頃から、人前でおかしなことを口走ったり、突然精神病者のように暴れ出さないか、自分のことが心配だったよ。 オイラが小学1,2年の頃かなあ。親戚の家で留守番したことがあったんだ。とにかくオイラはいつもひとりぼっちで、学校から帰っても、親戚に預けられることが多かったね。ところが、そこで親戚の家の留守番も頼まれることになったんだ。詳しいことは良く覚えていないけれど、オイラはその家から100円を盗んだらしい。かあちゃんから「叔母さんから、あんたの家では、泥棒がいるのか?」と言われたと、何度もオイラに叱るのさ。たぶん、とうちゃんからも、こってりと怒られて、農作業小屋に閉じこめられたはずだが、幸運にもあまり覚えていない。お金が欲しかったと言うより、100円札しか見たことの無かったオイラには、100円玉が珍しかったからなんだけどね。 それから3年くらいしたある日、学校から帰ると、とうちゃんの顔写真が印刷された紙がたくさん家の中に置かれていた。字が書いてあるけれど、よくわからなかったね。オイラは頭が悪くて、まだ漢字が読めないんだ。ただ今勉強中ってわけだ。実際、学校で教科書を読むのは大嫌いだが、漫画は大好きだから、それを読んで字の勉強だ。だから普段使わない漢字ばかりが得意になって困る。教科書もふりがなをふってくれるとありがたいねぇ。おっと、家の中の謎のチラシの話を忘れていた。そのチラシは選挙ポスターと言うらしい。とうちゃんが村会議員に立候補したんだ。近所の人たちがこれから忙しくなるから大変だぞとオイラの顔を見るたび、話すんだ。これ以上、毎日忙しくなるかと思ったら、憂鬱になったよ。早く隠居したいなんて、子供ながらに思ったね。でも、あと50年くらい先かと思ったら、あまりに遠くて考えるのをやめてしまったけどね。 しばらくしたら、近所で同姓の人が立候補した。名前が違うから、大丈夫じゃないかとオイラは思ったけれど、投票で姓しか書かない人もいるから、票が損すると大騒ぎになった。ついに、同姓の立候補者の所へ押しかけて、やめるように話してきたらしい。ついに、その人は立候補をあきらめたから、めでたしめでたしてわけさ。選挙が始まったら、オイラの家は正月のように賑やかだったな。朝起きると、台所には知らない人が、朝食を作っている。正確にはオイラの朝食ではなくて、他の人の朝食みたいだ。煮物とおにぎりがずらりと数え切れないくらい並んでいる。それを見ているだけで、オイラのお腹はもう一杯。「いっちゃん、好きなのを選んで食べてきね。」近所のおばちゃんがなんだかうれしそうにオイラに話しかけてきた。できたての温かいおにぎりを一個だけもらって、ごちそうの並んだテーブルの片隅でいただいた。 一週間後、とうちゃんは当選したが、その後は意外なことに、家の中がとても落ち着いたんだ。とうちゃんが議員の仕事で忙しくて、オイラのことをこき使うことが無くなったんだ。おかげで、日曜日はのんびりできるってわけだ。でも、たまにとうちゃんが家にいると、朝早くたたき起こされる。仕事は無いけれど、オイラがのんびり寝ているのが気に入らないらしい。オイラもなんでこんなに毎日眠いのかわからないけど、きっとそんな年齢なんだろうね。じいちゃんは寝られないと言っている。選挙の時に、友達の家に泊めてもらったことがあるけど、あいつの家の夕食はおいしかったなぁ。あいつの家にずっと住んでいたら、オイラもきっと太るんじゃないかな。 楽しくてのんびりした生活も、やがて終わってしまった。とうちゃんが村会議員を辞めたんだ。なんでもじいちゃんに家の仕事をするように言われたらしい。この家の仕事をすると、知事より給料がもらえるぞ、と説得されたのが決定打だったらしいよ。とうちゃんは短気だから、なかなか仕事が続かない。取引先をよくけんかをして帰ってきた。帰ってくると決まって「家の戸締まりをしっかりしておけ。けんか相手が押し込んでくるかも知れないからな。」なんてオイラや女たちをおどかすってわけだ。女子供には威張るけど、本当は怖かったに違いない。けんかばかりしているから、普通の仕事は出来ない。それで、じいちゃんが見かねて、村会議員にしたってわけさ。これなら、評判も上がるし、はくもつくってもんさ。 とうちゃんが議員を辞めて、家でぶらぶらするようになった頃、オイラは家を出たから、大変な目には合わなかったけれど、たまに家に帰ると、やっぱり朝早く「いつまで寝ているんだ!」なんて怒鳴られた。しかめっ面がとうちゃんのふつうの顔だ。オイラを見て笑っていたことなんて滅多にない。ニコニコしているのは金がたんまりと入ったときか、他人から褒められたときだ。笑顔をオイラに見せるのは損だと思っているのかも知れない。それでも他人にはいい顔を見せたいから、無理にいい人を演じているんだ。だけど、そいつは長く続かない。とっても疲れるらしい。
別の川の話もしよう。家の後ろにも川があったな。この川は細いから、工業排水なんて用途には適さなかったと思うよ。だから、まあまあきれいだった。なんでそれ程きれいじゃないわけは、生活排水はあるんだ。ご飯の米粒が、底に沈んでいるのがよく見えた。フナやメダカが集まってそいつを食っている。小さな魚をねらってアメリカザリガニもやってきたな。黒いからわかりにくいけど、そいつらはゆっくりやってくるんだ。魚たちも全く気がつかない。そして、鋭い一撃!ハズレ!魚たちははじけるように離れていった。 話は戻るけれど、かあちゃんがオイラを産んだとき、産休は取らないで働いていたんだ。おかげで、オイラはお乳がもらえない。だから近所の女の人が乳母になった。こんなことを頼むにはお金を払うか、なにかしらオイラの家に恩義のある人だろうと思うよ。その人のおかげで、オイラはすくすくと育って、1年後にはまん丸に太っていたわけさ。ところが、健康優良児だったオイラは、離乳食になってからげっそり痩せてしまったんだ。でも、骨格はできあがっていたから、いまでも体格はしっかりしているらしい。その後もかあちゃんは働いていたから、オイラはばあちゃんに育てられた。だから、かあちゃんはオイラのことを自分の子じゃないみたいだなんて言うんだ。寂しかったね。 何度も言うけど、金持ちの家なのに、食事は質素だったね。朝は味噌汁とご飯だけ。夜はおかずが一品と味噌汁とご飯だ。農家だから、米はたくさんある。つまり、ご飯のおかわりはできるけれど、おかずのおかわわりはなし!おかずは近所の魚屋で煮魚の仕出しを取るから、もう無いって言うこと。食費は掛かるし、オイラには栄養は足らない。おかげで給食がおいしくてたまらなかった。給食が嫌いなんて言う子の気が知れなかった。だから、学校を休んだヤツのおかずをもらっていた。 それから、オイラの家には変なしきたりがあって、「食事中は水を飲まないで、食べ終わってから飲むこと。」えーと、それから、「脇を閉めて茶碗を持つこと。食事中は立たないこと。」それ以外にもたくさんあったけれど、覚えられなくてよく叱られた。だから、食事中は気が抜けない。それ程好きでもないメニューだと、食べるのが大変なんだ。隣では、じいさんがご飯に牛乳をかけて食べている。牛乳の臭いで気持ち悪くなるけれど、ぐっと我慢して早く食べないと、また注意される。唯一の楽しみはふりかけだ。オイラはすき焼きふりかけが大好きだったけれど、高価だから贅沢するなと言われて、いつも遠足の友というあまりおいしくないふりかけだった。それでもオイラにはおかずがないから、仕方がない。 オイラには妹が2人いるけど、オイラとは違ってできが良いから、両親には気に入られていたね。特にとうちゃんは妹たちがかわいいからといって、家の手伝いはさせなかったね。それに比べるとオイラとの関係はまるで主従関係さ。親に従わせることばかりだ。甘えは許されない。子供の時にはそいつに気がつかないで叱られる度に、「オイラは怠け者だ。」と自分ばかり責めていたよ。 かあちゃんの実家は牧師をやっている。だから厳しい。特に祖父は学校の教頭もしていたから、オイラの家と変わらないくらい口やかましいんだ。そんな家風だと、おじやおばたちも結構神経質でね、ここでもオイラは色々と注意をされたものさ。でもそれを叱るときはいつも「こんな行儀の悪い子は見たことがない。」とか、「どういう躾をされている。」とかそんな言い方が多かったな。こちらの家族は何でも完璧にやろうとする。それができる間は良いけれど、いつかは親の理想から離れていくから、祖父の前とそうじゃ無い時ではリラックス具合が違うんだね。長男であるおじさんは祖父の期待が一番強いから、大変そうだった。オイラから見たら一番優しそうだったけれど。親の期待と従順になることをしつけられ続け、それに耐えきれず、アルコールに依存してしまったよ。オイラにはよくわかるなあ。幼少時に、自分にされたいやなことを他人にする人もいるけれど、おじさんは優しいから、自分の身体をいじめってしまったように思うね。 とうちゃんはじいちゃんから、長男として、資産を減らさないで、家を継ぐことを厳しく言い聞かされてきたから、人が自由にやっているのを見ると腹がたってしょうがない。「あれしちゃだめ、コレしちゃ駄目。」でがんじがらめの教育を受けたから、教えられたこと以外はとんとわからない。つまり空気が読めないってヤツさ。オイラの従兄弟は山登りが大好きで、今度、アメリカの山に登れるって喜んでいたのに、「長男はそんな危険なことをしてはだめだ。」と抗議をしに行ったよ。もう一人の従兄弟は飛行機が大好きで、中古のセスナを買って楽しんでいたんだ。でも、親父はその親戚にも抗議をしに行ったね。「飛行機には長男は乗るな(正確に言えば、操縦するなだ)」。オイラの場合は、もっと強烈だったよ。職場に乗り込んで社長に、「長男だから、いつかはここを辞めさせてもらう。」と言いに行ったね。おかげでオイラはちっちゃな会社に左遷されちゃったよ。その時はオイラのことを思っているからとそんなことをしたんだ、と我慢したよ。そうそうこんなこともあったなあ。しつこく家業を手伝えと言うから、会社に辞表を出したことがあるんだ。そうしたら、親父はなんて言ったと思う?「そこまではしなくても良い。」て言うんだ。その冗談はおもしろくなかったね。それで仕方なく、社長に辞表を取り下げてもらうように頼んだけれど、さんざん嫌みを言われたよ。「きみは働かなくても食っていけるそうだが、うらやましいね。それだから、ここじゃあまり一生懸命働いてないだろう?」てさ。学生時代には、親に認めてもらおうと一生懸命勉強したら、とうちゃんから「勉強だけできても専門バカだ。」といわれた。その頃からオイラは精神的におかしくなって、たぶん今思えば、神経症だと思う。生きているのが嫌になったんだね。かといって、死ぬのも怖いから、宙ぶらりんの状態さ。いつ死んでも良いと思っていたから、行動が投げやりで、遂に大きな自動車事故を起こしてしまった。事故後、オイラの身体は治ったけれど、神経症はそのままだったよ。 親戚たちをよく見ると、親の犠牲になっている人たちはオイラだけじゃない。おじさんや叔母さんたちの結婚相手は、たいてい朗らかな人を選んでいるね。オイラはその相手に何度か会ったことがあるけれど、つまり年下のオイラからしても、明るくて話しやすいのさ。どういったらいいのかな...オイラの知っている大人にはいないねえ。なんか肩の力を抜いて話せる感じだ。残念ながら、かあちゃんと結婚した人はそうじゃなかった。だからオイラにしたら、二人を相手にするから大変だったよ。かあちゃんもオイラが、強情を張ると、怒って叩くんだ。それも必ず「あんたが悪いから、ぶつんだ。」と言うね。その時はオイラも自分が悪いから叩かれても仕方がないと思っていた。かあちゃんも自分が子供の時に叩かれたらしいね。だから、すぐに手が出てしまうのを押さえられず、折檻を正当化しようとしたのかもしれないなあ。 子供って、乳児のころには素直で、優しいし、公平だ。その後、大人が教育やしつけと言って、犬みたいに従順にしようと、厳しくするから歪んでしまうんだ。歪んでも親も本人も気がつかない。気がつくのは子供の精神がおかしくなったり、犯罪を起こしたときくらいかな?まあ、そんな親はきっと祖父や祖母からきびしく育てられたから、繰り返しだと思う。同じ被害者かも知れない。 子供が夜更かししても、親が酒を飲んで機嫌が良いときは怒らない。なのに、夕方家に帰るのが30分遅れたぐらいで、すごく怒るのは、愛情で子供を叱っているんじゃないね。第一、怒るほどのことじゃないしね。オイラがその場にいないときのとうちゃんの叱り方って知っているかい?オイラの作ったプラモデルを木っ端みじんにするんだ。家に帰ってきてびっくりさ。そういえば、オイラが県外に住んでいたときには、叱りたいけどオイラと連絡が取れないからと、「ソフキトク」と電報を打ってきたこともあるなあ。だまして呼び寄せてから叱るつもりだろうね。目的達成のためには手段を選ばないってやつさ。こういう人は戦争ではヒーローになれるだろうけど、今は平和だから残念だと思うよ。正直に、「こんなことしたら駄目だ」と電報を打ってくれた方が、オイラとしては良かったね。働くようになったら、オイラも少しは言い返せるようになった。ある晩、ちょっとしたことで、恥ずかしいけどけんかの原因はたいてい金のことなんだ、その時は税金関係だったかな、とうちゃんと口げんかになったんだ。でも、今度は包丁を持ち出してきたから、これもびっくりしたね。まあ、とうちゃんは本気じゃないと思うけど、オイラを脅かすには十分だったよ。それで、しばらく家出したってわけさ。それで、オイラを飼い慣らすのに、家の財産をエサにしていたなあ。でも、家が傾いた途端、オイラの給料を当てにしたり、恩着せがましく財産相続の話をし始めたよ。 専門的に言えば、オイラの病気は強迫神経症と言うらしい。わかりやすく言えば、物事を白黒はっきりさせないと気が済まないって性格だ。もっとわかりやすく言えば、いつも不安なんだな。取り柄は人に迷惑をかけないって所かな。寂しい点は、人からは、オイラが病気だなんてわからないことさ。 また気が向いたら、書き足すかも知れないけれど、今はこれくらいにしておこう。じゃあな、元気で。 「正確な自叙伝を書ける人はめったにいない.ルソーの懺悔録もしかり...ハイネ」 後記:最近になり、自分が被虐待児童であったことがわかりました。手荒い躾や過剰にきびしい躾は慢性の虐待になります。子供の頃の食事や就寝の時の緊張感を忘れることができません。厳格なコントロールをされていました。親の好意を得るために、職業的には成功したとしても、本当の自分ではなくて、演じてきたため達成感がなかったのです。幸運なことに、ある本によって、心的外傷のことを知りました。徐々にですがPTSDによる体調不良がよくなってきているように思います。 |
|||
|
もう5月だ.嫌になるほど時間が過ぎる.誰かが一生懸命生きていないから,早いのだと言った.一生懸命,嫌な時間を過ごせば誰だって長く感じるものだ.楽しい時間なら終わるのはすぐである.くだらない時間を苦しみながら日々の糧のために働けば,そりゃあ長くなるってもんだ.俺の職業を楽な仕事だと思っているやつも多いから,わんさかと大学をめざす.やりがいがあるなんてことを聞くが,どんな仕事も突き詰めればやりがいがあるよ.結局は効率である.いかに楽してもうけられるか?それなら高卒で公務員試験を受けて,それなりの身分にでもなれば良いと思うがね.それで毎日,退職金を楽しみに暮らせばいいって. (終)
|
|
ヨゼフ:こんにちは,僕の愛しいマリア.きょうはどちらへお出かけ? 向こうの方から,友達の魚屋がやってきた.2人に気がつくと,丁寧なあいさつをして話しかけてきた. 魚屋:いつも仲が良くて,うらやましいですな.
魚屋の姿が見えなくなるとヨゼフはマリアに話しかけた. (終)
|
|
|
|
ー祖母を偲んでー
(終)
|
|
|
|
目を開けると、布団の中だった。さっきよりは少し吐き気が和らいだが、とても眠くて、頭の中がはっきりしない。寝返りを打とうとしたら、何かに当たる気がした。布団の中に人がいて、非常に驚いた。私が目が覚めたのに気がつくと、女がこちらを向いた。不思議なことに女は私より身体が大きくなっていた。白い腕を伸ばすと、私の首すじに強く抱きついてきた。私はからみつく腕を振り払うことが出来ずに、そのまま重なり合って左右に転がった。私は揺すられて、そのうちに強い吐き気を催した。 (終)
|
|
100mごとに短く鳴るベルは、静まりかえった艦内に響いていた。すでに3万5000m以上も潜り続けている。窓の外は暗い青緑色。超高耐圧プレキシガラスは厚さが1mもあるので、景色がぼんやりしているのが、ガラスのせいなのか、外が濁っているのか判然としない。操縦士のジョン・ロードは、宇宙飛行士になってからまだ半年である。手元にはマニュアルが大事そうに置いてある。時折、後ろの席に座っている艦長の顔を伺いながらも、落ち着いているように思わせていた。彼にとって、トゥルーダイバーと呼ばれる超深海用の乗り物を任されるには、重荷のように思えた。トゥルーダイバーは、長さ約100mの楕円形の潜行艦である。潜水艦と異なるのは、水の中を潜るのではなく、液体メタンの中を潜ることである。最も注意することは、メタンは酸素と混じると爆発しやすいことである。チャンドラ星は太陽系の海王星に似ている。色は緑がかった青色、いわゆるターコイズブルーで、陸地は全く存在しない。海王星に比べると、自転速度が遅いため、昼と夜では自然が異なっている。惑星表面の温度は摂氏マイナス160-150度で、恒星に照らされる昼の面は、蒸発したメタンと水で、もやがかかり、穏やかな雰囲気だった。反対に夜の部分は、黒い液体メタンが少しの波音も立てずに漂っていた。トゥルーダイバーが母船から切り離されて、ここへ潜行してから、すでに10日間経過している。目的は資源調査である。艦長のイアン・ペイスは歴戦の元軍人である。何度も死の淵から戻ってきたおかげで、身体の半分以上は機械化されている。服を着て遠目で見る限りは人間らしく見えるが、近くで見れば右目が義眼であることと、右手の動きがなめらかでないことから、機械化されていることはすぐにわかる。艦長が立ち上がるときには、コンプレッサーから空気が抜けるような音がした。更に、歩き出すと細かいモーターの断続音が、中央制御室にこだました。他の乗務員は、なるべく艦長の機械化されている身体のことには、気にしないように振る舞っていた。しかし、乗務員が艦長が後ろにいることに気付かず、突然モーターのような音がして、なにかの故障かと思い、機械のパネルをあけようとしたことが何度かあった。
移住
一人 艦長を除いて。
|
|
|
|
鋭い閃光が,目の前を覆うやいなや,真っ赤な炎と黒い煙を放って,風防を持たないロケットのような戦闘機が,下の方に落ちていった.攻撃機のリーダーである黒木は,最後まで爆発したか,自分の目で確認をしたかった.しかし,地上からの攻撃が激しく,危険を冒すことは出来ない.ここはレーダーに任せて,次の迎撃機のインターセプトコースに進入した. 「いい加減にやめなさい.」
|
|
|
|
目を覚ました。 ーエピローグー 三田村が過去だと思った場所は、同じ空間に存在する死後の世界だった。そして、そこで出会えたのは、亡くなった人々のみだった。 (終) |
|
|
|
25階の真っ暗な部屋の中央に男が一人倒れていた.顔は床の方を向いていたのでよく見えないが,息はしていないようだった。更に,その頬の部分から床にかけて,何かの液体で黒々と濡れていた。突然後ろのドアが開き、廊下の光が男の身体を照らした。一組の男女が倒れた男を見下ろすように立った。その男の顔は青白く痩せ、黒いスーツはその身体を更に細く見せた。 1週間前 徐々に日差しは強くなり,上からの光は野坂の疲労感を誘った.バスを降りて,坂を登ると,あたりは大きな家々がこれでもかと言わんばかりに,高い塀をめぐらせていた。この時間には,ほとんど人通りがなかった.唯一であったのは,自分と同じ格好をした男であった.バスを降りて10分ぐらいだが,既に何時間も歩いているような疲れである.目的の家は,この先の交差点を右に曲がったところにある。野坂は熱でほだされた身体を引きずりながら、今日の仕事が滞りなく終わることだけを考えていた。歩いても,歩いても,同じような白い高い塀が果てしなく続くと,日常離れした場所に来たような気がした。どこか知らない世界で迷路にはまりこんだ気分になった。白い壁の果てには大きな門があり、扉は格子戸であるが、自然の木ではなくて,木をまねた金属で,鈍い反射を放っていた。 真っ赤な光が頭の上からやってきた。野坂の住むアパートに朝日が真横から照らしだした。野坂の体は昨日と同じ場所にあった。うつぶせの背中は光の加減で黒く見え、心なしか小さくなったようである。それでも、7時の目覚まし時計が鳴ると,むくむくと起き出し、ぶつぶつとひとり事を言いながら洗面所に向かった。 「これだから、新人は困るのよね。」あからさまに大きな声で、白崎栄子は何人かの新入社員を前にしていた。 その頃、野坂は仕事も終わり電車で家路を急いでいた。満員の車内は、外よりもむっとした生暖かさで、健康な人でも気分が悪くなりそうである。野坂は運良く座ることが出来た。雨のせいでいつもより混んでいるようだ。膝の近くまで人の足が迫っている。突然、手の上に水が落ちたような気がした。誰かの傘のしずくかと思って手を見たら、真っ赤な血がそこにはあった。近くの乗客たちも、びっくりした様子で後ずさりを始め、野坂のまわりには大きな円が出来上がった。驚いて自分の顔を押さえると、ぬるぬるした感触が口のまわりにあって、指で触ると頬に穴が開いて、自分の歯に触れた。急いで最寄りの駅で降りると、頬の部分をハンカチで押さえて洗面所に駆け込んだ。 ローズウッドの床に古風な椅子やソファーが並ぶ部屋の奥の方に、ここには不釣り合いな金属製の机が置いてあった。そこだけ青白い蛍光灯で明々と照らされていた。一人の男が一生懸命にお湯の入ったガラスボールの中で小さなコップを揺らしていた。そのコップの中にある白い液体は泡立ちながら、少しずつその体積を減らしていた。男は目を見開いてそれを大切そうに眺めていた。 様々なきらめく光が交差していた。そんな繁華街の道をゆっくりと走る一台のタクシーがあった。窓越しに一組のカップルが熱中して話し込み、話がとぎれれば見つめ合った。何も知らない他人が見れば、楽しくて仕方がないカップルに勘違いされそうだが、男は仕事が目的であった。何としてもユアマン証券会社の経営が良好か調べて、本社に報告しなくてはならないのである。 時間がどれだけ過ぎたのだろう。野坂が、次に目を覚ましたときには、ベットの上で全く動けない状態だった。顔を持ち上げると、遠くに人の気配がした。手を動かしてみようとしたが、どこかに縛られているようで、両手足共に動かなかった。声を出そうとするが、頬に穴が開いてうまく発音が出来ない。それで、頬に穴が開いたのは現実だと実感した。口の中は消毒液と血液が混じった最悪な味がした。もし健康だったら吐いてしまうほどである。やがて、野坂のうめき声を聞いて、誰かが近づいてきた。 明るい日差しが、ビルの窓から差し込んでいた。岸本は、今、眠りから目覚めたように大きな伸びをした。時刻は10時を過ぎようとしていた。「昨日は、ほとんど寝ていないから、きょうは大変ね。」しかし、昨日の矢崎との一夜を考えると、心は元気であった。その証拠に資料室に向かう足取りは速かった。 ビルの間には、細い路地がつきものである。高級マンションやオフィスが建ち並ぶ表通りの清潔さに比べて、色んなゴミが吹き貯まっている。人前には出られない人間もそこにはいる。何年も着古したジャケットを大切そうに着た男が、ごみ箱の中をあさっていた。「ここにも、食べられそうなものは無いようだ。」 「酷い話もあるものだ。」中年の刑事が話した。 「しゃれたレストランよりも、ここの方が落ち着くわ。特に秘密の話をするときにはね。」 支店長が無くなって2日しか経っていないにもかかわらず、横浜信用金庫では、いつもと同じような業務が支障なく行われていた。どれほど重要な人でも、いなくなったら、すぐに変わりが見つかるのが世の常であった。 「私、横浜警察署の刑事ですが、こちらに野坂順一さんという方がいますか?」ちょうど裕子が会社で受付をしているときだった。2人の刑事が尋ねてきた。 突然、耳元の電話が鳴り出した。同時に留守番電話のメッセージが流れる。 (終) |
|
黒い空を見るのも今日で一ヶ月になる.唯一見える景色は頭の上で輝いている地球だけだ。陸も海も地図で見たとおりの形をしていて,まるで現実感がない.後三日で,帰れるかと思うと,毎日の単調な仕事も楽しくなるから不思議だ.帰還したら久しぶりに海外旅行でもしてみようか?スペインなら今頃は牛追い祭りでにぎわっているだろうな.二千十五年に首都になったバルセロナはとても近代化されているらしいから一度見てみたいものだ.「おや,遠くから何かが接近してくる.最新型の遠距離スキャンでは・・・何もうつっていない?」急いで旧式のマイクロ波を使ったレーダーに切り替え,副操縦士の山下を呼ぶ.神経質でやせている山下の顔がこわばっている.船外カメラで見たところは,虹のように見える.真ん中に明るい光点があり,炎のように揺らめいている.「どういうことだ?遠距離スキャンでとらえられないとは,エネルギーを持たない物質なのか?それなら最近発見されたマイクロブラックホールかも知れない.このままじゃ衝突するか,衝突しなくてもなにか恐ろしいことが起こりそうだ.」副操縦士に命じてスラスターを使い周回軌道を地球に近づけた. 「せっかく無事に帰ってきたのに,今,そんなこと言わなくても良いだろ」山下は妻からの言葉に憤った. ガラスの塔の北側に駐車場があり上級社員用のエアーカーがある.そこまではいつもは地下道を通るのだが、きょうは狭い通路を歩く気分にはなれない。小道の途中に花壇があり白い小さな花が咲いている。名前はわからないが、いつから咲いていたのだろう。こんな小さな花に気をとられることなんてなかったのに、きょうは何気ないものが気になる。いままでどれだけのはかないものがおれの目の前をすぎていったのだろう。宇宙飛行士になるのに大事なものを忘れてきた思いが強まる。駐車場につく頃には太陽も黄色くなり、まぶしさを増している。暗い気分を打ち消すようにラジオの音楽に耳を傾けた。どこかで聞いたことがあるが、歌手の名前は初めて聞くものばかりだ。大気圏外での活動は記憶障害を起こすのかもしれない。久しぶりの本物の重力が体につらい。 「黒川君にも困ったものだ。報告書に今回の事故をそのまま記載するものだから、これじゃあ、社長も今後の宇宙開発を見直さなくてはならないことを、文部科学省に言わなければならないなってしまったな。大北部長」貴重品のたばこを吸いながら、丸山常務が深いため息をついた。 「宇宙飛行士用の保険か...」壁面テレビを見ながら山下はつぶやいた.給料の多い人は高額の保険に入れるが,少ない人はその命の価値も少ないと言うことだから命に不平等があるわけだ.山下は悩んでいた.どんなに働いても給料の少ない人はお金のためなら,多少の危険は顧みず,私みたいに危険な宇宙飛行士を志願するわけだ.宇宙飛行士ならまだ危険は少ないが,もっと危険な,二千百十二年アメリカで承認された傭兵制度を利用して,海外へ戦争をしに行くことができる.一生分のお金を稼げるらしいが,戦死率が三十%を超えている.それでも多くの人が志願している. 黒川が自宅に戻ったのは夜の二時を過ぎていた.日記,写真,パソコンなど,過去の自分を確認できるものを調べてみた.几帳面では無いがすぐにものを捨てられない性格は自分では気に入っていない.そういえば日記は三日しか付けていなかった.写真はどうだろう.「二千二十四年十月,出発直前の写真だが鏡で見たように今の自分と同じだな.いや,待てよ.鏡と同じ...鏡と同じ写真と言うことは左右逆か?髪の分け目が逆だ!どういうことだ!!!」 暑い.長時間昼側の静止軌道上にいると,一気に外壁温度は五百度以上に跳ね上がる.今日の太陽はとても近くに感じる.あのときと同じ暑さを感じる.あれからオレはうまく報告書を作り直し,有明号のポジトロンコンピューターのシステムエラーが原因ではないかと言うことで決着を付けた.そのおかげで再び艦長として有明号二世で短期の実験飛行を行うことができた.それはある計画のためだった.ロシアの物理学論文の中にプラズマ状態での量子理論で次元の変換が起こると言う報告があった.つまりプラズマ化すると量子運動ではじき飛ばされた原子が他の次元に移動してその空いた部分に他次元の原子が補完されるという理論だ.前回の事故でプラズマ化した有明号全体がはじき飛ばされて他次元に移動したことは理論的には考えられる.そうならばもう一度同じ状態が起これば,他次元に移動できるわけだ.オレ以外の乗員には悪いが,この世界の日本では自分はやっていけない.根本的に求めるものが違っているのだ.効率ばかりを求める会社,命にお値段を付けそれをつり上げようとする家族,出世のためなら人の責任を押しつける上司,富と権力に群がる人がなんと多いことか.テレビによる世論の操作,監視カメラによるプライバシーの喪失,いくら豪邸に住んでお金があっても,ここには誠も意志もないあるのは,動物のようなただ楽して生きている今を守ろうとする人々だ.これでは人間の形をした野獣の国だ.生きていく知恵はあるが,よりよく生きる智慧もない.結果の善し悪ししか判断しない世の中ではその過程に不正があろうと気にしなくなる.気に入らない隣国には傭兵を雇って攻め込む.まさに頭が良いが野蛮な野獣の国だ. 大気圏への進入角度を既定値より三度多くした.アメリカのスペースシャトルなら燃え尽きるところだが,最新の九谷のセラミックタイルなら二千度まで耐えられる.「大気圏への再突入開始します」副操縦士の山下の顔がゆるんだ.彼もオレの計画を知って,うまく自分の病気を認めて,治療に専念し退院できたと言うわけだ.お互い目を見ただけで考えていることは同じだとすぐにわかる. |
|
「二十五室の患者は様子はどうだ。」杉谷精神神経科病院の第七病棟の黒川医長が尋ねた。長く広い廊下で話していると、声が隅々までこだまする。黒川は今年で四十五歳になるが,出世は同僚に比べて遅い方だった.それは能力というよりも,そのまじめさと,頑固なところが原因しているようだった.この病棟には病室は全部で五十一室あり,その病棟の中央に位置する廊下の長さは百メートル以上ある。永遠に続くようなデザインの廊下の両側には病室に通じる頑丈なドアが同じように並んでいる.少しでも気分を和らげるために絵が掛けられているが,人物画が多く,その大きさも同じため,かえって不気味さと冷たさを募らせるようだ.廊下の作りも左右対称でありわざわざ中央線まで引いてある.つまりこの病院のような近代的な建築物では機能性が一番であり,次に頑丈さを求めて建てられている.それは人間性がおろそかにしている西洋的な考えからくるものだろう.反対にアジア的な建物なら火事には弱いが,コンクリートは使わず,木材を中心に作られ,さらに代が変われば新しく建て直されるのが日本人の建物に対する考えである.しかしここにあるのは外から鍵がかけられる閉鎖病室であり,外を歩く患者や家族を見かけることは無く,すべての人間性が排除されている.おまけに防音もしっかりされているので,病棟は夜中の湖のように静まりかえっている。 |
|
校門の近くの桜の樹にはまだ花が残り、さわやかな風に揺られていた。「きょうはなんだかとっても眠いや。」山田 一は眠気をこらえて5時間目の社会科のS先生の小さい声に耐えていた。山田君は今年で六年生である.上級生がいなくなって、せいせいする気持ちが強いけれども、同時になにか心に物足りないものを感じていた。五年生のときから上級生とけんかすることが多く、そのしゃべり方が生意気だということで二,三人を相手にしてけんかすることもあった。たいていは校内で事件は起こるので、怪我をする前に先生たちが止めてしまうことになるのだが、それでも、体は小さくてもがっしりしているので、上級生がやられて泣いていることもあった。彼の言い分を聞くと、上級生が会ったときにあいさつをしないとか、影で悪口を言っているとか、人のうわさが原因になっていることが多かった。しかし,同級生とけんかすることはなく、クラスでも友人は多かった。その中の小島君とは入学したときから、クラスが一緒で,とても話が合うので学校が終わってからも一緒に遊んだ。2人の好きな話といえば、友達のことや学校での出来事や贔屓のプロ野球チームの話だった。小島君は背は高いが、痩せているのでがっちりした体格の山田君に比べれば幼く見えた。話の内容は自分が見たり感じたことをそのまま会話にしているので、その話しぶりには幼さが感じられた。しかし,柔らかな言葉は育ちの良さを物語っていた.ただしとても寂しがり屋で、誰かと話をしていないと不安になり自分が仲間はずれになっている気分になってしまうのであった。その心とは反対に人から見ると社交的で誰とでも打ち解けやすいということで人気があり、クラス委員や人前で話すことが多く,教師のウケも良かったが,それで大きなストレスを感じていた。 |
|
爆発 学習塾 20年後,南極地下都市 知能強化装置 真実 手術 横領 脅迫 繁盛するのも限度を超えると苦痛でしかない.研究所に併設されている塾はその限度を超えていた.機能強化装置は休むことも故障することも許されず,夜間も午前2時まで働き続けた.研究所の職員も2交代で勤務することを余儀なくされ,給料は増えたが休暇はほとんど無かった. 白一色の雪原は方向感覚を狂わせ,自分がどこにいるのかわからなくなる.それも今は冬だから,天気が良くても一日中闇の世界である.雪明かりと手に持ったライトが頼りである.清水は受け渡し場所に向かっていた.その場所は少しくぼんだ盆地のような部分でまわりには小さな雪の山が有り,人の目を避けるには好都合である.すでに,荷物はそこに置かれ,まわりには人影は無かった.素早くそれをポケットにしまうと,あたりを見回しながら,地下への抜け道へ向かった.受け渡しに警察が介入すれば,会社の汚職もわかってしまうわけだから,つけられる心配は無い.清水は自分の仕事が完了したことに大きな満足を得た.後は柳原のしでかした横領の跡を消すだけである.柳原はすでに退職していたが,まだ就職先が見つからず南極都市にいるという話しである. 手紙 KI病院 一階 脳神経外科 待合室 敬具 」 結末 50年後南極都市. |
|
光は人間にいろんなことを連想させてくれる。希望、命、爆発、そして消滅である。自分がいる現在だけでは無く未来と過去があることを知っているのは人間だけである。動物が気楽に生活しているように見えるのは現在しか考えていないからである。 いつもと変わらない朝がやってきた。交差点にある時計は午前7時を指していた。青く澄んだ空が、太陽の光に混じって輝いていた。研究所近くのレストラン
では朝食を摂る人でにぎわっている。突然テレビで臨時ニュースが流された.「昨夜午前2時頃,大きな爆発がマケーナス研究所で起きました.死傷者はいない
模様ですが,研究所で仕事中だった新道博士が行方不明になっています.なお,放射線や危険物質の汚染はありません.」そこにいた人たちは事故を知らなかったのか,一様にざわついた様子で,テレビを見ていた. 再び大きな衝撃音で、男は目を覚まされた。依然としてまわりは果てしない暗闇だった.時間は午前8時を過ぎている.手探りで地上に出る階段を探した。何 度か転んだが、ようやく地上に出ることが出来た。しかし地上もお昼だというのに薄暗く、太陽は見えず、黒い雲が空一面に広がり夜のように思えた。辺りの風
景も全く昨日とは変わっていた。建物らしいものは何も無く、黒い地平線がどこまでも続いていた。「ここは地球じゃないのか?」驚きと疲労の影が彼の心を包 んだ。 |
|
大学病院―手術室 |
|
武生市から東の方に20kmほど行くと,今立町という山に囲まれた自然の豊かなところがある.冬には雪が屋根まで届くほどの山奥であった.唯一そこで開けた平地には20戸ほどの世帯があり,文代はそこに室町時代から続く寺の7人兄弟の2番目の長女として生まれた.文代の生まれた昭和九年は,満州国が独立し,徐々に日本の軍国主義が濃くなってきた時代である.それでもまだ自給自足の生活が当たり前であった今立の片田舎では、食料などや日常品を欠かすことは無く、のどかな雰囲気があった。 |