 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
片口酒器セット:赤鉄砂土 白化粧の重ねがけ 木灰透明釉吹きがけ:成形時に口辺の水分を多目にして柔らかくし、ぐいっと引っぱり下に押して片口に。素焼き化粧土の荒々しくかけた感じが一応生きているかな?たっぷり酒が入るようにサイズには注意しました。白化粧の流れを見ながら一杯呑むのは楽しそう。高10.0
径8.8×14.0 ぐい呑みは高6.0 径7.3 |
|
くちばし付き酒器セット:土と釉薬は左に同じ。生土にかけた化粧土は薄く溶け、また、素焼き化粧土は少なめにかけたため、赤鉄砂土の鉄粒が前面に出ている感じに。ざらざら感が好きな人には受ける酒器かも。2個あるぐい呑みのお腹の膨らみは、それぞれ少し違うのだけどそれもまた楽しいかも…高9.4
径9.0×7.5 ぐい呑み高:6.0 径6.7 |
|
湯呑み:土と釉薬は左に同じ。口辺の高さを揃えることにこだわらず、一気に挽き上げただけのものなので、ろくろ目に沿って口辺の山道に辿り着くのも楽しいかもしれない。白化粧が流れて底に溜まりかけている景色も結構楽しい。高5.2 径8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
汲み出し:信楽白土はぜ石混ぜ 生土白化粧土かけ 木灰透明釉:白土に白化粧という面白くない組み合わせだけど、清楚な感じがします。生土かけの化粧土がほのかに流れているところが、けばけばしくなく趣があります。はぜ石が外側によく出ている。ご飯茶碗にも使えるサイズ。高5.5 径10.6 |
|
壷:赤鉄砂土 青銅マット釉:青銅マットは白土にかけると大体は青銅色に出るのだけど、赤鉄砂土にかけるとこんな色になった。ほとんど「緑」という感じだ。どぼ浸けかけをしたが、かなりうまく釉がかかっている。微妙に細かい濃淡が出ていて、部分的に釉の流れもある。この色は気に入ったので今後も挑戦したいですね。高:11.9 径10.5 |
|
大振りの茶漬け碗:赤鉄砂土 漆黒釉+いぶし黒釉+木灰のMIX釉:まず素焼きの下地にどっぷりと酸化第二鉄を刷毛塗りし、その上からMIX釉を刷毛塗りしました。なぜかマット調になっています。茶漬け碗として使ってもいいけど、芋の煮物を入れたり、または大根のつまをたくさん敷いて刺身を盛ってもいいかも…。高6.7 径13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
茶漬け碗2個組:赤鉄砂土 釉薬は大振り茶漬け碗と同じで、酸化第二鉄も同じように下地に塗ったもの。ただしMIX釉を吹きがけしているので、とてもきれいなマット状になっています。釉の変化はないのですが、きれいなので使ってみたいという人は多いと思います。高8.0 径12.6 |
|
丼鉢:信楽白土はぜ石混ぜ 左に同じく下地に酸化第二鉄を塗った後、MIX釉吹きがけ。MIX釉はきれいにかかり工業化された生産品のような感じ。はぜ石の白が眩しく、覗き込めばまるで天空の星を見ているかのような感じ。でも触るとはぜ石のぶつぶつが気になる。高6.8 径13.2 |
|
浅めの飯碗:釉薬はMIX釉 刷毛塗り 酸化第二鉄は塗っていない:刷毛塗りであえて重なる部分の釉の変化を試してみた訳ですが、いまいち面白くなかった。刷毛の動きが見える仕上がりとなったが、きたない感じになってしまった。MIX釉は吹きがけが無難かもしれない。高5.0 径12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
黒陶土 半乾き時に削り模様を入れ、素焼き後に素焼き化粧土を埋め込んだ象嵌細工。石灰透明釉を薄くかけて仕上げました。象嵌の細工はまあまあでしたが、仕上がりはいまいち。透明釉をもっともっと薄くかけないと趣が出ないような気がする。薄くかけると実用性はマイナスだけどね。高2.1 径14.3 |
|
黒陶土 石灰透明釉:半乾き時に白化粧土を吹きがけして、真っ白にならないところで止めたもの。これまでの経験からきっと白は薄くなると予想していましたが、全くその通りになり、残念な結果となりました。次回からは白天目釉またはタルク白マット釉を使ってみたいと思います。高4.2 径14.0 |
|
黒陶土 石灰透明釉:半乾き時に白化粧土を内側に吹きがけ。白が斑状になってしまった。これはこれできれいなのだがやや期待はずれ。外側は無釉にすればよかった。とても薄い作品できれいです。左 高7.1 径10.3 右 高7.0 径8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
豆皿:赤鉄砂土 白化粧土 古代呉須 木灰透明釉:生土の白化粧が薄くなって渋さが出ました。呉須もやや薄めにして渋くなるようにしました。左は放射状の木賊模様、右は青海波模様です。ともに径8.5 |
|
作りは左に同じ。左側の皿は「蛸唐草紋様」のつもりだけど、間違っているかもしれない。右は干支のいのししを描いたもの。素焼き後に素焼き化粧土を塗り、絵付けしたものと比べると、化粧土の溶け解け具合に変化があって面白い。蛸唐草は8.7 いのししは径8.5 |
|
苔小鉢:赤鉄砂土 生土化粧土と素焼き化粧土の二重かけ 木灰透明釉:いい苔を見つけたので活けるために気軽に作ってみたもの。ともに三つ足。面白い形になったと思う。苔を早速活けてみたい。左長10.0 右9.0×4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
苔小鉢 赤鉄砂土 タルク白マット釉:九隆庵の女将が、玉子を半分に切ったような苔鉢を作りたいというので作ってもらったもの。白いのはタルク白マット釉。ぶつぶつの鉄粒は要らなかったようなので、次回からは普通の信楽土で作るようにしたい。左 高4.0 径5.5 右 高4.0 径5.8 |
|
信楽白土 織部釉の鉢:厚く掛けてもなかなか濃く発色しない織部釉。今回も内側は薄め。外側はろくろ目を強くしておいたので、窪みに釉が溜まっていい感じになりました。ややぽってりとしていて、日常使いには欠けも少なくて使いやすいはず。高4.8 径13.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生土の化粧土の良さ、素焼き化粧土の良さをそれぞれ実感することができました。
次回は化粧土に共土を入れて、さらに渋くなるようにトライしてみたいと思います。
黒の器は大体、軌道に乗ってきましたが、今度は錆の雰囲気を出せるように頑張りたいと思います。
まだまだ満足はしていません。
黒陶土は、薄い作品を作るのには向いていますが、完成度も高くないと見苦しくなりますね。
それなりの覚悟で、時間を掛けた作品作りが必要のようです。
豆皿や苔鉢は結構いい雰囲気です。こういうのを作っているときは気が本当に楽です。
とにかく年の初めに本焼きが完了したことはとてもうれしく、今年も頑張ろうという気になります。
適当な物ばかり作っている九隆庵ですが、今年もどうぞよろしくお願いします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
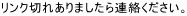 |
|
 |
|