 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
飯碗:赤鉄砂土 漆黒釉+いぶし黒釉のMIX釉の吹きがけ:飯碗としては丁度いい大きさかもしれない。ムラが出ないように吹きがけにしたため、変化は乏しいけれどしっかりとした造りになり、日常的に使いやすい感じになった。鉄粒が噴き出した跡をよしとするかどうかは意見の分かれるところかもしれない。高 7.4
径12.8 |
|
黒丸平皿:信楽赤土にはぜ石ごく少量混じり 左と同じ釉薬:ベースは赤土なので鉄粒の噴き出しもなく、落ち着いたしっとりたした雰囲気になった。所々ではぜ石が顔を出しているがわざとらしくなく馴染める。内側に削り線を入れたのがいいアクセントになった。今回の中で1番いい焼き上がりかも…。高3.2
径16.2 |
|
小皿:赤鉄砂土 漆黒釉+いぶし黒釉のMIX釉の刷毛塗り:適当に塗った釉が溶けてにじみが広がるのを期待していましたが、塗ったテクスチュアーがそのままになって残ってしまい楽しさが半減してしまいました。よく見ればとても渋くは見れるので和え物などわずかに盛ると意外といいかも…高3.8 径12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
大鉢:赤鉄砂土 素焼き白化粧土 石灰透明釉:化粧土を手杓子で大胆にかけたもの。化粧土の垂れ具合が丁度良かった。鉄粒の噴き出しもこの大きさになると心地よい感じがします。大鉢なので厚さも大きさに合わせて少し厚めを意識して成形しました。口辺も変化を持たせるとともに欠けにくくしています。今回の中で2番目の出来かも? 高7.0 径18.2 |
|
平皿:グレー御影土 素焼き化粧土欠き削り 石灰透明釉:グレー御影土は色使いが難しく今まであまり使ってきませんでしたが皿物で試してみました。白化粧とのコントラストは甘く、変化も乏しいのですが、実はこういう控えめな皿にご馳走を盛ると結構いい感じになるかと思います。高:4.0 径19.8 |
|
平皿:信楽赤土にはぜ石ごく少量混じり:素焼き化粧土 石灰透明釉:化粧土をしっかり掛けた後、口辺の内側の線削りの部分を中心に、タオルで化粧土を拭き取り、化粧土と素地土との重なり具合の変化を出すようにしました。土の茶色が顔を出してなかなかいい雰囲気です。これも主張は控えめ。料理が待ってますね。高3.4 径19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
中鉢:グレー御影土 素焼き化粧土 模様は古代呉須 石灰透明釉:模様の丸玉の部分は白化粧土を削ってから呉須で色を付け、線の部分は白化粧の上から呉須で描いたもの。呉須の色の変化が出て楽しい感じが出ました。この方法は今後も生かせそうです。土のグレーと呉須の組み合わせもよい感じです。高4.7 径15.8 |
|
中皿:赤鉄砂土 素焼き白化粧土 口辺は漆黒釉 石灰透明釉:口辺に漆黒釉をかけて、その後、透明釉をかける予定でしたが、すっかり忘れてしまいそのまま焼いてしまったもの。だから白の部分はザラザラ。食器としては使えなくなってしまいました。飾り皿としてなら白がきれいでいけるかも…高3.4 径17.2 |
|
長皿:赤鉄砂土 生土掛け白化粧 素焼き白化粧の2段かけ 石灰透明釉:2段かけは前回の焼成で味をしめたので、柳の下の2匹目のどじょうを狙ったもの。やっぱりいい雰囲気出ますね〜。硬めにした土を叩いてひび割れ状態にして、そこに白化粧を滲み込ませています。長21.4 短7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
フリーカップ:信楽赤土にはぜ石ごく少量混じり 素焼き化粧土 石灰透明釉:ろくろ目を強くして成形して、化粧土は手杓子がけ。ろくろ目に化粧土が溜まったりしている雰囲気は見ていて飽きないものです。湯呑みによし、小鉢によしの手頃なサイズになってます。高7.0 径10.8 |
|
カップ左:赤鉄砂土 素焼き白化粧かけ 線削り:欧州の街並みをデザインしました。鉄粒が絵の邪魔をしてしまったので次回は普通の赤土でトライします。
カップ右:同じ土で青海波釉かけ:もっと青くなるはずでしたが中途半端。それでも雰囲気は悪くはないので、まあ使えそうです。ともに高7.7 径10.0 |
|
小皿:グレー御影土 素焼き化粧土 模様は赤絵具 石灰透明釉:赤絵具で梅紋を中央に描きました。梅紋のお陰でかわいい感じになりました。手びねりで成形する小皿はとてもかわいい雰囲気が出ます。径12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
湯呑み:グレー御影土 黄いらぼ釉吹きがけ:いらぼの吹きがけは変化が出ず面白さが出なかった。ベージュっぽい中に御影の粒が茶色になって表面に出ています。雰囲気的には梨地釉に近いものになっています。高7.0 径8.0 |
|
小物入れor観葉鉢:信楽赤土 口辺は緋色釉塗り 石灰透明釉:緋色釉の発色を試してみました。透明釉を上からかけたためか発色はいまいち。緋色釉単体で発色テストをしてみないといけない…高5.0 長14.8 短8.0 |
|
茶漬け碗:赤鉄砂土 素焼き化粧土 いぶし黒釉 赤絵具:完全に失敗。汚くなってしまった。陶絵具の赤が本当に毒々しい。しかも赤鉄砂土とは完全に合わない感じ。この組み合わせは当分ないだろう。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今回は自己評価の点数は低いです。満足感はあまりありませんが、「なるほどね〜」と
うなづくことは色々とありました。
白化粧は共土を多めに入れて、色の変化を狙ったのですが、予想に反して変化は微妙な感じでした。
赤鉄砂土は面白い土ですが、基本的に渋さを狙った作品に絞った方がよさそうです。
グレー御影土は白化粧と呉須の組み合わせが、結構面白かったです。
今回のメインコンセプトの皿系の作品は、まあ何とか様になったのでよかったです。
皿物は、「どんな料理が合うかな?」と楽しみが広がるので、酒器制作とはまた違った楽しみが
多いですね。窯の容量と相談しながらまた作ってみます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
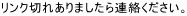 |
|
 |