 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
中鉢:信楽白土+五斗蒔白土+はぜ石 金彩マット釉 口辺の内側部分にいぶし釉を刷毛塗り:ガラスのボウルにてたたら成形。口辺部分はてかりがでていい味わいです。中央部分はマット状ですがこれがまたいい味わいです。径16.0 高4.5 |
|
中鉢:土、釉薬は左に同じ。口辺はやや内向き。左のものより黒の中に浮かぶ銀のにじみがやや弱い感じ。全体的にマット調が強い。この渋い鉢に色の鮮やかな食材を盛ると相当美味そうに感じるのではないかな?径15.5 高5.0 |
|
大皿:月ヶ瀬白土 金彩マット釉 たたら成形での平板大皿。全面に金が波のように浮き出て渋さは抜群。薄作りで、狙っていた金属質の感じが出て満足です。たたらのため口辺の歪みが微妙にありますがこれがまた真鋳の皿のようで面白い感じです。径26.0 高1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
筒型深鉢:月ヶ瀬白土 金彩マット釉 たたら成形 内側はいぶし釉、外側は金彩マット釉。内側は黒の上に銀が浮いています。外側は金の筋状の縞が見られます。用途を意識せずに作りました。径11.8 高6.0 |
|
小皿2枚組み:月ヶ瀬白土 金彩マット釉 たたら成形 月ヶ瀬の締りのよい土とあいまって、狙い通りの金属質な感じが出ました。口辺部分は金の発色がよいのですが、中央部分はほぼ黒のマット状になっています。径13.8 |
|
中皿:赤鉄砂土:信楽赤土=1:1 金彩マット釉といぶし釉のラインの上に漆黒釉を重ねがけ。金彩はつやが出た感じになり、いぶしは沈み込んでいます。この土には漆黒釉をさらに厚掛けしないと土に負けている感じがします。径16.8 高3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
小皿3枚組:赤鉄砂土:信楽赤土=1:1口辺は白化粧土、中央は漆黒釉 手びねり成形。まるで灰皿のような形ですが、こういうのもいいかと…。若干重めですが、面白い感じは出ているかと思います。径11.0 |
|
木の葉皿:グレー御影土 マスキングしてわら灰白釉萩釉をたらしがけ 白萩釉の濃い部分は少し青味を帯びて白濁しています。木の葉のイメージカラーは茶色が無難かなと思いますが、こういうのもまあ洒落ていていいかな?長26.8 短10.2 |
|
湯呑み5個:赤鉄砂土:信楽赤土=1:1 生土化粧土かけと素焼き化粧土の二重掛け。木灰透明釉 安定した感じのできです。手取りも大きさも丁度よい感じに仕上がりました。化粧土をどの程度の割合でかけるかが良さの分かれ目です。径11.5 高7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
碗:半磁器土 石灰透明釉 ろくろ目を残した碗です。歪みやキズもなくきれいに焼けました。ろくろ目がきれいに出ているので見ても触ってもいい感じです。もう少し薄く仕上げてもいいかもしれませんが碗ならこの感じでいいかも…というところです。径12.0 高7.0 |
|
一輪挿し5種:半磁器土 石灰透明釉 口の細いもの2個にキズがあります。他はきれいに焼けました。半磁器土の土でろくろで一気に立ち上げると、その勢いがそのままリアルに残りますね。今後も修行を積みたいと思います。 |
|
湯呑み:信楽白土+五斗蒔白土+はぜ石 ひいろ釉刷毛塗り 化粧土垂らしがけ 石灰白萩釉 高台までの曲線をゆるやかににすぼめたフォルムの湯呑み。ひいろ釉は塗りのテクスチュアーがそのまま出るので意外と気を張ります。径8.7 高8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
小物各種:奥のミニ花器は手ひねり、化粧土+呉須の絵付け、左の秤みたいなのは化粧土かけ、右の豆皿は金彩マット釉。金彩マット釉はきれいに発色しているのでかなりいい感じです。どれもかわいい感じです。 |
|
|
|
|
|
かなり予想していた感じどおりにできたので嬉しく思いました。
黒の中に滲み出る感じの金や銀、そして虹色の色合い。いい渋さにできました。
金属質+焼き場から出てきた感じの目標に近づいてきたかと思いました。
さらに渋さを求めてがんばってみたいと思います。
その他、いろいろ試してみましたが、そこそこよかったので安心しました。
暑くなってきました。汗を流して作陶したいと思います。
7月中にどれだけ成形できるかが夏場の勝負どころです。
|
|
|
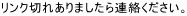 |
|
 |
|