 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
四角皿:赤土+白土+土鍋土のMIX 中央部分に化粧土塗り 古代呉須絵付け 木灰透明釉:鉄粒が混じっていると予想してましたが、ほぼきれいな赤土系の仕上がり。少しだけはぜ石が出ています。菓子皿などにいいかも?13.5四方。8枚。 |
|
四角皿小:土や釉薬は左に同じ。この皿シリーズは粘土を少しずつ押し広げなら成形したもの。皿の端の部分の変化の具合が見ていて結構楽しめます。暑くなった部分は削って取っていますが、化粧土の部分の塗りの厚さの調整がなかなか難しい。11.5四方。2枚。 |
|
長皿:土や釉薬は左に同じ。左の四角皿よりも厚みを持たせ、ぽってり感を出したもの。上面はスクレイパーで押しているので平面ですが、釉薬の変化があるので趣はあるように思えます。季節のものを少しずつ盛って、色合いを楽しむのもよいかもしれません。長20.0 短8.0 6枚。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
中鉢:赤土系粘土 口辺に金彩釉 漆黒釉:金彩釉を筆塗りしましたが、塗りすぎて垂れてます。金彩の垂れは余り好きではないのですが、何か不思議な迫力が感じられます。径15.7 高4.5 |
|
カップ:赤土+白土+土鍋土のMIX 化粧土かけ 木灰透明釉:ろくろと手びねりの両方を組み合わせて成形し、手作り感を全面に出しました。少し変形していますが、持ち手とのバランスは取れています。径10.2 高9.3 |
|
湯呑み:土や釉薬は左に同じ。薄作りで手頃なサイズにできました。口辺の反りと薄さ、手取りのよさがお茶の味わいを増してくれるかと思います。径10.4 高6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
湯呑み:土や釉薬は上のカップ、湯呑みに同じ。少しだけ肩の部分に窪みを持たせたので、壺風になっています。お茶が窪みに少しだけ残りやすくなりますが、口辺の反りがあるので飲みやすさはあると思います。左径9.3 高7.6 右径9.0 高7.7 |
|
木賊模様鉢:赤土系粘土 古代呉須線描き 木灰透明釉:予想していたよりも土色に焼けたので、落ち着いた雰囲気になりました。木賊の縦のラインはもう少し多めに入れてもよかったかもしれない。左径13.8 高7.1 右径12.8 高7.7 |
|
小物各種:土はいろいろ 左手前小皿は表は黒、右手前は青海波模様、左奥はぐい呑み、右奥はシンプルな白土系豆皿:小物はいろいろテストしながら作っていくので、また違った楽しみが持てます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
思ったよりも渋く仕上がりました。
薄い皿物は、手びねり独特の風情が出て、成形としてはそこそこ満足できるものでした。
鉢物はやはり思い切りがなくやぼったくなって趣が足りません。
混成土で作るのは、釉薬との相性が予想しにくくて難しいのですが、落ち着いた雰囲気で仕上げるなら
なんとかこなしていけるかもしれません。今回の結果は今後、役に立つとは思います。
8月中の2回の本焼きということで頑張りました。当初の予定は、こなせたかと思います。
9月中にも本焼きできるように少しずつ成形していきたいと思います。
|
|
|
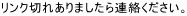 |
|
 |
|