 |
 |
|
 |
|
 |
|
四脚器:信楽白土と赤鉄砂土を10:1で混成、はぜ石混ぜ、火色釉、化粧土かけ、織部釉、木灰透明釉:化粧土は二重かけ。手取りのバランスもよく、いい雰囲気に焼けました。狙っていた雰囲気を出すことができました。径6.9 高6.9 |
|
四脚器:土や釉薬は左に同じ 化粧土のかかり方や表面の面白さは左の作品には負ける感じだが、底の部分の荒々しく削った雰囲気はこちらの方がよいように思えます。径7.2 高7.0 |
|
四脚器(ぐい呑み):土や釉薬は左に同じ 口を広げたぐい呑み どべを擦り付けてあるので、表面はかなり面白い。また、予想以上に安定感があるので、酔って倒してしまうということもないだろうと思います。径7.8 高5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
四脚器(湯呑み):土や釉薬は上に同じ 火色の焼けたような感じや、火色に織部が重なって複雑な色合いになっている部分など、見所があります。織部の表面の輝きもなかなかいい感じです。径9.0 高6.9 |
|
湯呑み:土や釉薬は左に同じ これは脚がないもの。化粧土をかけた後、螺旋のひねりの凹の部分に化粧土を残すように擦り落としたもの。口辺の織部の雰囲気はまあまあ。もう少し濃くてもよかったが、まあかわいいかんじになりました。径10.0 高5.4 |
|
飯碗:土は左に同じ。わら灰白萩釉を碗の左右でかけ分けています。写真では見えにくいのですが、釉の境目は緋色が出ています。わら灰白萩釉がかかっていないところは透明釉をかけてあるので水は滲みこみません。これで御飯を食べたい!径13.2 高7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
飯碗:土は上に同じ。内側、口辺、高台周りに化粧土をかけました。手びねり成形なのでほんわかとした感じがあります。化粧土と土の部分の境目がぼやけた部分があるのが残念です。径10.4 高7.0 |
|
盃:土は上に同じ。化粧土かけ、木灰透明釉:やや大きめの盃。織部や火色釉はかけてないのでシンプルです。小物入れにしたり、ミニ剣山を入れてミニ花器にしてもいいかな?径8.6 高6.0 |
|
中皿:信楽白土と赤鉄砂土を5:1で混成、はぜ石混ぜ、化粧土かけ、木灰透明釉 化粧土の二重がけですが、はぜ石が化粧土を押し上げているので、ぶつぶつした感じがあります。シンプルな白の器です。径19.5 高5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
小鉢:信楽白土と赤鉄砂土を5:1で混成、はぜ石混ぜ、化粧土かけ、木灰透明釉 素焼化粧土はたらしがけです。透明釉が薄かったので、若干マット状になっています。径11.0 高6.3 |
|
四脚器:信楽白土と赤鉄砂土を5:1で混成、はぜ石混ぜ、化粧土かけ、火色釉、織部釉、木灰透明釉:上段と同じ作りですが、脚長になっています。底の削り方を工夫しました。径7.4 高8.5 |
|
珈琲カップ:土は左に同じ。化粧土かけ、木灰透明釉。カップの半分だけ素焼化粧土を二重かけしてあります。いい感じですけど、変形しました。やはりもち手が引っ張られます。径8.0 高8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
花器:土は上に同じ。象嵌模様を入れました。凹の部分だけでなく、凸の部分の化粧土も少し残しておいて、象嵌が目立ちすぎないようにしました。結構かわいくできました。横9.0 縦6.5 高10.0 |
|
三脚小鉢:土は左に同じ。化粧土かけ、木灰透明釉。丸い玉を手の中で形にしたもの。わざと指跡を残して、化粧土をかけたときの変化が出るようにしてあります。いい雰囲気です。径8.5 高3.8 |
|
変形長皿:土は左に同じ。化粧土かけ、木灰透明釉。化粧土をかけたときに底が抜けてしまったので、広げて皿にしたもの。何だかついつい手に取ってしまいます。長22.5 短7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
大皿:信楽水ひ白土と五斗蒔白土を1:1で混成、はぜ石混ぜ、漆黒釉。うまく成形でき焼きあがりもかなり満足です。口辺が少し反っているので、盛った物がこぼれるのも防げます。これくらいの黒の大きめの皿は、あると便利ですね。径25.0 高6.2 |
|
長皿と豆皿(左):土は左に同じ。長皿はわら灰白萩釉かけ。豆皿(左)は呉須絵付け後に木灰透明釉かけ。豆皿(右)は赤土に化粧土をかけた後に絵付けして木灰透明釉かけです。長皿の長は23.0 |
|
湯呑と小鉢:赤鉄砂土と白土を3:1で混成。化粧土の二重がけ。鉄粒が出すぎてしまい、感触はいまいちです。鉄粒を隠すためには化粧土をかなり濃く、厚くかけないといけません。径10.8〜11.5 高6.7〜7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
苔鉢:赤鉄砂土と白土を3:1で混成。下半分は生土化粧土。口辺から垂れているのは素焼化粧土。部分的に織部が乗っかっています。妙にいい出来です。長9.8 |
|
|
|
|
特別目新しいものはないのですが、思っていた雰囲気は出せたのでよかったと思います。
化粧土、火色、織部の組み合わせは今後も深めていきたいと思います。
赤鉄砂土の化粧土かけは、簡単そうで実は結構難しいです。化粧土の濃度調節をきちんとしないといけません。
黒の大皿は眺めてよし!手に取ってよし!という感じですので、しばらく飾っておきたいと思います。
今度は、どんなテーマでするかまだきまっていないので、しばらくイメージ作りをしたいと思います。
次回も、お楽しみに!
|
|
|
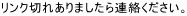 |
|
 |