2006年(平成18年) たづ日記
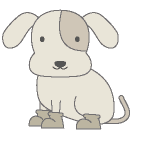
あい工房金沢
| 三碧木星年 丙戌 思いつくまま書き始めた日記も2年目を迎えました。 あい工房での出来事や個人的な事などを、私なりの感じ方で綴っています。 皆さんのご意見やお便りなども載せていきたいと思っていますので、どんどんこちらまで送ってくださいね。  こちらまで こちらまで |
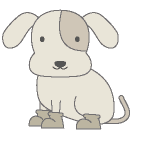 いぬ 2007年へ
いぬ 2007年へ | あい工房文化祭 第6回を終えて  |
今年は他の行事などと重なった事もあり、参加者が例年より少なくなりましたが、又、別の出逢いもあり、楽しい雰囲気で進められて本当に良かったと思います。 数ヶ月前から、「今年の発表会はこの曲にするわ」とカラオケ教室の人たちは勿論、大正琴や、しの笛の人たちも選曲に余念がありません。 当日は都合がつかない方たちも、いろんな形での気持ちが伝わってきて、ありがたいなーと思います。 中でも、前日にお嬢さんの結婚式をあげられたしの笛の宮永さんは、ほんとにお疲れだったと思いますが参加して下さいました。電話で私が「大丈夫ですか?無理しないで下さいね」と言うと、「練習する間がなくてうまく吹けないかも知れないけど大丈夫やよ。賑やかな方がいいが・・・」と彼女らしいさっぱりとした口調で、気を使わせない心配りに人柄を感じます。 又、文化祭の数日前に、あい工房にひょっこりお見えになった方が文化祭のある事を知り、籐で作るペンダントに興味を持たれて、当日参加して下さった事。そして、その方たちとは三国の花火の時、西出さんによんで戴いて同じブルーシートの上で観ていた方達だったとは・・・ご縁を感じます。当の西出さんは「どうしてここにいらっしゃるの?」と目をパチクりさせながら驚きの歓声をあげられていました。 体験の部から発表の部に移る間のティータイムは、皆さんのあまりに楽しげな様子に、幹事さんも「いいがの、終わってから汽車にでも乗るわけじゃなし」との計らいで少々予定オーバーとなりましたが、楽しい秋の一日となりました。本当にありがとうございました。 |
| 「ひなたぼっこ」文化祭で・・ 「はぐるまの家」坂岡さんの話  |
坂岡さんが曲の合間に子供たちの事を淡々と話されましたが、語るその表情は母親、いいえ「お母さん」そのものでした。一人ひとりの子供たちのデビューの場所を考えていらっしゃるとの事です。演奏を木陰から見守る姿にも心打たれました。 それから、坂岡さんのお母様が「人の荷物はしょってみないと分からない。人の事をあれこれ言うものではない」と常日頃おしゃられたそうです。本当、そうですね。 この文化祭をお手伝いされているひなたぼっこの皆さんが、私たちに心から「来て下さってありがとう」っておっしゃるんですね。皆さんで作り上げている文化祭という感じで、いいなー素晴しいなーと思いました。5周年おめでとうございます。 |
武生菊人形に行って来ました  |
菊花マラソンの日と重なった事もあり、菊人形会場は大勢の人で賑わっていました。 何時も家の中に居る車椅子の母は、私たちが外へ連れて行ってあげるのをとても楽しみにしています。暖かな秋の日ざしの中で、菊の花を見ながら母と歩ける幸せを感じた秋の一日でした。   |
| 感動塾に参加して |
その通りだと感心するやら、苦笑するやら・・・ そして、とんちでおなじみの一休和尚や、沢庵和尚が住んでいたところでもある、大徳寺の中の瑞峯院を訪れました。しっとりと小雨の降る午後のひと時、しばし時の経つのも忘れて庭を眺めていた時、「お嬢さん、背筋を伸ばしてみませんか?」とお坊さんに声をかけられ、「丸い背中にしていると、お年をめした方に見えますよ」と言われ、ハッと自分の姿勢に気づき、思わず一斉に背筋を伸ばしたものです。 背筋が整えば、呼吸がととのう。 呼吸が整えば心がととのう。 心が整えば顔がととのう。 いい言葉ですね。 でも、お坊さんのこの言葉をつい忘れてしまい、思い出してスッと背筋を伸ばしています。 |
| こころの笛 寶山左衛門先生 |
対談のなかの一部をご紹介しますね。 先生にとって笛とは?・・・笛は自分の人生の・・・そう<人生の宝物>ですね。その笛が良い 笛になるか悪い笛になるか、自分ひとつのことですから。 この道で一番大切なことは?・・・「最後は人柄だね」、「誰とも喧嘩しちゃいけないよ」。それから絶対腹を立てちゃいけない。どんな事があっても僕は腹を立てない。それが芸に出てしまいますからねとおっしゃったそうです。 日本の抒情歌を大切にされていて、先生の吹かれる笛の音は勿論ですが、私は先生の書かれた譜面が大好きです。文字の温かさが伝わってきて、その譜面をみて吹くときはゆったりとした心で吹ける様な気がします。 昨年の国民文化祭に来られた、寶先生のお弟子さんの福原徹先生が吹かれた「赤とんぼ」や「荒城の月」は本当に心に沁みました。それ以来、笛を手にする時、荒城の月を吹いている私です。こころで吹けるのはいつのことやら・・・ |
しの笛との出逢い 越前焼きの中村豊さんの作品 |
NHKの大河ドラマの「花の乱」で流れた笛の音が心に残っていて、その合宿に惹かれたのだと思います。それまで、横笛を見たこともなかった私は、田中敏長先生の指導で作った、その笛に初めて息を入れ音を出してみました。まず荒城の月を吹いてみましょうと譜面を貰いましたが、笛の譜面を読めもせず、音も出なくて、大変なスタートでした。 夜の懇親会で、寶山左衛門先生(福原百之助先生)や福原徹先生のお話をお聞きし、私も吹きたいと、その合宿でお会いした福原一笛先生(その数年後に襲名されました)の元へ通い始めました。 月に2回、夜8時半になると家を出て、先生のお宅に伺って教えていただきました。 今は笛の愛好会の皆さんと、楽しみながら吹いています。 大好きな笛と、これからも細く長く付き合っていきたいと思います。 |
| お盆に 30年ぶりの出逢い |
娘時代に通っていた武生の料理学校から、結婚を機に転校という形をとって貰い、中村料理学園へ通いましたが、その後、週2回助手としても働かせて頂きました。 週2回、それも1年位しか勤めていなかった私を誘って下さった事もとてもうれしかったけれど、人生を心豊かに生きていて、あーみんな頑張っているんだなーとホントうれしく思いました。 仲間の中で一番のお姉さま(私と1つしか違わないのだけれど)が、人と付き合うとき、チョットだけ自分が引けばうまくいくのよね・・・と言われ、みんながその通りねとうなずく・・・生き方の知恵のようなものも貰いました。 時を経て、其々がいろんな人生を送ってきたと思いますが、その言葉やみんなの表情に、あーいい仲間と仕事していたんだなーとうれしくなり、とてもいい気分でした。 次回の予定をたてるほど、良い時間を過ごす事が出来た1日でした。 |
| お盆を迎えて 兄と同期の方たちに感謝  |
平成12年4月に亡くなった兄も、早いもので今年で7回目のお盆を迎えました。 結婚して外に出ている私たちは、日常の雑事に追われ、ともすれば兄のことを忘れがちになる事もあり、あー申し訳ないなーと思う事があります。 しかし、北陸財務局の金沢に勤めていた兄の同期の方が、兄が亡くなってから、毎年お盆には一度も欠かさず兄の墓前とお仏壇にお参りして下さる事を聞き、本当にありがたく頭がさがる思いです。そして今年も又、金沢から3人がお参りに来て下さったそうです。年老いた母にもやさしい言葉をかけて下さり、7年経った今も兄の事を忘れずにいて下さる事を、母もうれし涙で私たちに語ってくれました。 常に温厚で誠実な兄でしたが、今もなお忘れずに来て下さる友達のお心遣いがうれしく、なかなかまねの出来ることではないと、母や姉達と感謝し、兄の人柄を今更ながら誇りに思います。自分を振り返ってみれば、いろんな場面でも、知らず知らずのうちに不義理を重ねているのではないかと、兄の友人の姿に、改めて反省する私です。 |
| 三国花火を通して 出会った人達 |
朝から場所確保、そしてお弁当作りに大忙しの西出さんのお陰で、お腹も一杯になり、開始時間の7時半を待つばかり。スタートの合図でドドーンと打ち上げられた大輪の花火のシャワーにすっぽりと包まれ、大歓声が上がります。 カメラに撮ろうと構えてみても、あまりの迫力に圧倒され、画面がたりなーい!! 全部うつらなーい!! とあちらこちらから聞こえてきます。海から打ち上げられる花火はお腹の底まで響いてきてそれはそれは迫力満点でした。 終了後の渋滞を避けるため、西出さん宅で他のお友達と一緒にゆっくりとくつろがせて頂きました。初めてお目にかかる方達でしたが、マラソンを楽しみ全国の大会、いいえ、海外まで出かけられる方もおられるそうで、人それぞれ、人生の楽しみ方もいろいろあるものだと感心しながらお話をお聞きして、本当に楽しい夏の一夜を過ごしました。 三国の花火ってこんなにすごいとは思わなかったと大喜びで、スイスイと車も快調に帰りました。本当に有難うございました。 |
那智の滝で・・・ |
熊野本宮大社、那智大社に参拝し、那智の滝では、ほとばしる滝のしぶきを仰ぎ、これぞマイナスイオンと、しばし時の流れを忘れる程、身も心もゆったりとした気分に浸りました。 (旅行はいいわー、家を出てしまえば、家の事も何にもしなくていいしー)と超現実的な事を考えながら・・・ そして、滝の入り口では、さかずき一杯のお水を頂くと10年長生き出来ると書いてあり、主人に飲まないの?と聞くと、「俺はいい。あんたは飲んで長生きして、俺の面倒を見てくれ」 普段、何にもしない主人は、さすがしっかりしていると思わず笑ってしまいました。 友達に言ったら、「本当に残りたくないんやのー」と呆れるやら感心するやら・・・ やっぱり私は元気で長生きしなければ・・・でも一人だけでそう長くも居たくないしと思い、お水は一杯だけにしましたけどね。 熊野古道も少しだけでしたが歩き、今度はゆっくりと歩いてみたいなーと又、新たな楽しみが出来ました。 (大好きな熊野を旅して) |
| 歳を重ねて、今思う事 |
昔、休日には、お昼にお風呂を沸かして母に入ってもらっていた時の事ですが、両手にシャンプーとリンスを持ってきて、シャンプーはどっち?リンスはどっち?と何度も何度も聞きに来た事がありました。その頃、認知症が始まっていたので、それで解らないのだと思っていました。勿論それもあったでしょうが、見えなかったのでしょうね。 元気な主人が言う事は、素直に見えないんだと思えた事が、病気が始まっている母に対しては、本当は見えなかったのかも知れないのに、呆けたからだと思ってしまいました。 私も50代後半になり、やっと今、少しだけ母のその時の気持ちが解ってあげられる年齢になりました。 申し訳なかったなと今、思うのであって、10数年前の健康な時には解らなかったですね。 若い頃はお互いが嫁と姑の葛藤もありましたが、それを通り越したから、老いた母と一緒に、同じスプーンでプリンやアイスクリームが食べられるようになったのだと思うと、その歴史は無駄では無かったのですね。そう思います。 |
| 最近・夫との会話 ホーホケキョ♪♪ |
4月5日の朝、今年最初のうぐいすの鳴き声を聞き、うれしくて私が「うぐいすが鳴いたよ!! 今年初めて聞いたの!!」と主人が起きるのを待って、うれしそうに言ったので、それから耳を澄ませて聞いているのでしょうね?。 でも、聞いていてくれると知ってか、まるで、お話しているかように元気に聞かせてくれています。春の朝の幸せなひと時です。 うぐいす、この鳴き声を聞くと、私はうれしくてうれしくて・・・春を実感します。 そして今朝も、今日も元気やなーで始まりました。 心身ともに健康で居られる事を感謝しなければと思います。 |
結婚記念日はホワイトデー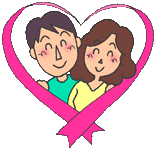 |
今から、35年前の3月14日も雪の降るお天気でした。私達の結婚記念日です。 福井市と鯖江市を結ぶ戸の口トンネルを越えて、お嫁に来ましたが、今の様に融雪装置がしてなかったので、戸の口坂が通れるかどうか心配したそうです。 でも、春の淡雪とはよく言ったものですね。私が上河北に着いた頃には雪も止んでいて、晴れていた様に思います。 でも、その当時は婚礼の道具も同じ日に出るのが普通だったので、朝早くから大変でした。 もちろん、結婚式も披露宴も自宅の座敷で行うのが普通でしたから、とにかく、足が痺れない様に我慢するのが大変で、次に席を立つ時にうまく立てるかしら・・・そんな心配をしながらの結婚式でした。座敷に居るのは花嫁だけで、昔から新郎は台所で酒の燗をしているといった笑い話?がありますが、あの時、主人は何をしていたのでしょうかね。今は結婚式場で行うので本当に羨ましいです。 朝の雪景色を見て、当時を懐かしく思い出しました。 |
リフトアップ車を買いました |
実家の母は、今は車椅子から自力で助手席に移乗出来るけれど、今後の事を考えるとやはりその車を諦めきれず、今までの四駆をやめ排気量も少し落として、その分を助手席がリフトアップする車を選びました。 もうすぐ90歳になる母は、今後更に不自由になっていくと思います。外の景色を一度でも多く見せてあげたいと思います。 |
| 顧客、感動実践クラブを 終了して思う事  |
訪問したお店の方は、試行錯誤しながら勉強されて、実績をあげていらっしゃる方々ですが、それでも自ら希望して、広く意見を聞きたいと言う、熱心な方々です。 参加した人が其々に気づいた事を言うのですが、今後の勉強の為に参加させて頂いている私の意見は、時には異業種だからこその気づきもあると思いますが、的外れで気分を害される様な事もあったかと思います。それでも謙虚に話を聞き、有難うございますと言われる姿勢には本当に頭が下がります。 真剣に取り組まれている事が良く解かります。 参加者の中でレディースマスダさんは、いつもご夫婦で参加されていて、おっしゃる事をお聞きしていると、本当に良く勉強されているんだなー、プロだなーと感心します。 全日程を、全部参加させて頂いて、いろんな方との出逢いもあり教えて頂く事ばかりで、本当に受講して良かったと思います。 このセミナーは実践する為のものとコーディネーターはいつも言われています。 出来る事から、1つづつ始めたいと思います。 皆さん本当にお世話になりました。有難うございました。 |
人生は・・・ |
商工会議所主催のセミナーの講師として来られた、アミング専務のお父様が常日頃言われている言葉だそうです。 この世を去る時に持っていける物。それは・・・心の徳である(この世で、どれ程役にたったか) ・・・人生の目標を明確にし、達成までの努力の期間中に人は成長する・・・ ・・・目標は期限付きだよ・・・(1年?、5年?、10年?、20年???) 内容により、期限設定はそれぞれだと思いますが、目標を明確にすることが、まず実現への第1歩だという事ですね。 目指すものが有ながら、なかなか期限を付けられないで逃げている自分がいます。 だから、いろんなお話の中で心に残っているのだと思います。 さあ、勇気を出そう!! |
| 父の命日に・・・ 母に、そして実家の家族に 感 謝 |
姉妹4人が実家に集まり、母と一緒にお昼ご飯を食べました。車椅子生活にはなったけれど、元気でいてくれる母のお陰で、私たちは楽しい時間を持つ事が出来ました。 あい工房で皆さんと「戯れ句」を楽しんでいる事を知っている姉から 老いてなほ 母あることのありがたく 素直に親の温情いただく 短歌をたしなむ姉が詠んだ歌をもらって帰った夜のカラオケ教室で、長生きしてね お母さんと歌う原田悠里さんの「母鏡」を習いました。 70歳半ばの方が、お母さんを偲んで、歌いながら声を詰まらせていました。 待っていてくれる母がいる間に、一度でも一時間でも多く母の話し相手になりたいと思います。 ・・・忙しいなんて言わないで・・・ |
| テレビドラマ 「白い巨塔」を見て思う |
「白い巨塔」何度見ても最後は涙があふれてきますが、その時々の感じ方って違いますね。最後の方で、手土産を持って被害者宅を訪ねる大学病院の医師が、父親を亡くし必死に働く母と子の姿を見て、黙って帰っていくシーンがありました。 自分のやった事をいまさら詫びたところで、その家族には何も変わらない。ただ自分が楽になる為に来ただけだった。逃げないで、もう一度大学病院に残って頑張ってみる。そのような内容だったと思います。 生きていく中で、してはいけない事、取り返しのつかない事をして後悔する事があります。 自分の気持ちを楽にしたくて詫びたいと思う事もあります。この場面を見てジーンときて、考えさせられました。本当にその通りだと思いました。 |
| 頂いた年賀状より・・3 身体の話  |
竹や柳が折れない様に、しなえるように生きましょう。 寝床で「あーあー」と伸びをしながら・・・。ゆっくりと穏やかに・・・無理をせず・・・ 私にとって必要な言葉でした。気持ちを若く持つ事はとても良い事だけど、身体が出している信号を無視しないようにと、健康診断でひっかかった血液検査の再検査をして来ました。 年齢と共に少しずつ高くなっているコレステロールの数値に気を付けようと、先日、万歩計も買い、歩く事にしました。二ヶ月後にしっかりと予約を入れられてしまったので、つまみ食いと寝る前には食べない事を実行したいと思います。 あたりまえの事がチョットきつい、意思の弱いわ・た・し |
| 頂いた年賀状より・・2 言葉の話  |
人の体の3分の2が水です。綺麗な言葉を使うと美人になるかも・・・楽しい言葉を使うと長生きするかも・・・さて、今年はどんな言葉を使いましょうか?] この年賀状を頂いて江本勝著の「水は答えを知っている」を思い出しました。 ガラスのビンに水を入れ、言葉を書いた紙を水に向けて貼るのです。「ありがとう」という言葉を見せた水は、六角形のきれいな形の結晶をつくり、「ばかやろう」を見せた水は、結晶がばらばらに砕け散ってしまったそうです。この結果は、まさに驚くべきものになりました。 同じように、「しようね」という語りかけの言葉を貼った水は形の整った結晶になり、「しなさい」の方の水は結晶が出来なかったそうです。こわいですね。 水が喜び、花が思いっきり開いたような形。それは「愛・感謝」という言葉を見せた水でした。これほど美しく華やかな結晶を見たことがありません。それは、私の人生を変えてしまうほどの美しさをもった結晶の写真でしたといった内容の本でした。 本を持っていながら、つい忘れていた事。年賀状のお陰で改めて自分の使う言葉の大切さを再認識しました。ありがとうございました。 |
今、我が家のお正月 |
朝、晩欠かす事無くお仏壇に参りお経をあげる母は、主人のたどたどしいお経に、クスクスと笑いながらも後ろで教えながら、家族みんなでお仏壇にお参りして、正月の朝が始まります。 お参りが終わると、主人は会社に行き一年の始まりの挨拶をして座敷に戻り、お屠蘇とお節料理を頂き、お年玉を手渡すのが、我が家の正月の慣わしとなっています。 その後は近所の氏神様へ初詣に出かけたり、寝正月といろいろですが、ついたちの朝の慣わしは気持ちも引き締まって、これからもずーと続けていきたいと思います。 |
お正月・・・(旧姓の頃) |
それでも大体の鐘の数だけ鳴らした後は、その仲間の家に集まって夜の更けるのも忘れて、一年の出来事を語り明かしたものでした。(どんな流れで決まったのかは忘れましたが、毎年集まる家は違っていた様に思います。) 夜更かしをして帰っても、眠たいなんてはお構いなしで、六時半になると、お仏壇でお経をあげる父の声の恨めしかった事。 昔の時代は父親の言う事に逆らったりしませんでしたからね。 懐かしい楽しい思い出です。 |