1 北極圏の温暖化?身近に忍びよる影~「2050年の世界地図」からの警告
2012年12月5日、九州電力LNG受入基地がある北九州市戸畑港にロシア・ロスアトムに所属するガスタンカー「オビ・リバー」号が入港した。
同船は耐氷型のガスタンカーで、約13万5千立方メートルのLNGを積んで、同年11月7日ノルウェー北部・ハンメルフェスト港を出航し、冬期に入った北極海をロシアの二隻の原子力砕氷船の随伴を受けて北東航路を通過してきたものだが、冬期時のアイスクラス(耐氷型)のガスタンカーによる新規ルート開拓の成功の裏には、我々の身近な形で表れた「北極圏の温暖化」が見え隠れする。
このような北極圏の温暖化について、米・UCLA地理学教授のローレンス・C・スミスは、北半球北部の水文学・氷河・氷床・永久凍土等の研究・探査などから、気候変動が寒冷圏に及ぼす影響を科学的に分析した結果を、2010年「The
World in 2050:Four Forces Shaping Civilization'sNorthern future(邦題:「2050年の世界地図」~迫りくるニュー・ノースの時代)」(以下「2050年の世界地図」という。)として発表し、近未来の「北極圏」について詳述している。
2 「2050年の世界地図」に見る北極圏の気候
⑴ 北極圏の温暖化は避けられない
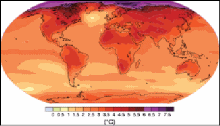
「2050年の世界地図」は、国連機関「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)」の「第4次評価報告書(2007)」中の右図のような複数の気候予測モデル(3パターン:将来想定される温室効果ガス濃度、エネルギー技術、GDP、人口増等の要素を元にして作成)を取り上げ、三つの気候予測モデルのいずれにも現出している「北極圏の温暖化(楽観的な数値から悲観的な数値の幅での)」が、CO2排出規制など技術面でどういう方向に進もうとも、避けられないものだと指摘している。
⑵ 温暖化は北極圏で大きく増大~北極海の海氷消滅
これらの気候変動には地理的なばらつきがあり、上図のとおり、温度の上昇幅は海上よりも陸上が大きいが、とりわけ北極圏の温度上昇が激しい。
「2050年の世界地図」は、このような気候予測モデルの全てのパターンが、地球規模の気候変動は北極圏で大きく増大することを繰り返し伝えているとして、北極海の「海氷の消滅」の不可避性について言及している。
2007年7月における北極海の突然の気象現象(北極海の海氷の40%近くが消滅)は、「2050年の世界地図」の著者を初めとする研究者に衝撃を与えた。
IPCCの気候予測モデルから、2050年夏の海氷消滅を論議していた研究者にとって、その予想を超えた余りにも早い海氷消滅だったのだ。
その後も、夏期における北極海の海氷消滅は進み海氷域面積は年々減少傾向で、2016年夏は観測史上最小の面積(約340万平方キロ)を記録した。
3 「2050年の世界地図」が描く北極海航路海運ルートの可能性
北極海航路(北東航路)は、1878年にスウェーデンの蒸気船「ヴェガ」号により航路が発見されたが、20世紀の終章までは海氷による海路の凍結など厳しい気象条件から海運ルートとして開通することはなかった。
2007年からの海氷消滅の現象は、地球規模の環境破壊の証左と捉えられる反面北極圏の温暖化のメリットとして、北極海航路経由の国際的な海運ルートの可能性が注目され始めた。
航路として開通できるのは海氷が縮小する夏期の2ヶ月のみで、耐氷型商船でも他の期間の海氷に覆われた北極海は航行不能である。航路としての恒常的運航は期待できないが、将来的な北極圏の温暖化により、海氷縮小の規模の拡大に伴い航行可能な期間が長くなると予想される。
また、欧州~アジア間の航路としてのメリット
○ 航行距離が1万2千~1万5千kmとスエズ経由(約2万km)ケープタウン経由(約3万km)に比べて輸送時間の大幅短縮、輸送 コストの大幅削減が可能
○ ソマリア海域(海賊問題)、アデン湾(国際紛争)、マラッカ海峡(航路狭小)などのチョークポイントが皆無
から、アジア・欧州の各諸国が関心を寄せている。
「2050年の世界地図」は、このような北極海航路の優位性を認めながらも、将来的に解決しなければならないリスクを挙げている。
○ 重砕氷船の絶対的不足
海氷でも多年氷(硬く、厚さ5mに達することもある)を破砕できるポールクラスの重砕氷船は、ロシア14隻前後、アメリカ3隻、カナダ2隻と少ない。
○ NSRA(ロシア北極海航路局)運航規則による制約
国連海洋法条約第234条に依拠したロシア北極海航路局の「運航規則」により、北極海航路を運航する耐氷型商船は2隻の砕氷船の随伴を義務づけられており、北極海航路の運航が本格化すると重砕氷船の絶対的不足からダイヤグラムの作成が困難
○ 海運ルートとしての採算性
航路の不安定性(運航期間が短期間、運航可能期間が予測不能)、建造単価の高額な耐氷商船の建造、沿岸港湾の未整備(岸壁が大型船に未対応、荷役に必要なインフラの不足等)、海氷航行による航行速度の低下など採算的なマイナス要因の存在。
このようなリスク以外にも、ロシアが恣意的に設定可能な「NSR運航規則(通行料の課徴も可能)」や「砕氷船随伴費用など輸送コスト」など、今後どのようになるかリスキーな部分もある。
4 北極圏で展開するフィールドゲーム~「2050年の世界地図」はどうなるか?
2008年、USGS(アメリカ地質調査所)は、環北極圏資源評価を発表(北極海に世界の未発見天然ガスの30%、未発見原油の13%が存在)し、北極圏諸国(ロシア、アメリカ、カナダ、デンマーク、アイスランド、ノルウェー、フィンランド、スウェーデンの八カ国)に少なからぬインパクトを与えた。
ソ連崩壊による冷戦終結後、北極圏における地政学的相剋(とりわけアメリカとソ連との関係)は、海氷と同様に急速に溶解し、北極圏諸国による軍事力のプレゼンスも縮小していたが、新たなる埋蔵エネルギー資源の存在は、2009年以降北極圏諸国に軍事的復活の動きを活発化させた。
「2050年の世界地図」は、このような動きを
○ アメリカ
「北極政策」を国家安全保障等の優先課題のトップに位置づけ、アラスカ配備の兵力(陸軍・空軍・沿岸警備隊等2万5千人)を維持、大陸間弾道ミサイル迎撃施設をアラスカ・フォートグリーリー基地に建設
○ ロシア
北方艦隊を一新(2020年までに新型攻撃潜水艦、弾道ミサイル搭載原子力潜水艦を建造、5~6群の空母打撃群を構成可能な艦船 数の拡大)、カナダ・アラスカ・北欧諸国の空域付近への長距離爆撃機の巡回再開、北極海フランツ・ヨシフ諸島とノボシビルスク諸島に2空軍基地の建設を計画
○ カナダ
カナダ北方領土と北西航路に対する主権を再確認、耐氷型哨戒艦の新造、レゾリュート湾に軍事訓練基地を建設、砕氷船1隻を調達
○ ノルウェー
統合戦闘システムのイージス艦5隻を調達、F35ジェット戦闘機50機購入の計画
○ フィンランド・デンマーク・スウェーデン
相互同盟もしくはNATO加盟の可能性を検討
○ アイスランド
安全保障の強化について検討
として詳述している。
2015年8月4日、ロシアは国連大陸棚限界委員会(CLCS)に対し、北極海の120万平方キロにわたる範囲を自国の大陸棚の延長とする申請を行った。この範囲にはデンマーク、カナダも支配権を主張しているロモノーソフ海嶺などの海嶺が含まれており、北極海海底の領有を主張する北極海周縁の各国の思惑とも対立するもので、ロシアの北極海での覇権を求める野望を含蓄したこの申請の取り扱いがどうなるか注視されるところである。
5 北極圏の盟主になりえるか?~ロシアの東方回帰の行方
⑴ 甦った「双頭の鷲」
2012年5月、再選されたプーチン・ロシア大統領は施政方針演説において「アジアシフト」を宣言し、2013年3月にロシア極東地域の経済発展を「最重要の地政学的課題」と位置付けた「極東及びバイカル地方の社会・経済発展に関する国家プログラム」を策定した。
国家大計として、ロシアの「国章」の双頭の鷲(東ローマ帝国に由来し、帝政ロシアのローマ帝国正統後継を表す。ロシア連邦の発足により「国章」として再度復活した。「双頭」はアジアとヨーロッパに渡る統治権を象徴している。)を具現化し、世界に冠たるユーラシア大国(強いロシア)を建設しようとするものである。
しかし、その背景にはロシアが東方回帰せざるを得ない真の理由がある。
⑵ 「グラーク(強制収容所)」に支えられたシベリアの開発
歴史的に、帝政ロシア時代に端を発する「シベリア経営」は、同時にロシアの毛皮商人や金鉱目当ての山師などが行き来する以外は先住民がまばらに存在しているだけの荒涼たるシベリアへの「ロシアからの移民」政策の始まりでもあった。
帝政末期のシベリア鉄道の全線開通(1916年)に加え、帝政時代からの反体制派に対する「シベリア流刑」、ロシア南部地域の人口飽和、農奴制の廃止等を受けてシベリアへの移民政策が進められ、シベリア地域も徐々に人口の増加が見られたが、シベリアの大幅な人口増・工業化が進められたのは、スターリン専制下の「グラーク(強制収容所)」システムによる強制的な労働力の移住によって成しえた部分が大きい。
1920年代末にソ連共産党と政府を完全掌握したスターリンは、反動分子粛正の名の下に大規模な政治的弾圧を行い、多数のロシア人政治犯が一般犯罪者とともにシベリアの「グラーク」に送られ、その数は1940年には200万人以上に上ったといわれている。
これら流刑者たちが鉱山開発、森林伐採、道路・鉄道・工場などのインフラ整の過酷な使役に従事し、今日のシベリア地域の礎を築いたのだ。
そして、過酷な労働に耐え生き残って刑期を終了しても帰郷を禁じられた流刑者の家族達が逆に流刑地の近くに移住(強制的定住)し、町を形づくっていった。
このようなシベリアの歴史上の暗部を踏まえて、シベリアの工業化も進み、流入する人口も増加し、中国国境と接するロシア極東地域についても1990年にはロシア極東地域全域で804万人弱の人口を擁するまでに発展した。(2012年「ロシア極東ハンドブック」資料編:東洋書店発行)
⑶ 「ソ連崩壊」によるシベリアの地盤沈下~人口の減少
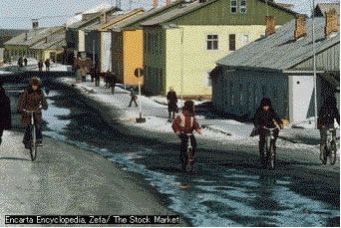
しかし、1991年のソ連崩壊(冷戦の終結)により、シベリアの地政学的な存在意義が低下し、政治的・軍事的配慮から続けられていた中央政府からのシベリア地域に向けた優遇措置(辺境住民に対する「割増給与」など)も全廃された。
ソ連の計画経済のもと、「富の傾斜配分」により人工的な経済繁栄を享受してきたシベリア経済も、自由市場体制に急速に移行し(というよりも、放り出され)たが、非効率な生産活動が常態化していた経済構造により、これら急激な環境変化に十分に対応できず慢性的な構造不況に見舞われた。
このようなシベリアの地盤沈下は、経済的メリットを無くした人々のシベリア地域外への人口流出となって表れた。とりわけ、「シベリア寒気団」の凍える寒さに晒されていたロシア極東地域の住民達の、温暖で生活利便も確保されているロシア南西地域等に向けた人口流出が急激に増加した。
ピーク時に800万人を超えていたロシア極東の人口(1991年)は、2013年には625万人と20%以上減少し、今後とも減少傾向は続くと予想されている。
⑷ 中国の影に怯えるロシア~「タタールの軛(くびき)」の悪夢
一方、ロシア極東地域と長い国境線で対峙する中国では、1970年末からの改革・開放経済による経済成長により旺盛な経済活動が国境付近でも活発化した。
このような状況は、表面的には露中の国境を跨いだ経済交流の進展として捉えられるが、中国国境に接するロシア極東地域(南部)の対中国貿易依存度(2009年)を見ると、沿海地方55.8%、ハバロフスク地方50.2%、アムール州83.8%、ユダヤ自治州98.0%(2012年「ロシア極東ハンドブック」:東洋書店発行)と、中国の経済活動に組み込まれているロシア極東地域の実態が浮かび上がってくる。
また、ロシアと国境を接する黒竜江省など中国東北3省の人口は1億人以上で、労働力不足となっているロシア極東地域への労働力供給地域としての存在感を増しているが、ロシア極東地域に労働者として入り込んだ中国人は、その地域にとけ込むことなく排他的な「中国人共同体」を形成し、実質上、ロシア極東地域の「中国化」の拠点となっている。
また、中国人の不法滞在も増加の一途をたどり、2012年だけでもハバロフスク地方で千人以上の中国人が不法滞在(偽の就労証明書で在留許可を取得)で「ロシア連邦保安局(FSB)」から摘発されたという。
2013年には「極東の耕作地帯」としてロシアの大豆生産の過半を占めるアムール州の州政府は、広大な農地を求めて大量に流入する中国人労働者を抑制するため、中国人労働者による農耕作を禁じる措置を施したが、実効性の無い施策として形骸化しているのが現状だ。
中国東北3省の1億人を超える人口は、600万人台の人口をかろうじて維持しているロシア極東地域にとって、労働力の供給源以上の圧倒的な「人口圧力」として、13世紀の「タタールの軛(くびき)」の悪夢を甦らす恐怖の対象となっているのだ。
⑸ 対中国を意識したロシア軍の改編~右手で握手、左手で手拳
このようなロシア極東地域の経済的停滞、大規模な人口減(労働力の枯渇)は、この地域の民生力の衰退として、ロシア極東の安全保障に暗い影を投げかけた。
加えて、2008年10月の中国艦船4隻による津軽海峡通過(日本海→太平洋)は、温暖化する北極海への中国海軍の近い将来の進出のシグナルとして捉えられ、忍びよる新たな中国の脅威としてロシアに危機感をいだかせた。
中国の圧倒的な民生力を背景としたプレッシャーを受けたロシアは、ロシア極東の領土・領海の保全及び国境管理(なし崩し的な「ロシア極東の中国化」の浸透を阻止)の徹底に向けて、2010年2月に「軍事ドクトリン」を改訂し、同年末までにロシア軍の改編(軍管区の統合:6軍管区→4軍管区)を行った。
ロシア極東地域については、従前は中国との国境線を2軍管区によりカバーしていたが、これを東部軍管区の一元的対応に移行するとともに、同軍管区に「統合戦略司令部(OSK)」を設置し、軍管区内の陸・海・空軍部隊の統一的指揮機能を与え、有事即応体制を強化した。
このような流れを背景にプーチン大統領は、2013年12月20日モスクワで開催された国境警備に携わる保安機関職員会合で「カフカス・北極・極東の国境の保全システムの改善に真摯な注意を払うよう」指示した。
また、北極圏・ロシア極東地域における中国の影響力の拡大を受け、2014年2月6日、ロシア東部軍管区司令官(セルゲイ・スロビキン)と日本の陸上自衛隊陸上幕僚長(岩田清文)が会談し、東部軍管区代表の来日で基本合意するなど、中国の軍事的台頭を意識した露日の軍事的連携も見据えた動きも垣間見える。
加えて、ロシアは北方艦隊の一新(2020年までに新型攻撃潜水艦、弾道ミサイル搭載原子力潜水艦を建造、5~6群の空母打撃群を構成可能な艦船数の拡大)により、温暖化するロシア極東海域を含めた北極圏でのプレゼンスを強化し、北極圏の盟主としての地位の確立を図ろうとしている。
⑹ ロシア極東地域開発の成否~帝政ロシアからの歴史的課題
ロシア政府は、2013年3月に策定した「極東及びバイカル地方の社会・経済発展に関する国家プログラム」に基づき、2020年を目途として、経済的停滞と人口減が続くロシア極東地域に道路・鉄道・港湾等のインフラ整備などの大型プロジェクト投資(約9兆ルーブル)を行うこととしている。
その狙いは、温暖化する北極圏・ロシア極東地域の豊富な天然ガス等のエネルギー資源を開発し、経済成長の著しい東アジア市場(中国・日本・韓国)に売り込むことである。
従来、ロシアの天然ガスの需要先として重きをなしていたヨーロッパ市場は、経済的成熟期を迎え、今後の需要の拡大は期待できない。
これに対し、高成長を今後も維持すると見られる東アジアは、そのGDP比率が2030年頃には世界全体の過半を占めると予想されており、エネルギー資源輸出が国家の生命線となっているロシアにとって、旺盛なエネルギー資源需要が見込まれる東アジア市場の開拓は喫緊の課題となっている。
しかし、このような大型プロジェクト投資はインフラ整備としての効果はあるものの、果たしてそのことがロシア極東地域の持続的な民生力の強化(地域産業の振興、雇用の創出、生活利便の向上、住民に対する優遇措置等)に繋がるか疑問である。
また、ロシアが天然ガスの大口需要先と目している日本では、アメリカ・カナダからの安価なシェールガス(LNG)の輸入(日本の年間輸入量約8700万トンの約20%)が予定されており、高値のロシア産天然ガスの日本への輸出の見通しは明るくない。
2014年3月に勃発した「クリミア危機」をめぐりロシアとウクライナは今後とも緊張関係が続き、ロシアのウクライナに対する天然ガス供給停止等経済制裁は必至の情勢であるが、安易なガス輸出停止は西側の経済制裁(原油・天然ガスの輸入制限、投資抑制等)を喚びロシア経済への悪影響(ロシア原油の70%が欧州向け→原油価格の下落)が懸念される。
ロシアは2016年連邦予算の歳入編成の基準となる原油予想価格を公称で1バレル50ドルに想定し、国家予算の収支のバランスを図ろうとしているが、原油価格の急落(1バレル30ドル台)はその足下を大きく揺るがし、歳入は当初予想を大きく下回っている。このような財政事情の悪化を受けて、極東開発省は極東開発計画の予算削減を決定している。
「シェールガス革命」の進展により資源大国ロシアの優位性も揺らぐ中、エネルギー資源輸出による収入が連邦予算のほぼ50%を占めるなど恒常的に財政基盤の脆弱なロシアの将来は予測しがたく、エネルギー資源に依存する経済構造を抱えたロシアの未来に展望は開けていない。極東開発計画のような大規模な国家プロジェクトを完遂できるだけの財政的能力をロシアが有しているのか見極める必要がある。
ロシア極東地域の開発は、帝政ロシア以来の歴史的課題であり、「グラーク」システムなど強権的施策を押し進めた旧ソ連の力をもってしても解決困難であった。
その足枷となっていたのが、シベリアのツンドラ気候であった。
アメリカの西部開拓のスタート(1848年:カリフォルニアでのゴールド・ラッシュ)に二百年も先んじて始まった帝政ロシアのシベリア進出(1639年:コッサクのシベリア横断)にもかかわらず、温暖な地中海性気候の沿岸部を抱えるアメリカ西部地域(人口五千万人超)の現在の繁栄に比して、人口640万人が点在するだけのロシア極東地域の抱える課題は多い。
ロシア極東地域でのリトライが、プーチンの「Legacy(歴史的な遺産)」となるか、それとも「Legacy Issue(負の遺産)」となるか、その成否が注目される。
6 「2050年の世界地図」~「The North Pole」から俯瞰する世界
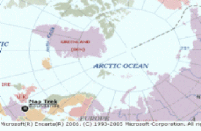
2013年9月、「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)」は「第5次評価報告書(2013)」で地球温暖化の現状と今後の予測を発表した。
この報告書にある地球温暖化の進行や北極海における雪氷量の減少は、「2050年の世界地図」で著者が警告していた懸念を裏付けるものである。
「2050年」という近未来を取り上げた類書も散見されるが、これらは社会科学という経験科学的側面からの論旨の展開を行っており、推測・推論の域を出ていない。その点、自然科学的側面から得た科学的知見を網羅し、確たるデーターで描く「2050年の世界地図」の地球の未来像には説得力がある。
ただ、人口問題・食糧問題・自然保護・海面上昇・エネルギー問題・水問題・地政学的相剋など広範囲にわたる博覧強記の著者の論理展開は間口が広すぎ焦点が絞りにくい趣もある。とは言え、「2050年の世界地図」は環境保護を重視するサイドからは地球環境に対する警告書として一読の価値があり、北極圏の温暖化が開く可能性を希求する立場の人にとっては展望の書ともなりえる一冊である。
見方が異なるにせよ、「2050年の世界地図」は、「The North Pole(北極点)」から俯瞰する地図が我々の視座となるのは間違いない。
