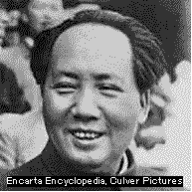「中国農民調査」とは
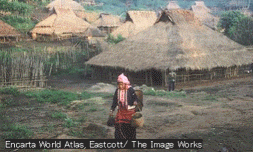
本書「中国農民調査」の原著は、2004年1月に、当時の中国農村の実態と中国農村政策の問題点をとらえたルポルタージュとして中国で出版され、2ヶ月あまりで発禁処分を受けた。
「中国農民調査」著者の陳夫妻は、「訳者あとがき」にあるように、決して中国共産党の独裁体制の批判はしておらず、本のタイトル名も毛沢東が解放前に行った「農村調査」に由来しているもので、著者夫妻の虐げられた無辜の農民を慈しむ真摯な姿勢が、逆にあまりにも生々しく農村の窮状と中国農村政策の欠陥を浮き彫りにし過ぎた。
また、このルポは中国社会の深部に内在しているこのような実態が中国崩壊という国家の存立を大きく揺るがす「危機要因」として看過できないものであることを全世界に示した。
その様な背景がある中で、この「中国農民調査」などが取り上げた「三農問題」は、2004年年3月の全国人民代表大会の政府活動報告で政策的用語として認知され、「三農問題」の解決は胡・温政権の最重要政策課題として位置づけられた。
中国全土に衝撃を与えた本書が発禁処分になってから早や十数年が過ぎ、その間中国では都市部を中心にした経済成長が著しく、表面的には今や世界第二位の経済大国の地位を占めるまでになったが、その反面、此の「三農問題」は依然として
Vital issue (核心的問題)として残置されていて、「三農問題」を抱えた農村の疲弊はますます進み、農村と都市との経済格差もほとんど解消されていない。
十数年前に本書「中国農民調査」で指摘された問題点は果たして解決されたのか、それとも無為に過ぎた「失われた十年」として中国崩壊という体制の危機に至ろうとしているのか、もう一度本書「中国農民調査」の第2章「何が問題なのか」を中心に繙(ひもと)き考察したい。
「中国農民調査」が指摘する中国農村問題の本質
「中国農民調査」の核心~解消されない「三農問題」
本書「中国農民調査」において「三農問題」は、具体的には「農業」の低収益性と低生産性、「農村」の荒廃、「農民」の低所得と高負担の問題として規定されている。
この「三農問題」のもともとを辿れば、毛沢東の大躍進政策の失敗と人民公社の崩壊に端を発しているが、さすがにこの部分については「中国農民調査」では、アンタッチャブルな領域として触れられていない。
現在の「三農問題」の根源に深く関わる「生産請負制」・「郷鎮制」・「農村戸籍」等は、農村の人・モノ・金という資源を都市化・工業化に傾斜配分するための施策として逐次制度化され、長年にわたり、農業からの搾取や農民の差別が行われてきた。
加えて、80年代半ばのいわゆる「先富論」による沿岸部での特区制定などにより繁栄する都市部に比して農村部はますます立ち後れ「三農問題」はより一層深刻化した。
一つ目の「農業」の問題であるが、本書「中国農民調査」発刊時における農民一人当たりの耕地面積約0.4haは十数年後の現在もほぼ変わらず、日本の平均耕地面積1haよりも半分以下の規模である。
このため、農業の集約化・大規模生産等による生産性の向上や収益性の改善、国際競争力の強化等は見込めない。また、1989年の「天安門事件」を契機に、都市部対策としてとられた「物価抑制政策」により農産物価格は抑えられ、今もって中国の農業は貧農の状態から脱していない。
必然的に、農民は現金収入を得るため都市部へ出稼ぎに行かざるを得ないが、2003年中国国務院白書「中国の雇用状況と政策」によれば、当時その数だけでも9,800万人を超えていた。以来、農民工の総数は右肩上がりで増え続け、2013年「中国国家統計局・中国農民工調査監視報告」発表では、2012年現在の農民工総人数は2億6千万人に達している。
「中国農民調査」で指摘された零細化した農業の低収益性・低生産性は、我が世の春を謳歌している中国経済のアキレス腱であることに変わりはない。
二つ目の「農村」の問題であるが、中国の急速な発展(工業化、都市化)は、大量の農地を都市用地に転換したことにより成り立った。改革解放が始まった1978年からこれまでに1,000万haを超える耕地が消失し、「2011年中国都市発展報告」(中国社会科学院)によれば、その失地農民数は四千万人を超えると言われている。
また、地方政府によるこのような「土地の強制収用」は、全国的な「群体性事件(集団抗議活動)」の高まりの誘因となっており、中国政府の統治機能を脅かす社会問題となっている。
ひとたび土地を失った農民は収入を得るために 農民工となって都会に流れ込み、農村に残るのは老人・婦女子が主になり、農業の担い手を失った農村はますます荒廃しているのが現状だ。
今後、中国のバブル崩壊などにより過剰農民の受け皿となっていた都市部経済が収縮しても、職を失った大量の農民工の帰る故郷はない。
三つ目の「農民」の低所得・高負担の問題である。都市と農村の所得格差は「中国農民調査」発刊時の2004年には3.2倍であったが、2016年現在で2.73倍(「中国国家発展改革委員会」発表の政策的数値)とその格差は相変わらず大きい。
この間の所得格差の微減に貢献したのは、出稼ぎ労働者の賃金の上昇分であり、これを差し引くと本来の農村所得の上昇とは言えない実態が浮かんでくる。農民は今もって都市部との所得格差に苦しんでいる。
もう一つの「高負担」の問題を見ると、2006年の人頭税的な「農民税」の廃止などにより、表見的には、過剰負担の軽減が進んでいるかに思われるが、これにより農業への課税が無くなった訳でなく、農家も年収が800元以上あれば税金は徴収される。つまり都市と農村の税制度の一本化がされたに過ぎない。
過剰負担の悪弊の象徴であった「三提五統」の廃止は、農民の負担を大きく軽減したことは間違いないが、そのしわ寄せは郷鎮政府の問題に大きく転化され、「三農問題」をより複雑化している。
「中国農民調査」の要約版「中国農民の『九大痛苦』」
本書「中国農民調査」に前後して、その出所・典拠は不明であるが巷間に流布された 「中国共産党が中国農民に与えた九大痛苦」 なる文書も農民の痛みを赤裸々に訴えた内容で、「中国農民調査」と同様に、今目を通しても肯く部分が多い。田治一基氏の翻訳による全文を参考として掲載する。
「さかのぼること200年、中国人として生まれることは、幸せであった。しかし、今日、中国人として生まれることは、そんなに幸せなことではない。とりわけ中国の農民として生まれることは、苦しみである。(中華人民共和国)建国後、我々は“追いつき追い越せ”戦略、すなわち短期間に国の総合力を向上させ工業化を迅速に実現する戦略を実行した。
この戦略の下、中国の都市と農村で“二元構造の管理モデル”を実行した結果、都市と農村の対立を生じさせ、また、異なる2種類の管理方法の採用により二つの構造(都市と農村)間の移動が制限を受け、資本は優先的に都市に向けられた。
二元構造の重要な標識は戸籍制度である。当然、二元制管理構造は中国の工業化の進行過程に対して巨大な推進作用を果たし、現代中国の工業システムの構築及び中国の工農業の鋏状価格差(工業製品の価格と農産物の価格との差)の上において相当程度有益な結果を得た。
現在、中国の市場経済はすでに数年の歳月を経ており、二元制構造は依然改変の兆しは無い。農民問題、農村問題は、すでに現代中国社会の安定に対する潜在的不安材料となっている。これらは全て二元構造が引き起こした災いと相当程度言うことができる。
現在の中国農民は、言うに耐えられない苦しみを受けていると言え、要約すると“九大痛苦”が有る。この苦しみに対して必ず手段を講じ一歩一歩解決しなければならない、そうでないと中国農民は苦しみを受け止め、耐えることが出来ずに、社会危機が絶対に爆発する日はそう遠くないだろう。
第一の苦しみ、大量の役人の扶養
中国の政権体制は、高度の中央集権体制を行っており、中央と各地方の行政機関は巨大な公権力を保有しており、また中央と地方の各級行政機関の五大グループ(中央、省、市、県、郷)は世界で最も膨大な官僚機構を形成している。
これらの官僚機構の運営と人件費は中国の財政収入のほとんどを食べ尽くしてしまう。とりわけ県・郷の両末端機関に至っては、地方財政収入では多数の役人を扶養出来ず、不足部分は民衆から取立てるのが末
端機関の現実的選択となっている。
あらゆるでたらめな費用取立て、でたらめな平均負担割りの根源は、すべて膨大な行政支出から生じる地方財政不足から源を発している。また、両末端行政は巨大な公権力を有し、その手中の権力を利用して民衆、とりわけ広大な農民に直接割当てていて甚だしいものは現代中国農村における公害ともなっている。
報道によれば、中国の最末端行政機関の郷・鎮の行政機関の債務はすでに2千億人民元に到達し、農村信用協同組合・中国自助基金はすでに或いはまもなく崩壊しようとしている。
第二の苦しみ、教育難
農村の教育資本はもともと乏しく尽きており、数多の農村の教師の給与は常に支払いが滞っている。農民の教育難は争えない事実で、このことはすでに古い話題となっている。また教育の産業化政策の下、数多くの農民の子弟は高校・大学へ進学してさらに官吏になることが困難になっている。
中国農民の子弟の教育難は、一つには教育資本の乏しさを表し、これはハード面ソフト面を含んでいる。二つには教育費とりわけ大学の費用が農民の収入に対し非常に高額で支払いが困難である。三つには各省、市の大学入試は同じで無く、それぞれ異なる採点方法を採用しており、広大な農村地区と都市を対比すると大学入試の採点差は非常に大きく、農民子弟に対して公平さを失っている。
農民子弟は大きな困難を経てやっと大学入試の大きな関門に到達出来るが、さらに都市住民子弟との高いハードルを越えてこそやっと大学へ入学できる、これは実に不公平である。
第三の苦しみ、移転難
中国の都市と地方の二元制構造は中国を身分制社会にした。都市とりわけ大都市に生まれた者は丁度天国に生まれたのと同じであり、政府の資本は全て中心都市に向けられる。しかし農村とりわけ遠く辺鄙な農村に生まれた者は地獄に生まれたのと同じである。
中国の農民は自己の居住条件を改善しようと寂れて荒涼とした農村に別れを告げようとした時、移転の自由は無い。都市に移転して仕事に就く農民は身分の役職制限により全ての面で都市と無関係で、とりわけその子弟の就学は大変困難である。
中国社会の現実は極めて複雑であるため人口の流動を放置することはよくないが、一 つの省、市、区において農民に移転の自由を持たせるべきである。
第四の苦しみ、社会保障の欠乏
農民には養老保障は無く、ほとんど子供の家庭で養老され晩年を過ごす。これもまた中国農村の計画出産の数々の障害の重要要素である。また、農民の医療保障はさらに議論する余地は無い。社会保障の欠乏は農民の第四の大きな苦しみである。
第五の苦しみ、観念(見識)の立ち遅れ
農民として生まれてきたことによってほとんど土地に固定され見識が浅く、同時に後日教育を受ける権利も保障が欠乏している。このことは中国の多数の農民の見識が普遍的に立ち遅れており、とりわけ未発達地区の農民に至っては甚だしきは無知蒙昧である。
これは彼らの第五の苦しみである。観念の欠如によって、相当な困難な生活を送り、多くの苦しみを生み出している。とりわけ法制観念の立ち遅れと臆病で余りにも用心深い伝統的な考え方は、多くのその他の苦しみを派生させている。
第六の苦しみ、資源の欠乏
中国各地の資源はすべて計画的に分配される。それゆえ中心都市は優先的に各種資源を得ることが出来る。すなわち中央財政当局の誘導で成り立つ。そして地方都市は、地方財政の政策を優先して取捨できる。
各種資源が都市に長期に渡って偏った結果、中国農村での各種資源の欠乏を招いた。教育、医療、道路資源など一連の資源は農村において極端に欠乏している。
第七の苦しみ、表現の権利の欠如
中国の政策決定者は全て都市に住んでおり、たとえ農民が人民代表者大会委員に選ばれても、素養が低いことによって真に多数の農民に代わって発言することは出来ない。
だから中国の農民はもともと表現の権利は無く、上部機関に向け自分の権限を反映させる方法は無い。 当然彼らの表現能力は低く、また他の人が彼らに代わって表現することも無い。表現の権利がないことは中国農民の第七の苦しみであると言う事が出来る。
これは政策決定者が政策を決定する際、真実の情報が全面を占めたり、数多くの農民の声を届けることは困難であるため、より良い政策を行う保障は困難である。
第八の苦しみ、創業と財を得ることの困難
中国農村の各種資源の乏しさと政策保障の欠乏は、中国農村における創業を困難ならしめ、経済的に立ち遅れて、農民の収入は低く、金を稼ぐのも難しい。
消費も低迷し、中国農村経済は、一種の悪循環に陥っている。 ここ数年来“農民の収入を高める”といったむなしいスローガンは、農民が金を稼ぐことが難しいことから実現は困難である。
第九の苦しみ、常に侮辱を受ける
我々の都市・地方の二元制構造が長期に渡って行われた結果、都市の住民に、その内心の奥に強い優越感を生じさせた。この制度はそれ自体・それ自身ある種の意義の上から強い差別的傾向を帯びていたと言える。
中国農民の素養は低く自己防衛の理解も無く、また防衛も出来ない。上訴の道も無い。農民が常に侮辱を受けることは一種の普遍的な現象となっている。
締めくくると中国の農民は以上のように苦痛だらけであると言うべきである。しかし、これは全て相当程度は中国の国情が決めたものであり、追いつき追い越せの戦略の必然的結果である。
今日、中国はすでに工業化を加速する段階に入っており、政府は当然中国農民の苦しみを正視するべきである。
経済面においては、都市化建設の加速を通じて中西部地区の公共施設への投資を増大する。
政治面では、農民に表現の権利を持たせる、とりわけ表現と上申権と上申のルートを拡大させる。
政策決定の体制において、農民を代弁する機構を作る。
管理体制上においては、出来るだけ早く都市農村の二元制対立の構造を終結させ県から市・省に至るまで一歩一歩広げていく。
その他に、役人とりわけ県、郷の役人を整理減少させ、利益獲得で人民と競争させない。
当然、中国農民の苦しみは、全ての発展途上の国家が直面する問題で、農業国が工業国に向かって進展変化する上で必ず通る段階であり、発展中の問題である。中国経済の進展に従って中国農民は苦界の日々から逃げ出すのもそう遠い先ではない。」
※ この「九大痛苦」の最後に、この「痛苦」は工業化への段階で必ず起きる発展中の問題と指摘しているが、似たような混乱は、その形 態に多少の差異はあっても日本を含めた工業先進国でも「工業化」の過程で経験した事象であることは間違いない。
ただ、中国のように半世紀を超えてもなお問題解決に至らず、多くの農民が苦界に沈んだままでいる例は過去に見当たらない。