- 《目 次》
- 1 ツキジデス「戦史」における基本テーマ
- 2 ポリスの誕生
- ⑴ ギリシャの地勢
- ⑵ 先史時代のギリシャ人の民族分布
- ⑶ ポリスの誕生
- 3 アテナイの海上交易
- ⑴ 海上交易による「富の蓄積」と「食糧の確保」
- ⑵ 新たな「セキュリティ・リスク」となったアテナイの「シーレーン」防衛
- 4 スパルタの国内統治システム
- ⑴ スパルタの支配体制
- ⑵ スパルタの軍制
- 5 ペロポネソス同盟の誕生
- 6 アテナイの台頭
- ⑴ 「イオニア反乱」におけるアテナイの台頭
- ⑵ 「ペルシャ戦争」の勝利と「ヘラスの盟主」アテナイの登場
- 7 スパルタの盟主からの転落
- 8 「デロス同盟」の結成
- ⑴ 「デロス同盟」の変貌、アテナイの「覇権主義」
- ⑵ アテナイの「覇権主義」を助長した同盟諸国の愚挙
- 9 アテナイとスパルタの決定的な離叛
- ⑴ アテナイの政治的指導者ペリクレスの「主戦論」
- ⑵ 「エピダムノス・ケルキュラ紛争」の勃発
- 10 ペロポネソス同盟の開戦決定とスパルタ王アルキダモスの諫め
- 11 ペロポネソス戦争の長期化とアテナイ・スパルタが抱えた「セキュリティー・リスク」
- ⑴ アテナイにおける疫病の発生
- ⑵ アテナイ艦隊の機動作戦に翻弄されるペロポネソス勢
- ⑶ 将軍プラシダスによるスパルタの巻き返し
- 12 和平の機運ー両陣営の事情
- 13 「ニキアスの和約」の成立とペロポネソス情勢の混迷
- 14 アテナイ同盟軍のシケリア遠征
- ⑴ シケリア遠征に向けたアテナイの動き
- ⑵ シュラクサイ民会の動き
- ⑶ シュラクサイ攻防戦の始まり
- ⑷ シュラクサイ攻防戦の転機ースパルタ将軍ギュッポリスの活躍
- ⑸ シケリア遠征アテナイ同盟軍の壊滅
1 ツキジデス「戦史」における基本的「テーマ」
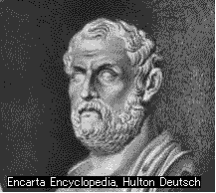
本書の著者は、原語発音的には「トゥキュディデス」となり、「戦史」という書名についても「トゥキュディデス」は何も書き留めてなく、後世の史家がつけたその書名「ΙΣΤΟΡΙΑΙ」からすれば、「歴史」が外題としてふさわしいとされている。しかし、修辞的意味合いを云々するのは本意でなく、我々市井人レベルの利便性を考慮して、この名著を、ツキジデス著「戦史」として読み解いていきたい。
この「戦史」の翻訳本については、久保正彰氏による抄訳版「戦史」が巷間流布しているが、その抄訳部分での翻訳者の解釈の影響を避けるため、オックスフォード版全訳による筑摩書房「世界古典文学全集11
トゥーキュディデース:歴史(小西春雄訳)」を底本とした。
このことにより、久保版「戦史」で大幅に割愛されていた「ナショナル・セキュリティ(安全保障)」関係の各章をほぼ取り上げることができた。
これら各章を総覧すると、本「戦史」が単なる戦史でなく、「ナショナル・セキュリティ(安全保障)」を希求する各ポリスの相克のドラマであることに気付き、そのドラマを鋭い洞察力で分析した「安全保障」論の先達としてのツキジデスの考えをよく理解することができる。
この「戦史」に流れる基本的「テーマ」は、ギリシャ世界に勃興した各ポリスが
○ その「生存」確保という「ナショナル・セキュリティ(安全保障)」のために、いかに各ポリス間で合従連衡(デロス同盟などの結盟 、相対的な防衛条約の締結等)が行われたか~『自衛』のための『他衛』が具体的にどのように行われたか
○ そして相対立する同盟間で「安全保障のジレンマ」という相互不信がどのようにして生まれていったか
○ スパルタを凌駕するアテナイの栄華が何故その覇権主義を醸成していったか
○ 地中海世界へと拡大していったアテナイの覇権主義が新たに抱えた「セキュリティ・リスク」とは何だったのか
等多岐にわたっており、このような「テーマ」に対するツキジデスの冷徹な分析と明快な論理は、現今の国際政治学のメインストリームである「現実主義」理論に通じるものであり、2500年の時空を超えて未だ色褪せていない。
現代の複錯した国際社会の有り様を理解する上での道標としても今なお意味深いものがある。
なお、本稿が「戦史」から引証した部分は「土色」で表示した。
2 ポリスの誕生
〔二〕 ……現在ヘラスと呼ばれる地域に、かつては一定した居住者がおらず、始めは流浪の民であって、数の上で優勢な一団に圧迫されると彼らはそのつど惜し気もなく各人自分の居所を捨てたように見えたためであった。つまり交易が皆無であった上に、海陸を問わず互いに接触することは危険を伴ったので、それぞれ命をつなぐだけの物質を所有するにとどまり、余剰物質も持たず地を耕すこともしなかった。そして日々の命を保つに必要なだけの物資はどこにでも得られると考え、移住の生活を苦にしなかった。このため都市国家としての規模も、また他の蓄財の面でも彼らは強大にならず、特に地味の肥えた土地は居住者の変動がいつも激しかった。それらの地域は今日のテッサリア地方、ボイオーティア地方、それにアルカディアを除くペロポネーソスの大部分、およびその他の土壌のよい地域であるが、地味の豊かなために、特定の人々の力が増大すると、内乱が起こり、全体の発展がさまたげられ、さらに外部からも策謀が企まれることが間々あった。しかしアッティカ地方はその大部分が痩せ地であったために内乱がなく、同じ種族の者たちが昔から変わることなく住んでいた。そのよい証拠は、アッティカが外来移住者によって他の面で無類の発展をした状態に惹かれて、そこに定住したからであった。そして彼らがアテナイ市民に加えられたので、アテナイ市の人口はつとに膨張して、後々アッティカには充分な物資がなかったところからイオーニア地方にまで植民を送り出したのである。(ツキジデス「戦史」巻一第2章)
(1)ギリシャの地勢
(地質)
ギリシャは三畳紀、ジュラ紀、白亜紀の石灰岩の地層により覆われており、後のアルプス造山活動により地形が持ち上げられ、その褶曲作用により国土の70%超が山岳地帯で海岸線も出入りの激しい地形がほとんどである。
また、ギリシャ国土の2/3が石灰岩に覆われていて地味は乏しく、畑作可能な耕地面積は国土の約20%でそれなりの平野が開けているのは、ボイオティアとテッサリアのみである。
これら造山活動の影響を受けた海溝型や断層型の地震が多く発生しているが、このような地殻変動を経てエーゲ海域には数多くの島々が点在している。
(鉱業資源)
活発な地殻活動からマグネシウム(世界埋蔵量9位)、ニッケル(同14位)、銀等各種埋蔵鉱物資源が豊富である。
(2)先史時代のギリシャ人の民族分布
古代ギリシャ人の祖先は、前3000年末頃ドナウ川からバルカン半島に移住してきたインド=ヨーロパ語族のアカイア人と言われているが、その一部が前2000年頃バルカン半島を南下し、現在のギリシャ全域、小アジア西域の沿岸部にイオニア人(中心地アテナイ)、アイオリス人(中心地テーバイ)の集団として居住した。
前1200年頃、バルカン半島北辺からドーリア方言を話すドーリア人が鉄製武具を用いて南下してペロポネソスに進みペロポネソス半島を征服した。先住していたアカイア人たちは「ヘイロータイ(隷属農民)」として奴隷化しドーリア人(中心地スパルタ)の支配を受けた。
(3) ポリスの誕生
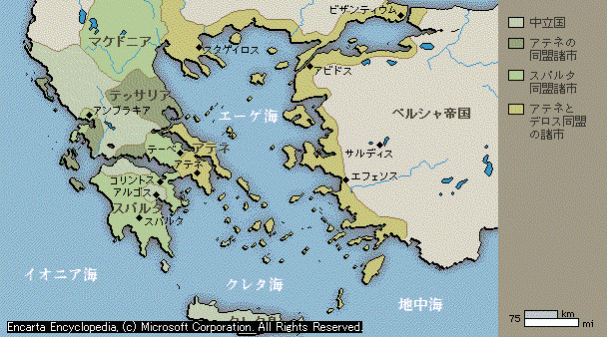
前8世紀初め、ギリシャ人はその国土の地形・地勢に合わせた都市国家「ポリス」を誕生させる。その当時のギリシャ世界では突出した人口を擁したアテナイ(人口10万人)やスパルタ・コリントス・テーベは大規模なポリスであったが、大半のポリスは国家的擬態をとってはいるものの、その人口は、日本における地方の町村同等程度であった。
これらポリスは、急峻な山岳地帯に点在する盆地や海が迫った海岸線の若干なだらかな傾斜地に依拠し、互いのポリスとの往来は険しい山道・谷間・海路などの交通路のため頻繁でなく、ギリシャ内陸部の地味豊かな一部の平野で隣接し合うポリス間の経済的動機に基づく侵略・紛争等から無縁な分立状態が続いた。
また、ギリシャ本土のポリスの発展に合わせて、地中海世界の沿岸各地に対し植民活動を開始し、 〔一二〕……アテナイ人はイオニアやその他の多くの島々に植民し、ペロポネーソス人はイタリアおよびシケリア島の大部、それに他のヘラス諸地域にも植民した。 (ツキジデス「戦史」巻一第12章)」
ポリスは相互に発展するにつれ、海上からの海賊行為や勢力拡大を目指す隣接ポリスとの紛争に対抗するため、その町の居住区域、祭祀場、公共施設等の周囲に城壁をめぐらせた。これは、一部の富裕なポリスを除き大部分のポリスでは農業経済の生産性の低さから飛躍的な人口の増加(ポリスの発展)を望むべくもなく、ある程度の軍事力(市民兵等)で城壁を利した防衛(攻勢側は莫大な損害を受ける)を図るものであった。
当然のことながら、その様な軍事力では隣接ポリスを侵略するだけの能力は無く、侵略しようとしてもほとんどのポリスが多大な軍事力の損耗を賭けるだけの経済的魅力も有していなかったため、ツキジデスが述べたとおり、〔二〕……アッティカ地方はその大部分が痩せ地であったために内乱がなく、同じ種族の者たちが昔から変わることなく住んでいた。……(ツキジデス「戦史」巻一第2章)のであり、以上のようなポリスの誕生の流れの中に、ポリスの「生存」という「ナショナル・セキュリティ(安全保障)」概念に対する意識の芽生えが徐々に培われていった。
(TOPに戻る)
3 アテナイの海上交易
〔一四〕……、アイギーナ人、およびアテナイ人、またその他の一部の都市にも僅かながら海軍はあったが、その多くは五十櫂船から成っていた。アイギーナと戦っていたアテナイ人に、異語族の来寇も予測される頃になって、テミストクレースが漸く船を建造することを説得した。そして事実、この船を使用して実際にアテナイ人は戦った。しかしこれらの船とて全体に甲板は張られていなかった。
〔一五〕……このような状態にもかかわらず、これに関心を払った者は、収入が増えさらに他を征服して大いに国力を貯えた。つまり彼らは、特に充分の領土を持たない者たちは、島々に船で渡ってはこれらを支配下に置いた。…… (ツキジデス「戦史」巻一第14、15章)
(1) 海上交易による「富の蓄積」と「食糧の確保」
ギリシャでの海上交易は、初期(「暗黒時代」の数百年間)は通商目的より海賊行為や農業移民の移住先確保を目的とすることが主であったと言える。その頃、ギリシャ世界での海上交易の担い手となったのは商業都市・コリントスであった。ツキジデスはコリントスについて、 〔一三〕……コリントス人が一番早く現代様式に最も近い船の構造を採用し、三重櫓船もヘラスで初めてコリントス人が建造したといわれている。……これはつまり、コリントス人の都市が地峡に位置していて、当時から常に交易が盛んだったからで、往事のヘラスはペロポネーソスの内部と外部の往来を、海上よりも陸路によってコリントス市を介して交易していたため、彼らは富んで強力になった。この事実は往事の詩人たちによっても示されているとおりで、彼らはこの土地を『富みたる』と形容している。…… (ツキジデス「戦史」巻一第13章)と述べ、海上交易によるコリントスの「富の蓄積」を指摘している。
アッティカ地方の弱小ポリスに甘んじていたアテナイも、前9世紀中ごろ、海上交易の拠点となるピレウス外港一帯の周辺地域を領土に加え、地中海交易の先達であったフェニキア人やコリントスを追いかけることとなった。とりわけ、有望な銀鉱山を有するアテナイで鋳造された良質な銀貨は地中海の海上交易における「兌換通貨」的位置を占めて広く用いられ、その優位性を利したアテナイの海上交易は、「物々交換」により成り立っていた旧来の海上交易を圧倒し、アテナイの国勢を伸張させていった。
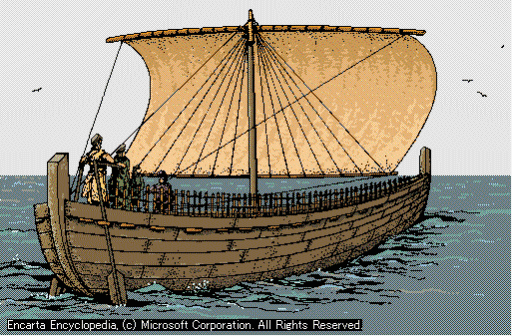
これら海上交易に使用された古代ギリシャの帆船は汎用船タイプで120~150トンクラスと陸上交通手段(馬、荷車など)と比べものにならない積載量を誇り、追い風次第で4~5ノットの航行速度を有し、季節風に乗ればギリシャ本土からエジプトナイル河口まで10日に満たなかったと言われた。このように、海上交易はその規模・所要時間から陸上交易を圧倒的に凌駕し、海陸における流通経済の主役となっていった。
また、アテナイでは前594年からの「ソロンの改革」により「三段櫂船」等海軍力の拡充強化を図り、海上交通を阻害する要因であった海賊の跋扈や競争相手であったフェニキア勢力をギリシャ沿海やエーゲ海から駆逐し、海上交通の安全と交易先の拡大を確保したアテナイはその海軍力の充実とともに海上交易国としての覇権を徐々に確立していった。
(2) 新たな「セキュリティ・リスク」となったアテナイの「シー・レーン」防衛
この海上交易には、アテナイにとって、海上交易による「富の蓄積」とともに、「食糧の確保」という国家としての「安全保障」上のもう一つの大事な側面があった。
「ソロンの改革」は海上交易や商業の発展という経済改革に重点をおいたが、その反面、農業生産に従事していた貧農民の職業転換(「三段櫂船」の漕ぎ手など)、輸出作物のオリーブの作付け拡大による穀物畑の減少、商業奨励による他都市からの商業者(メトイコイ)の移入などにより、農業の生産性のさらなる低下と食糧自給能力の脆弱化をもたらしたのだ。
以後のアテナイの隆盛は、非生産性人口の増加による「繁栄」とともに「食糧の欠乏」も常態化させ、黒海地方やエジプトからの穀物の輸入を担う海上交易路(シー・レーン)はアテナイの生命線となっていった。この新たな「セキュリティ・リスク」となった「シー・レーン」防衛のためのアテナイの海軍力の整備拡充はその後のアテナイの命運を左右する重要なファクターとなっていった。
4 スパルタの国内統治システム
(1) スパルタの支配体制
スパルタ人(ラケダイモン人)の始祖となるドーリア人が鉄製武器を用いてペロポネソス半島を征服したのは前1100年頃であったが、この地はイオニア海から約30km内陸部のタイゲトス山のふもと、エウロタス川右岸の平野部にあたり、豊穣な土壌から先住していたアカイア人たちにより農業が盛んであった。
侵入部族のドーリア人はこの地に都市国家スパルタをたて、このアカイア人たちをペロポネソスの地から駆逐することなく「ヘイロータイ(隷属農民)」として奴隷化し、その地で農業に従事させた。
しかし、スパルタ人の支配を受けた「ヘイロータイ」の人口は支配部族のスパルタ人の人口を大きく凌駕し、同じドーリア系であるものの兵役の義務はあるが市民権を持たない従属身分の「ペリオイコイ」を合わせると被支配階級の「ヘイロータイ」「ペリオイコイ」が多数派となり、少数派の支配階級スパルタ人による統治は大きな不安定要因を抱えた。
加えて、前743年の富有な沃野を有する隣国「メッセニア」の征服は、スパルタをギリシャの最強国としたが、「ヘイロータイ」として奴隷化されたこの地のメッセニア人は膨大な数に上り、メッセニアにおける「ヘイロータイ」による反乱や抵抗は、スパルタ人の支配の間隙を縫って根強く展開され、支配階級スパルタ人と被支配階級「ヘイロータイ」の緊張関係はその後長くスパルタの「セキュリティ・リスク」として存在し、「国内の安寧」という「ナショナル・セキュリティ(安全保障)」を大きく揺るがし続けた。
(2) スパルタの軍制
スパルタは、前9世紀頃におけるリュクルゴスによる一連の社会改革(リュクルゴス制)でスパルタ市民の皆兵制等徹底した軍事国家体制を敷衍することにより、メッセニアなどの不満勢力の弾圧・粛清を図った。
このリュクルゴス制は、
・ 二人の王(軍司令官)を含めた元老会(30人構成)の設置(寡頭制の採用)
・ 民会の定期的開催
・ スパルタ市民に対する土地の平等な配分
・ 市民の共同食事制(夕食の共同食事義務:フィディティア)
・ 家族制度(既婚者も30歳までは兵舎暮らし)
・ 少年の教育(出生男子は国家の共有物、7歳から軍事教練、20歳で入隊)
・ 軍隊の編成(20~60歳のスパルタ成人男子は全員「重装歩兵」の兵役義務)
など以後のスパルタの統治体制の骨子となるものであったが、支配階級スパルタ人と隷属する被支配階級「ヘイロータイ」との対立という社会構造を解消するものではなく、依然として「国内の安寧」に問題を抱えたスパルタの運命に大きな禍根を残すこととなる。
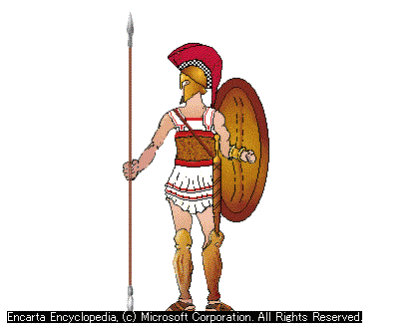
スパルタでは、市民皆兵による「重装歩兵」が長槍・盾で武装した「ファランクス(長槍密集隊形)」が戦場の主力となったが、その精強さからギリシャ国内だけでなく、ペルシャ帝国まで武名が広がっていた。
しかし、この最強のスパルタ軍もその軍峰は「国内の安寧」に向けられていたため、「ペロポネソス戦争」以前は、敵対するポリスに対し膺懲的にその領地に侵入して収穫期の耕作地を荒らし、これを防ぐために反攻してきた敵軍に決戦を挑んでこれを討ちスパルタに帰還するという伝統的な戦法を踏襲していて、遠隔地のポリスを侵略しその地で遠征軍を長期駐留するようなことはなかった。
(TOPに戻る)
5 ペロポネソス同盟の誕生
スパルタはペロポネソス半島における突出したポリスとしての地歩を築き、その最強の軍事力を駆使して半島域内に勢威を張り、前6世紀頃から、域外勢力からの防衛を目的として半島内のポリスとスパルタを盟主とした同盟を構築し始め、前六世紀末にはペロポネソス諸ポリスを糾合して同盟組織「ラケダイモン人とその同盟者たち」(後世の呼称「ペロポネソス同盟」)を結成した。
ペロポネソス同盟は、「バンドワゴン型」の集団安全保障体制というよりも有事の集団防衛体制と言ってよく、戦時下におけるスパルタの軍事指揮権を認め、各同盟国への戦費負担や軍隊供出をスパルタが命令するが、有事以外はスパルタの専権は認められず、同盟への貢納金義務もなかった。
このような「集団防衛」体制は、ペロポネソス各ポリスの独立性を最大限に保障するとともに、その生存を最小限の軍事力で担保する「緩やかなalliance(同盟)」として機能したと言える。
スパルタが何故このような形態を選択したかについて、ツキジデスは〔一九〕 ラケダイモン人が同盟諸都市に年貢を賦課しないで支配し、諸都市が単にラケダイモーン自体に都合のよい政体を維持するように寡頭制を支持した……(ツキジデス「戦史」巻一第19章)と述べ、スパルタにとってのペロポネソス同盟の目的は、(internal security=国内治安)の維持のための(external
security=対外安全保障)の確保にあり、域外勢力の攻撃によるペロポネソス半島の混乱を防止し、域内の安寧によりスパルタの軍事力を国内の抵抗勢力「ヘイロータイ」への鎮圧に向けることがその目的であったことを明らかにしている。
6 アテナイの台頭
(1) 「イオニア反乱」におけるイオニア系ポリス・アテナイの台頭
小アジアのイオニア地域の諸ポリスは、前500年中葉から「ペルシャ・アケメネス朝」の支配下にあったが、前499年に、小アジアの有力ポリス・ミレトスを先頭にギリシャ系ポリスがペルシャ帝国に対する反乱を起した。これら反乱軍は、「ヘラス(古代ギリシャの呼称)」の盟主・スパルタに来援を請うたが、スパルタ王クレオメネス一世はこれに応じることはなかった。
このため反乱軍は同じイオニア系のポリスであり、「海上交易」により国勢の著しい伸張を遂げ、その海軍力の充実により海上交易国としての覇権を徐々に確立していったアテナイに援軍を求めた。これを受けたアテナイ民会は、同じイオニア系ポリス・エレトリアと合同で「櫂船」数十隻を派遣し反乱軍に加勢した。しかし、この「イオニア反乱」は前494年のミレトスの陥落により潰えることとなった。
(2) 「ペルシャ戦争」の勝利と「ヘラスの盟主」・アテナイの登場
「イオニア反乱」への助勢では一敗地に塗れたアテナイであったが、その後の二次にわたる「ペルシャ戦争(前490年、前480~479年)」で膺懲目的でヘラスに侵攻してきたペルシャ軍に対しヘラス連合の主戦力として戦い、「マラトンの戦い」・「サラミスの海戦」・「プラタイアイの戦い」で勝利を収め、前480年のサラミスの海戦でアテナイ艦隊の指揮をとりペルシャ軍をやぶったテミストクレースに領導されたアテナイは「ヘラスの盟主」としての地位に着実に近づいていった。
しかし、ヘラスの中心的ポリスとしてのアテナイの登場は、スパルタを中核として「集団防衛」体制を確立していた「ペロポネソス同盟」諸国に強力な仮想敵国としての警戒心を呼び起こし、以後のアテナイの動向は、これら同盟諸国に猜疑心を持って見られることとなる(「Security
Dilemma=安全保障のジレンマ」の陥穽)。
ツキジデスは、アテナイの勢力拡大に至る状況について〔八九〕……ペルシャが海陸ともにヘラス軍に敗れて欧州から引き揚げるときミュカレーでその逃亡中の船団も撃破されると、ミュカレーのヘラス軍を率いていたラケダイモーンの王レオーテュキデースはペロポネーソス同盟諸軍をまとめて帰国した。しかしアテナイ軍とペルシア王の支配から早速離叛したイオーニアおよびヘレースポントス地方の同盟軍は、ペルシアが確保していたセーストスに留まってそれを包囲した。越冬の後、この地を陥し、異語族もそこを去ってから、彼らは初めてヘレースポントスを離れて各自の都市に帰国した。アテナイの大衆は異語族が自分たちの地を去るとただちに婦女子を連れ戻し、退蔵してあった諸財を持ち込み都市と防壁再建の準備を整えた。……(ツキジデス「戦史」巻一第89章)旨述べている。
このような状況の中で、ペルシャ軍により徹底破壊されたアテナイの城壁の復旧・再構築はスパルタのアテナイに対する「Security Dilemma(セキュリティ・ジレンマ)」の好餌となった。相互不信が芽生えたスパルタとアテナイのやりとりをツキジデスは下記のように詳述している。(ツキジデス「戦史」巻一第90~93章)
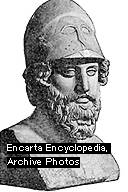
〔九〇〕 この動きを知ったラケダイモーン人は使節団を送って干渉して来た。この理由はラケダイモーン人自身もアテナイや他の都市が防壁を持つのを見て決して好感を抱く筈もなかったが、主にアテナイの未曽有の海軍力とペルシア戦に示された彼らの勇気に怖れを抱いた同盟諸都市に唆かされたからであった。彼らはアテナイに防壁を築かないように要求したばかりでなく、ぺロポネーソス外でまだ残っている防壁の取壊しに彼らと協力するように申入れた。自分たちの意図と恐怖をアテナイ側に悟られないように、万一、異語族再来の折りには、前回のテーバイ基地化の轍を踏まずに、敵にどこにも拠点を与えないようにすることを主張した。そしてペロポネーソス全土を反撃の基地とすることで充分であると説いた。ラケダイモーン人のこの発言に対して、アテナイ人はテミストクレースの提案を採用し、申入れの件に関しては使節団をラケダイモーンに送る予定であると回答をあたえて早々に帰らせた。テミストクレース自身は自分を早速ラケダイモーンに派遣するように要請すると同時に、同行者として選ばれた他の使節の即時出発を、防壁が守備に耐える最低限の高さに達するまで待つように命じた。これと同時に都市にいる者を総動員して築壁に従事させ、工事に役にたつ物資があれば、その公私の区別なくすべてを使用するようにと命じた。このように指示を下すと、更に、ラケダイモーンでの一切は自分の責任で取扱うと付加えて出発した。そしてラケダイモーンに着いたテミストクレースは政府に出頭せず、理由を構えては時を稼いだのであった。要人が彼の議会に出頭しない理由を訊すと、多忙のためにアテナイを離れられないでいる同僚使節の到着を待っているのだと答え、彼らが早急に来ることを希んでいるし、かつ、彼らがいまもって到着していない事実に驚いているのだと答えた。
〔九一〕 ラケダイモーン人はテミストクレースに好意を持っていたのでこれを聞いて納得していたが、他の者たちが来て築壁工事の進行と既にそれが相当の高さに達していることをはっきりと告げると、彼らはその報告を信ぜざるをえなくなった。テミストクレースはこれを知って、ラケダイモーン人に人の言葉に信頼がおけぬから、信用のある人格者を彼ら自身の中から派遣して、実際に目撃したことを報告させるようにとすすめた。そこで彼らが言われたとおりにすると、テミストクレースは彼らについて秘密にアテナイに連絡しできるだけ密かに彼らをアテナイに留めて、アテナイ使節団が帰国するまで待たすように命じた。つまりラケダイモーン人がはっきりとこの事情を知れば、アテナイ使節団を抑留する恐れがあると考えたからであった。そこでアテナイ人は指示どおりにラケダイモーン使節団を引きとめ、また、テミストクレースはラケダイモーン人の所に行き、アテナイがすでにその市民を守るに足る防壁を設けた事を言明した。また、もし、ラケダイモーン人なりその同盟都市なりがアテナイに使節を送ろうとする場合は、今後は自国の利益とヘラス全体の利益とに分別のある都市を相手にすることになると告げた。……つまり均衡した力を持たない限り共通のことに関して対等な立場で談合するのは不可能であるとテミストクレースは述べ、そのため、同盟都市の全部が防壁を持たないか、さもなくばこのようにアテナイが防壁を持つのが正しいと考えたのであると言った。
〔九二〕 これを聞いたラケダイモーン人はアテナイ人に対する怒りを表には出さなかったが、企図の挫折には秘かに不快の念を抱いた。こうして双方の使節団は紛争を起さないまま帰国した。
〔九三〕 さて、アテナイは以下のような方法で都市の防壁を短時日で築いた。この防壁が急いで作られたことは、今日でさえもその作り方から判断できる。礎石にはあらゆる種類の石が使用されており、ところどころには個々の石が運ばれた時のままで手が加えられておらず、また、多くの墓石や磨かれた石が壁の中に押込んである。アテナイを取り巻く壁を各方向に拡張したので、あらゆる物が動員された。その上、テミストクレースはペイライエウスの残部を構築することも説得した。そのわけはこの土地が有望で、三つの自然港を持ち、しかもいまや彼らは海の民となっていたので、この地が力を得るに大きな役割りを果すと考えたからであった。これで彼が直接的にアテナイ帝国の礎石を置くことになったのである。テミストクレースの発案で、アテナイ人は、今日なおペイライエウス周辺で見られるような厚さの壁を作ったが、それは石を運搬する二台の車が擦違えるようにしたのが原因である。壁の中身は砂利や瓦ではなく、大きく四角に切り揃えられた石が用いられ、その外側は鉄と鉛で互いに止められた。しかし防壁の高さは、テミストクレースが企図した約半分が完成されたのみである。彼の計画では壁の厚さと大きさで敵の攻撃を防ぎ、少数のあまり強力でない部隊でも充分に守備ができるようにして、他の者は船に乗組めるようにする考えであった。そのわけは、思うに、ペルシア軍の進撃が陸より海の方が容易であったことをテミストクレースは経験から知って、海軍に重点をおいたのであろう。彼はペイライエウスは、上市(※アテナイ市)よりも役に立つと考え、何度もアテナイ人に、万一、陸で圧迫されるような場合には、ペイライエウスにおりて海軍力で世界を睥睨するように勧めた。アテナイ人はこのように、ペルシア軍退却の後にただちに、防壁を構築し、他の設備の設置を進めた。
7 スパルタの盟主からの転落
アテナイの台頭により、「へロスの盟主」としての地位が危うくなったスパルタであったが、前478年のへロス連合軍による「キュプロス攻略・ビュザンチオン包囲戦」では、スパルタの将軍パウサニアスが軍司令官として連合軍を率いてペルシャに勝利しスパルタの面目を保った。
しかしこの戦役において、パウサニアスの専権的な行動はペロポネソス以外の連合諸国からの不信を買い、加えて、パウサニアス自身による敵国ペルシャとの自己保身を図った通謀が露見してパウサニアスは司令官を解任されスパルタ本国に召還された。
スパルタはパウサニアスに代えて後任の司令官を派遣しようとしたが、ペロポネソス諸国以外の連合軍諸国がその指揮権を拒否したため派遣することを取り止め、以後司令官を派遣することはなかった。
(TOPに戻る)
8 「デロス同盟」の結成
ペルシャの二度にわたるヘラス侵攻を駆逐したヘラスの諸ポリスであったが、ペルシャの軍勢を壊滅したわけでもなく体勢を立て直したペルシャ軍のさらなる来襲が危惧された。とりわけ、エーゲ海やイオニア地方沿岸の諸ポリスはペルシャの圧倒的な軍船による海路からの来寇を怖れ、前477年、ヘラスにおける海軍最強国のアテナイを盟主とした攻守同盟「デロス同盟」を結成した。
ツキジデスは「デロス同盟」設立の経緯を次のように述べている。
〔九六〕 アテナイは、同盟諸都市のパウサニアースに対する憎悪から統治権をこのようにして引き受けると、対異語族活動に諸都市が収めなければならない税や徴船の制度を制定した。これはペルシア王の領地を討って彼らが受けた災害の報復をするという表向きの理由の下に行われた。そしてヘラス公庫財務職がアテナイのために初めて設立された。この官職は貢金の収納を司り、収納される貨幣をプォロス(貢金)と呼んだ。最初の貢金総額は四六〇夕ラントに上った。この同盟の財務局はデーロス島に置かれ、同島の神殿で同盟会議が開かれることになった。(ツキジデス「戦史」巻一第96章)
同盟諸国は、対ペルシャ戦争に向けた戦費、軍船、兵員を拠出する義務を有したが、実際はアテナイ艦隊の提供、アテナイの指揮権掌握を内容とし、自国海軍力を保有していたロドス・キオス・レスボス等一部の都市を除いた軍船・兵員を提供できない諸都市は年賦金をデロス島にある同盟宛て貢献することが義務付けられた。
このような内容から、『デロス同盟』は、強国・アテナイを中心とした『バンドワゴン』型の集団安全保障体制として捉えられ、同盟内におけるアテナイの専権が拡大し、事後のアテナイの『覇権主義』へと繋がっていく。
(1) 「デロス同盟」の変貌、アテナイの「覇権主義」
「デロス同盟」結盟を図るアテナイの勢威は、偏に「海上交易」という商業(流通)活動に依拠した経済構造による「富の蓄積」に支えられていた。
一方、前9世紀頃からリュクルゴス制による軍事国家体制を400年余り墨守していたスパルタは、農奴「ヘイロータイ」による生産性の低い農業生産活動に依存した国家経済の体質は変わらず、その国威はアテナイの急成長の前に徐々に色褪せっていった。
アテナイは、民主派の政治的指導者ペリクレス(前495頃~前429)のもとで、民主政治の徹底を図るとともにパルテノン神殿の建設や文化の奨励を進め、「ペリクレス時代」のアテナイは学問・芸術の中心となり、アテナイ市民の精神的高揚は絶頂期を迎えた。
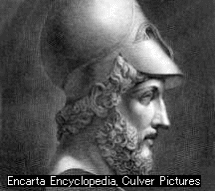
そしてその栄華は、アテナイをヘレス世界の理想とし、その顕現をヘレス世界に広めていくという「選民意識」と「覇権主義」に結びついていった。
ペリクレスは前425年冬の「国葬演説」で、ヘレス世界に覇を唱えるアテナイの「正当性」を市民に対し次のように宣明した。(ツキジデス「戦史」巻二第41章)
〔四一〕 まとめて言えば全市がヘラスの師範なのだ。しかも我々市民は、一人一人が独立してそれぞれ広域にわたる分野の活動を積極的に楽しんでいると思う。……これが実際の真実であることは、このようにして我々が得たこの国の力が実証している。つまり試練にあって名声を凌ぐ力を示したのは、現代において我々だけである。我々に破れた敵も我々だけには恨みを抱かず、従う属国も我々以外にはその権力にふさわしい盟主はないと信じている。大いなる徴しをもって紛うかたなき力を生んたこの我々は、今日の人々にも、未来の人々にも讃嘆の的となろう。事実がまことを物語るならばホメーロスの讃歌も、耳に儚き言葉の綾も我々には無用となろう。我々の勇気の前に屈したすべての海陸は、ともに道を開いて我らを受け入れ、世のすみずみに到るまで我々はその盛衰の塚を永遠に残した。……
本来は、〔九七〕……各々が主権を持って同等の立場で議会を運営する同盟諸都市の長としての役をアテナイはつとめていた。…… (ツキジデス「戦史」巻一第97章)が、このようなペリクレスの「選民意識」とその「覇権主義」は「デロス同盟」の対ペルシャ攻守同盟の性格をアテナイへの従属機構へと変質させていった。
「選民意識」に基づく「覇権主義」は、近くはヒットラーの「ゲルマン民族の優越」を基底とする「第三帝国」論や日本における世界統一原理「八紘一宇」論、アメリカの「マニフェスト・ディスティニー」論を生み、現今では、ロシア「国章」の双頭の鷲(東ローマ帝国に由来し、帝政ロシアのローマ帝国正統後継を表す。ロシア連邦の発足により「国章」として再度復活した。「双頭」はアジアとヨーロッパに渡る統治権を象徴している。)を具現化し、世界に冠たるユーラシア大国(強いロシア)を建設しようとするロシアや「中華民族の偉大な復興」を核心とする「『中国の夢』の実現」を国家の統治理念としている中国の蠢動に繋がっている。
このような「覇権主義」によるアテナイの帝国主義化は、敵対するペロポネソス同盟諸都市をいたく刺激した。とりわけアテナイと近隣のペロポネソス同盟都市のコリントス、アイギナなどとの利害対立が顕在化した前四三二年頃、反アテナイの急先鋒であったコリントスの要請で招請されたペロポネソス同盟諸都市会議はアテナイの罪状を数え上げる場と化した。
ツキジデスは、会議開催時にたまたま他用務でスパルタを訪れていて本会議に急遽出席したアテナイ人の代表のペロポネソス同盟諸都市のアテナイ批判に対する反駁の形で、デロス同盟諸都市に対する「統率」の正当性について言及している。(ツキジデス「戦史」巻一第75、76章)
「〔七五〕ラケダイモン人諸君、我々はこのような勇気と智恵のために、我々がヘラスの世界に支配権を保持しているのに対して、これほどの嫉妬を受けるのは一体ふさわしいことであろうか?つまり我々は暴力をもって支配権を獲得したのではない。諸君がペルシャ軍の残留部隊に抗して留まることを望まなかったために、同盟軍は我々を頼りにして、統治権の設立を我々に依頼したのである。そしてまさにこの事態から、はじめは特に恐怖から、ついで名誉のために、そして最後に利益のために、我々は今日までこの支配圏を統治するようにまず強要されたのである。さらにこれ程多くの国から嫌われているのでは安全とも思えず、しかもすでに或る都市は反乱を起しては罰せられていた上に、貴国も我々に以前のような好意を持っておらずに、有るものは疑いと紛糾のみであったので、成行きに任せては危険と判断したのである。さもなくば、我々からの離叛者は貴国の手に早速落ちることになったであろう。何人も危険にあっては最善を尽くすのに非難を受ける理由はない。」
「〔七六〕ラケダイモン人諸君、まことに貴国も貴国の便宜に従ってペロポネソス内部の諸都市を統率してきた。もしも、貴国がかの時期を通じて統治の首座に留まって我々のごとくに嫌われていたならば、同盟諸都市にとっては貴国は現在の我々と同様に憎悪の対象となっており、諸君は帝国主義を強制するか、さもなくば自国を危険にさらす結果になったことは判りきっている。このように我々は決して驚くべきことを為したのでもなければ、人道に悖ったことをしたのでもない。一旦与えられた支配権を引き受けた以上は、体面と恐怖と利益の三大動機にとらえられて我々は支配権を手放せなくなったのだ。しかしこの例は我々を持って嚆矢とするのではない。弱肉強食は永遠不変の原則である。そして我々にはその価値があると自負している.しかも諸君でさえこの事実を従来認めてきた。ところが今になって正義論が都合よくなったためにそれを楯にして我々を攻撃している。力に恵まれれば、それを行使して獲得できる獲物の前を素通りする人間なぞあり得ない。支配欲は人間の本性であるが、それを力によらず正義に則って満足させる者は真に賞賛に値する。思うに、我々の権力を他の者が持ったならばいかに我々が寛容であるかを証明するであろう。ところが不当にも賞賛どころか誹謗を招いている。」
以上のようにデロス同盟諸ポリスに対する支配の正当性を強者の論理で強弁するアテナイの姿勢は、アテナイの専制を嫌った同盟諸国の離叛の動きを認めると、〔九八〕……アテナイは離叛したナクソスに対しても戦いを起こし、包囲作戦で降伏させた。これは後々、事あるごとに最初の取り決めに反して他の同盟諸都市を隷属化した最初の例となった。(ツキジデス「戦史」巻一第98章)
(2) アテナイの「覇権主義」を助長した同盟諸国の愚挙
ツキジデスはアテナイ人の同盟支配権成立の顛末を以上のように詳述しつつ、このような覇権主義を助長した同盟諸国の愚挙についても冷徹に指摘している。
〔九九」同盟を離脱したという理由として最大のものは、貢金と徴船の不払いであったが、ある場合には派兵拒否もあった。なぜならばアテナイは厳格にこの徴税を実施、強制したので、その圧力に慣れず、また、それを好まぬ都市はアテナイを嫌ったからである。……多くの諸都市人たちは、国を離れるのを嫌って出兵するのを好まず、協定負担分を船で治める代わりに現金で支払い、アテナイはその支払金を資金として船舶数を増大したゆえ、諸都市が反乱を起こすときには、諸都市は不充分な準備と経験で戦いに直面するようになった。(ツキジデス「戦史」巻一第99章)
(TOPに戻る)
9 アテナイとスパルタの決定的な離叛
前464年頃、スパルタで発生した大地震の混乱に乗じ、スパルタの国有奴隷がイトメ山塞に立てこもり大規模な反乱を起した。スパルタは反乱鎮圧の長期化から、他ポリスからの加勢を求めアテナイも多数の援兵をスパルタに送り込んだ。しかし、反乱軍との籠城戦の長期化により、アテナイ軍のスパルタ駐留も長きにわたり、アテナイ軍への期待を裏切られたスパルタは逆にアテナイ軍の反乱軍への寝返りを猜疑することとなった。このような状況をツキジデスは次のように述べている。(ツキジデス「戦史」巻一第102、103章)
〔一〇二〕 イトーメーの反乱軍との戦いが長引き、ラケダイモーン人は他の同盟諸都市とアテナイにも援助を求めたので、キモーンを将軍としたアテナイの大軍が派遣された。ラケダイモーン人が彼らを呼んだのは、特に彼らが城壁攻防戦にたけていると知られていたからで、長期包囲戦にはこのように腕力で拠点を奪うような軍隊が必要のように思われたからであった。ここに到って、初めてラケダイモーン人とアテナイ人との紛糾が明らかになった。つまり、アテナイ人が拠点を武力で取り損うと、彼らがドーリア族でないことと、それに勇気と革新の気風を持ったアテナイ人を長居させると、イトーメーの者たちに説かれて寝返りでも打ちかねないとラケダイモーン人は考え、同盟軍中でアテナイ軍だけを送還した。もちろん、彼らはこの危惧を表に出すことなく、彼らをもはや必要としなくなったと説明した。しかしアテナイ軍は、疑いのために芳しからぬ理由で送還されたと知って、感情を害し、ラケダイモーン人からこのような取扱いを受けるに値いしないと帰国した。そして早速、ペルシア戦後にペルシアに対抗して成立された同盟を離脱し、ラケダイモーン人の敵、アルゴスと手を組んで同盟を作り、また、同じ条件でテッサリア人とも同盟を結んだ。
〔一〇三〕 イトーメーにいた者たちは十年間の戦いに耐えきれず、身柄の安全の保証の下にペロポネーソスを離れ、再びその地に足を踏み入れない条件で妥協した。そしてもしペロポネーソスの中で誰かが捕えられるような場合は、その者は捕えた者の奴隷となることに同意した。これはラケダイモーン人には、イトーメーのゼウス神殿への哀願者は放免せよというデルフォイの神託が以前からあったからである。ペロポネーソスを離れた彼らと女子供を、ラケダイモーン人への反感からアテナイ人が引き受けてナウパクトスに入植させた。ナウパクトスは、それを領していたオゾリスのロクリス人から最近アテナイが獲得した地である。
メガラがラケダイモーン同盟を離れてアテナイ同盟に加入したのはコリントスとの国境紛争があったからで、アテナイはメガラとぺーガイを獲得するとメガラ人のためにその都市からニーサイアに到るまでの長壁を築きアテナイの守備隊をおいた。このことがコリントス人のアテナイに対する感情を大いに悪化させるまず始めとなった。
(1)アテナイの政治的指導者ペリクレスの主戦論
スパルタとの開戦が不可避と判断したアテナイの政治的指導者ペリクレスは、来たるべき大戦の帰趨を左右するのはアテナイの「海軍力(海の支配)」にあることを洞察し、アテナイ海軍の軍港でもあるペレウス外港の整備を図るとともに、アテナイ市街とペレウス外港の間に囲壁を構築し、防御態勢を固めた。
このアテナイとピレウス外港を結ぶ長城壁が、海上からの物資補給を保証してくれるため、アテナイは長期戦に耐えることができ、スパルタ軍が刈入れ期にアテナイに侵攻して郊外の焦土作戦を行っても、郊外居住の市民を長城の囲壁の中に避難させ、ペレウス外港からの十分な食糧補給も得られることとなった。
前432年に開催されたペロポネソス同盟諸国会議で、アテナイとの戦争決議が採択され、スパルタから最後の使節がアテナイを訪れた。使節の「ラケダイモンは平和を希望する。アテナイ人がヘラスの自由を奪わなければ平和は可能だ。」との最後通告を受けたアテナイ民会はその対応を協議することとなった。
ツキジデスは、民会でのペリクレスの透徹した現状分析とこれに基づくアテナ海軍主体にした戦略を内容とする主戦論を次のように記述している。(ツキジデス「戦史」巻一第140~143章)
〔一四〇〕 「アテナイ人諸君、ペロポネーソスに譲るべからずという私の意見は終始一貫して変っていない。もとより、人は開戦に駆られるのと同じ感情で実際の行動はとれず、事態の変化でその意見も変る事を私が知らないわけではない。それを承知していればこそ、私は今も以前と変らずほとんど同一の勧告をしなければならないのだ。そして意見を変えた諸君は、我々がたとえ失敗したとて、議会の決議をあくまで支持して、自説の正しかった事を誇ってはならない。なぜならば、人間の立てる予定同様に事態の成行きも分らないからだ。このために理屈どおりに事が運ばないと我々は天を恨んで諦める。さてラケダイモーン人が我々に策略をめぐらしている事は以前から明らかであったが、今や疑問の余地は全くなくなった。つまり条約には紛争の法的調停の相互受授が規定され、また彼我の現状維持が明記されているにもかかわらず、彼らは法的調停を求めた事もなければ、それを申込んだ我々の要求を受けいれた事もない。彼らは法よりも戦争で紛争解決を希んでいて、高圧的要求に終始して合法的に苦情を訴えて来たためしがない。すなわち彼らはポティダイアからの撤兵、アイギーナ主権返還、メガラ法令撤回を命じて来ており、しかも彼らの最後の使節にいたってはヘラスの自由解放を我我に公言した。しかし彼らが現在もっとも重視しているメガラ法令を我我が撤回しなければ、些細なことで戦争を起したことになると思ったり、それに固執さえしないならば戦争は避けられると考えたりしてはならない。つまらぬ事から戦争を始めたと後々自らをせめる必要もない。なぜならばこのような細事に諸君の安全と決意の成否が全面的に懸っているからだ。そして一歩ゆずれば、それを怖気づいた証拠として、すぐにさらに大きな要求を彼らは押しつけて来るにきまっている。逆に諸君が彼らに毅然とした態度をとれば、彼らも諸君を対等の立場で扱わなければならない事に気がつくであろう。」
〔一四一〕 「ゆえに諸君は被害を受ける前に屈服するか、あるいは私の主張するように、敵の大小の言いがかりにめげず、持てるものを安心して保持できるように開戦を決意するか、この場で決しなければならない。つまり対等の国家間で問題の軽重にかかわらず、一方だけが法を無視して要求してくる事は、他方の隷属を強制するにひとしいからだ。そこで諸君に悟って貰いたいことは、彼我の現有戦力、資源を逐一比較の上我々が決して敵に劣っていないことである。すなわちペロポネーソス人は農民であるから個人も国家も資財ももっていない。そのため近隣との短期戦は戦えても、貧しいために長期戦や海外戦の経験をもたない。畑仕事を犠牲にはできず、さらに費やす私財もない上に船がないのだから、船に人を乗組ませる事も、陸兵を頻繁に派遣する事も不可能なのだ。しかも戦争維持には不断の蓄財を要し、当座の戦時税では賄いきれない。農民は戦いに体を使う事は心得てはいようが資金は使えない。つまり危険には五体を挺して耐えられるとしても財資に欠乏してしまうからだ。おそらく今回の戦いは長びくであろうが、予期以上にそうなるとこの恐れは特に格別である。なぜならば、ペロポネーソス勢とその同盟諸軍は一回だけの戦闘ならば全ヘラスをさえ相手にしうる実力を備えていようが、異質の装備をもった敵と戦争をする能力には欠けている彼らには衆議を一決する機構がない上に、すべてにひとしく投票権があたえられているので、異種族の各国家はそれぞれの私利にとらわれてしまい何ごとも即決即行できないのだ。この状態が続くかぎり何一つ成功しよう筈もない。つまり各都市が最重要とする関心事がそれぞれ異っていて、ある都市は復讐に固執すれば他の都市は失費の削減を苦慮するという工合なのだ。しかも彼らはなかなか会議に集らず、漸く開かれた会議ではほとんどが私利の追求に費されて、公事を議するいとまのないほどである。そしてこの無責任な態度が全体に及ぼす害に思いをいたさず、自分たちの先行きは他の者が心配してくれるものと考えている。この結果すべてが利己的な行動をとるので知らぬ間に共同の利益が犠牲になってしまうのだ。」
〔一四二〕「ともあれ、彼らの最大の弱点は軍資金にある。その調達に手間どっているかぎり彼らは何もできない。しかも戦機は人を待たない。また彼らの海軍も要塞も恐れるには足りない。平時においてさえ都市に対する要塞の築構は難しいのに、ましていわんや戦争になって、我我に敵のそれを防ぐ用意ができている場合にはますます困難である。しかし彼らがたとえ小防砦を作る事に成功して、そこに脱走者をかくまったり、そこから出撃してアッティカを部分的に荒せたとしても、我我がペロポネーソスに渡り彼らの地に要塞を築いて我々の利点とする海軍で彼らに抵抗することを敵は阻止できない。なぜならば、我々の上陸技術の方が彼らの陸からの海防技術よりはるかにまさっているからだ。しかも彼らが海事を習得するのは容易ならざることだ。つまりペルシア戦役直後から海事に研讃を積んできた諸君でさえも完璧の域に達しているとは言いがたいのに、いわんや海洋民族でもない農業国民に一体、注目に価いする何ができようか。しかも我々の船団は常時、敵の港口を封鎖して、彼らに習練の機会を全くあたえないであろう。封鎖船団の規模が小さければ数を恃みに無智を勇の糧として攻撃をしかけてくるかもしれない。しかし多数の船には行動を停止せざるを得まい。そうなると敵はますます習練を欠き、判断力が鈍くなる。それに従って勇気も失ってしまうであろう。海事は一種の技術であるから、他の技術同様に、一貫して本腰の入った訓練が必要であり、それに専念することが要求されるのだ。」
〔一四三〕「さらにまたかりに、彼らがオリュムピアなりデルフォイの神庫から資金を動員して我々の船員の中から外人傭員を高給で引抜こうとしたとしよう。その場合に我々市民や居留民が船に乗組んでも間に合わないのだとすれば、敵のこの政策はまことに恐るべきものである。しかし今日の我々には充分にその力がある。それどころか、まさに我々の強みは、市民が船長であり、他の乗組員も質量ともにヘラスのどの都市よりも秀れている点なのだ。しかも外人傭員にしたところで、自らを亡命者にしてまで短期の高給のために危険を承知で敵に味方し、勝ちめのない戦いを我々に挑もうとは考えまい。以上がペロポネーソス側の実状かあるいはそれに近い状態であると私は判断する。これに反して我々の側には、私が敵の弱点としてあげた短所の心配が全くない。我々の戦闘条件は比較にならないほど優っている。敵が我々の領土を陸勢をもって侵略してくるならば、我々は彼らの領土に軍船で渡る。たとえ我々がアッティカ全土を失うとも、彼らがペロポネーソスの一部を失うよりはその損害は遥かに軽いのだ。この理由は彼らはその損失を補うに戦いを必要とするが我々は広大な領土を大陸や海洋諸島に持っているからである。つまり強さは海の支配にあるのだ。我々が島国都市であったら、過去において我々よりも落しにくい都市があったろうか。諸君、よく考えてみてくれ。我々は今日にあっても島国都市にできるだけ近い政策を採用し、土地や家屋を顧みず、海防と都市防衛に留意すべきだ。土地や家屋にとらわれて逆上してしまい、数的に優るペロポネーソス陸勢と戈を交えるようなことはしてはならない。このわけは一戦に勝ってもすぐ前回に劣らない新手と戦うことになるし、一旦敗けたとなれば、我々の原動力でもある同盟都市を失うからだ。つまり我々の足下をみすかして彼らがじっとしている筈がない。家屋や畑の損失を嘆かず、人命こそ惜しむべきである。すなわち畑屋敷は人を生まず、人がそれを作るからだ。私に諸君を説き伏せられる自信があったとしたら、畑屋敷のために敵に屈するような事のないことを。ヘロポネーソス側に示すためにも、そこを捨て焼き払ってしまえとさえ私は命じたに違いない。」
〔一四四〕「ともかく諸君が戦争中に帝国の版図拡大を企て、自ら危険を招こうとしないかぎり、勝利の見込みを約束する理由は他にも多くある。私が心配するのは外敵の計略より、かえって国内にある我々自身の誤りだ。……」
〔一四五〕 ベリクレースは以上の要旨を述べた。そこでアテナイ人はこれをもっとも健全な忠告であるとして、その主張どおりに票決した。そして一部始終ペリクレースの案に沿ってその提唱に従い、ラケダイモーン人の要求には一切応じられないが協約による法的調停を通して平等の立場で対等に紛糾の解決を計る用意があるとラケダイモーン人に回答した。そしてこの使節団が帰ってくると彼らはその後ふたたび使節を派遣しようとはしなかった。(ツキジデス「戦史」巻一第145章)
〔一四六〕 以上が、エピダムノスとケルキューラ紛争の直後から戦争が始まるまでの期間に、両者の間で交換された非難と弾劾であった。それにもかかわらず、両国間の往来は平時のとおりであった。しかし互いの猜疑心が消えた筈もなく、いかなる事件の発生も条約違背を意味し、戦争の端緒に直結していたのである。(ツキジデス「戦史」巻一第146章)
(2) ペロポネソス戦争の導火線となった「エピダムノス・ケルキュラ紛争」の勃発
紛争の発端となったのは、「ケルキュラ」を母市とするアドリア海に面する港湾都市「エピダムノス」の内紛に絡む「エピダムノス・コリントス」連合と「コリントス」の植民市であった「ケルキュラ」との対立であった。
当時強大な海軍力を有していた「ケルキュラ」は、ペロポネソスにもアテナイにも与しない「武装中立」をとっていたが、コリントスとの初戦に勝利したもののコリントスの本格的な反攻を恐れ、アテナイに同盟を求めた(前四三三年)。
ツキジデスは、同盟を求めるケルキュラ人の述懐の形で、「中立路線」の愚かさを述べている。(ツキジデス「戦史」巻一第32章)
〔三二〕 「……我々の一貫して変らぬ政策は貴国に対する実際面において我々を矛盾におとしいれ、しかも今日の我々自身にとってもそれは不都合な政策になってしまった。すなわち、今日までいずれの国とも盟約を結ばなかった我々が、今や積極的にこれを他に求めてここに来たということ自体が政策に一貫性を欠くことであり、また現在の対コリントス戦では、このことのために、我々は孤立化して不都合な状態に追い込まれた。
すなわち我々の政策、つまり他国と盟約を結ばず、隣人の危険に巻き込まれまいとする政策は、従来賢策とされてきたが、今やそれは愚かで弱点であったようにさえ思われる。前回の海戦では、我々はなるほど、我々だけの力でコリントスを撃退した。 しかし彼らが、ペロポネーソスや他のヘラス諸都市から更に強力な装備を集めて、再度攻撃を加えて来れば、我々は自力だけではとてもそれに抵抗しきれまい。また、万が一敗れた場合その結果がどんなに重大かを熟知していればこそ貴国および他の諸都市からの援助を求めざるを得ない。したがって不正の策とは呼べずとも誤算であった従来の孤立政策に敢えて反対する次第である。」
ケルキュラに結盟を請われたアテナイであったが、ペルシャ戦争時にペロポネソス諸邦と盟約を交わしていたことから、ケルキュラとの同盟はペロポネソス側との破約となるため、これを断念し、ケルキュラと〔四四〕……相互防衛協定を結び、ケルキューラあるいはアテナイもしくは両者の同盟国に攻撃が加えられた場合にのみ相互を援助するように取り決めた。そのわけは、ペロポネーソス戦争が差し迫っているとアテナイが判断してもいたし、大規模な海軍力を持つケルキューラがコリントスと手を結ぶことを好まなかったからである。かえって両者の激しい争いで双方の疲弊を計っておいて、必要とあればコリントスや他の海軍を持つ国と戦いを始めればよいと考えた。と同時に、ケルキューラ島は、イタリアやシケリア島に向かうにはその航路上に位置しているので好都合と判断したからでもあった。(ツキジデス「戦史」巻一第44章)
前433年晩夏、シュボタ海域でのケルキュラ対コリントスの戦いにおいてケルキュラに加勢していたアテナイ海軍は、コリントス海軍と戦闘を交えた。これをツキジデスは大戦勃発の誘因の一つに数えている。
(TOPに戻る)
10 ペロポネソス同盟会議での開戦決定とスパルタ王アルキダモスの諫め
前432年頃、反アテナイの急先鋒であったコリントスの要請で招請されたペロポネソス同盟諸都市会議は二度にわたり開催された。一度目の会議でスパルタ人は同盟諸邦の代表によるアテナイに対する非難とアテナイ代表の反駁を聞いた後、スパルタ人以外を退場させ、現状の検討を行った。
出席者の意見の大勢は開戦論の主張で、耳を傾けていたスパルタ王アルキダモスはペリクレスと同様に大戦の長期化を予測し、拙速な戦争開始を諫め十分な準備を整えた上での開戦を説いた。しかし、開戦に傾いた会議の大勢を止めることはできなかった。
そして、スパルタの会議結果を伝えられた同盟諸邦の代表は、これを持ち帰り各民会での票決を得た後、再度同盟諸都市会議を開催し開戦を決議した(前431年)。
同盟諸都市会議におけるアルキダモスの諫めの内容について、ツキジデスは次のとおり記述している。(ツキジデス「戦史」巻一第80~83章)
「〔八〇〕ラケダイモン人諸君、私はたくさんの戦いを経験した。しかも諸君の中にも私と同年輩で同じ思いをした者が見受けられる。それゆえ未経験のために多くを災いに落すような戦いに憧れたり、戦いを善として危険でないと考えたりしてはならない筈だ。そして現在検討中のこの戦争を冷静に論理を立てて分析すれば、これが大戦争となる可能性のある事に気がつくであろう。つまり我々と同質の戦力をもつペロポネーソス人とか隣国相手ならば、我々はどれに対しても速々かに攻撃できる。しかしこの相手は遠くに本国をもち、しかも海軍力に比類のない経験をもっているのだ。その上、他のどの部門をとっても彼らは最善の準備をしている。公私の富、船舶、騎兵、重装兵を有し、人口においてはどのヘラス都市にも優り、さらには幾多の属国に貢税をおさめさせている。このような国に対して、戦端を安易に開けようか? 備えも顧みずして何を頼りにできるのか? 海軍はどうか。我々の方が劣っている。たとえ今から専心して対抗準備をするとしてそれには時間が必要である。それでは財力はどうか? この点では我々は更に遥かに劣っている。我々には公金もなければ私金を徴する機構も持っていない。」
「〔八一〕 敵領を侵略して荒せる我々の重装兵力の優勢を指摘して勇気を鼓舞する者があるかもしれない。しかしアテナイは他に広範な領土を支配しており、必需物資の輸入もできる。また、たとえアテナイの同盟都市の離反を謀っても、それらの大部分が島国である以上は、それを助けるにはきわめて大きな海軍力が必要となる。では我々はどんな戦争を予期すべきか? 海軍力で優勢を把握するか、あるいはアテナイ海軍の財力源を断つかしないかぎり、我々はさらに多くの損害を受けよう。その上、ことにこの場合にもし我々が戦争を挑発したと考えられると戦争終結が困難になろう。すなわち、アテナイの領土を荒せば戦いは早急に解決するというかの楽観論に我々は喜んでいてはならない。それよりも、おそらく我々はこの戦争を次代の者達に残して行くのではないかと私はそれをおそれる。つまり陸地に恋々としたり、戦争に未経験で度を失ったりするようなことはアテナイには起りそうもないことである。」
「〔八二〕 しかしながら、私は決して我々の同盟諸都市がアテナイから被害を受けているのを無関心に放置したり、その謀略を見逃せと主張しているのではない。私の主張は今すぐに武力に訴えるのではなく、使節を送って非難はしても開戦の意志を明らかにしたり、また逆に、弱味を見せてもならないという事である。そしてその間に、もしも、船舶なりとも資金なりとも、我々の力を増すものがあるならば、ヘラス、異語族諸国を問わず、いずこからでも得られるものを得て、我々および同盟諸国の態勢を整えるべきである。そしてこれと同時に我々自身も準備を怠ってはならない。もしアテナイが我々の使節に耳を傾けるならば好都合である。さもなくば、ここ二、三年は様子をみる方がのぞましい。しかもなお勝利の希みがあれば備えを固めてから彼らを敵とすべきである。そして我々に充分な用意ができたことをアテナイ人が知り、その用意を背景にして我々が談判すればアテナイもおそらく譲歩するであろう。ましていわんや、その領土も無傷のままとあればわざわざ幸せな現状をあえて破壊しようとは考えないであろう。アテナイの地味が良好なだけにそれを失うとその損失も大きい。ゆえに土地が良く耕されていればなおさらそれを一種の人質とも見倣すべきである。できるだけ彼らの土地を荒すことを避け、彼らを失望に追い込み、頑なにしてしまうようなことがあってはならない。つまり、不完全な用意で、同盟諸都市の言葉に載せられてアテナイ領に侵入し、ペロポネーソスに恥と困難を招いてはならない。紛糾の段階では公私ともに和解のメドもつくが、私憤で全体が巻込まれて戦争を始めてしまっては、先行きも判らないままとなって恥しくない結果に到達しにくくなる。」
「〔八三〕 また、味方の多数の都市が一都市を攻撃するのをためらったからといって臆病と考えてはならない。そのわけは、アテナイは税を取りたてられるたくさんの同盟都市をもっていて、戦争は ― 特に陸上勢力が海上勢力に対する戦争では ― 武器そのものよりも、武器を購う財力が決定的な意味をもっているからである。我々は、同盟諸都市の言葉に唆かされる前に、まず財力を蓄積しなければならない。事の結果の良し悪しの責任の大半は我々に帰するのだから、それだけに落着いて成行きをまず見きわめるべきだ。」
11 ペロポネソス戦争の長期化とアテナイ・スパルタが抱えた「セキュリティ・リスク」
前431年5月頃、ペロポネソス同盟軍はアッティカに侵入し、アテナイの要衝オイノエを攻略した。しかし、アテナイはペリクレスの籠城戦術により、陸軍主力を温存しオイノエに急派することはなかった。
オイノエでのアテナイとの総力戦によりアテナイ軍の壊滅を意図していたペロポネソス軍はその目論見が外れ、加えて頑強に抵抗するオイノエを陥落させることもできず、これを諦めアテナイ北方約10キロメートルのアカルナイ地区まで進み陣を固めて刈り入れ時期の農地を荒らし、一ヵ月ほど破壊活動行って糧食が尽きたのち撤退した。
一方、アテナイ側は、陸上では精強なペロポネソス軍との戦いを避け、籠城戦術により戦力の温存を図りつつ、他方、海上では圧倒的に優位な海軍力を利して、〔二三〕……ペロポネソス軍がアッティカ領内にいる間に、重装兵千名、射手四百名をかねてから用意の軍船百隻に乗せるとペロポネソス沿岸周航に出発させ……(ツキジデス「戦史」巻二第23章)、ペロポネソス軍のアッティカからの引き揚げ後も〔二五〕……ペロポネソス周航中の百隻のアテナイ船隊と五〇隻のケルキュラ援軍船隊は、その同盟諸勢とともに沿岸諸地を荒らしていた。……(ツキジデス「戦史」巻二第25章) 以後、数年次に渡り、ペロポネソス軍のアッティカ侵攻とこれに対抗するアテナイのペロポネソス沿岸諸都市に対する海上からの攻撃が繰り返されたが決定的な打撃を双方いずれにも与えることなく、際限のない消耗戦が長期化した。
(1) アテナイにおける疫病の発生
この頃、アテナイ国内では、疫病が二度にわたり発生した。一度目はペロポネソス軍のアッティカ侵攻後数日を経ずしてアテナイ市民に疫病の兆候が現れ、ペリクレスの籠城戦術により市外から移ってきた移住者に多く犠牲者が出た。
疫病はアテナイ市内にいた者ばかりでなく、遠征軍兵士も倒していった。〔五八〕……クレオポンポスは、ペリクレス麾下の船団を率いると直ちに出航してトラキア地方のカルキディケおよびいまだ包囲されたままでいたポティダイアに到着すると破城装置を起用するほか、あらゆる手段を講じてこれを落とそうとした。しかし彼らはこの攻略に失敗し、装備は無用の長物と化した。このわけはここでもアテナイ勢に疫病が蔓延し、彼らを甚だしく苦しめたからだ。疫病は攻囲軍兵士を倒し、ハグノーンの援軍が到着するまでは健康であった在来のアテナイ兵士も援軍の兵士からこれに感染した。……ともかくハグノーンが配下の船団を伴ってアテナイに帰ってみると、この約四十日間の遠征で四千名の重装兵の中から千五百名の生命が疫病に奪われていた。……(ツキジデス「戦史」巻二第58章)
二度目の疫病の蔓延は、前427年で〔八七〕冬になると、疫病が再びアテナイを襲った。はじめの時との間に休息状態はあったがそれでも完全に消滅してしまったことはなく、再発した疫病は一年以上も続いた。しかも最初は二年間も続いたのでアテナイを苦境に立たせる最大原因となり、その国力に悪影響を及ぼした。兵籍にある者から重装兵が四千四百以上、騎兵が三百、それに無数の群衆が死んだ。当時は地震もアテナイ、エウボイア、ポイオティア、そして特にポイオティアのオルコメノス地方などに頻繁に起こった。(ツキジデス「戦史」巻三第87章)」
このような災害(疫病、地震等)に対する「耐性」は、古代のみでなく現代においても「ナショナル・セキュリティ(安全保障)」上の大きなファクターとなっている。最近例で言えば、2011年3月11日「東日本大震災」発災直後におけるロシア情報収集機の飛来(3月29日、5時間にわたり九州沖から北海道西方まで空自の警戒態勢や電子情報を収集)や中国ヘリの海自護衛艦への異常接近(3月26日、南西諸島公海上で警戒監視中の海自護衛艦に異常接近し周回する)は、罹災時における自衛隊の対処能力など仮想敵国である日本の「セキュリティ・リスク」への対応力を見極めようとした動きと言える。
(2) アテナイ船隊の機動作戦に翻弄されるペロポネソス勢
ペロポネソス戦争の長期化につれ、イオニア海など周辺海域の制海権を完全に掌握しているアテナイ船隊の存在は戦況をアテナイ側に有利にしていった。
精強なスパルタ兵を中心としたペロポネソス同盟諸邦軍は、毎年のように穀物の収穫期にあるアッティカに侵攻しアッティカの曠野を荒らしてアテナイの食糧事情を逼迫させようとした。
しかし、アテナイ船隊の海上防衛により確保された海上交易ルートを通じて黒海方面などからの穀物輸入がアテナイの外港ペレウスの港から安定して行われていたため、アテナイが食糧に困窮することはなかった。
他方、アテナイ船隊のペロポネソス沿岸諸都市に対する機動作戦(多数の重装兵を伴って、沿岸諸都市に「ヒット・アンド・アウェイ=敵勢力を見極め、情勢有利なら上陸し攻略する。強力な敵勢力の反撃があれば即座に海上軍船に撤収し、次の敵側都市を目指す」攻撃を行う。)は、アテナイ船隊の来襲が事前に予測できないことから、ペロポネソス勢に常時警戒態勢を強いることとなった。
前425年には、アテナイ船隊の機動部隊はスパルタ領域の西方に位置するイオニア海沿岸のピュロス島を襲い、スパルタとの攻防戦の末を撃破してこれを要塞化し、多数の重装兵を捕虜とした(ピュロス・スパクテリアの戦い)。翌年(前424年)には、ペロポネソス半島南方沖に位置し、海上交通の拠点で、軍事的にも要衝であったキュテーラ島を占領した。
〔五五〕 ラケダイモーン人は、アテナイ人がキュテーラを占領したことを知ると、自国の海岸線が攻撃されることを予期した。しかし、総力をあげてこれに対抗しようとはせずに、地域毎の必要度に応じて、重装兵をできるだけ多く各地方に派遣して、守備に重点をおいた。このわけは、スプアクテーリアにおける予想外の大被害やピュロスやキュテーラを奪われたために、戦争があらゆる面で急速に展開して、彼らの思惑が出し抜かれた形になってしまい、新しい内乱が起ることを恐れたからであった。そこで彼らは従来の習慣に反して、四百の騎兵隊と弓兵部隊を設置したが、彼らは今までにかつてないほどに戦いに臆病になっていた。それは彼らが自分たちの本来の戦法からは異なった海上戦に巻き込まれた上に、平穏にしていることは現実に何かを失っているのと同じように考えるアテナイを相手にしていたからである。しかも短時日に起きた多くの理屈にあわない事件は、完全に彼らの意気を沮喪させて、二度と再びスプアクテーリアのような非運に見舞われることのないようにと、彼らを臆病にしたのであった。以上のような理由で彼らはいよいよ戦意を失い、いまだかつて経験もしたことのないような災難で、自分たちの考えにも自信をなくしてしまって、どんな少しの動きでもとれば、すべて失敗に終るように思えた。(ツキジデス「戦史」巻四第55章)
〔五六〕 そこでアテナイ人が沿岸地域を荒しても、彼らは今や拱手傍観して、警備地の近くにアテナイ軍が上陸すると、自分たちは劣勢にあるとして、上述のように消極的態度をとっていた。……(ツキジデス「戦史」巻四第56章)
このようなスパルタの自信喪失は「ヘイロータイ」の反乱に対する極度の警戒心を生み、〔八〇〕……ラケダイモーン人は農奴のその数とその無謀さを恐れて、次に述べるようなことをした。ラケダイモーン人は農奴に声明を発して、この戦いで立派な働きをしたために自由にされるべきだと判断される者たちは自ら申し出るように告げ、彼らをためしたのだ。つまり、自分自身を他に先駆けて自由にするほどの働きがあると思うような者こそ、ラケダイモーン人に一番反抗しそうな者たちであると考えたのである。そこで二千名に達する農奴が名乗り出ると、頭飾りで解放されたことを現し、神殿に自由民として入ると、間もなく屠られてしまったが、誰もどんな方法で彼らが殺されたか知っているものはいない。……(ツキジデス「戦史」巻四第80章)
(3) 将軍プラシダスによるスパルタの巻き返し
前424年、スパルタは、イオニア海沿岸のピュロス島要塞を拠点としてスパルタ本国の攻撃を意図するアテナイに対抗し、アッティカ西部にある都市メガラの攻防戦に将軍プラシダスを派遣した。そして、プラシダス軍の奮闘によりアテナイ軍を避け、メガラは壁門を開いてプラシダス軍を受け入れ寡頭政権を樹立した。勢いを得たプラシダス軍は千七百の重装兵を率いてトラキア地方に入りデロス同盟側都市に攻勢をかけ、トラキア地方におけるデロス同盟の要衝だったアンビポリスを奪った。
このアンビポリスの陥落はアテナイに大きな衝撃を与えた。〔一〇八〕……特にこの都市がアテナイ人にとって、船材の輸入と貢納金の面で、極めて重要であったばかりでなく、……アテナイ同盟諸都市の同盟離脱も大いに憂慮されたのである。……(ツキジデス「戦史」巻四第108章)
(TOPに戻る)
12 和平の機運―アテナイ、スパルタ両陣営の事情
前422年夏、トラキア地方の要衝アンピポリスをめぐる攻防戦で、アテナイは敗退し将軍クレオンを失った。スパルタの将軍ブラシダスも深手を負い、勝利の勝ち鬨を聞きながら息を引きとった。
この会戦おけるアテナイ、スパルタ両陣営の主戦派の巨魁であった二人の死は、両陣営における和平交渉の気運を高めることとなる。
同年冬、将軍ラムピアスに率いられたスパルタ軍はトラキア平定を目論み、テッサリアのビエリオンに侵入したが、テッサリア人の頑強な反抗に遭った。先のアンビポリスの攻防戦でのトラキア平定積極論者の将軍プラシダスの戦死も相まって、ラムピアスはその機会を逃したと判断し、テッサリアを撤退しスパルタに帰国した。その理由は、彼らが出征時にスパルタ国内の意見がすでに和平に傾いていたことを知っていたからであった。
和平機運にあるアテナイ、スパルタ両陣営の事情について、ツキジデスは次のように述べている。(ツキジデス「戦史」巻五第14、15章)
〔一四〕 アムプィポリス戦とラムピアースのテッサリア撤退の直後に、双方とももはや戦いから手を引く状態が出現し、両陣営ともに和平を求める意見を持つにいたった。それはアテナイ側としてはデーリオンで痛められ、ひきつづきアムプィポリスでも敗れたので、以前には当時の好調に勝算ありとして和平交渉を拒否しうるほど自己の力に対して持っていた自信も今は失われてしまっていたからである。それと同時に、アテナイ同盟諸都市がアテナイの躓きに、好機到れりとばかりに一挙に同盟離脱行為に出る憂いもあって、ピュロス戦の後に和平を好条件の下で結ばなかったことを悔みもしていた。一方、ラケダイモーン側としても、この戦いはアッティカ領に侵入して土地を荒しさえすれば数年でアテナイの力を挫けると考えた予測に反した結果となり、しかもスプァクテーリア島事件のように、それまでスパルタに起きたことのないような災いに遇い、ピュロスとキュテーラからは領土を荒された。しかもこれに加うるに農奴の逃亡が相次いで頻発し、落ちのびた者たちが現状に乗じて、外部から以前と同じような反乱を起す可能性が常にあった。さらに、アルゴスとの三十年休戦条約がこの年に満期になり、アルゴスはキュヌーリアが返還されない限り条約の更新を拒否しているので、アルゴスとアテナイと両者を同時に敵に廻して戦えないと判断した。また、ペロポネーソスの都市の中にはアルゴスに組する都市が出てくる疑いもあったが、事実、この事態は実際に生じたのであった。
〔一五〕 このような理由から、双方ともに和平条約を結ぶべきであるという結論に達した。特にラケダイモーン人側がスプァクテーリア島上の者の復員を強く望んだのは、彼らが支配階級であり、かつまたその血族であったからである。そこでラケダイモーン側は、スプァクテーリア陥落直後に和平交渉を開始したが、アテナイ側は好調の折りから、ラケダイモーンと対等の立場で講和を結ぶことは承知できなかった。しかしデーリオンでアテナイ側が敗れると、ラケダイモーン側は今度こそアテナイも弱腰になったと判断して、一年間休戦条約をすぐに取り決めた。そしてこの一年の間に、更に長期の和平条約を結ぼうと望んだのである。
13 「ニキアスの和約」の成立とペロポネソス情勢の混迷
アテナイとスパルタが内部に抱える事情を受けて両国で高まった和平機運は、前421年「ニキアスの和約」として結実しペロポネソス・デロス両同盟に休戦をもたらした。
ペロポネソス・デロス両同盟の「安全保障のジレンマ」による緊張関係の増幅は互いの恐怖心を高め、ある極みを超えたところで「ペロポネソス戦争」という武力による両陣営の闘争へと発展していったが、この間においては、両陣営のポリスが抱える事情(隣接ポリスとの領土紛争など)は彼らの恐怖心による闘争の前に羈束され問題とはならなかった。
だが、「ニキアスの和約」による緊張関係の膠着状態は互いの恐怖心を沈静化し双方に落ち着きと正気心を戻させ、スパルタと対立していたコリントスなど諸ポリスに新たな猜疑心を生じさせることとなった。〔二五〕……この条約を承認した諸都市は平和を保ったが、コリントスとペロポネーソスの数都市は事態を動揺させ、同盟諸都市との間に新しい問題をラケダイモーンに対し提議したのであった。……(ツキジデス「戦史」巻五第25章)
スパルタでの講和会議に参加していたコリントス使節団は、その帰途中立国・アルゴスに立ち寄り、〔二七〕……アルゴスの執政者たち数人と会合を開いた。そしてラケダイモーン人がよからぬ目的のために、特に全ペロポネーソスの隷属を目論んでいるために、以前は不倶戴天の敵であったアテナイとさえも講和および同盟を結んだのである……(ツキジデス「戦史」巻五第27章)として、スパルタと利害が対立していたペロポネソス諸邦とアルゴスとの同盟都市としての相互防衛条約締結を提案して帰国した。
このようなペロポネソス同盟内の利害の対立の表面化はスパルタの妨害工作を受けつつも、前四二〇年夏、アテナイ、マンティネイア、エリス、アルゴスの四ヵ国条約に結実して、アテナイとペロポネソス内部の諸国との結束がかたまった。以後、ペロポネソスの盟主であるスパルタと反スパルタ諸邦との複雑な外交戦はペロポネソス情勢の混迷化を深めていった。
さらに、アテナイとの関係において、〔二五〕……時間の経過とともに、アテナイはラケダイモーンの誠意に疑問を抱くようになった。そのわけは条約に記された義務をラケダイモーンが確実に履行していないという点にあった。しかしともかく、両都市は6年と10ヶ月の間は双方の領土に直接的な敵対行動をとることは避けていた。けれども外地にあっては、不安定な停戦状態のまま相互にできる限りの損傷をもたらしあったので、ついに十年戦争後に締結した条約を破棄せざるを得なくなり、再び明らかな戦闘状態に入った。(ツキジデス「戦史」巻五第25章)
(TOPに戻る)
14 アテナイのシケリア遠征
(1) シケリア遠征に向けたアテナイの動き
前416年末頃、シケリアの同盟都市・エゲスからの来援要請を受けたアテナイでは、大規模な装備を持った同盟諸邦による助援部隊をシケリアに派遣し、この機会にシュラクサイ始めとするドーリス系ポリスを倒しシケリアを征服しようとする動きが起きた。
シケリア遠征の目的について、遠征積極論者であったアルキビアデスは次のように述べている。「〔九〇〕……我々のシケリア遠征の目的は、できるならば第一にシケリア島を掌中に収め、それからイタリア諸都市を落とし、その後にカルケードーン人とその主権まで襲ってみようとするものであった。そしてもしこのすべてかあるいは大部分の企てに成功したならば、それからペロポネーソスに手をつけようとしたのである。彼の地で新しく獲得したヘラスの兵力を総動員し、イベーリア族その他、今日好戦性をもって知られている多くの異語族を雇兵とし、さらにはイタリアの豊富な木材を用いて三重櫓船を造り、これを現有勢力に加え、もってペロポネーソス沿岸を封鎖もしたであろう。また陸上からも諸都市を陸勢をもって攻撃し、この都市は積極的襲撃により、あの都市は包囲作戦によるというように、次々と陥落せしめて、容易に諸都市を屈服させ、ついには全ヘラスの覇権を目指しもし、また資金、糧秣に関しても、好結果を得るためには、この地で徴収することなく、近時獲得の彼の地の所産で充当しようとしたことであろう。(亡命先のスパルタ議会での証言:ツキジデス「戦史」巻六第90章)」
当時のアテナイの有力指導者ニキアスは民会において、和約により休戦状態であったペロポネーソス同盟との敵対関係やトラキア地方の諸都市の離叛の動きからヘレスにおけるアテナイの支配が万全でないとしてこの提案に反対を表明したが、民会の大勢は扇動政治家アルキビアデスの具体性は欠くものの気宇壮大なシケリア遠征計画に描かれていた「アテナイの覇権を全ヘラスに具現化する」という「覇権主義」に惹かれていった。
このため、ニキアスは装備面での過大な負担を訴え再考を促した。(ツキジデス「戦史」巻六第20~23章)
「〔二〇〕……ナクソス市とカタネー市はレオンティーノ市の関係から我々に味方してくるとしてもその他に七つの都市があり、それらはすべてアテナイ市とほぼ同質の装備を持っており、ことに我々の最大目標であるセリーヌース市とシュラクーサイ市がその最たる都市である。これらの都市は多くの重装兵、弓兵、槍兵、それに多数の三重櫓船およびその全乗組員を擁し、経済面でも、個人の私有財産もあれば、セリーヌース市には市有の蓄財が神殿にあり、シュラクーサイ市などは一定の異語族に初年貢を収めさせているほどである。特に彼らが我々に最も優る点は、馬匹の所有量と、輸入穀物に頼る必要がない点であろう。
〔二一〕このような強国に対しては船舶に加えて少々の軍勢を送るばかりでなく、陸上勢力の大部隊を派遣しなければ、我々の企図に見合った活動もできず、特に彼の地の諸都市が恐怖から共同して我々との有効を拒絶し相互援助を打ち切って、エゲスタ騎兵隊以外にはを守ってくれる都市のない場合には、敵の騎兵隊に牽制されてしまって上陸さえもおぼつかないであろう。ともかく、撃退されることも不名誉ならば、初めの思慮の浅さを裏書きするように後になって増援部隊を送ることも恥ずかしいかぎりである。すなわち我々は一気に充分の用意をして出発しなければならない。我々は本土を離れて遠隔の地に行くのであって、隣国に侵入するのとは自ら違うことをよく悟り、……容易に糧秣の補給を近辺から受けられることもなく、冬になれば、その地から報告が来るのに四ヶ月かかっても難しいようなところであることを知っておかなければならない。
〔二三〕敵の戦闘員、すなわち敵の重装兵に匹敵するだけの装備を我々アテナイ人が持って行くばかりでなく、あらゆる部門にわたって我々が敵に優勢を保ち得るようにしない限り、敵に勝利を得ることはおろか自らの安全を保つことさえもおぼつかないであろう。……そして上陸第一日目に勝利を得て早急に領土を確保できる体制を整えないかぎり、万一この一戦に敗退するようなことがあれば、八方に敵が現れるであろうことを覚悟しなければならない。……」
アルキビアデスのアジテーションによりシケリア遠征に傾いていた民会の多数はニキアスの慎重論にも耳を傾けたが、「アテナイをヘレス世界の理想とし、その顕現をヘレス世界に広めていく」という「覇権主義」の道を選択し、ニキアスとその政治的ライバルであったアルキビアデスそして軍人として評価の高かったラマコスを派遣将軍として選び、将軍たちに兵数および軍船調達に関する全権を与えることを議決し、シケリア遠征を決定した。
ツキジデスは、アテナイのシケリア遠征が、彼我の勢力比の分析や事を構えるにあったての精緻な軍略の検討もないままで突き進んでいったことについて、〔一〕……多くのアテナイ人がシケリア島の大きさにも、ヘラス人や異語族をまじえたこの島の住民の数にも無知であったばかりでなく、対ペロポネーソス戦に比較して決してその規模において劣らない戦争に手をつけることになることに気付かなかったからである。(ツキジデス「戦史」巻六第1章)と述べているが、その背景には〔六五〕……アテナイ人は何でもすべてがうまくいっていたので、その幸運に酔い、彼らの向かうところ敵するものはないように思い、しかも、できることもできないことも、準備の大小にかかわりなく成就すると考えていた。このような考えの原因は、望外の繁栄にアテナイ人が夢と実力の違いを忘れてしまっていたからであった。(ツキジデス「戦史」巻四第65章)という思いがあった。
またツキジデスは、アテナイのシケリア遠征に従うアテナイ同盟諸邦についても、シュラクサイの政治的指導者ヘルモクラテスの言葉を借りて、〔七九〕……同盟は安全保障を目的に締結されたのであって、ある敵が諸君の領土に侵略行為を犯した場合とか、アテナイが不正侵入を他国から受けた場合とかのみに相互扶助の義務が生じる……(ツキジデス「戦史」巻六第79章)として、アテナイ自身が侵略者でその行為に正当性がない場合、同盟の諸条項は適応されない、と述べている。
アテナイは、ペロポネソス戦争開戦時におけるアテナイの政治的指導者ペリクレスの諌言「〔一四四〕ともかく諸君が戦争中に帝国の版図拡大を企て、自ら危険を招こうとしないかぎり、勝利の見込みを約束する理由は他にも多くある。私が心配するのは外敵の計略より、かえって国内にある我々自身の誤りだ。……(ツキジデス「戦史」巻一第144章)」を顧みる者もない中で、「自国の安全保障のため対外侵略を行う」という逆説的論理で、破滅の道に進んでいく。
(2) シュラクサイ民会の動き
アテナイ同盟軍のシケリア遠征の報を受けたシケリアの最大都市・シュラクサイは民会を開催し、その対応について検討が加えられた。
この民会において、政治的指導者ヘルモクラテスは勝利の可能性に言及し、「〔三三〕……ヘラスの大軍であれ、異語族の大軍であれ、自国を遠く離れた大軍が戦いに成功した例は稀だからである。しかも全住民が恐怖のために一致協力する以上、数の面でも、来襲する敵が現地人の数やその周辺の都市の人口に勝ることはあり得ない。そしてもし敵が不慣れな土地で物資補給に窮して敗退すれば、たとえその敗因が敵自らが招いたものであれ、勝利の名誉は防備軍の上にもたらされる。……(ツキジデス「戦史」巻六第33章)」とし、公民派指導者のアテナゴラスも「〔三七〕……アテナイ勢には騎兵隊が随行していないことを私は知っている。そしてシケリアでは、エゲスタ市が彼らをある程度助ける以外は、彼らはどこからも騎兵隊を徴収することはできない。重装兵の数にしても、彼らは我々と同数の兵力を船で送ってはこれない。とにかく空の船腹でもこれだけの距離を航行するのは難事なのである。ましていわんや、本市のような大都市を攻囲するための他の必需物資は決して少ないものではあり得ない。……全島が敵であるシケリアにあって輸送船の補給物資にのみ頼った陣地の中では、我々の騎兵隊の脅威の前に、その乏しい装備と設備から、あまり遠くには出られないであろう。……(ツキジデス「戦史」巻六第37章)」と述べ、ともに戦局の優位性を強調した。
しかし、その脅威の「急迫性」については意見が分かれ、ヘルモクラテスは「〔三三〕……このように敵が時を経ずして来る以上は、現状において最上の防備方法を考え、敵を侮って不備を衝かれたり、来襲を信じず全てを放置しておくようなことがあってはならない。……(ツキジデス「戦史」巻六第33章)」と述べ、「〔三四〕……でき得るならば全シケリア人を動員し、さもなければその大多数をもって、我々は二ヶ月間の供給物資とともに全現有海軍力を投入しタラース市沖およびイアーピュギア半島沖にてアテナイ勢に挑戦する……(ツキジデス「戦史」巻六第34章)」よう主張したが、アテゴラスを始めとする公民派は、寡頭派がこの機会に政治の主導権を握ろうとしていると猜疑しこれに応じなかった。このため、民会は「ナショナル・セキュリティ(安全保障)」を脅かす「アテナイの来襲」を目前にしながら、寡頭派・公民派の政争の中で結論を出し得ず散会した。
(3) シュラクサイ攻防戦の始まり
前415年夏、シケリア島に到着したアテナイ同盟船隊は三隻の先遣隊からの報告内容(レーギオン市の協力拒否など)からシュラクサイに対する即戦攻撃を断念し、アルキビアデスの提案により、シュラクサイ包囲網構築のためシケリア各都市への協力工作を開始することとした。しかし、アテナイ側の調略に応じて壁門を開く都市はほとんど見られないまま無為にその夏を終えた。(この年、アテナイの公民派による反アルキビアデスの工作が功を奏し、アルキビアデスは本国に召還されることとなり戦線を離脱した。アルキビアデスは身の危険を察知し本国への帰途途上スパルタに亡命した。)
冬を迎えてアテナイ同盟軍は、シュラクサイの軍勢がアテナイ側都市カタネーに対する攻撃に打って出た虚を突いて、海路からシュラクサイ近郊のオリュムピエイオン付近に上陸し、シュラクサイに向けて攻撃を仕掛けた。不意打ちを受けたシュラクサイ勢の戦列は崩壊し敗走が始まったが、シュラクサイ側が圧倒的優位を誇る騎兵がアテナイ同盟側の重装兵に対抗し態勢を立て直すことができた。
この冬、アテナイ同盟軍は〔七四〕……ナクソス市に帰投し、陣の周りに防柵と防濠を造って、そこを越冬の宿営地とした。アテナイには三重櫓船を送って、春と同時に軍資金と騎兵隊を送るよう要求した。(ツキジデス「戦史」巻六第74章)
一方、〔七五〕シュラクーサイ人は冬の間に防壁を築いた。この防壁は……エピポライ(※シュラクーサイ市の北に隣接する丘)全体に面して、たとえ敵が戦闘に勝ってもシュラクーサイ市の完全包囲のために余分の距離を必要とするように仕組んだ。……(ツキジデス「戦史」巻六第75章)
このようなシュラクサイ攻防戦は、翌年(前414年)にも引き続き持ち越し、双方とも決定的な打撃を相手に与えることができなかったが、アテナイ同盟軍側はアナポス河付近の戦闘で将軍ラマコスを失い、包囲作戦の要となるエピポライもシュラクサイ側に奪還された。
(4) シュラクサイ攻防戦の転機 ― スパルタ将軍ギュリッポスの活躍
この年(前414年)の夏、シケリア救援に急派されたスパルタ将軍ギュリッポスの船団がシケリア島北岸の都市ヒーメラに到着し、ヒーメラなどの協力都市の重装兵等を伴って陸路シュラクーサイ救援に向かった。
ギュリッポスの救援軍は、シュラクーサイ付近で救援の報を聞いて戦意の高まったシュラクーサイ勢と合流し、シュラクーサイ包囲の陣を敷いていたアテナイ勢を急襲した。その後、両軍対峙の中で、コリントスなどのシケリア救援の後続船団がアテナイ船団の警備の目を逃れてシュラクーサイに入港し、戦力が強化された防御側の士気はいよいよ高まった。
加えて、〔七〕ギュリッポスはシケリアの他の諸軍を訪ねて、陸海兵力を集め、今まで消極的であった都市や戦争圏外にあった都市等に積極的にギュリッポスに従うように求めた。……(ツキジデス「戦史」巻七第7章)
〔八〕 ニーキアースはこの動きを察知し、日毎に敵の力が増大するに反して自軍がだんだん苦境に落ちて行くのを目のあたりにすると、幾度となくアテナイに使者を送って、逐次、状況の変化を報告して来たが、特にこの時に到ると事態の緊迫化を理解し、至急、相当な規模の後続部隊の派遣のない限り、状況は絶望であると判断した。……(ツキジデス「戦史」巻七第8章)
ニキアスは、このような窮状を伝えるべく、ニキアスの書簡を携えた使者をアテナイに向けた。ニキアスの書簡において、敵の数的優勢の前に敵に包囲されているごとき事態に立ち至っていて、その主な原因は敵の優勢な騎兵隊によって陸上行動の自由が奪われているとしてその窮状を訴え救援軍の派遣を求めた。
とりわけ、優勢を誇っていたアテナイ同盟船隊の抱える問題に言及し、
「〔一二〕……わが軍の海軍力は船の乾燥度と船員の健康に相よって、その勢力はきわめて優勢であった。しかるに今や船はこのような長期にわたって水上にあったため完全に湿気をよんでしまい、しかも船員には欠員が頻出している。このわけは、我軍の船数に匹敵する、いやむしろそれ以上の敵の軍船がいつ何時我々に襲撃を加えてくるか判らないため、船を陸揚げして乾燥することができないからである。敵は明らかに演習を行っており、その好む時に攻撃がかけられ、敵が船を陸揚げして乾燥するのも、我軍と異なって他を警戒する必要がないためその思いのままの状態にある。(ツキジデス「戦史」巻七第12章)」と述べた。
※ この時代の軍船は、 船足を速めるために船の外板には松などの木質の柔らかい木材を使用していた。木質の軟らかい木材は水分を吸収しやすく船足が遅くなるため、使用時以外は海上などに係留することなく陸上に上げ乾燥する必要があった。
また、当時の軍船は船内に居留部分がないため、休息時は海上から安全を確保できる浜地などを確認し、軍船を揚陸して乾燥させながら、乗員が食事や休息をとっていた。
さらに 「〔一三〕 ……また過去において我々が船員を失い、現在もいよいよ欠員の数が増加の一途を辿っている原因は、まず第一に水、薪、糧株の徴発に遠距離の行動を要し、その間に敵の騎兵隊の襲撃を受けて多くの損害が出る点であり、第二にはわが軍の戦況の不利になるや従卒の脱走者が増加し、しかも雇兵の中のある者たちは船の乗り組みを強制されるやすぐに各隊の出身地に帰国してしまったり、他の者は当初から高給を目的に参加し、戦闘よりも賃金に興味があるところから、一朝予期以上の強力な敵船団の出現を目にするや、まことしやかな理由をつけて脱走して帰国したりするからである。さらにある者たちは、シケリアの豊かさのためにそれぞれ相当に富んでおり、自ら商業に従事さえしていて、三重櫓船の船長を説き、自分たちの代りにヒュッカラ人の奴隷を船に乗り組ませているため、我が船団の効率に著しい低下を招いているためである。(ツキジデス「戦史」巻七第13章)」として第一回遠征に劣らない陸海両軍の派遣と多額の軍資金の手当を要請した。
前413年春頃、ギュリッポスはシュラクサイの対岸に位置するプレーンミュリオンのアテナイ側陣営に対する海陸からの攻撃を仕掛けた。海戦においては練達なアテナイ船団の前にシュラクサイ船団は敗北を期したが、ギュリッポスの率いた陸上部隊はプレーンミュリオンのアテナイ側の防砦三ヵ所を落とし、ここに守備隊を置き警備することとした。
このプレーンミュリオンは、シュラクサイ包囲戦で行き詰まっていたニキアスが海戦に望みをかけ、〔四〕……軍勢と船団を移動し、三つの地点に防砦を築き、その中に主要軍需物資を貯え、輸送船や早船をその付近に停泊させた……(ツキジデス「戦史」巻七第4章)「兵站拠点」として極めて重要な地点であった。
(5) シケリア遠征アテナイ同盟軍の壊滅
同じ頃、ペロポネソス同盟諸軍は、十数年ぶりにアッティカに侵攻し、アテナイ市を望見することのできる高台デケレアに防塁を構築した。その意図するところは、デケレア砦に同盟諸軍を常時駐留することでアテナイ市を間断なく圧迫し、シケリアに展開するアテナイ同盟軍の動きを牽制しようとするものであった。
ツキジデスは、ペロポネソス同盟諸軍によるデケレア築砦がアテナイ側の事態の悪化に甚大な影響に与えた状況について、次のように述べている。〔二七〕……デケレア占拠以前には、ペロポネーソス側のアッティカ侵入の期間は短く、侵入期間以外は何の不便も感じなかった。しかしデケレアに常時敵が駐留しているとなると大変な圧迫を受けることになった。すなわちこの敵に対応するだけの守備隊が常置されなければならず、領土内での略奪行為がなされ、ラケダイモーンの王アーギスが終始何を措いても戦闘第一主義に徹していたので、アテナイ側の被害は厖大なものとなった。アテナイ人は全アッティカ地域から締め出され、二万人以上の奴隷が脱走し、しかもこの大部分は職人階級の奴隷であった。それに羊、家畜類は全滅状態で、馬匹も連日デケレア襲撃や諸地域警備のために酷使されて、連続した疲労や固い道のために、ある馬は跛になり、他の馬は殺された。(ツキジデス「戦史」巻七第27章)
ペロポネソス同盟諸軍によるデケレア築砦など攻勢を受けたアテナイ本国であったが、その年の夏を迎える頃には将軍デモステネスのもとシケリアに向け援軍を送り出した。その規模は、〔四二〕 ……約七十三隻の船に雇兵およびアテナイ人とその同盟諸都市の重装兵をほぼ五千名同行し、この他、異語族とヘラス人からなる投槍兵多数、弓兵、投石隊およびそのほか相当な装備を擁していた。これはその当座シュラクーサイとその同盟軍に少なからぬ打撃を与えた。つまりデケレア築砦にも拘わらず、アテナイは前回の遠征軍と同規模の軍勢を派遣して、アテナイの実力を余すところなく示していることを知って、シュラクーサイを脅かす危険の去る日のまだ遠いことを感じたからである。……(ツキジデス「戦史」巻七第42章)
しかし、シケリアに到着したデモステネスは、アテナイ側の兵站拠点であったプレーンミュリオンをシュラクサイ側に奪われるなど攻防戦の実情を知ると戦局が容易ならざることを悟り、〔四二〕……デーモステネースは実情を知ると、安閑と時を過してはおれず、またニーキアースと同じ轍を踏んではならないことを悟った。つまりニーキアースのシケリア到着はその当初大いに恐れられていたにも拘わらず、彼はシュラクーサイ市に直接攻撃をかけることを避けてカタネー市で越冬したため、その脅威も衰えてしまった上に、ギュリッポスに先を越されて、ぺロポネーソスからの軍勢がシュラクーサイ市に到着してしまったのである。この軍勢とて、もしニーキアースが到着後ただちにシュラクーサイ市を攻囲していれば、シュラクーサイ人はペロポネーソスにその派遣方さえ要請していなかったであろう。つまりシュラクーサイ人は彼らだけでアテナイ勢に初めは対抗し得ると考えて、包囲壁に囲まれてしまうまで自分たちの劣勢に気がつかなかったであろうから、たとえそれから援軍を要請したとしても、その到着の効果が実際に当時起きたのと同じではあり得なかったからである。ともかくこうしたことを観察したデーモステネースは、援軍はその到着当初が一番恐ろしく敵の目にうつることを考え、できるだけ早くこの恐怖を利用しようとした。しかもアテナイ側の包囲壁を阻んだシュラクーサイの防壁が一重壁であることを見て、エピポライの登り口とその敵陣を押えることさえできれば、誰も抵抗できる者はいないから容易にこの防壁を占領できると考えた。そしてこれこそ戦争終結への最短距離であるとしてこの作戦遂行を決心した。つまりシュラクーサイに勝つか、あるいはアテナイ軍を徹退させるかすることが、従軍兵の損失とアテナイ市の力の浪費を防ぐことになると考えたからである。……(ツキジデス「戦史」巻七第42章)
もはや時の浪費は許されないと判断したデモステネスは、シュラクサイ包囲戦の帰趨を左右するシュラクサイ北の丘陵地・エピポライへの夜間攻撃に着手した。敵の目を欺くための夜間攻撃は、アテナイ勢の夜襲を予想だにしていなかったエピポライ上のシュラクサイ軍の警備部隊を圧倒したが、救援に駆けつけたシュラクサイ勢との間で敵味方入り乱れる混戦状態となった。
ただでさえ現場の地形に通暁していないアテナイ同盟軍勢は、夜の闇の中で阿鼻叫喚の喧噪に阻まれ敵味方の合い言葉さえ聞き取れず大混乱に陥り総崩れとなって敗走した。〔四四〕……敗走した多くの者は追われるままに崖から身を投じて死んだ。これはエピポライから下の平地におりる路が狭かったからである……、後からエピポライに来た者たち(※第二次派遣兵士)は方向に迷って、その辺りを右往左往していたので、夜が明けるとシュラクーサイ側の騎兵隊にとらえられて殺された。(ツキジデス「戦史」巻七第44章)
エピポライの敗戦を受けて、〔四七〕……デーモステネースは、エピポライ攻略作戦が失敗した今となってはもはやこの地にぐずぐずしていても何の利益にもならないと総撤退を提案し、救援に来たアテナイ船を加えてアテナイ船団がまだ敵に勝てる可能性があれば、海を通れる間に早速、躊躇せずに行動すべきであるとした。もはや攻略の望みとてないシュラクーサイよりは、自分たちのアッティカに築砦している敵に挑戦した方がアテナイ市の為であるとも言って、ここに居坐っていればますます多くの冗費を使うことになると主張した。(ツキジデス「戦史」巻七第47章)
このようなデモステネスの主張に対し、ニキアスはこの攻囲作戦に固執し、同意することなく、アテナイ同盟軍は時間を空費したままその地に留まっていた。
しかし、その間もギュリッポスはシケリア島諸地から多くの軍勢を集めてこれらの諸勢により再びアテナイ同盟軍の陸海両軍を攻撃するべく両面作戦の準備を整えた。このような情勢の逼迫にさすがのニキアスも攻囲戦を断念し、撤退命令を全軍に伝えた。
アテナイ同盟軍の困窮した事情を察知したシュラクサイ側は、その船団に納得のいくまで幾日も訓練を積み重ねさせた後に〔五二〕……七十六隻の船を出撃させ、同時に陸上部隊は防壁に再び攻撃を仕掛けた。アテナイ側はこれに対して八十六隻の船をもって対抗し、海戦を展開した。……(ツキジデス「戦史」巻七第52章)
この海戦でシュラクサイ側はアテナイ側の船列の中央を破り、港の懐奥深く位置していたアテナイ船隊に総追撃をかけて、海岸に追い上げた。この海戦でアテナイ側は十八隻の船を奪われ乗組員は全部殺された。
海戦の敗北の前に〔五五〕……アテナイ勢は全く士気を喪失し、強い失望感に襲われ、いよいよこの遠征に対して後悔の情を強くした。……多くの面で失敗を重ねてきたアテナイ軍は、その対策に窮し、まして思いもよらなかった海軍の敗退によってますます苦境に陥った……。(ツキジデス「戦史」巻七第55章)
アテナイ側は軍議を開き、〔六〇〕……現状の窮境を種々検討したが、……物資の補給が急速に望めないこと、また制海権を握らないかぎり今後の物資の供給は不可能である……(ツキジデス「戦史」巻七第60章)とし、保有する全船舶に陸上勢から戦闘員を最大限乗船させ、アテナイ遠征軍の命運を握る船団決戦をシュラクサイ側に挑むべく決定した。
シュラクサイ大港にあるアテナイ側船団約百十隻と大港全体を取り巻く形で対峙したシュラクサイ側船団七十隻余は、港出入り口を閉塞していたシュラクサイ船列に対するアテナイ側の攻撃を端緒として双方合い乱れる海戦となり、長い戦いの後シュラクサイ側が勝利した。
この海戦にシュラクサイ側が勝利した背景についてツキジデスは次のとおり述べている。〔三六〕……前回の海戦の経験から有用と思われることは取り入れ、舳を切って短く丈夫にし、その両脇の吊錨架を厚くし、さらにそれを補強する支柱を舷側に延ばし、その長さは舷の内側と外側とを含めて六ペーケイス (※約3メートル) にした。この態様はナウパクトス海戦でコリントス船がその吊錨架に採用した型である。この理由は、シュラクーサイ側がアテナイの船は強度において劣っていることを悟り、舳と舳をぶつけあう戦法の目的よりも、迂回して敵の船腹にあたる戦法用に船が造られていて、その舳は長く鋭く、しかしそれだけに強度が足りないことを知っていたからである。(ツキジデス「戦史」巻七第36章)
〔七二〕海戦は熾烈をきわめ、両軍ともに多くの人数と船を失った。シュラクーサイとその同盟軍は敵を破ると漂流物や死体を拾い集めてシュラクーサイ市に帰港し、、戦勝塚を立てた。アテナイ人たちはあまりの現状のひどさに、死体や漂流物資拾集を申し入れることも忘れて、夜半ただちに撤退しようとした。しかしデーモステネースはニーキアースの所に来て現在でも使用できる残されたアテナイ船の数は敵船よりもまだ多いのであるから、できるならばこれらの船にもう一度兵士を乗り組まして、夜明けと同時に再び港外強行脱出を試みようと提案した。つまりアテナイ側には約六十隻の船が残されており、これに対してシュラクーサイ側は五十隻に満たないほどであったからである。ニーキアースもこの案に賛成して、彼らは兵士に船の乗り組み方を要求したが、船員たちは敗戦に完全に士気を失い、勝算のありようはずもないと乗船を拒否した。(ツキジデス「戦史」巻七第72章)
このためアテナイ同盟軍は陸路撤退案でまとまったが、現実は充分な糧秣もなくこの地に留まっていても座して死するを待つことを意味し、陸路の撤退も拠るべき撤退先もない中での逃避行であり、〔七一〕……今やアテナイ側にとっても何か奇蹟でも起こらないかぎり、陸地に救いを求めることは全く望めなかった。(ツキジデス「戦史」巻七第71章)
ツキジデスは、「戦史」巻七第75章以下その終章にわたり敗軍の逃避行を部隊の壊滅まで詳述しているが、他の巻で見られる冷徹で論理的な筆致と異なり、その記述の行間には遠い異国の地で斃れたアテナイ人への哀惜と憐憫の情が充ち満ちており、鎮魂の賦として読む者の涙を誘う。
〔七五〕……海戦の日より既に三日を経ていた。アテナイ市も遠征兵士自身も抱いた大きな夢の代りに、今や全船団を失って撤退することがこの事態を惨たるものにしたばかりでなく、離陣に当って目にも心にも忍び得ない苦悩が広がっていった。すなわち死体は埋葬されることもなく散らばり、その中に知人を見出せばいよいよ悲しさと恐しさに人々は襲われたからである。しかし生残っている者たちの心をさらに締めつけ苦しめたものは、これらの死者たちよりも生きながら後に残される重傷者や病人たちであった。彼らの哀嘆や懇願は行く者を困惑させ、一人一人が一緒につれて行ってくれと兵士に呼びかけ、叫び、同僚や知人と見かければ、この行く仲間に取縋って体力の続くかぎりその後を追った。そして力が尽き果てると彼らは神に訴える悲痛な声とともに後に置きざりにされていったのである。悲涙は全軍に満ち、たとえ今までに涙以上の被害を敵から受け、またこれから先行きどんな災いが待ち受けているか判らないという恐怖を行く者たちも抱いているにしても、この苦悩のために彼らの足は容易に前に進まなかった。そして失意と自責の念にさいなまれ、彼らの姿はあたかも包囲に破れた大きな都市の市民が落ちのびて行く姿の如くであった。この群衆は総計四万人を下らなかったが、これが一度に撤退を始めたわけである。それぞれ全員が役立ちそうな物資を負い、重装兵も騎兵も従来の習慣とは異って自から装備の下に糧秣をになった。これは奴隷に不足していたこともあるが、奴隷を信用できなかったことも一因であった。以前から脱走者はあったが、この時になるとその数は急激に増加した。しかしそれにも拘わらず、アテナイ勢は充分の食糧を携行していなかった。所詮アテナイ軍にはもはや食糧がなかったのである。苦労も分けあえば軽くなるとはいうものの、全将兵が一様に受けたこの時の不運と災難は決して安易なものではなく、ことにあれほどに豪華絢爛を極めた遠征当初から悲惨の果に至ったこの結末までの過程を振返えると、ますますその感を強くした。しかもこれほど大きな落差を味わったヘラス軍はこれまでになかった。すなわち他を隷属しようと遠征して来た部隊が今や隷属させられることを恐れて撤退し、武運の祈りと戦勝歌に送られて出征して来たのに反して敵の不吉な声に追われて去ろうとしており、船で来たにも拘わらず陸地を行き、海軍力よりも陸上兵力に頼らざるを得なくなっていたからである。しかしこれにも拘わらず、来るべき一大危機に比べれば、これらすべてを合わせてもまだ耐え易いように思われた。(ツキジデス「戦史」巻七第75章)
(TOPに戻る)
前413年夏、アテナイ側の敗軍は、陸路当て所なく活路を求めてシケリアの曠野に彷徨っていたが、包囲したシュラクサイ勢に退路を断たれ、アッシナロス河畔でついに降伏した。将軍ニキアスとデモステネスは処刑され、多くの者がシュラクサイ勢に殺されるか、あるいは虜囚の身となった。
ツキジデスは、アテナイ同盟軍のシケリア遠征失敗がヘラス社会にもたらした衝撃について、次のように述べている。(ツキジデス「戦史」巻八第1、2章)
〔一〕 アテナイにこの情報がもたらされると、状況を正確に伝えるためにシケリアから帰国していてこの災難を免がれた歴戦の兵士たちにさえ、あれほどの兵力がそれほど簡単に潰滅してしまったとは思えず、長い間その報は信じられなかった。しかし事実が確認されると、この遠征に賛成した政治家たちを、大衆は自分たちが遠征を支持して投票したことも忘れたごとくに非難し、当時シュラクーサイ遠征に望みを抱かせて大衆を煽動した予言者、占い者等々に対しても怒りを露わにした。人人はこの事件のために極端な恐怖と驚愕に全く打ちのめされた。重装兵隊を失い、騎兵隊を失い、そして兵役適令者層を失って、もはやその補充もきかないことは、都市全体にとっても、また一個の市民にしても、沈欝にならざるを得ないことであった。その上船庫の船は不足し、国庫には蓄財なく、船に漕手もいなければ救われる道なしと人々は絶望した。敵船団は、特にこれほどの大勝利を得たからには今にもシケリアからペイライエウス港に入港してアテナイを襲い、アッティカにいる敵も、アテナイとの同盟を破棄した諸都市を糾合し、あらゆる装備を倍増して陸海からアテナイを攻めたてるであろうと人々は考えた。それでも彼らは現状から降服することは得策でないと判断すると、用材、資金をどこからでも可能な所から集めて船団を建設し、同盟諸都市問題、殊にエウボイアとの関係の安定を強化し、国内にあっては財政引締めを計り、現況に関して必要ある時は勧告できる長老委員の選出を決定した。このように、民衆の動きの常ではあるが、現在の事に恟恟としてその安定化を求めたのであったが、ともかく、これらを彼らは決議するとその実行に移り、この夏は終った。
〔ニ〕 冬になると、シケリアにおけるアテナイ軍の大敗退はたちまち全ヘラス世界を動揺させ、今まで中立していた都市は、要請も受けないうちに、戦争を傍観していてはならじと打倒アテナイに踏み切り、アテナイが万一シケリアで成功を収めていれば必ず自分たちの所に押寄せていたであろうと各都市は思い、またこれを同時にこの戦争のやまも見えたとして、勝戦さに加わっておくことを上策と考えた。一方、従来のラケダイモーン同盟諸都市は早々に重い負担を片付けてしまおうと、前にもまして士気を大いにあげたのであった。中でもアテナイの支配下にあった諸都市は、感情に任せた情況判断から、自分たちの実力を無視して反旗を翻えし、アテナイが少なくとも来るべき夏は持ちこたえられるであろうという言葉にも耳を貸さなかった。ラケダイモーン人の都市を元気づけた理由の中でも特に重要なことは、シケリアにおけるラケダイモーン同盟諸都市は今までに必要に迫られて海軍を築きあげてきたが、その一大兵力をもって春と同時に遠征してくる可能性が強いという点であった。あらゆる面に明るい見通しを持ったラケダイモーン人は何の躊躇もなく戦争完遂に専心した。それは勝利を獲得した暁にこそ、シケリアを征服して終始ラケダイモーンをアテナイ人が脅かすというような危険から彼らが初めて逃れられ、またアテナイを完全に屈服させることによってようやくラケダイモーン人は安心して全ヘラスに君臨できるものと考えたからである。
以上のように、ツキジデスはアテナイの没落とスパルタの覇権主義への野望を予見しながら、「戦史」巻八終章「ヘレスポントス・キュノスセマの海戦」で「戦史」を擱筆している。
(TOPに戻る)
