1「大いなる眠り」とは
「大いなる眠り」の原書は、レイモンド・チャンドラーの推理小説の金字塔「私立探偵フィリップ・マーロウ」シリーズの記念碑的な第一作「THE BIG
SLEEP」として1939年に発表され、日本でも翻訳版「大いなる眠り」として創元推理文庫に長らく収められていたものを、早川書房が翻訳権を取得し、村上春樹訳による新訳版「大いなる眠り」として発表したものである。
「大いなる眠り」の訳者は、当代切っての売れっ子作家で多くの著作がベストセラーとなっているそうで、その評判と古典と言ってもよい原書「THE BIG
SLEEP」がどのようにマッチングするのか大変興味を持ちまた期待もした。
2 「大いなる眠り」の意外な訳
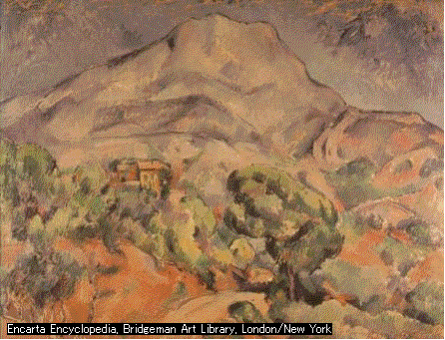
ところが、この「大いなる眠り」を期待を込めて開いたものの最初の1行目の訳文「太陽は姿を隠し、開けた山裾のあたりは激しい雨に濡れているように見えた。」で、目が止まってしまった。
情景のイメージが湧かないのだ。推理小説ファンなら、その程度の想像力、推理力が無くてはいけないとご叱責をいただくかも知れないが、今ごろマーロウを手に取る推理小説ファンの初級者にも成り得ない身には、そこから進むことができなかった。
と言うわけで、慌ててランダムハウスの「THE BIG SLEEP」を某所から借り受け、冒頭部分を繙(ひもと)くことにした。原文は
「It was about eleven o'clock in the morning, mid October,with the sun
not shining and a look of hard wet rain in the clearness of the foothills」
となっている。これはどう見ても、
「a look of hard wet rain in the clearness of the foothills」
と、マーロウのいる
「the sun not shining」
の場所が同一でなく、地域的に近接した場所で異なる気象状況であると解釈してよく、限られた小地域に降るにわか雨(私雨)が、小高い山の上の開墾地に激しく降っていて、しばらくすると曇り空の麓(ふもと)が雨模様になるかも知れない天候の変わりやすい「mid
October」を表現していると言ってよい。
チャンドラーは冒頭でこの「雨がいつ降るかわからない」という状況設定を読者に潜在的に意識づける訳だが、「THE BIG SLEEP」全編を斜め読みして総覧すると、この「mid
October」の変わりやすい天候の情景は「THE BIG SLEEP」全編のあちらこちらにちりばめられている。
それを全て紹介するわけにもいかないので、索引する利便も考慮して、以下の各章冒頭で「mid October」の変わりやすい天候の情景を取り上げているケースのみに絞って見てみよう。
SIX(第六章)
Rain filled the gutters and splashed knee-high off the sidewalk. Big
cops in slickers that shone like gun barrels had a lot of fun carring giggling
girls across the bad places. The rain drummed hard on the roof of the car
and the burbank top began to leak. A pool of water formed on the floorboards
for me to keep my feet in. It was too early in the fall for that kind of
rain. (排水溝から溢れた雨水を通りがかった車が膝の高さまで跳ね上げ歩道を濡らしていた。黒っぽい雨合羽を着た大柄な体躯の制服警官達が、近くでたむろしていた少女達を抱えて水のついた道路を横切って運んでいたが、警官達に抱えられた少女らはクスクス笑いをし、警官達も満更でない様子だった。コンバーティブル[1939
Plymouth P8 Deluxe Line?]の幌屋根に雨が激しく打ちつけ、その天井付近から雨が漏れ出し、車の床には足がつかるほど水がたまりだした。これだけ激しい雨の降りだしは秋口にしては少し早過ぎる。)
NINE(第九章)
The next morning was bright, clear and sunny.(翌朝は、日の光が燦々と降り注ぎ、空気の澄みわたった絶好な日和だった。)
TWELVE(第一二章)
The trees on the upper side of Laverne Terrace had fresh green leaves
after the rain. In the cool afternoon sunlight~(ラーバン通りの高台寄りにある街路樹は、雨あがりの露に濡れて目の覚めるような緑に包まれていた。その爽やかな昼下がりの陽光の中で~)
SEVENTEEN(第一七章)
A moon half gone from the glowed through a ring of mist among the high
branches of the eucalyptus trees on Laverne Terrace.(ラーバン通りのユーカリの木高い梢に漂う霧を透かして輝いていた半月が夜空を通り過ぎていった。)
TWENTY-FIVE(第二五章)
It was raining again the next morning, a slanting gray rain like a swung
curtain of crystal beads.(翌日の朝も再び雨模様で、鉛色の空から降る横なぐりの雨はクリスタルカーテンが揺れ動いているような感じだった。)
TWENTY-SIX(第二六章)
At seven the rain had stopped for a breathing spell, but the gutters were
still flooded. On Santa Monica the water was level with the sidewalk and
a thin film of it washed over the top of the curbing.(七時になってしばらくの間雨が止んだが、道路際の排水溝にはまだ雨水が流れていた。サンタモニカの道路では、溢れた雨水が歩道の高さまでになって、薄い膜を作って縁石の上を洗い流していた。)
TWENTY-SEVEN(第二七章)
“Give me the money."
The motor of the gray Plymouth throbbed under her voice and the rain pounded
above it.(「お金をちょうだい」女の声がグレーのプリマスのエンジン音に負けないかのように響き、そして激しい雨脚が車の幌屋根の上でドラムを叩くように音をたてていた。)
THIRTY(第三〇章)
This was another day and the sun was shining again. Captain Gregory of
the Missing Persons Bureau looked heavily out of his office window at the
barred upper floor of the Hall of Justice, white and clean after the rain.(日が変わり、明るい日差しが戻ってきた。失踪者対策課のグレゴリー警部は,事務所の窓から物憂げな眼差しで向かいの裁判所の鉄格子が施された二階部分を眺めた。汚れを雨で流れ落としたその建物は、雨上がりを受けて白く清潔な佇まいを示していた。)
チャンドラーはこのようにして各章冒頭で「mid October」の変わりやすい天候の情景を色々な角度から描写しながら、この小説の全編を彩る背景を形作ろうとしていることがよく分かる。
その意味で、冒頭の「大いなる眠り」の訳文「太陽は姿を隠し、開けた山裾のあたりは激しい雨に濡れているように見えた。」の素っ気なさでは、原著者・チャンドラーが表現しようとしたデリケートな意味合いが消えてしまっているのだ。
ちなみに、「大いなる眠り」のブックカバーの表紙裏のキャッチコピーには、「(「the sun not shining」の場所に)ほどなく雨の降り出しそうな」という端的なフレーズが使われていて、ほっと安堵した。
3 「大いなる眠り」を原著「THE BIG SLEEP」と比較する
その様なこともあって、期待が落ち込んだ分、「大いなる眠り」の訳文に少しばかりの不安を感じつつ、原書「THE BIG SLEEP」の、小説家が作品を書き出す時に一番心血を注ぐという出だし部分について取り上げ、本稿の中に「原文」、「大いなる眠り」訳文と、当方が「原文を読んで描いたイメージ」を並列して記載し、若干の比較をすることとした。
(「THE BIG SLEEP」原文)
It was about eleven o'clock in the morning, mid October,with the sun not
shining and a look of hard wet rain in the clearness of the foothills.
I was wearing my Powder-blue suit, with dark blue shirt, tie and display
handkerchief, black brogues, black wool socks with dark blue clocks on
them. I was neat, clean, shaved and sober, and I didn't care who knew it.
I was everything the well-dressed private detective ought to be. I was
calling on four million dollars.
The main hallway of the Sternwood place was two stories high. Over the
entrance doors, which would have let in a troop of Indian elephants,there
was a broad stained-glass panel showing a knight in dark armor rescuing
a lady who was tied to a tree and didn't have any clothes on but some very
long and convenient hair. The knight had pushed the vizor of his helmet
back to be sociable, and he was fiddling with the knots on the ropes that
tied the lady to the tree and not getting anywhere.
I stood there and thought that if I lived in the house, I would sooner
or later have to climb up there and help him. He didn't seem to be really
trying.
There were French doors at the back of the hall, beyond them a wide sweep
of emerald grass to a white garage, in front of which a slim dark young
chauffeur in shiny black leggings was dusting a maroon Packard convertible.
Beyond the garage were some decorative trees trimmed as carefully as Poodle
dogs. Beyond them a large green house with a domed roof. Then more trees
and beyond everything the solid, uneven,comfortable line of the foothills.
On the east side of the hall a free staircase, tile-paved, rose to a gallery
with a wrought-iron railing and another piece of stained-glass romance.
Large hard chairs with rounded red plush seats were backed into the vacant
spaces of the wall round about.They didn't look as if anybody had ever
sat in them.
In the middle of the west wall there was a big empty fireplace with a
brass screen in four hinged panels, and over the fireplace a marble mantel
with cupids at the corners.Above the mantel there was a large oil Portrait,
and above the Portrait two bullet-torn or moth-eaten Cavalry pennants crossed
in a glass frame. The Portrait was a stiffly posed job of an officer in
full regimentals of about the time of the Mexican war. The officer had
a neat black imperial, black mustachios, hot hard coal-black eyes, and
the general look of a man it would pay to get along with.
I thought this might be General Sternwood's grandfather. It could hardly
be the General himself, even though I had heard he was pretty far gone
in years to have a couple of daughters still in the dangerous twenties.
(村上版「大いなる眠り」訳文)

十月の半ば、午前十一時頃のことだ。太陽は姿を隠し、開けた山裾のあたりは激しい雨に濡れているように見えた。私は淡いブルーのスーツに、ダークブルーのシャツ、ネクタイをしめ、ポケットにはハンカチをのぞかせ、穴飾りのついた黒い革靴に、ダークブルーの刺繍入りの黒いウールのソックスをはいていた。小ざっぱりと清潔で、髭もあたっているし、なにしろ素面(しらふ)だった。さあ、とくとご覧あれ。身だしなみの良い私立探偵のお手本だ。なにしろ資産四百万ドルの富豪宅を訪問するのだから。
スターンウッド邸の玄関ホールの天井は、二階ぶんの高さがあった。インド象の大群だってくぐり抜けられそうな入口扉の上には、大きなステンドグラスのパネルがはまっていた。
暗い色合いの鎧(よろい)をつけた騎士が、木に縛り付けられたご婦人を救おうとしている図柄だ。女は一糸まとわぬ裸だったが、ひどく長い髪が具合良くその身体を覆っていた。騎士はかしこまって兜(かぶと)の面頬(めんぼう)を押し上げ、ご婦人を縛りつけているロープの結び目をほどこうとしていたが、どうにも歯が立たないようだった。
私はそこに立ち、もし自分がこの家の住人であれば、騎士を助けるために、いつかそこに上っていくことになるだろうなと思った。その騎士は真剣にロープをほどこうとしているようには見えなかったからだ。
玄関ホールの奥にはフレンチ・ドアがあり、その先にはエメラルド色の芝生が気前よく広がり、真っ白なガレージに通じていた。ガレージの前では真新しいゲートルを巻いた、黒髪のほっそりした若い運転手が、えび茶色のパッカード・コンパーティブルの埃を払っていた。
ガレージの向こうには何本かの装飾的な樹木があって、どれもプードル犬みたいに念入りに刈り込まれている。その先にはドーム型の屋根のついた大きな温室があった。それから更に樹木があり、それらすべての先に揺らぐことのない、不揃いにして心休まる山の稜線が見えた。
玄関ホールの東側には支柱のないタイル張りの階段があり、回廊へと通じていた。回廊には錬鉄製の手すりがついて、ここにもまた中世のロマンスを題材にしたステンドグラスがひとつはまっていた。
丸みのある赤いビロードのシートがついた大きな堅い椅子がいくつか、回廊を囲む壁のへこんだ部分に、引き込んで置かれていた。その椅子に実際腰掛けたものはまだ一人もいないように見える。
西側の壁の中央には空っぽの大きな暖炉があり、その前に四面のパネルを蝶番(ちょうつがい)で繋げた真鍮の衝立(ついたて)が置かれていた。暖炉の上には大理石のマントルがあり、その角にはそれぞれキューピッドが飾ってある。マントルの上には巨大な油絵の肖像画がかかり、肖像画の上には銃弾に引き裂かれたか、あるいは虫に食われたかした騎兵隊の二枚の連隊旗が、交差した形でガラスの枠に収められていた。
肖像画に描かれた人物はメキシコ戦争時代のものらしき完全軍装で、しゃちほこばってポーズをとっていた。綺麗に刈り込んだ威風堂々たる黒い口髭をたくわえ、石炭のような漆黒の、熱っぽく厳しい瞳を持ち、その風貌全体に人を寄せつけぬものがあった。
スターンウッド将軍の祖父かもしれない。その士官がスターンウッド将軍自身であるはずはない。たとえ将軍がこの何年かの間に、未だ危機をはらんだ二十代の娘二人を抱えるにしては、いささか老いぼれてしまったという噂を私が耳にしていてもだ。
(原文「THE BIG SLEEP」を読んで描いたイメージ)
10月半ばの、曇り空ではあるが、ここから見える小高い山の開墾地には激しい雨が降っていて、しばらくすると雨模様になるかも知れない朝方の11時頃であった。
私の身なりは、濃紺のシャツに、ネクタイ、ポケットチーフを飾った薄青色のスーツに、穴飾りを施した黒靴、黒いウールの靴下にはダークブルーの時計の模様がついているいでたちで、十分に小綺麗だし、ひげも剃り、今日は酔いも醒めている。まー、どうでもいいことだが。私は身だしなみをきちんと整えた私立探偵のあるべき姿そのものだった。なんと言っても、とてつもない大金持ちの資産家を訪問するのだから。
スターンウッド邸の玄関中央ホールは2階部分まで吹き抜けになっている。インド象の大群でも招き入れることのできる両開きの大扉の入り口の上部には幅広のステンドグラスパネルがはめられていて、そこには鈍色(にびいろ)の鎧を着た騎士が木に縛り付けられた全裸の女(丁度いい具合に豊かな長い髪が身体にまとわりついている)を助けようとしている図柄が描かれている。
騎士は礼を失することのないように兜のバイザーをはずし、女を木にくくりつけているロープの結び目を解こうとしたが、これがうまくいかない。
私は大扉の前で、自分がこの邸に住んでいるなら、むしろ早くそうしたいと言うか、遅かれ早かれそこに上って騎士を助けなければならないと考えた。どう見ても騎士は真剣にロープの結び目を解こうとしていないからだ。
中央ホールの奥はガラス格子の両開きドアになっていて、その向こうは白っぽい車庫に向かって鮮やかなエメラルド色の芝生がいっぱいに広がり、車庫の前では、黒光りしたレギングスを履いた痩せぎすの黒髪の若い運転手がえび茶色のパッカード・コンバーチブルの埃を払っている。
車庫の後ろにはプードル並みにしっかりと刈り込まれた庭木がある。その向こうは丸屋根の大きな温室だ。そして灌木の茂みがあって、茂みの向こうにはなだらかな起伏が連なる堅牢な山並みの稜線が続いている。
中央ホールの東側はタイル張りのらせん階段が、加工鉄製の手摺りのある、もう一つの恋物語を描いたステンドグラスがかかった階上の廊下に続いていた。2階の回廊になっている廊下の壁のところどころに設けられた窪んだスペースには、赤い毛羽のあるビロード地の丸みを帯びたシートを敷いた大きめのハードチェアが置かれていたが、一度も使われていない感じだ。
ホールの西側の真ん中ほどの壁の部分には、四枚組の真鍮製の網状のスクリーンを炉前に設けた、薪の焼(く)べられていない大きな暖炉があって、暖炉の上部の大理石製の炉棚のそれぞれの角にはキューピッドが彫られていた。
その炉棚の上には大きな油絵の肖像画が掛けられていて、額縁のガラスの内側には銃弾で裂かれたか虫食いされたかした騎兵隊の三角旗二枚が肖像画の上に交差するように置かれていた。
その固く強ばったポーズの肖像画はメキシコ戦争当時と思われる士官のいでたちで、綺麗に整えられた黒い顎髭と口髭、情熱のたぎった黒い瞳の厳しい目つきの風貌は、なかなか難しい人柄を示していた。
この肖像画はスターンウッド将軍の祖父かも知れない。将軍その人だと考えるのは難しいだろう。と言うのも、将軍自身、何をしでかすか分からない二十歳代の二人の娘を持って、その行状に悩まされ、ここ数年、かなり酒に溺れて惚(ぼ)けてしまったと聞いているからだ。
(※ 拙い描写に加え若干の誤りもあるかも知れません。ご寛容下さい。)
4 「大いなる眠り」の直訳部分について
訳者が原文の意味合いを損なわないように、極力直訳することは大切だと思うが、これもあまり直訳すぎると読者も戸惑ってしまう。
例えば、「大いなる眠り」訳文では、庭の情景の説明部分で、ガレージの向こうにある「decorative trees」を「装飾的な樹木」と訳しているが、これでは読者は首を傾げてしまう。これは単なる「decorative」な「trees」でなく「decorative
trees」として訳さないと意味が分からない。
「decorative trees」は、洋風庭園を熟知している読者なら、動物の形などに刈り込んだ木を思い起こされると思うが、日本には、西洋との文化や美的感覚の違いからその様な概念の木はなく、どちらかと言えば「ornamental
tree」が日本語の庭木に近い。
このような背景を理解しつつ、ここは無理矢理「装飾的な樹木」と訳すのでなく、素直に一番近い意味の「庭木」と訳したほうが、「大いなる眠り」の読者の理解を得ることができる。
次に、2階の回廊になっている廊下の壁のところどころに設けられた窪んだスペースにある「hard chair」を、「大いなる眠り」訳文では文字通り「堅い椅子」と訳しているが、この「hard
chair」は、背や座の部分が木製の「single chair」に類するものとすべきで、このような大邸宅の長い回廊の途中に設けられたスペースで、出入りする人々が時には座って打ち合わせに使ったり、小用を座りながら処理するために使われたりするもので、機能的に安息や休息のためにレイアウトされているものでない。
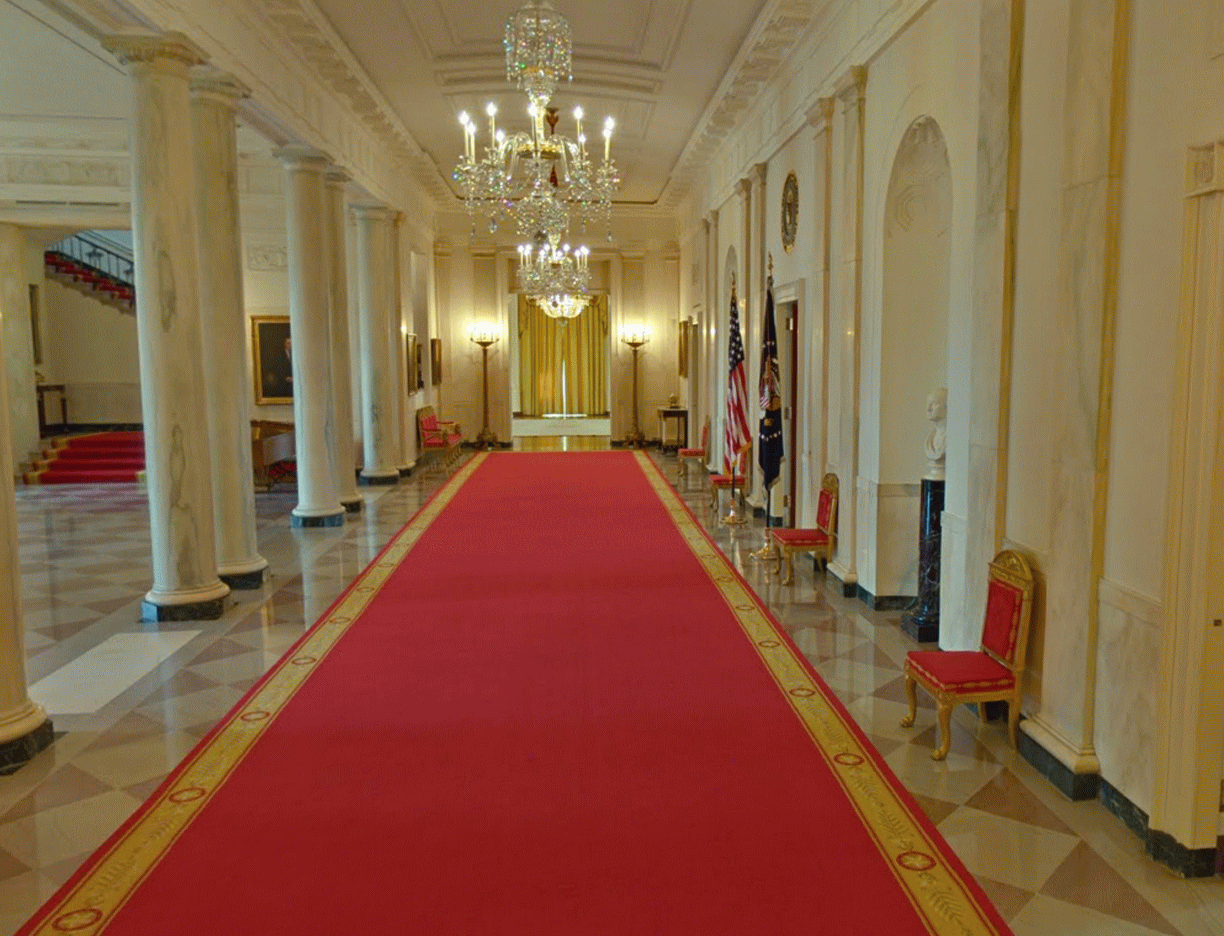
(イメージとしては、ホワイトハウスで大統領がステートメントを発表するときによく使われる赤い絨毯敷きの「クロスホール」の廊下沿いの壁際にレイアウトされている豪華なハードチェアが参考になる。)
この場面はそういう意味で、ハードチェアが置かれているぐらいの長い回廊を持つ大邸宅であるが、そのチェアに座った形跡がないほど人の出入りがない閑静さを表しており、「大いなる眠り」訳文のように単に「堅い椅子」と情景描写されると原著者のチャンドラーも椅子からずり落ちてしまう。
また、「大いなる眠り」訳文では中央ホールの「free staircase」を「支柱のない階段」と訳しているが、これでは何のことか分からない。通常、「free
staircase」とは、らせん階段またはビルの外壁に設置された階段を意味することが多いが、この場面では、二階に通じるらせん階段を表していると思う。
同じく中央ホールの西側にある暖炉の「a brass screen in four hinged panels」を「大いなる眠り」訳文の「四面のパネルを蝶番(ちょうつがい)で繋げた真鍮の衝立(ついたて)」としてしまうと、暖炉が使えない。
ここは、「四枚組の真鍮製の網状のスクリーン」とすれば、火入れもできるし、埋もれ火の暖気も網目を通して伝わるし、熾(お)き火がはじいても網状のスクリーンが防いでくれる。欧米の暖炉のある家では、この 「fireplace
screen」を実用的な機能と装飾も兼ねて暖炉に設けるのが普通で、原著者・チャンドラーもそういう意味で描いていた筈だ。
他にも、マーロウが見上げる「the solid, uneven, comfortable line of the foothills.」という山並みの稜線の情景を、「大いなる眠り」訳文では、「揺らぐことのない、不揃いにして心休まる山の稜線
」としているが、これでは訳文の文字を追っているうちに理解不能な不揃いなイメージが頭の中で揺らいで空中分解し、とても心を休めることはできない。
5 「大いなる眠り」のよく分からない訳について
次に指摘したいのは「大いなる眠り」訳文のよく分からない訳である。
冒頭部分で主人公マーロウの様子を原著「THE BIG SLEEP」は「I was neat, clean,shaved and sober」と描いているが、「大いなる眠り」訳文ではこれを「小ざっぱりと清潔で、髭もあたっているし、なにしろ素面(しらふ)だった。」と訳している。
細かいことであるが、この一節の「clean shave(髭を剃る)」と「shaved(酔っぱらっている)and sober(酔っぱらっていない)」は意味の掛け合いになっていて、「十分に小綺麗だし、ひげも剃り、(日頃は酒浸りだが)今日は酔いも醒めている。」とした方が、マーロウの酒好きを捉えていると思う。
引用した原文「THE BIG SLEEP」の終わり近くの、将軍の状態を表す「he was pretty far gone」についても、「大いなる眠り」訳文では「いささか老いぼれてしまった。」と単純に訳しているが、ここも原文の一節には「酔ってかなり出来上がっている。」というもう一つの意味もあるところから、「かなり酒に溺れて惚(ぼ)けてしまった。」としたい。
その方が、原書「THE BIG SLEEP」の第2章で、お互い酒好きなマーロウと将軍が、初対面にもかかわらずブランディーを飲み交わす場面がより生きてくる。
つまり、取り上げた二つの箇所は、その後に続くストリーの展開の起点となっているのだ。
次に、マーロウが訪れたスターンウッド邸の玄関の場面であるが、入口の扉について、「大いなる眠り」訳文では「インド象の大群だってくぐり抜けられそうな入口扉」と訳しているが、この訳では読者は片開きの扉に押し寄せる象の大群をイメージしてしまう。(1946年製作の米映画「THE
BIG SLEEP」では、インド象の大群はとてもくぐり抜けられそうもない片開きの扉でした。)
また、この扉の上部を飾る「ステンドグラス・パネル」であるが、「大いなる眠り」訳文の「大きなステンドグラス・パネル」では、この扉との一体性が全く表現されていないため、読者としてはそのイメージづくりに戸惑ってしまう。
原文「THE BIG SLEEP」では、この扉を「doors」としているところから、両開き扉(a double door) と解して、ここは「インド象の大群でも招き入れることのできる両開きの大扉」とすると、インド象の大群もスムーズに通り抜けられるし、マーロウが訪れたスターンウッド邸の荘厳な佇(たたず)まいもより強調され、両開きの大扉の上部を飾るステンドグラス・パネルも大扉の横幅に合わせた豪勢な「abroad
stained-glass panel (幅広のステンドグラス・パネル)」となり、いっそう輝きを増す。
また、マーロウがたたずんでいる両開きの大扉の上に掲げられた幅広のステンドグラス・パネル上に描かれた物語の中で、女を救おうとしている騎士に対して「I
would sooner or later have to climb up there and help him」というマーロウの気持ちを、「大いなる眠り」訳文では「騎士を助けるために、いつかそこに上っていくことになるだろうなと思った。」と素っ気なく訳しているが、ここも「I
would sooner(早くしたい)」と「sooner or later(遅かれ早かれ)」の意味の掛け合いとして、マーロウの気持ちを「むしろ早くそうしたいと言うか、遅かれ早かれそこに上って騎士を助けなければならないと考えた。」とすると、原著者・チャンドラーのユーモアもよく分かる。
その他、大邸宅の中央ホールに入ったマーロウが見上げる将軍の肖像画の「a neat black imperial,black mustachios」を、「大いなる眠り」訳文では「綺麗に刈り込んだ威風堂々たる黒い口髭」としているが、「imperial」は皇帝髭とも言われ、顎髭を表している。ここの部分は「綺麗に刈り込んだ黒い顎髭、口髭」では駄目なのだろうか。
その後に続く「Cavalry pennants」も、「大いなる眠り」訳文は「騎兵隊の連隊旗」と訳しているが、「連隊旗」は、通常は「regimental
colors」と言われ、その大きさも卑近な例で言うと、大相撲の優勝旗や夏の高校野球甲子園大会の優勝旗に近い。
「大いなる眠り」訳文では、肖像画の額の内側にこのサイズの二枚の旗をクロスさせているとしているが、これでは肖像画が想像し難い大きさになり、見上げるマーロウも後ろに反っくり返ってしまう。
これは、素直に「西部劇」でよく目にする所属連隊を示す「騎兵隊の三角旗(連隊標章旗)」としてはいけないのだろうか。
6 「大いなる眠り」の世界に迷い込んで
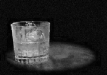
以上のようなわけで、引用した「THE BIG SLEEP」の原文の一部を読んで描いたイメージと「大いなる眠り」の冒頭の訳文二頁を比べたが、フィリップ・マーロウの世界に入り込むどころか、違和感と言うか失望感とも言うべき世界に迷い込んで疲れてしまい、原書「THE
BIG SLEEP」巻末の最後の4行目にある「On the way downtown I stopped at a bar and had a
couple of double Scotches. They did't do me any good.(ダウンタウンへの道すがら行きずりのバーに立ち寄りスコッチのダブルをあおったが、とても酔える気分になれなかった。)」と嘆いたマーロウの気持ちが身に沁みて分かる結末となってしまった。
村上版「大いなる眠り」には、それなりの解釈によるマーロウの世界が展開されていると思うが、マーロウの本当の世界を堪能したい読者には、たとえ時間がかかっても、スコッチのダブルでも口にしながら、辞書を片手にランダムハウスのビンテージ本「THE
BIG SLEEP」を読解することをお勧めしたい。
