「ユーロ消滅?」とは
本書(「ユーロ消滅? ドイツ化するヨーロッパへの警告」。以下「ユーロ消滅?」)では、「リスク社会」論で有名な社会学者ウルリッヒ・ベックが、ギリシャの国家財政の破綻に端を発したユーロ危機について、ユーロ圏随一の経済大国ドイツ主導による新たな権力状況の生起に警鐘を鳴らしている。
加えて、汎ヨーロッパ主義・コスモポリタニズムの立場から、ユーロ消滅にも繋がる危機の内実を分析・批判し、このユーロ消滅の危機を歴史的な欧州没落の延長線上の現象としてでなく、その内包する政治・経済・社会上のリスクを止揚する形での欧州の新時代への兆しとしてとらえ論じている。
「ユーロ消滅?」が指摘する決定的過ち
おもしろいことに、読者のユーロ危機に対する認識が「欧州没落の延長線上の現象」であるか「新時代への兆し」であるかにより、本書「ユーロ消滅?」は「政策社会学者の戯言(たわごと)」にもなり、「未来志向のバイブル」にも成り得る玉虫色の性格を有している。
確かに、ユーロ圏は、19加盟国、3億3,000万人余の人口を有し、圏内における人、サービス、商品の移動の自由、ユーロという域内の単一通貨による恩恵(通貨の両替、交換レート等の解消)など、多大なる成果も示している。その点で、欧州は変わったことに間違いない。しかし、ユーロ危機により、本書「ユーロ消滅?」でベックが指摘しているとおり「現在の状況は、ユーロ誕生時から存在する決定的な過ちを意識させている。」のだ。

結果論であるが、ユーロ圏内の財政統合のないままで、ユーロという通貨統合のみ先行させたことにより、各国経済間の不均衡を調整する調整弁(通貨間の為替レート)がなくなり、その経済的水位差により、ドイツでは過熱した経済によるさらなる繁栄を謳歌する一方で、ギリシャでは極端なデフレに直面し経済の停滞や失業の増加に悩まされ、国家財政の破綻にまで繋がってしまった。
今次のユーロ危機に際して、各国の銀行を監視するための銀行同盟がユーロ圏内で検討され2015年1月に欧州中央銀行(ECB)による銀行監督制度(SRM:単一破綻処理メカニズム)がスタートしたが、このような方策等が実効性のあるものとなるための根本的な前提条件であるユーロ圏内の財政統合については、加盟各国の共通認識も充分でなく、具体的な方向性がまだ見えてこないのが現状である。
酷な言い方をすれば、欧州連合体を束ねた形での予算編成権を持たない欧州議会、域内各国に対する財政規律権のない欧州中央銀行、拘束力に疑念をもたれるユーロ各国の収斂基準(各国の赤字国債発行額、インフレーション率の上限等を規定)など、財政・金融の基本原則に徹することのできない欧州連合体・ユーロ圏の諸制度を見ると、近未来の欧州には、混乱と停滞を打破する有効な手段もなく、欧州の新時代が開けるとはとても言えない。まさしく本書の「ユーロ消滅」が現実のものとなってくるかも知れない。
「ユーロ消滅」回避のために
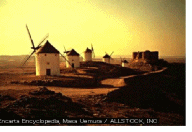
ベックは、このような「ユーロ消滅」の悲観論に対し、ユーロと欧州が崩壊する危機的状況の中では発想の転換が必要だとして、ルソーの「社会契約論」をベースにして、社会契約の主体・客体を「国民・国家」としてではなく「世界市民(コスモポリタン)・欧州」という概念でとらえ、「下からの欧州」、「世界市民の欧州」による新しい「政治的なるものの創造」を図らなければ適切な答えは見いだせない、と主張している。
しかし、いくら「ユーロ消滅」という危機的状況を前に発想の転換が必要だとしても、突然の「社会契約論」の登場はあまりにも唐突であり、「客体」である「欧州」がルソーの時代の絶対王制のような国家主権の総体としての存在であるかは、前述したとおりはなはだ疑問である。
卑近な例で言うと、アメリカのトランプ大統領や中国の習近平国家主席の名前を知っていても、加盟国28国、5億人の人口を有する欧州連合の欧州理事会議長(欧州大統領)の名前をどれだけの読者が知っているだろうか。
名前を知る機会もないし、知る必要性もほとんどないほど政治的にも有名無実な存在といってよい。現実の欧州連合も、よく似た存在と言えなくもないのである。
思うに、ベックにターゲットにされた「欧州」は、ラ・マンチャ出身のドン・キホーテに突撃された「風車」の気分を味わっているだろう。
また、「主体」であるベック流の「世界市民」についても、欧州連合加盟条約の批准拒否(1992年イギリス・デンマークの国民投票)、欧州憲法条約の批准拒否(2004年フランス・オランダの国民投票)、リスボン条約の批准拒否(2008年アイルランドの国民投票)など例を挙げれば枚挙にいとまがないほど、欧州統合を推進する立場の各国政府に足枷(あしかせ)をしたのはベックがユーロ消滅回避の担い手として期待した各国の「世界市民」たちである。
2014年5月に実施された「欧州議会選挙」では、反「EU・欧州統合」勢力のフランス・国民戦線(FN)、イギリス・英国独立党(UKIP)、デンマーク人民党などfar-right(極右)勢力が各国で第一党を占めた。
「世界市民」は、欧州統合の理念や必要性については理解しているものの、今次ユーロ危機を見て、経済統合を含めた欧州の一体化が果たして未来の輝かしい展望を保障するものか疑念をもっている。
このような経緯を踏まえると、今様の「社会契約論」の構図を成り立たせることは難しい。
政治的側面を見ると、2013年9月のドイツ総選挙において、メルケル首相与党のキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)は第1党を占めたものの過半数に達せず、最大野党・社会民主党(SPD)との大連立を組んだ。
メルケルには、銀行同盟や通貨統合の強化等欧州統合の深化に向けたリーダーシップが期待されるものの、今次ユーロ危機に際しての際限ない域内支援の苦い思い出がドイツの納税者にあり、加えてメルケルの「難民寛容政策」に対する根強い不信感が存在する。このため、メルケルにとって国内の政治的安定を最優先せざるをえない状況にある。
フランスでは、2017年5月の大統領選挙で親EUで中道・無所属のマクロンがフランス史上最年少の大統領として選出されたが、景気後退に伴う雇用の悪化等により財政緊縮策をとっているフランスの経済の立て直しや国内治安を揺るがすテロ対策等喫緊の課題などが山積していて、マクロンにとり「ユーロ問題」は政権の最重要課題となっていない。
イギリスでは、2016年6月24日に欧州連合(EU)残留を問う国民投票が実施され、「EU離脱派」が国民投票の多数(51.9%)を占め、イギリスの二年後のEU脱退が確実となった。
国内的には、EU離脱派が多数を占めたイングランドとEU残留派が多数を占めたスコットランドなどとの政治的相克が尾を引き、スコットランドの英国からの独立が現実味を増すなかで、イギリスの政治的リーダーは「EU問題」以上に国家体制の維持に難しい舵取りを迫られることとなった。
かつて、イギリスの名宰相であったチャーチルは、第二次世界大戦終結の翌年 1946年9月にスイス・チューリッヒでの演説で、欧州の歴史的栄光を取り戻すための「欧州連合体」を提唱し、そのバラ色の未来を強調した。
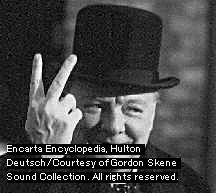
If Europe were once united in the sharing of its common inheritance, there
would be no limit to the happiness, to the prosperity and glory which its
three or four hundred million people would enjoy.
(Zurich19th September 1946.)
しかし、この John Bull の生国イギリスは、一九世紀以来の「イギリスの繁栄(Pax Britannica)」を保持するための伝統ある「孤立政策(Splendid
Isolation)」のスタイルを踏襲し、その後のEU・ユーロに対しても、常に stand out な姿勢を保ち続け、今日のEU離脱へと繋がっている。
かつてのイギリスの「孤立政策」は世界に君臨した[大英帝国]の圧倒的な経済力・軍事力により支えられていた。それらを欠いた現今の状況下での「孤立政策」は結果的に国家の衰亡を招来するものであり、その歴史的皮肉の中にイギリスの命運が尽きようとしている。
「ユーロ消滅?」で見えてくるもの
ユーロ危機に関し、この「ユーロ消滅?」を含めて多くの類書がその根元的な問題点を指摘した。今次ユーロ危機では、欧州中央銀行(ECB)の南欧国債の大量購入や欧州金融機関に対する資金供給等の非常措置により危機を回避したが、火元となった問題点は何ら解消していない。
このような諸情勢を踏まえると、今後、ユーロ消滅が現実のものになるか否かは別にして、ユーロ圏の拡大や欧州の完全統合にはほど遠いに状況にあるのは間違いない。
ただ、有史以来、民族の興亡をかけた戦いを繰り返し、また、20世紀には二つの世界大戦を経験した欧州には、破壊・征服・ホロコースト・凌辱など忌まわしい思い出として欧州各民族の遺伝子に深く刻み込まれている怨讐(おんしゅう)がある筈だが、これらを超えて欧州統合を図ろうとしているその固い意志に、女神ミネルバの末裔としての知恵の深さと、古代ギリシャから近代・現代までの世界史をリードしてきた欧州の矜持(きょうじ)を垣間見ることができる。
そういう視点で、本書「ユーロ消滅?」を繙(ひもと)けば、また別の世界が見えてくるかも知れない。
