《いま何故「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」?》
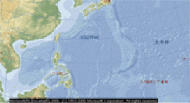
沖縄返還に伴う秘密交渉に深く関わった国際政治学者若泉敬は、1994年にその秘密交渉の経緯を『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文芸春秋社刊)によって明らかにしました。
近年、中国の海洋進出ドクトリンに伴い、尖閣諸島を含めた東シナ海で、日本と中国の間の地政学的相剋が厳しさを加えています。
沖縄の地理的重要性は言うまでもなく、その軍事的プレゼンスの如何が我が国の存立など将来の帰趨を大きく左右する歴史的なターニングポイントを迎えた中で、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」刊行の二年後に自裁した若泉敬が遺した本書のレゾンデートルはますます重みを増しています。
とは言え、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」が600頁以上の大著であるのに加え、随所に学究的立場からの資料の著述が多いため、「核の密約」を含めたその内容の重要性、衝撃性などは他の国際政治学の類書に比肩するものがないにも拘わらず、今もって読者にとり「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」が難渋な書物であることは歪めません。
《「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」を解く》
「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」は、国際政治史として当然のことながら編年体で著述されていますが、超一級の国際政治学者である若泉敬が渉猟した膨大な資料を流れに従って縦横無碍(むげ)に読み込むのは至難と言ってよいでしょう。
また、事実を事実としてのみ伝えるというそのスタイルから、若泉敬が核戦略と安全保障をフィールドワークとしていながら、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の冒頭を除いて、その関係部分を迂遠な言い回しで(あるときは、関係者の著述を引用して)おさめているため、読者にとって行間を読む作業を強いられることになり、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の「厚さ」と「深さ」の前に逡巡(しゅんじゅう)してしまうのも詮(せん)無いことです。
このため、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の内容を大まかに三区分(国際情勢、国内情勢、若泉敬の動向)の視点から取り出してみました。
「稀代のエージェント」は生まれるべくして生まれた
国際政治学者としての若泉敬を理解するため、その揺籃期の国際情勢等を見てみましょう。
若泉敬の学生時代は敗戦という現実に加えて、ソ連・中国など国際共産勢力の台頭による極東情勢の緊迫化が一段と進み、1950年には「朝鮮戦争」が勃発し在日米軍が国連軍として朝鮮半島に展開しました。
中国・人民軍の参戦などから38度線をはさんで戦線は膠着状態となり、日本でも不穏な国際情勢を背景に国土の復興と国の存立を奈辺に求めるかで世の中が沸き上がりまた混乱していた時期でもありました。
1950年に東大に入学した若泉敬は、ソ連・中国の国際共産勢力の対日工作の影響のもと左翼学生運動が主流となる中で、「学生土曜会(体制内改革を目的として、左翼学生運動と一線を画す)」のメンバーとして活動しました。
1952年には、国連アジア学生会議日本代表としてインドを訪問。帰国後発表した「独立インドの理想と現実」で英国の植民地支配によるインド民族の自主独立の気概の欠如を指摘しました。そのような行動の軌跡が、愛国の国際政治学者・若泉敬の原形を育んでいったのでしょう。
また、米国の核保有に加え、ソ連核実験(1949)・中国核実験(1967)等「核の時代」の到来を目の当たりにした若泉敬が安全保障政策のスペシャリストとして世に出て、書斎に籠もるだけでない行動派の国際政治学者として活躍したのは当然の成り行きと言って過言でありません。
振り返ってみれば、その若泉敬を「時の女神」が必要としていたことに気付きます。「稀代のエージェント」は求められるまま為すことを為し、そして忽然と消えたのです。
「核の密約」は、沖縄返還の便法
1950年代後半になると核兵器の小型軽量化、弾道ミサイル技術の進歩があり、アメリカの核戦略はそれまでの「B52搭載の核爆弾による大量報復攻撃という『打撃力』の保持」から、「長距離弾道ミサイル・アトラス(1959年配備)、潜水艦発射中距離弾道ミサイル・ポラリス(1960年配備)等による『抑止力』の保持」にシフトチェンジしました。
このような時代の流れを背景に、1960年米政府内の「琉球諸島研究グループ」が沖縄米軍基地撤去や安保条約破棄を回避するため、5年以内の沖縄返還等を内容とする報告書を提出したことに加え、1969年沖縄基地研「日米京都会議(若泉敬が主要メンバーの一人として参加)」における沖縄に核を置く必要性について、米側(ウォールステッター・シカゴ大教授)は、「①沖縄の核体系は他の新しい戦術体系で代替え済み②アジアの局地戦での戦術核兵器は効用がない③核付き返還はNPTの趣旨に反する」として、「米国にとり必要なのは核の潜在権を保持することだ。」と述べ、沖縄の本土並み返還(核抜き)に向けた動きにプラスとなった訳です。
残る焦点は、「日米京都会議」で指摘された核抑止力の選択肢の保持でした。この点は、核戦略に通暁し、現実を直視するリアリストでもあった若泉敬が胸中にテイク・ノートするのにこだわりはなかったと推察されます。
「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の中で詳述されている若泉敬とキッシンジャーとの秘密交渉の中で生まれた「核の持ち込みと事前協議」を内容とする「核の密約」は、沖縄返還に向けた対米議会・軍部対策としての色合いが強く感じられます。
今日我が国が置かれている情勢(核を保持し、運搬手段としてのミサイルを持ちつつ、隣国を恫喝する国々に囲まれている)を考えると、核抑止力の選択肢のフリーハンドは当然のことです。
このことについては、1969年沖縄返還日米共同声明発表時に、当時の[進歩的文化人(何が進歩的であったのか、今になるとよく理解できませんが)]を代表した英文学者・中野好夫なるものが、雑誌「世界」に発表した「日米共同声明と『沖縄返還』-内外解釈の重大な食い違いについて-」の中で述べた「(共同声明を批判した後)余計な不信も、もちろん避くべきであろうが、決して手放しの善意などどこの国にもない。信ぜず、疑わず、冷酷なまでの自愛利己欲、その発現こそ国際外交なのではなかったのか。」の言辞に首肯せざるを得ないところです(「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」から一部引用)。
一部の人達は今もってこの「核の密約」の存在を根拠に沖縄の核疑惑を云々しますが、弾道ミサイルの特徴(発射から到達までの所要時間が短い。2012年12月の北朝鮮ミサイル発射では北朝鮮の発射場から沖縄・先島諸島付近を通過するのに約11分)を理解していれば、沖縄への核配備は有効な抑止力には成り得ないことがわかるだろうと思います。
批判的立場は仕方ないにしても、2003年7月21日付け「しんぶん赤旗」掲載記事中のサブタイトル「日本への持ち込み体制を維持」程度が妥当でないでしょうか。
「沖縄返還」に絡んだ糸
日米間の繊維問題は、1955年に米国の繊維製品の関税引き下げで日本製綿製品の輸入が激増し、米国内で輸入制限運動が激しくなったことに端を発しますが、1968年米大統領選挙で繊維の輸入規制を公約していたニクソン大統領の登場以後繊維問題は「通商問題」から沖縄返還に絡んだ「政治問題」へと発展していきました。
このあたりの日米の相克は時が経つにつれ激しさを増し、最終的には若泉敬とキッシンジャーとの秘密交渉での決着へと繋がっていくのです。この「もう一つの密約」は若泉敬の本意とするものでなく、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の中で後悔と反省の弁が述べられています。
《喜ばれなかった「沖縄返還」》
日米共同声明で「沖縄返還」が発表された沖縄の反応について、若泉敬は「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の文中の小見出しに「屋良朝苗琉球政府主席の沈痛な表情」と記し沖縄県民の複雑な胸中をシンボライズしました。
また、文中に沖縄返還に関する各新聞の見出しを並べて記載しましたが、当事者中の当事者でありながら、評価に欣喜雀躍(きんきじゃくやく)することもなく、批判に釈明したりすることなく事実を事実としてのみ伝えています。すべては「後世史家の批評にまつのみ」という「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の第18章の標題から若泉敬の思いを忖度(そんたく)できます。
この沖縄県民の反応は、1971年6月の沖縄返還協定調印後に琉球政府が作成した「復帰措置に関する建議書」に現れています。
その中には、沖縄の苦悩そして呻吟から発せられた問題で今もって襟を正して拝読しなければならない部分もありますが、「建議書」が結論として述べているのは、米軍基地の撤去と日米安全保障条約の廃止でした。
まさしく、当時の左傾思潮に基づくプロパガンダそのもので、こと基地の存在になると「悪の根源」と断定し「基地のない平和の島を強く望んでいる」云々や中国の国連加盟など好転する情勢を踏まえた基地の態様の再考(これは、前述した進歩的文化人・中野好夫も首を傾げるような論理構成)など論理的飛躍と思い込みで記述されていました。
「建議書」は、その政治的プロパガンダとしての性格からか日本全土の関心を沖縄の問題に惹きつけるべき求心力を有することはできませんでした。
《時は待ってくれない》
「建議書」にいう「基地のない平和の島」の希求はボヘミアンの論理としてはよく理解できます。しかし、「建議書」が謳った好転した国際情勢とは何であったのでしょうか。
昨今の中国の海洋進出に伴う周辺諸国との軋轢(あつれき)を例にするまでもなく、沖縄が「裸の島」であり続けることができるほど、東シナ海に善意と友愛が満ちあふれていたとはとても言い難いところです。
現に沖縄に対する歴史的な宗主国を主張している中国は、様々なチャンネルを通じて、沖縄の独立、中国への帰属など発信していますが、そのような動きの中に「基地のない平和の島」を支持する(または目指す)文言・発言は見あたりません(これからも無いでしょう)。
何故なら、中国にとって沖縄が中国の勢力圏(領土化または属国化する)に入れば、対米防衛線の「要石」として位置づけられる沖縄に「五星紅旗」の軍事基地をプレゼンスするのは自明の理であるからです。
現状の日本は日米安全保障条約が頼りであることは紛れもない事実です。しかし、これとてもアジアの東縁のホットエリア(朝鮮半島、台湾問題)が片づけば、米国は日本の都合にかまうことなく、条約の論拠を失った日米安全保障条約を解消し、米軍基地の撤収を図るかもしれません(1971年7月のニクソン・ショックを思い出していただきたい)。
そうなれば、徒手空拳(としゅくうけん)でことの成り行きを唖然と見るしかない沖縄・日本は、真空地帯となった太平洋の海原で亡国の奈落の底に沈んでいくでしょう。
若泉敬は、1952年に国連アジア学生会議日本代表として第二次世界大戦後に独立したインドを訪問しましたが、長年にわたる英国の植民地支配によるインド民族の自主独立の気概の欠如を痛感したようです。
冷徹な国際情勢を熟知し、リアリストであった若泉敬は、この「思想的原点」から、まず沖縄復帰を果たし、日本全体で民族としての誇りと気概を醸成し、そして日米安全保障条約を見直すことのできる法制・軍制等の統治機構・機能の確立を図っていこうとしていたのでしょう。
しかし、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」には、歴史の表舞台から去った後の若泉敬の軌跡は描かれていません。その沈黙の帳(とばり)は何を意味していたのでしょうか。
若泉敬は「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の跋(ばつ)文にその赤心の一片を吐露していますが、ここでは、あえてその遺珠には触れません。
残念ながら、「愚者の楽園」に耽溺している我々がその達見達識について行くことができなかった。
若泉敬にとっては、只々、時が無為に過ぎてゆくばかりであったでしょう。
祖国のために殉じた多数の沖縄県民の方々や防人達の御霊は、この国の行く末を憂えて、今も摩文仁の丘で歔欷(きょき)の風となって吹いています。
これが若泉敬を自裁に追い込んだ因由かも知れません。後悔先に立たず。まさに時は待ってくれない。

亡き縁者を慰霊する沖縄婦人たちの傍らで一市井人として祈る若泉敬
(1995年6月:摩文仁の丘にて)
