英訳版 序文原稿「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」について

沖縄返還に決定的役割を果たした若泉敬は、青年期(1952年)に国連アジア学生会議日本代表として第二次世界大戦後に独立したインドを訪問し長年にわたる英国の植民地支配によるインド民族の自主独立の気概の欠如を痛感した。
冷徹な国際情勢を熟知し、リアリストであった若泉敬は、この「思想的原点」から、まず米軍占領下の沖縄の本土復帰を果たして、日本全体で民族としての誇りと気概を醸成しつつ、日米安全保障条約を見直すことのできる法制・軍制等の統治機構・機能の確立を図っていこうとしていた。
しかし、沖縄の本土復帰を果たしたものの、その後の日本は「戦後復興」の名の下に国中が経済至上主義に走り、沖縄の過剰な基地負担を軽視し、また、戦陣に散り戦禍に斃(たお)れた御霊のこの国の行く末を憂える声を顧みることはなかった。
このような「愚者の楽園」と化した日本の現状に失意落胆した若泉敬は、1980年に故郷・福井に居を移し、政界・論壇など中央との繋がりを絶っていった。
そして、徒爾(とじ)の日々を越前の野に在る多くの草莽(そうもう)の士に支えられながらも、沖縄返還に関わった当事者として、沖縄攻防戦で散った二十数万の御霊と実質占領下の状態が続く沖縄県の人々に対する「畏怖と自責の念」はますます強くなり、沖縄での慰霊・遺骨収拾と硫黄島での慰霊鎮魂の「心の旅」を経た後、その「結果責任」を執るべく若泉敬が自裁したのは1996年7月であった。

亡き縁者を慰霊する沖縄婦人たちの
傍らで、一市井人として祈る 若泉敬
(1995年6月:摩文仁の丘にて)
この英訳版 序文原稿「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」は、1994年に若泉敬が「沖縄返還交渉」の内実を明らかにしたその著書「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の英語版「The
Best Course Available:A Personal Account of the Secret U.S.-Japan Okinawa
Reversion Negotiations」(2002年刊行)の序文原稿として、若泉敬が自裁する四ヶ月前に沖縄・与那国島において執筆したもので、その述作するところは沖縄戦に散った人々の御霊に対する慰霊鎮魂として捧げられたが、また一面、若泉敬が激動と混乱が続く世界情勢を達見しつつ、世界平和希求に対する来るべき若い世代の可能性に託す若泉敬の「置き状(遺されたメッセージ)」としての位置付けがされるものである。
本書 英訳版 序文原稿「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」は、若泉敬の謦咳(けいがい)に接し、その薫陶(くんとう)を受け、「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の著作権継承など若泉敬自裁後の後事を託された福井県在住の鰐渕信一氏(福井未来研究所
代表、早稲田大学資源戦略研究所招聘研究員)を発行者とする私家本であるが、その内容が竹帛(ちくはく)に残るべきものにもかかわらず、今まで一部雑誌に掲載されたのみで衆人の知り得るものではなかった。
今般、鰐渕氏から本書 英訳版 序文原稿「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」の提供を受け、若泉敬の遺珠を全文掲載することとなった。
末尾に発行人である鰐渕氏の後書きを付した。また、序文原稿文中の読み仮名の一部は省略した。
英訳版 序文原稿「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」

“領土返還交渉”という権謀の国際政治外交について証言するこの散文的著作への英語版序文として、私は世にも美しい花を供えて戦死者の霊を慰め、そして静かに祈るという話を述べたいと思う。
夏の夜半にたった一度だけ、白色の光を燦然(さんぜん)と放って開花し、短時間に凋(しぼ)んでいく大輪の花がある。
その名を日本語では ″月下美人″という。(学術名、Epiphyllum oxypetalum)。強い芳香を放つその神秘的な短命の花は、月光を受けながらそれ以上に青白く輝き、観る人をしてその名の如く妖精にも似た淡い幻想の世界に誘いこむといわれる。夏の一夜の夢と言うには、余りにも清楚で儚(はかな)い。
月下美人は、メキシコを原産地とするサボテン科の一種で常緑多年草であり、愛好家によって観賞用として鉢植される。中南米の熱帯地方以外に自生しているところは少ないのだが、太平洋に浮かぶ硫黄島には自然群生している。この硫黄島は、東京の南方約一二五○kmの小さな離島(面積約22平方キロ)である。
太平洋戦争の末期、一九四五年二月十六日、強力な海軍、空軍の支援の下に米国海兵隊は硫黄島上陸作戦を敢行した。日本本土侵攻をめざして太平洋を北上する米軍は、この小島を戦略上の重要な拠点と考えていたのであった。本土決戦の第一陣として、これを迎え撃ったのは、栗林忠道陸軍中将に率いられた約二万一千名の硫黄島守備隊だった。
日本軍は、灼熱地獄にも似た地下壕に潜りながら死力を尽くした持久戦を展開した。いまもなお地熱を伴って噴出する硫黄の強烈な匂いが鼻を突く過酷な自然環境下での、日米両軍の戦闘は、最後には筆舌に尽くし難い凄惨な″白兵戦″となった。
米国の首都ワシントンの近郊、ポトマック河畔に近いアーリントン国立墓地の一角に建ち一般には「硫黄島メモリアル」(Iwo Jima Memorial)と呼ばれているのは、米海兵隊員六名が硫黄島で唯一の高地摺鉢山(169m、556Ft)の頂上に星条旗を押し立てた場面を再現した巨大なブロンズの彫刻である。
それは、AP通信の従軍特派員であったジョー・ローゼンソール(Joe Rosenthal)が撮影した写真に基づくもので、その台座に刻まれているごとく″稀有の勇気″(uncommon
valor)を示した英雄的な海兵隊員の姿を象徴する有名な記念碑である。それを見上げるアメリカ人の目は誇りに輝いている。
硫黄島には、数知れない英雄たちが人に知られることもなく眠っている。全員玉砕に近かった日本軍の英霊は一万九九〇〇名(なお戦傷者と生還者は僅か一〇三九名)、米軍の英霊は六八二一名(戦傷者は二万一八六五名)にものぼった。戦死した日本兵士のうち約一万三千名の遺骨は、いまだに島に埋もれたままになっている。
硫黄島に引続く次の大規模な戦闘が行われたのは、同年四月一日から開始された沖縄本島への米軍侵攻だった。
私は、敗戦後の米占領時代からその沖縄の地を何度も訪問しているが、二年前の一九九四年五月十五日に本書を日本語で出版して以来四度、沖縄を訪れた。それは、運命のなせる業とも言うべきか、沖縄返還の日米交渉に深く関わることとなってしまった私にとって、ささやかながらも真摯な慰霊のための″心の旅″であった。
「生者が死者を忘れることは許されない」と本書の中で書き、また本書の公刊それ自体を、国命を報じそれぞれの大義を信じて散華(さんげ)した日米双方二十数万柱のすべての英霊の冥福を祈念して彼等に捧げた私にとって、沖縄戦に散った人々の御霊に対し安らかに永久(とわ)に眠り給え(rest
in eternal Peace)と現地において祈りかつ慰めることは私の″神聖な義務”である。
申すまでもなく、この度公刊される英語版の本書もこの私の義務と信条に従って、慰霊鎮魂のために捧げられる。
この沖縄への旅を続けるなかで私は、同様の義務を自らに課して洞窟(地下壕)の奥深い暗闇の中で蝋燭(ろうそく)の小さな灯(ともしび)を頼りに黙々と自らの危険を顧みずに縦数メートルの瓦礫を少しづつ掘り返して遺骨を探し出し、本職(自営業)を持ちながらも永年に亘り慰霊の営みを続けている一人の高徳の士に巡り遇うことが出来た。
この方は、家族を郷里のこの地の戦闘で喪いその遺骨の確認はできないという他の多くのこの地の人々と同じ悲痛の体験の持主であり、昨年と今年、私は一日ずつこの方と御一緒に″聖なる作業″を手伝わさせていただいた。
一心不乱にこの作業を行っている時に、以前から沖縄と同じように私の心中に深く重くのしかかっていた「硫黄島」のことが生々しい現実性を帯びて甦り、そこに眠る英霊が私の祈りを待っているように切実に感ぜられたのである。
沖縄戦の直前に展開された硫黄島戦。この戦闘における日本兵士の勇猛果敢な戦いぶりに慄然とした米軍は、戦略戦術上可能な限りの巨大な戦力を次の沖縄攻略に投入した。それは世界最強の米軍の最も志気高揚した時期の戦いであったともいえよう。
この二つの戦場における戦闘の苛烈さを詳しく述べることは私の本意ではない。そのような戦いに散った両国の人々の、その中には多くの若い青年たちも含まれていたが、生きていれば豊かで実り多いものになるべき多様な可能性を秘めた彼らの人生が、開花を待たずに道半ばにして無残に断たれてしまったことを私たちは決して忘れてはならない。
彼等の断切の後に幸運にも生き残っている者の義務は、彼らの霊を衷心から弔うと共に、国家の命令に従った行為だったとはいえ彼らの殉じた志と大義を高い次元で受け留め、現世をより良きものとして次の世代に継承し発展させることである、と私は信じている。
沖縄でその決意を新たにした私は、今年の一月、長年の願いでありながら渡航手段が至難で延引していた硫黄島訪問を漸く実現した。

蒼い空と海に囲まれたその硫黄島は、私の眼には、悲しくも虚(むな)しい″不毛の孤児(barren orphanhood)″であった。米海・空軍の激烈極まる艦砲射撃と爆撃によって変形してしまったといわれるほどのこの小さい火山島は、遺骨収拾を殆ど不可能にしている。それは、私の直感的印象では、いわば
″太平洋に浮かぶ一大墓標″ であった。
そして、もしもそうだとすれば、地熱が高いため草木も満足に生育しないその地に数ヶ所不思議にも自然群生している冒頭に紹介した月下美人の花は、この墓標への永遠の
″供花″ であるように感じられた。
私に出来ることは、いくつかある慰霊碑に詣でると共に、硫黄島の南海岸で太平洋を見渡す場所に建っている高さ120センチ、幅1メートル、厚さ12センチの御影石の碑に額(ぬか)ずき、静かに祈り続けるだけであった。
この小さなモニュメントの片方には英語で、反対の面には日本語で「REUNION OF HONOR」と書いてある。そして、日英両文で次の趣旨の文章が刻んである。
「硫黄島戦闘四十周年に当たり、曾(か)っての日米軍人は本日茲(ここ)に、平和と友好の裡(うち)に同じ砂浜の上に再会す。我々同志は死生を越えて、勇気と名誉とを以て戦ったことを銘記すると共に、硫黄島での我々の犠牲を常に心に留め、且つ決して之を繰り返すことのないよう祈る次第である。
一九八五年(昭和六十年)二月十九日
米国海兵隊第三、第四、第五師団協会(米側)
硫黄島協会(日本側)」
この記念碑の除幕式が日米両国の元軍人や家族、遺族の参列の下に行われた時、目撃し体験したことを、硫黄島戦に参加した祖父に連れられてきた高校一年生(16歳)のマイケル・ジャコビーはドナルド・レーガン米大統領(当時)宛の手紙に書いた。
同時にこの手紙は、その年の暮れに国際ロータリー・クラブが全世界の青少年を対象として行った「平和への手紙コンテスト」に応募した作品であり、約四万五千点の中から選ばれて最優秀の国際大賞を受けている。
マイケルは、除幕式の模様に触れた後に、次のように書いた。
「大統領。私はあの現場で、そのあと何が起こったかをぜひともあなたに見ていただきたかったと思います。両国兵士の未亡人や娘たちは互いに近寄って抱き合い、身につけているスカーフや宝石などに思いのたけを託して交換しはじめました。男同士も近づき、最初はやや躊躇(ためら)いがちに握手していましたが、やがてがっちり抱き合うと泣き出してしまったのです。
かっての、この戦場での記念としていた品を″敵″に返している人もいました。ふと気がつくと、誰かが私の頭の上に帽子をのせてくれました。かっての、日本軍人です。彼は笑顔を見せながら自己紹介し、彼が被(かぶ)っていたという日本軍の帽子を私にくれるというのです。祖父もそばに来て彼と話しはじめました。大人二人は若い私がこの場に居合わせて、この体験をしっかりと見聞したことを大変喜んでいるようでした。
(中略)
四十年前、二人はお互いに殺し合おうとしていたのです。いま私たちがいるこの場所は、四十年前に爆弾や銃弾、火炎手榴弾が飛び交い死と憎しみに満ちていたはずです。それがいま、わずか四十年でどうしてこれほど変化したのでしょうか。
祖父と日本兵の様子を見ながら、私は誰も知らない何かを知ることができたような気がしました。どんなに憎み合い相手を殺そうとして戦った敵同士でも友人となり仲間となることができるという事実を、この米国人と日本人の二人によって、全世界の人々に向かって知らせてもらいたいとさえ思いました。二人は手を携え、平和の使節として世界を廻り、その体験を人々に話しかけてもらうことができたらと思いをめぐらした次第です。
(中略)
私は祖国を愛しており、祖国を守るために必要があれば戦うつもりでいます。しかし私自身の孫がいつか敵の孫と友情をもって抱き合える日があるかもしれないと思うと、敵を殺していいものかどうか心乱れるでしょう。」
そして最後にマイケルは、「私は硫黄島で感得したことを、できるだけ多くの人々に伝えるのが私の義務だと思っています。そこで、レーガン大統領、最初にお伝えする人として貴方以上に重要な人は、思いつきません」と結んだのであった。
私は、マイケルの瑞々(みずみず)しい感性(感受性)と品位ある知性に敬意を表したいと思う。そしてこのような有為の若者が一人でも多く育ち、やがて世界の国々の指導的立場に立ってくれることを望んで止まない。
人間の感性は、理性や英知が発揮されるための前提をなす。マイケルの手紙に示された素直な人間的感性は、時代や場所を超えたものである。だからこそ、人々の琴線に触れるものがあり、国際ロータリー・クラブでもこの手紙を最優秀作品に選んだのであろう。
私の郷里福井県には、近代日本の黎明期に生きた 橘 曙覧(一八一二~六八年)という高潔で清貧に甘んじた無名の詩人がいた。彼は世俗的な名利を追うことが人生の眞の価値や幸福に結びつかないことを知っていた学者でもあった。
一九九四年に国賓として訪米した今上天皇皇后両陛下を歓迎するホワイトハウスでの公式スピーチで、ビル・クリントン大統領は、「たのしみは朝おきいでて昨日まで無かりし花の咲ける見る時」という百年以上も前に詠まれた彼の歌を引用した。
想うに、生活は貧しくても誠実に生きる人にとっては、清々しい夏の朝、吾が陋屋(ろうおく)の小庭に新たに見つけた一輪の可憐な花に己の生の新たな意欲と悦びを覚えることもあろう。
戦場の片隅に楚々として咲く名も知れぬ野の花を眺め、死生線上の勇者の心がふと和(なご)み潤うこともあるだろう。
橘の一首に盛られた詩心は、世界のすぐれた詩が皆そうであるがごとく、麗しい人間的感性への深い共感を喚び興こす。その感性と想像力の上に新しい眼に見えぬ文化創造性の花が咲く。
その感性や想像力を活(い)かす道(可能性)さえ閉ざされてしまった人々。沖縄にはそのような人々が判明しているだけでも、日本、米国、南北朝鮮、台湾出身者等の合計、二十三万四千数百人いる。
彼らの氏名は、一九九五年六月二十三日の沖縄戦終結五十周年に当たって除幕された久遠(くおん)の墓標、即ち沖縄県民が自ら発願(ほつがん)し、永久の慰霊鎮魂を祈念して全てを企画作製した「平和の礎」という広大な百十四基にも及ぶ屏風状の刻銘碑に刻み込まれている。
私たちは、自らの最も尊いものを公のために捧げて倒れた人々の名誉を讃えると共に、その人々が夢み、抱いたであろう彼らの志や理想、希望と情熱は、彼らの人間としての悩みや苦しみ、絶望と痛みと共に、私たち自身に胸中に刻み込み引き継いで行かなければならない。彼らが再び生き還れない以上、彼らの分も含めて、現在そして将来、私たちは何をすべきなのか、何をなし得るのかを考えるべきであろう。
私がいま認(したた)めているこの拙著英語版への序文で本書の主題と関連して、私はたまたま例示として、硫黄島と沖縄を採り上げた。しかしながら、言うまでもなく、このような悲劇は全世界で枚挙にいとまがないほど繰り広げられてきた。
「世界と平和」と言う人類の原罪的命題に関わる不可避的課題としての英霊の鎮魂、そして生き残った者とその後継世代に課せられた義務と責任について考えよう。
これが、心ある読者に対し一貫して私がこの序文を通して問いかけ訴えていることなのである。そして恐らくこのことは、地球大の広がりのなかで時間を越えて人間すべてに妥当する普遍的・根源的な課題だと言えるのではないだろうか。
沖縄戦に破れた日本軍の組織的抵抗が終わって爾来(じらい)丁度半世紀に当たる一九九五年六月二十三日の「慰霊の日」、沖縄本島の南部戦跡では、沖縄県民多数に加え、日本国首相、立法・司法各界最高責任者はもとより、米国駐日大使や沖縄で戦った米退役軍人等の各国関係者多数も特別に参列して「沖縄全戦没者追悼式」が挙行された。
その地に建立された「平和の礎(いしじ)」を除幕すると共に、沖縄は自らの経験を踏まえての、自らの天与の使命として恒久平和の発信地たらんと宣言した。
このオキナワ・アッピールは、その意義深い式典の後方において一人の日本国民として参列し祈りを捧げていた私をして、「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」と宣言した国連ユネスコ憲章の前文を鮮明に想起させ、改めて次に述べるような根本問題を考究させることとなった。
幕を閉じようとしている二十世紀は血腥(ちなまぐさ)い革命と戦争に彩られた暗い不幸な時代だったと言えよう。
同時に、近来顕著に見られる注目すべき傾向は、科学・技術の驚嘆すべき発達がもたらした情報伝達、通信、交通、運輸手段等の飛躍的開発によって、われわれの住む地球は心理的・物理的により小さな存在となったことであり、宇宙を飛行中の人間が天体に浮かぶこの小さな惑星-宇宙船地球号-を肉眼で眺めてそのことを実感できるようになった。
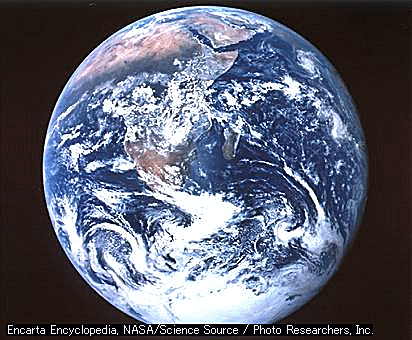
ヒト、モノ、カネなどが情報の洪水の中で自由かつ迅速に動き廻るようになった″グローバル・ビレッジ″では、人類は運命共同体としての自覚を高めてその生き残りを考えなければならないと言われている。恐らくその通りであろう。
にもかかわらず、現状はどうか。主権は最高にして、独立と安全保障、領土の保全は絶対なりと古典的に定義されたいわゆる主権国家が大小合わせて百八十にも及び、それら主権国家の対等平等の原則の上に成り立つ国際社会の基本構造は変わっていない。
予見し得る将来、主権に基づく民族国家が発展的に解消され世界連邦や世界国家が成立するような展望を持つことはまず私には考えられない。
従って、差し当たってわれわれは、なかんずく諸国家とその為政者たちは、せめて国際連合創設の原点に立ち還り、国連を設立した決意を厳しく再確認し、今日まで史上で無数に繰り返されてきた歴史の愚行に終止符を打ち、戦争を無くさなければならない。
そのことは、いまや正気の物事を根源的に考えることのできる人間にとって自明の至上命令とも言うべきものとなっている。
だが果たして、そのことは実現可能なのであろうか。論ずることは易いが、いざとなると誰も楽観的な解答を用意しているようには見受けられない。
私がいまさら強調するまでもなく、求められているのは宇宙船地球号を構築する哲学と原理であり、それに基づき明確な意思、聡明な英知、不退転の勇気を以って戦争放棄に向かって全世界が連帯し行動することである。
さもなければ、戦争手段が核兵器を含めてその極限近くにまで開発されてしまい、″ダモクレスの剣″の下で辛うじて生きている怖るべき状況下においては、戦争が人類を無くすることになりかねないからである。
残された時間は余り多くないかも知れない。然しながら無限に愚行を繰り返す人間の本性をそのことに必要なレベルまで、限られた時間内に急速に画期的に前進させることは果たして出来るのであろうか。
前述の死活的課題に加えて、われわれは自らの住むこの惑星上に現在さまざまの巨大な諸問題が全人類に挑戦をいどんできているのを見る。
地球が支え切れないほどの人口の爆発的増加と飢餓の蔓延、貧富の懸隔(けんかく)の拡大と南北問題の矛盾対立の過激化、加速する都市化現象とスラム化、地球の生態系を根本から脅かすような自然や環境の組織的で大規模な汚染や破壊、エネルギーと資源の浪費・涸渇とその争奪戦、文盲退治と教育の普及向上、これらはすべて二十一世紀を通じての不可避の人類の巨大な課題であろう。
宗教・人種・部族・言語そして領土問題等の諸要因をしばしば複合して起る対立抗争の過激化は悪循環を呼び、その背景にある宗教や文化の根深い歴史的対立をからめて、地域紛争の解決を至難なものにしている。
加えて、難民の激増、テロリズム、脅迫犯罪、麻薬、難治疾病等々、数え上げればきりがなく途中で気が遠くなるような想いに駆られてしまうのは私だけではないだろう。
しかし、ある意味では、叙上(じょじょう)のいずれに比べてもより本質的・根源的な次元において深刻なのは、人間の実存に関わる哲学的問題かも知れない。
いま地上では、神は死に、伝統や道徳は衰退し、家族は崩壊に瀕し、金銭物質の欲望追求を至上としながら愚者の楽園に住む人々、彼らの魂は病んでいる、という指摘もある。
もしもそれらが的外れでないとしたならば、古来の賢者には、それを癒し心の平安を回復する捷径(しょうけい)は、貪欲、傲慢、猜疑心の虜囚になりがちの人間の、それをもたらす″自己中心性″を統禦することであると教える人もいる。
そして、感謝と愛は、その最良の特効薬であるだろうという。私はそれに共感を覚える。そこで、喧嘩ではなくて静謐(せいひつ)のなかで、まず、感謝と愛を籠めた敬虔な祈りを捧げることから始めてみようではないか、と私は提唱したいと思う次第である。
ここで私は、再び若い世代の人々への熱い期待を表明したいと思う。
私は、特に二十一世紀において主導的役割を担う世界の有為の人々に一人でも多くこの英語版を読んでいただきたいと願っている。この著作とそこに流れる私の志が彼らの魂に点火し得るかどうか、私には解らないが、その可能性を持っていることを信じたいと思う。
無知、偏見、そして差別と速やかに決別し、″オキナワ・アッピール″が本気で訴えたように多様性への理解と寛容・慈悲に基づく「対話」を実らせ、硫黄島で米少年が感動を以って確認したあの「和解」を地球大で実現することが出来るならば、国境を越え、グローバルな試練と挑戦にめげずにたくましく生きる若い世代の人々の間に芽生える相互の友情、信頼、そして連帯は不動のものとなり得るであろう。
その実現をひたすら切望する私は、そのため少しでも役立ちたいと願ってこの英語版を公刊するものである。
伸びゆく若い世代がこのような問題意識、価値観、行動様式のコペルニクス的精神革命に成功するならば、人間普遍の感性、理性、品性、英知を活き活きと蘇生させ、先に述べてきた悲観論的な現実と展望を超克し、文化創造の大輪の花を開かせることが可能となり得よう。
そのことは、文化や芸術が光輝き、人間の志や魂が躍動する世紀の到来を多分に意味するかもしれない。
戦争の若き悲劇的英雄たちが生あらば共有したであろう、このロマンと希望、夢と理想、の未来図の礎石を次の若い世代にきちんと引き継ぐために、われわれは眞剣に考えて明日のために最善の努力を捧げようではないか、と提唱したいと思う。
私は信ずる、そのことは、即ち今日すべての指導者に課せられた ″高貴な義務″である、と。
ここで私は、理想をめざす未来の展望から国際政治の現実に暫時立ち返りたい。
占領下にある沖縄百万の同胞と日本国内の世論の動向、両国の政治情勢を勘案しつつ、数年間に亘(わた)って二人の米大統領を相手にタイミングを測りながら粘り強く交渉し、日米両国が共有する道理と利益を力説強調して説得に努め、遂にその目的を果たした佐藤栄作首相が、一九七二年五月十五日の沖縄祖国復帰記念式典で述べた式辞の次の一節を引用しておきたい。
しかしその前に、一言、太平洋戦争で日本と戦い自国の将兵の血で以て勝ち取った沖縄を、米国にとって軍事的に沖縄が不可欠の重要な役割を果たしていたベトナム戦争の真最中にあって、テーブル上の交渉によって日本に返還するという大局的英断を下した、リチャード・ニクソン米大統領に深い敬意を捧げておかなければ、著しく公正を欠くこととなろう。
「戦争によって失われた領土を、平和のうちに外交交渉で回復したことは史上きわめて希なことであり、わたくしはこれを可能にした日米友好のきずなの強さを痛感するものであります。今後日米両国は太平洋をはさむ先進国家としてともに世界の平和と発展に大きな責任を持つ立場におかれます。」
これは、佐藤氏(首相)の自画自賛ではないだろう。戦争の結果として失った領土を一兵たりとも動かさず終始平和裏の交渉で回復する、ということは確かに歴史上希なことである。
ニクソン大統領も佐藤首相ももとより完全無欠なステーツマンではなかったが、緊張した東西冷戦の最中、しかも米国が本格的に軍事介入していたベトナム戦争が激化しているなかで、この至難に近い大事業を達成したことは、外交の本質的な部分において、両者が政治的英知と強力なリーダーシップを発揮したことを意味する。
ベトナム戦争はもとより冷戦も終熄(しゅうそく)し、二十一世紀を目睫(もくしょう)にしながら、国際社会の現状は既に述べたように決して楽観を許されない。
大小さまぎまな問題を抱え、混迷が深まり、紛争が続発している。そうした中で、領土問題は相変わらず極めて厄介な難題の一つであり、領土の大小、軽重にかかわらず民族感情が根強く絡んでいて、何時爆発し火を吹くかも知れぬ戦争の危険を伴っている。
われわれは残念ながら予見し得る将来、この領土問題の解決をめぐってひどく頭を悩まされ続け、場合によっては全く不釣合の代償を強いられることとなるだろう。
この点で、「沖縄返還」の″成功物語″は、佐藤首相がそのことによってノーベル平和賞を日本人として初めて授与されたことに象徴されるように、古くて新しいこの国際的大難題の平和的かつ理性的な解決に曙光を与えることにはならないだろうか。有意義なモデルまたはエキザンプルとして少しでも役立ち得ないだろうか。私はそうなることを切に願わずにいられない。
次に、佐藤首相が式辞でも指摘したように、沖縄返還後四半世紀を迎えようとする今日、日米両国が基本的かつ永続的な友好親善のなかで相互に協調し対等に協力することは、両国の利益に合致するのみならず、アジア・太平洋のみならず世界全体の安定と平和、発展と繁栄にとっても肝要であろう。
日米の″グローバル・パートナーシップ”を単なるスローガンではなく実効あらしめることは両国の担う責任でもある。
私の尊敬するマイク・マンスフィールド元駐日米大使(元米上院議員)の「日米関係は世界で最も重要な二国間関係である、比類(例外)なく」という有名な定義は依然として説得力を持っている。従って、一時の感情的無思慮やことがらの成行(なりゆき)委せから、時計の針を再び数十年も前に逆戻りさせて、日米友好の絆を断ってしまうような愚挙は許されない。
これこそ、日米両国の英霊たちが死を以って償わされたことである。これこそ、彼らが私たちに「繰り返してはならない」と忠告することなのである。
同時に、この際、私は主として日本人読者を念頭に置いて書いた本書日本語版の「践(はらい)」において、真に対等な日米関係の抜本的再構築の必要を説いたことに注意を喚起しておきたい。
言うまでもなく、いかなる国際間の条約も普遍で永遠ということはあり得ない。個人間の友情と異なる。
敗戦と占領以来米国軍隊がそのまま居座る形で今日までいわば惰性で維持されてきた日米安保条約を中核とする日米友好協力関係を、国際社会の現状と展望のなかで徹底的に再検討し、長期的かつ基本的な両国それぞれの利益と理念に基づいて再定義することは不可避であり、双方にとって望ましくかつ有意義なことであろう。
そして、その作業の大前提として私は、まず日本人が毅然とした自主独立の精神を以って日本の理念と国家利益を普遍的な言葉と気概をもって米国はもとより、アジアと全世界に提示することから始めなければならないと信じている。
本書は、もともと日本語で書き下ろされた。もとより、本書を「歴史の一齣(ひとこま)への私の証言」と位置づけていることからも明らかなように、私は当初から読者を日本人にのみ限定して考えていたわけではない。
願わくば、本書が関係当事国である米国のみならず広く世界の人々の炯眼(けいがん)に触れ、関心ある識者の眞剣な検討と批判の対象にしていただければ、これに勝る喜びはない。
幸いにして、この度本書の英語版が、ジョン・スェンセン=ライト氏、サラ・ファルベイ氏、マヤ・モリオカ・トデスティーニ氏の全面的な御協力を得て完成し、出版されることになった。
英語版では、浩瀚(こうかん)な日本語版の相当な部分が割愛されている。それは、専ら物語(ストーリー)の筋道をより明解にし、話の流れを円滑にするとの配慮によるものであって他意は無い。
また、英語版では出来る限り日本語版に忠実なものにするように努めたつもりであるが、異なった言語体系ゆえに若干のニュアンスの差異が出たり、いささか意訳したような部分が見受けられるかも知れない。
しかし、その点について言えば、意図的に、即ち、修文の意図をもって訳されてそのような結果になっている部分は無い。いずれにしても、日本語版はもとより英語版もすべての文書作成上の責任は著者である私に存する。
とは言え、前述の三氏の献身的な御協力なしにこの英語版の完成は不可能であった。ここにそのことを特筆大書して衷心からの感謝の意を表したい。
またこの著作の英語版の公刊を快諾され、格別の理解と配慮をもって責任ある作業をすすめていただいた出版社(社名および関係当事者の氏名)に対しても、この際篤く御礼を申し述べる次第である。
夜の帳(とばり)に覆われた淡い月光の下で、「月下美人」の供花と敬虔な祈りを了(お)えたわれわれの前途には、太陽の昇る爽やかな朝が必ず訪れる。
そして、新しい一日が始まる。人間の歴史において旭日の輝きは何時でも何処でも希望の光明を象徴してきた。
今あらためて歴史と古典を繙(ひもと)き思慮を重ねている私は、多々述べたこの序文の個人的結語として、普遍的な神の敬示(※世界の主要宗教でいう「神」を全て包括する概念として使いたい。)に基づく正義と慈悲心の下で、人間性の奥深く内在する霊性と品性の陶冶(とうや)の顕現(けんげん)を信じたいのである。
私は先に理想を目指す未来の展望について述べたが、人間の性質が本来的に「善」なることを信じ、後継世代の成長する未来を大局において楽観視することにしたい。そして、生ある限り吾が心中に希望の光明への祈りを絶やさぬことを明言して、この長くなりすぎたかも知れぬ「序文」を結び、ここで私は拙いペンを折る。
そして、静謐(せいひつ)と沈黙の世界に帰る。
蛇足ながら、最後に一言、私事に触れることをお赦(ゆる)し願いたい。
太平洋戦争の敗戦を十五歳の時に郷里福井の草深い山村で迎えた私は、その時受けたあまりに深刻な衝撃波を契機として、吾が志(※「志(こころざし)」の英訳は難しいと思いますが、この「序文」全体を通じてのkey
wordです。)を立てた。
広く世界に目を拓(ひら)こうと希って、まず東京に出て学び、さらに英米両国にも留学し、爾来(じらい)今日まで国際政治の一学徒の途を歩んできた。
ささやかながらも、私の立志は多分に幕末に郷土(越前)が生んだ偉大な志士であり、当時既に世界の大勢を洞察した思想家でもあった 橋本左内(一八三四~五九年)の「啓発録」に点火されてのことであったと思う。
左内は、明治維新の到来を目前にして、若干二十六歳、時の徳川幕府によって反逆者として処刑された。彼こそ、この序文で論述してきた尊い英霊の一人である。
幸か不幸か今日まで馬齢を重ねてしまった私は、吾が ″余命″(※「余生」と区別して「余命」といった。)を、左内と同じ時代に生きた 橘 曙覧(たちばな あけみ)をモデルにして、残念ながら詩歌を詠む能力はないが、彼のように清貧の隠棲(いんせい)に入りたい。
吾が素志を堅持しながら孤高の沈思黙考をめざし、己の心耳を澄ませて生死(しょうじ)を超え魂に喚(よ)びかけてくる静かな祈りの声を聴き、心眼を開いて眞実の世界を観たいと思う。
これが、私の負う歴史への結果責任を自ら執るため私の選んだ途である。
一九九六年三月沖縄県与那国島にて記す(「序文」了)
平成六年(一九九四年)五月、若泉敬先生は「鎮魂献詞」「宣誓」「謝辞」に始まる著書『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文藝春秋)を公刊され、その宣誓において「畏怖と自責の念に苛(さいな)まれつつ私は、自ら進んで天下の法廷の証人台に立ち…」と述べられました。
同年六月二十三日(沖縄慰霊の日)には、沖縄本島摩文仁の国立沖縄戦没者墓苑にて沖縄全戦没者に献本の後、沖縄県民に宛てた歎願状を懐き自裁を覚悟されていました。その歎願状の一節には、「一九六九年日米首脳会談以来歴史に対して負っている私の重い『結果責任』を執り、武士道の精神に則って、国立沖縄戦没者墓苑において自裁します。」と記されていました。
漸く思い留まられた先生は、余命を慰霊巡拝と著書の英訳出版に捧げることを決意され、昭和天皇武蔵野陵、靖国神社などへの参拝や硫黄島での慰霊鎮魂、沖縄での遺骨収拾などに献身的に尽くされました。
そして、一人病魔と闘いながらも、亡くなる年の三月には、日本最西端の与那国島にて本稿、英訳版序文を執筆されました。
平成八年(一九九六年)七月二十七日、福井県鯖江市の自宅、無畏無為(むいむい)庵にて英訳出版に関する最終協議を行い「合意議事録」に署名捺印の後、関係者を見送られました。
その日の早朝には無畏無為庵邸内社において最後のご参拝も終えられ、十四時五十分、その壮絶な一生に幕を閉じられました。
この度、先生の七回忌にあたる日を前に、英訳版の出版が実現いたしました。
その序文にこめられた先生の心と志と魂に触発され、日本語による原稿ならびに偉大な足跡の一端を綴らせて頂きました。
平成十四年六月二十三日
