1 ウクライナの「民族紛争」の背景~「大ロシア主義」の策動
2014年2月の親欧米派によるウクライナの政変に端を発するロシアのクリミア併合の余波は、ウクライナ東部のロシア国境に接するドネツィク州やルハーンシク州などロシア系住民が約40%を占める地域におけるロシア系住民とウクライナ系住民との「民族紛争」を激化させている。
⑴ ロシアとウクライナの「近親憎悪」的関係~「民族紛争」の「構造的要因」
歴史を紐解けば、ウクライナは源流的には帝政ロシアの「発祥の地(キエフ・ルーシ)」であり、 言語としてもウクライナ人とロシア人はともにスラブ系民族としてスラブ語派に属し、ロシア人にとってウクライナとはスラブの「郷愁」を感じさせる「同朋」の地であった。旧ソ連時代もウクライナ共和国はスラブ系共和国としてロシア、ベラルーシとともにその一翼を担うなど、ソ連邦の枢要国として重きをなしていた。
しかし、その内情はロシア人のウクライナ人に対する支配関係を前提にして表見的な「友邦国」として成り立っていたのだ。
ウクライナは9世紀後半にキエフを首都として建国した「キエフ大公国(キエフ・ルーシ)」が1240年代にモンゴルの侵攻で滅亡して以来、その地にウクライナ人の国家を再興出来ず、帝政ロシア・ポーランド・リトアニア・オスマン帝国などの国々により分割統治され、その後帝政ロシアの勢力拡大に伴い帝政ロシア領として収斂されていった。
19世紀初頭には、ウクライナ系知識人による文化運動等民族意識の高揚を図る動きが活発化したが、帝政ロシアはこのような運動を分離主義的性格を有するものとして警戒し、そのウクライナのロシア化政策の中でウクライナ語を「小ロシア方言」と位置づけ、ウクライナ語書物の刊行等を禁止する(1876年)など徹底的な弾圧を行った。
このように、ロシア人とウクライナ人の支配・被支配関係等民族対立における政治的緊張から派生する社会的・身分的な対立が、両者の近親憎悪的関係をますます増幅し、抜き差しならぬ「民族紛争」の引き金となる「構造的要因」として浮かび上がってくる。
⑵ 「民族紛争」に見え隠れする「大ロシア主義」
2014年のロシア及びウクライナ領クリミアの親ロシア派による「クリミア危機」の周到迅速な一連の動き(3月11日ウクライナからのクリミア独立宣言、16日住民投票、17日クリミアのロシア編入決議、18日編入条約締結)を分析すると、その背景に深慮遠謀な「大ロシア主義」の存在が垣間見える。
2000年3月ロシアの第2代大統領に就任したプーチンは「強いロシア」を標榜し、以来今日まで、国家大計として、ロシアの「国章」の双頭の鷲(東ローマ帝国に由来し、帝政ロシアのローマ帝国正統後継を表す。ロシア連邦の発足により「国章」として再度復活した。「双頭」はアジアとヨーロッパに亘る統治権を象徴している。)を具現化した世界に冠たるユーラシア大国の建設を企図している。
プーチン大統領は、旧ソ連時代の国歌のメロディーや赤軍旗を復活させるなどその愛国的姿勢を強めていたが、それは旧ソ連時代の欧州の半ばを占める東欧圏を手中にし、東は中央アジアから極東まで支配していたユーラシア大国の栄光の日々への郷愁ばかりではなく、「大ロシア主義(旧ソ連領・旧帝政ロシア領であった他の共和国領土の一部または全てを取り戻し、とりわけ、グルジア、モルドバ、ウクライナ、バルト三国の単一ロシア国家への併合を目論む)」を掲げるロシアの民族主義者・領土回復主義者の強固な支持を得て進められている。
この「大ロシア主義」はロシア版の「中華思想」の類いであるが、帝政ロシア・旧ソ連時代に対象国の「ロシア化政策」としてロシア人の大量移民、先住居住民族の強制移住、ロシア語の強制(公用語化、ロシア語学校の普及・民族語学校の廃止)、ロシア正教信徒化などの統治政策として行われた。
この「大ロシア主義」のターゲットとなっているのが、旧ソ連邦共和国のうち、ロシアにとって死活的な地域として見なされている
○ 旧帝政ロシア領の国 ~グルジア、モルドバ、リトアニア、ウクライナ
○ ロシア系住民が多い国~ウクライナ17.2%(’01年)、エストニア25.2%(’11年)、ラトビア27.8%(’13年)
で、とりわけ今次「クリミア危機」の発端となったウクライナ・クリミア半島については、そのウクライナ帰属の経緯から「大ロシア主義」者の策動の標的となっていた。
⑶ 歴史に見るクリミア半島の変遷~「民族紛争」の原点
クリミア半島は、古代においては、ヘロドトスの「歴史」にも著述されているように、アジア系遊牧民のキンメリア人・スキタイ人の居住地であったが、周囲に急峻な山渓の存在しないクリミア半島は容易に域外からの他民族の侵入・支配を受け、各種民族の坩堝(るつぼ)の地となっていた。
1238年のモンゴルの侵入により、クリミア半島は南ロシアのモンゴル王朝「キプチャク・ハン」国の支配下に入り、「キプチャク・ハン」国の衰亡後は、オスマン帝国の保護を受けたバプチサライを首都とする「クリミア・ハン」国に統治(1441-1779)されていた。
オスマン帝国と対立関係にあったエカテリーナ2世治下の帝政ロシアは、1767年、1787年の二度にわたる露土戦争勝利でオスマン帝国の属国であった「クリミア・ハン」国を併合した。
以来クリミア半島は帝政ロシアの版図の一角を占めてきた。
ロシア革命後、1921年にクリミア半島は「クリミア自治共和国」としてソビエト連邦の一部を形成していたが、第二次世界大戦末期の1944年に先住居住民族のクリミア・タタール人のドイツ協力を理由に、クリミア・タタール人の中央アジアへの強制移住後、翌年「クリミア自治共和国」は廃止されロシア共和国の州となった。
1954年、フルシチョフ書記長治政下でクリミア州はロシア共和国からウクライナ共和国に移管された。その移管は、ウクライナがロシア皇帝の領土の一部となってから300周年を示す「象徴的意味合い」が理由とされているが、この移管には、フルシチョフ個人の性向(ウクライナに親近感を持っている。)が大きく影響していたと言われている。
18世紀以来、風光明媚で温暖なクリミア半島はロシア人にとって憧れの「ロシアの大地」であったが、その歴史の中に、クリミアがウクライナの領土や属領等になった痕跡は認められない。
このような背景のもと、ソ連崩壊によるウクライナの独立により起きたクリミアのロシアからの分離は、人口の過半を占めるクリミアのロシア系住民やロシア国民に大きな衝撃を与え、1990年代の半ばまでこれらロシア系勢力によるクリミアの独立運動などウクライナ国内での「民族紛争」が激化し、ウクライナ政府も1996年憲法改正である程度の自治権を有する「クリミア自治共和国」の樹立を認めていた。
⑷ ロシアと旧ソ連諸国の微妙な関係
廣瀬陽子 著「旧ソ連地域の紛争-石油・民族・テロをめぐる地政学」(慶應義塾大学出版会)は、ソ連解体後のロシアがかつての「帝国」領域に対する影響力を保持するため、EU・NATOに接近を図る旧ソ連諸国の民族紛争・テロ対策・経済問題・エネルギー問題等に関与し、武力介入、経済制裁、貿易制裁等を繰り返している、と指摘している。
その関与の態様は、モルドバの「ドニエストル紛争」(1991年)、グルジアの「南オセアチア紛争」(2008年)、ウクライナの「クリミア危機」(2014年)など反露的傾向の強い他国の「民族紛争」への強権的介入からグルジア・モルドバ産ワイン輸入禁止(2006年)、ウクライナへの天然ガス供給停止(2006年)、ベラルーシ産乳製品の輸入禁止(2009年)、ウクライナ産チョコレート菓子の輸入禁止(2013年)などの経済・貿易制裁まで多岐にわたり執拗な揺さぶりがかけられている。
このようなロシアのプレッシャーを受けている旧ソ連諸国の現況を見ると、「大ロシア主義」のターゲットとなっている各国に共通の反露傾向が見られる。
圧倒的な軍事力・経済力を有するロシアという巨人の周縁に位置する旧ソ連諸国は、旧ソ連時代の「ロシア化政策」等に警戒心を持っているものの、国内経済や自国の安全保障等からロシアに依存せざる面もあり、微妙な立ち位置を保っている。
⑸ プーチンの危険な「ドミノ理論」~「民族紛争」への介入
2014年の「クリミア危機」に際し、プーチンは「自分はロシアの子供たちを守る母なるロシアに使える役目を負っており、国境の外側にいる子供たちも、守らなければならない。」と述べ、「大ロシア主義」に基づく今回の行動の正当化を図るとともに、反露的傾向の強い周縁諸国(ウクライナ、バルト三国)での「民族紛争」に対する介入についても否定はしなかった。
このプーチンの国外の「ロシア系住民の保護」を名目にしたモルドバに対する軍事的介入(1992年)や今回のクリミア併合のスタイルは、外交的な自衛権である「自国民保護」の論理を侵略の手段としたヒトラー・ナチスによるチェコ・ズデーデン地方併合(1938年)と同様に、正当な理由もない、そして際限のない「ドミノ理論」の範疇であると言ってよい。
このように旧ソ連諸国に対する強権的な拡張主義の動きをとるプーチンの行動は、ロシア民族の遺伝子に深く刻み込まれている民族的特質の成せる業と言ってよい。
ロシアの始祖となる「モスクワ大公国」が一三世紀に都としたモスクワの地は、地勢的にロシア平原の中央部に位置するが、その広大なロシア平原の標高平均は200メートルにも満たず、山系といえば平原西端のカルパティア山脈(2,016メートル)系だけで、外敵の侵入が容易であった。
外敵の侵入を受けても、一朝一夕で領土を蹂躙されないだけの領土の拡大は、揺籃期の「モスクワ大公国」にとって自己生存本能といってもよく、この拡張主義に基づきロシア平原に割拠していた群小公国との併合を繰り返し、ロシア平原の中央部を支配する帝政ロシアへの発展に繋げていった。そして、19世紀末までには東欧をほぼ手中にして懐の深い「緩衝地帯(バッファー・ゾーン)」をロシア平原に設けることができた。
この「緩衝地帯(バッファー・ゾーン)」は、ナポレオンの軍事侵攻(1812年)やヒットラーの電撃作戦(1941年)において、敵主力を広大なロシアの大地に引き込み損耗を図るのに大きく貢献し最終的な勝利を帝政ロシア・ソ連にもたらした。
ロシア人にとって、この歴史的教訓は彼らの血肉となり、ロシアの外縁に「緩衝地帯(バッファー・ゾーン)」を設けることは基本的ドクトリンとして今なお存在しており、ソ連崩壊後の現状がロシア人にとって決して許容されるものではない所以である。
2 世界に蔓延する「民族紛争」
⑴ 「民族紛争」と「民族自決権」
ジョセフ・S・ナイ・JR.他 著「国際紛争-理論と歴史」(有斐閣)は、1989年「冷戦終結」以来今次「クリミア危機」までの25年間に起きた89件の国内紛争(内戦)のほとんどがエスニックまたはその共同体をめぐる「民族紛争」で、そのうち20件は外国の介入をともなう国内紛争であったと指摘している。
そして、世界の中での単一民族国家(nation-state)はユーラシア大陸の東縁に位置する数ヵ国(日本・韓国・北朝鮮)に過ぎないとし、ほとんどの国が民族的に同質とは言い難く、文化・言語・宗教・価値観等民族的差異に基づく「クリミア危機」のような「民族紛争」勃発の可能性に言及している。
このような「民族紛争」の萌芽は、1648年のウェストファリア体制での「他国領土の尊重」・「内政不干渉」等国際法上の基本原則が適用された「領邦国家」の誕生により、人工的な国境線で分断された「民族」が地域によっては少数民族の立場になったり、また複数の民族が一地域で拮抗する形で存在するようになったことに端を発するが、これら民族の自決(帰属先の選択等)については一顧だにされることはなかった。
この「民族の自決」の権利は、1919年「パリ講和会議」での米大統領ウィルソンの提唱により、ベルサイユ条約で少数民族の「自決権」として認められた。
ウィルソンの本来の意図は、欧州で勢威を張るソ連等多民族国家の弱体化やドイツ・ソ連の影響下にあった東欧諸国・バルト三国の独立を支援するものであったが、その後、「民族自決権」は第二次世界大戦後のアジア・アフリカでの植民地独立闘争を支えるイデオロギーとして発展し、国際法上の権利として確立した。(1960年「植民地独立付与宣言」)
⑵ 世界の主な「民族紛争」
「民族自決権」の行使は、多数の植民地が独立した今日の世界ではその一定の役割を終え、新たに一つの国家における先住民・少数民族の権利として捉えられる傾向にあり、これら先住民・少数民族集団による「民族自決」を掲げた「民族紛争」が世界各地で勃発している。
月村太郎著『民族紛争(岩波新書)』は、下図のような「民族紛争」の事例から、進行中の「民族紛争」、再燃の恐れのある「民族紛争」、戦後復興の過程にある多民族国家(イラク・アフガニスタン)や深刻な民族問題を政治的に抑圧している地域(中国・ロシア)での「民族紛争」が世界に蔓延化している状況を挙げ、国際的な問題としての「民族紛争」は決して消滅したわけでも、解決されたわけでもないと指摘している。
世界の主な「民族紛争」
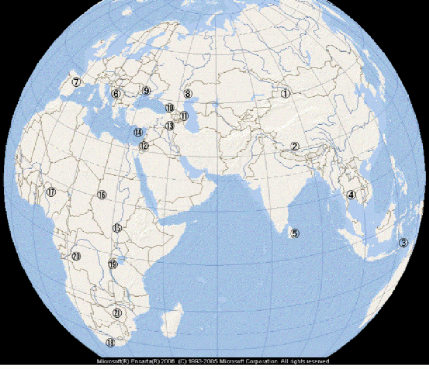
①新疆ウイグル自治区独立運動(1946-) ②チベット独立運動(1959-) ③東ティモール紛争(1975-2002) ④タイ深南部紛争(2004-) ⑤スリランカ内戦(1983-2009) ⑥コソボ紛争(1991-) ⑦バスク独立運動(1959-) ⑧チェチェン紛争(1994-) ⑨モルドバ・ドニエストル紛争(1991-1992) ⑩グルジア紛争(2008) ⑪ナゴルノカラバフ紛争(1988-1994) ⑫パレスチナ紛争(1948-) ⑬トルコ・クルド武装闘争(1923-) ⑭キプロス内戦(1974-) ⑮スーダン内戦(1983-2005) ⑯ダルフール紛争(2003-) ⑰ナイジェリア紛争(2009-) ⑱南アフリカ・人種間対立(1950-) ⑲ルワンダ・ブルンジ内戦(1994-) ⑳コンゴ紛争(1997-) 21ジンバブエ騒乱(2008-)
⑶ 何故「民族紛争」は発生するのか?
「民族紛争」は、文化・言語・宗教・歴史・価値観等の民族的差異や複数民族間の支配・被支配関係等の政治的・経済的緊張関係から派生する社会的・身分的な民族間の対立などが引き金となることが多く、その態様はその民族のおかれた「構造的要因」により千差万別・多種多様と言ってよい。
月村は、その著『民族紛争』において、これら「民族紛争」を惹起する「構造的要因」のキー・ワードとして、「民族の居住分布」「民主化」「歴史」「宗教」等を挙げている。
○「民族の居住分布」~複数民族が地域に混在し、その居住密度が比較的類似している場合、その地域の争奪を巡り「民族紛争」が発生しやすい。
○「民主化」~民族間関係に緊張がある場合、有権者は民族的に同じく帰属する個人・政党に投票する。そのため、選挙結果はその民族構成を反映した投票結果の「国勢調査化」に陥る。このため、選挙前から敗北が決定的な少数民族派は、その選挙の正当性を否定しボイコットする可能性がある。また、民族間関係が悪化すると少数民族派は、その居住地領有の正当化のための手続きとして住民投票を行うこともある。
○「歴史」~民族の盛衰の繰り返しのなかで、特定地域を支配する民族が変遷してきた場合、各民族がかつての領有を根拠に対立し「歴史主義」に固執した「民族紛争」に繋がる可能性がある。
○「宗教」~宗教は、その教義・教理上からその宗教だけが真理であるという「宗教的排他主義」に陥りやすい。宗教が公的信仰として国家や民族と結合すると、異教徒民族間の宗教的対立をともなう暴力的な「民族紛争」に発展しやすい。
○「言語」~言語はその民族のアイデンティティ(統一性・主体性)の表象であり、支配・被支配関係にある民族間で、統治民族による言語の強制(公用語化等)が被支配民族の反発を生み「民族紛争」として激化する可能性がある。
⑷ 「民族紛争」の激化・拡大~安全保障のジレンマ(Security Dilemma)
月村はまた、「民族紛争」の特性として、「民族紛争」の激化(暴動、内戦、大量殺戮、民族浄化等)・拡大(隣国への波及、隣国の介入)と長期化の傾向を挙げている。
「民族紛争」の激化は、対立する民族間の相互不信が相手への敵意や恐怖感を醸成し、双方が欲していないにもかかわらず紛争発生の危険性を高める、いわゆる「安全保障のジレンマ(Security
Dilemma)」に陥ることにより増幅されると言われている。
そして「民族紛争」の激化が紛争地域の拡大に繋がり、時として隣国への波及を生み、隣国の政治情勢・社会情勢等に影響を及ぼす。
影響を受けた隣国が紛争の鎮静化等防衛的動機または自国の影響力拡大を企図した侵略的動機により「紛争地域」に介入した場合、その「民族紛争」の解決はより一層困難になり、長期化の様相を呈してくることになる。
⑸ アフリカの「飢餓」を生む「民族紛争」
前記「世界の主な『民族紛争』」図中においてアフリカ大陸の「民族紛争」が際立っている。これは、アフリカには800以上の部族が地域に入り込んで混在しており、加えて植民地時代の列強による直線的な国境設定による部族の分断や部族間対立をあおる統治政策なども「民族紛争」の遠因となっている。
そして、アフリカでは今もって植民地時代のプランテーション農業(先進諸国の嗜好品・必需品となる商品作物を大規模に単一的に栽培する農業=コーヒー、カカオ、ゴム、コショウ、サイザル麻などの兌換作物栽培)の名残などもあり、食糧自給に繋がる作物栽培などの近代的な農業基盤の整備は脆弱と言ってよい。このため、「民族紛争」当事国の政治的・経済的騒乱状態による農民の難民化(耕作地放棄)や国家的機能の麻痺、市場の混乱等により食糧の配給など受けられない多くの国民が飢餓状態に陥ることとなる。
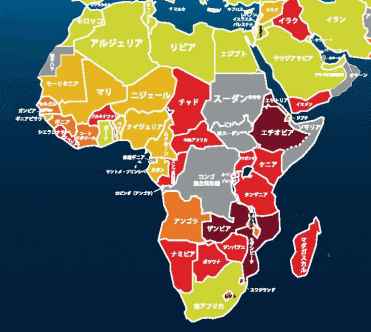
図は国連WFPの「世界の飢餓状況2013」(アフリカ部分を引用)であるが、アフリカの「民族紛争地域」とその「飢餓地域」が符合するのは偶然の一致でなく、アフリカにおける「民族紛争」が多くの地域で飢餓難民を生み、事態を悪化させていることを示している。
※ 飢餓率:■15-24%、■25%-34%、■35%-、■統計不能
⑹ 解決の帳(とばり)の見えない「民族紛争」
「民族紛争」が文化・言語・宗教・歴史・価値観等の民族的差異よる「構造的要因」に影響を受け、これら「構造的要因」が民族の遺伝子に深く刻み込まれている民族としてのアイデンティティーの表象として存在している事実は、「民族紛争」の根深さと解決の「困難性」を如実に物語っている。
そして、世界は1648年のウェストファリア体制から始まった「国家」という政治的擬制により秩序化され、今もって、国際政治学者 若泉敬が英語版「他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス」序文で長嘆息したように、世界は「独立と安全保障、領土の保全は絶対なりと古典的に定義されたいわゆる主権国家が大小合わせて百八十にも及び、それら主権国家の対等平等の原則の上に成り立つ国際社会の基本構造は変わっていない。」
このような「古典的」世界観では「民族紛争」を解決する方途が見えないのも間違いなく、世界は「民族紛争」という歴史的課題を突きつけられているといっても過言でない。
月村太郎著『民族紛争』は新書版ではあるが、「民族紛争」に特化した構成で総覧的に「民族紛争」を理解する上で十分な内容となっている。
民族的にほぼ同質(98.5%:「国際紛争-理論と歴史」から引用)で、その居住地域が「国家」の領域とマッチングしている我々日本人にとって、その希有(けう)な偶然性に感佩(かんぱい)しつつ、本書『民族紛争』を通じて世界に蔓延する「民族紛争」の現実を直視することは、「愚者の楽園」に安穏としている我々の「ガラパゴス化」を防ぐ一助ともなるだろう。
