「国家理念」を喪失した中国
社会主義国・中国の現実~失われた「プロレタリアートの夢」
2014年7月25日、北京大学・中国社会科学センターは「中国家庭追跡調査(China Family Panel Studies:以下略称CFPS)」を発表した。
「CFPS」リポートはその中で、中国社会における富裕層の「富の偏在」について、
「中国の一般的世帯の保有資産分野では、全国の世帯平均的資産(2012年)は約43.9万 元となっているが、この個人保有資産約118.4兆元の中身を見ると、中国における世帯間の資産の不平等は急速に高まっている。 2012年調査のジニ係数(世帯間の所得格差の指標)は0.73に達していて、富裕層のトップ1%の世帯が全国の個人資産の三分の一以上を占有しており、低所得者層にあたる25%の世帯が保有する資産総額は全国の個人資産の1%ぐらいに過ぎない。中国の個人保有資産の不平等は収入の不平等より明らかに顕著である。」
と指摘した。
このような状況は、中国が「人民搾取の不平等社会」として唾棄するアメリカにおける所得格差と対比(※ アメリカの高額所得者層の上位1%が総世帯所得に占める割合は19.3%:UCLAバークレー校、E・サエス教授による2012年「内国歳入庁」データの分析結果)しても、中国の個人資産の三分の一以上を占有している中国・富裕層の「富の偏在」はアメリカの1.7倍で、「人民搾取の不平等社会」の権化たるアメリカを大きく凌駕した、中国の格差社会の実態を端的に示した。
また「労働分配率(生産により得た付加価値に占める賃金の比率:雇用者所得/名目GDP)」を見ると、アメリカの「労働分配率」はこの20年間概ね55~60%のゾーンで安定しているが、中国の最近20年間の「労働分配率」は1992年の50%弱から2012年約45%と長期低落化の傾向を示している。(「富士通総研」、「三菱UFJ経済調査室・香港」資料参照)
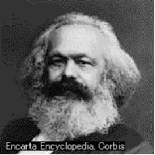
マルクス経済学の基本概念である「剰余価値論」から言えば、「労働搾取」の物差しとなる「労働分配率」の数値は、労働者階級が主役であるとされる社会主義国・中国においては、限りなく上昇志向の性向を有しなければいけないが、現実は「人民搾取の不平等社会」と揶揄されるアメリカの方が「労働の搾取」を強めている中国よりも「プロレタリアートの夢」に近づいていると言ってもいいかも知れない。
これら「労働の搾取」により蓄積した中国の富裕層の莫大な富に対しては、税制による所得の再分配が機能していない(相続税が存在しない)反面、賃金所得には最高45%の累進課税が適用されており、中国におけるこれら富裕層の「有産階級(ブルジョアジー)」と賃金労働者などの「無産階級(プロレタリアート)」の「富の乖離」はますます拡大している。
⑴ 体制維持のためのツールと化した「共産主義」
中国の「富裕層」とは、1949年の中国共産革命後、国家権力を掌握した中国共産党の高級幹部、国有企業経営幹部、政府出資による民営企業幹部並びにこれら特権階級の家族・縁戚等係累関係にある一群の存在を言う。
このような共産主義制度化における「新しい階級」は、ミロバン・ジラス著「新しい階級ー共産主義制度の分析(1957年)」でその存在をいち早く指摘されていたが、共産主義国家における党官僚が「階級なき社会における新しい支配階級」として君臨している事実は、今日の世界では「周知の事実」として誰も否定し得ない。
2014年12月5日開催の中国共産党中央政治局会議は、党中央規律検査委員会の「周永康の重大規律違反事件の審査報告」を審議し、周永康・前党中央政法委員会書記(前党中央政治局常務委員)の反党的政治規律違反・職権乱用による収賄・不正蓄財などを認め、その党籍剥奪と司法機関による刑事訴追を決定した。
しかし、中国共産党中央規律検査委員会が指摘する、職権乱用による巨額収賄・親族等のビジネスへの便宜供与や巨額に上る不正蓄財は中国の「富裕層」に共通する形態であるにもかかわらず、その中で周永康が党中央規律検査委員会のターゲットとなったのは、薄熙来(元重慶市党書記)と同様に中国共産党の権力中枢からスピンアウトされた者の哀れな末路と言ってよく、党中央指導部を頂点とする中国の「富裕層」のピラミッド構造に変わりはない。
かつてマルクスとエンゲルスは「共産党宣言」の中で、封建的階級やブルジョアジーなどの「人間的俗性」を徹底的に剔(えぐ)りだし、彼らに対する「プロレタリアートの前衛たる」共産主義者の階級的優位性(無謬な、殆ど神格化された存在)を描き出したが、権力を掌中にしたあとの共産主義者の「人間的俗性」については一顧だにすることはなかった。
中国の共産革命後六十余年を経て、中国共産党の高級幹部らは、本来邁進すべき「高次な共産主義社会の実現」を放棄し、その後の周恩来の「四つの現代化(農業、工業、国防、科学技術」、鄧小平の「改革・開放政策」、朱鎔基の「三大改革(国有企業、金融制度、行政機構)」など社会主義市場経済への一連の動きの中で「経済発展を第一の目標に(2002年11月『第16回党大会』江沢民総書記政治報告での発言)」して富の蓄積にいそしみ、今や、「共産党宣言」的表現で言えば、富と権力を掌中にした中国の「富裕層」は中国の至る処でブルジョアジーという「幽霊」となってさまよい歩いているのだ。
そして、この「幽霊」たちは、彼らの支配体制を維持するとともに、その権力・権益拡大のためのツールとして中国共産党の一党独裁制を堅持し、中国共産党・政府批判など反革命的(?)な策動に対する徹底的な弾圧を行っている。
2015年7月1日 、第12回全国人民代表大会常務委員会は第15回会合で新しい「国家安全法」を協議し採択したが、同法第1条で「国家の安全(※国家権力を第一義とする国家の重大利益を指す。第2条に規定)、人民民主独裁政権と中国の特色ある社会主義制度の防衛」を規定し、同法第4、15条で、そのための「中国共産党の領導の堅持」を謳っている。
加えて同法第15条では、「国家への裏切り、国家の分裂、反乱煽動、転覆或いは人民民主独裁政権の行為の転覆煽動」など反革命行為に対する懲罰を定めている。
このような条項を内容とする「国家安全法」の制定の背景には、「我が国の経済社会は深刻な変化が発生して、社会矛盾が多発しますます増大している。(2015年1月23日開催、中共中央政治局「国家安全戦略会議」冒頭での習総書記発言)」という中国首脳部の危機感があった。
⑵「国家ナショナリズム」への誘惑~「中華民族偉大復興」の道
中国の支配者層における「富の偏在」は、鄧小平の「改革開放路線」に依拠する「先富論」の提唱後ますます顕在化した。加えて経済的な地域間格差の拡大、党幹部・高級官僚の不法利得・贈収賄などの腐敗体質の蔓延化などにより、中国国民の不満は鬱積し、全国的な「群体性事件(集団抗議活動)」の高まりの誘因となって、中国政府の統治機能を脅かす社会問題へと発展していった。
中国共産党は既に中国国民の信頼を失墜しており、党規約に規定する「マルクス・レーニン主義」、「毛沢東思想」、「鄧小平理論」等イデオロギーの欺瞞性を中国国民は熟知している。
このような状況の中で、中国共産党指導部は国民の不満のエネルギーを他に転化するための新たな国家理念の構築を求められた。
その逼迫性のなかから生まれたのが、1993年江沢民の国家主席就任以来展開された「勿忘国恥(国の受けた恥辱を忘れるな)」をスローガンとした「愛国主義」運動に象徴される「国家ナショナリズム」への傾倒である。
以後、この「国家ナショナリズム」は、2002年11月開催の「第16回党大会」で採択された江沢民「三つの代表」論で「中華民族の偉大な復興」の文言として「政治的認知」を得、さらに2012年11月開催の「第18回党大会」において、「中華民族の偉大な復興」を核心とする「『中国の夢』の実現」が統治理念となった。
中国共産党指導部を魅了するこのような「ナショナリズム」は、概念としては、ネーション(民族、国家)という中心核に向けた民族意識の昇華・純化作用で、その作用の過程の中で厖大な集束エネルギーを創出する。
歴史的に見れば、そのような厖大なエネルギーは、19世紀における西欧での近代国家の形成、第2次世界大戦後のアジア・アフリカにおける植民地の独立や1991年のソ連崩壊(冷戦の終結)後の社会主義国の完全独立などに大きく影響を与えた。
また反面、その「昇華・純化」の反作用としての「ナショナリズム」固有の「排他性」や「偏狭性」が国家という「政治的擬制」と深く結びつく(「国家ナショナリズム」という融合体になる)と、負の側面として、政治的支配者が国内矛盾等を糊塗するための手段となり、「外的エネルギー」としての対外侵略や「内的エネルギー」としての国内少数民族の排斥などのツールとして用いられることがある。
中国独自の社会主義の発展形態と位置づけられる「中華民族の偉大な復興」の核となる中国の「国家ナショナリズム」が中国国内でどのように作用し、また、対外的にどのような形で影響を与えているのか、「中国の少数民族問題」と「中国の海洋進出」の観点から、若干考察したい。
中国の少数民族問題
⑴ 中国の多民族性は侵略の歴史的痕跡~「万里の長城」は何処にある?
中国の少数民族は、ウイグル族、チベット族、モンゴル族など公称55族とされ、ロシアに匹敵する多民族国家とされている。中国の人口(2010年国家統計局データ)は、総人口13億4千万人のう
ち漢族が十二億二千六百万人(91.51%)、少数民族は一億一千三百万人(8.49%)で圧倒的な漢族社会である。
地理的には、漢族が沿海東部から中央部にかけて居住し、少数民族の居住区域は、中国の東北部・北部・西部・南西部・南部の辺境地域に偏在しているが、この少数民族の存在は、歴史的に見て歴代中国王朝の他民族が依拠していた周辺域への侵略・支配の痕跡といってもよい。
下図は、漢民族王朝・明時代(1368~1644)の「万里の長城」位置図(━橙色:━茶色は前漢時代)である。
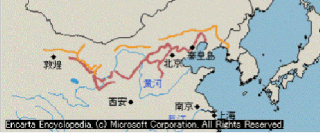
これら長城は北の異民族の侵略に備えるため明時代の北辺国境に構築されていったものであるが、その後の清王朝時代の中国周辺域への侵略による版図の拡大(明王朝の版図の3倍)により、明時代に北辺国境を示していた「万里の長城」は、現在、中国の北辺国境からほど遠い中国中央部に位置していて、中国の侵略国家としての歴史を証明する「世界遺産」となっている。
⑵ 中国における少数民族の処遇~「共産主義」と「民族主義」の不可融合性
マルクス・エンゲルスの「共産党宣言」中の有名なフレーズである「プロレタリアートに祖国はない」に集約されるように、「民族」は共産主義の階級史観において歴史的発展の中で消滅されるものとして規定されている。
中国共産党の「民族」観も同様で、1957年9月「第8期三中全体会」での鄧小平の「整風運動に関する報告」で、少数民族による「民族主義」をブルジョア主義と規定し、プロレタリアートの利害と根本的に相容れないものとして、とりわけ少数民族における社会主義教育と反右派闘争においては、「民族主義」の傾向に反対することを重視すべきと強調した。
⑶ 「国家ナショナリズム」と融合した「中華民族多元一体構造」概念の欺瞞
中国の「少数民族問題」とは、「民族主義」の否定と少数民族の「漢化(漢民族への同化)」に帰結し、「漢民族」を主体にした「国家ナショナリズム」の「排他性」や「偏狭性」に支えられて強権的に進められている。
1988年11月、中国の社会学者・費孝通が「中華民族多元一体構造」概念を発表した。
この「中華民族多元一体構造」概念の骨子は、次の三点に集約される。(※は、筆者の説明文)
1 多元主義の視点から中国における各民族(基層)を中華民族(上層部)なる概念に包摂することにより、 各民族は互いが離れることのできないもう一つの「アイデンティティ」を有している。
※ これがために、各少数民族が本来有する分離・独立などの「民族自決権」は、中華民族の一体構造により否定され、「民族自決権」を根拠とする少数民族の活動は、反国家・反共産主義の「国内的」な騒乱・テロとして捉えられることになる。
2 各民族が分散した多元状況は一体化されなければならず、その一体化の凝縮の過程で中核となるのは「漢民族」である。
※ 「中国共産革命」の主体的勢力であった「漢民族」の先進性・優位性の下に、民族の多元状況の一体化を進めることとなり、具体的には、これら少数民族の「漢化」施策として推進される。
3 高いレベルと低いレベルのアイデンティティは排斥し合うものでなく併存両立できる。
※ 高いレベルのアイデンティティ(漢民族)と低いレベルのアイデンティティ(各少数民族)は互いに排斥し合うものでなく、相対立する内部矛盾はその弁証法的発展の中で高レベルのアイデンティティ(漢民族)へと止揚されていくこととなる(「漢化」の達成)。
ここで言う「中華民族」という概念は、古来から語り継がれた歴史的な用語ではない。おおよそ百年前の清朝末期に、清王朝に対する諸外国からの干渉に反撥する「ナショナリズム」の覚醒に合わせ、当時のジャーナリストや政治家が使用した「ナショナリスティック」な「政治的用語」を起源としており、その概念は定まったものではない。
そのような経緯の中で、費孝通の「中華民族多元一体構造」概念は、中国共産革命以来、各地の少数民族統治に難渋していた中国共産党指導部に、その少数民族の統合に向けた理論的背景として提示されたものと言ってよい。
この概念は、「国家ナショナリズム」を背景とした「少数民族統合」という政治的意図の下に、費孝通の社会科学者として蓄積してきた知見を外見上もっともらしい推論で展開し結論的に「少数民族」の「漢化」へと辿り着くという「sophism(詭弁)」で糊塗された欺瞞性に満ちたものであるが、中国共産党指導部にとって、少数民族対策のツールとしての操作性や利便性から重宝され、今や少数民族政策の欠くことのできない基本理論とされている。
⑷ 中国における「漢化」ターゲット~新疆ウイグル・チベット・内モンゴル自治区
新疆ウイグル・チベット・内モンゴルの各自治区は、とりわけ中国政府の「漢化」政策のターゲットとなっている。
この三地域は、1911年の辛亥革命後の混乱期に、清朝支配を脱し独立回帰を図ったが、外モンゴルを除いて独立を果たすことができなかった。
これら地域に居住する新疆ウイグル族、チベット族、モンゴル族の各少数民族は清朝支配下においても、「漢化」の進む他の少数民族と異なり、それぞれ固有の地域を拠点としてイスラム教やチベット仏教を中核にした民族の団結と地域の独立性を希求していた。
中国政府としては、このような歴史的経緯に加え、この地域の重要性(三地域で中国国土の60%超を占め、ロシア・インド・中央アジアに接し中国の安全保障上重要。また、石炭・レアメタル等鉱物資源が豊富)から、三地域への「漢化」施策(「漢語教育」の必修化、「漢族」の大量移住と同化の促進など)の徹底と、これら地域における武装警察部隊による分離独立運動の弾圧や新疆ウイグル族活動家の「国家分裂罪」での訴追などを推し進めているが、「天安門突入事件(2013年)」や「チベット僧侶等の焼身自殺(2011年~)」など新疆ウイグル族、チベット族等少数民族の激しい抵抗を受けている。
2015年7月1日制定された新しい「国家安全法」では、同法第26条で「民族交融(漢化)」の強化とともに、上記のような抵抗運動を「民族分裂活動」と規定し懲罰対象とした。
とりわけ、強権的なチベット統治をさらに推し進めるため、中共中央は2015年8月「西蔵(チベット)工作会議」を北京で開催し、習主席は同会議で新しい「治蔵方略(チベット政策)」を指示した。
その中で、チベットにおける中国共産党の領導・社会主義制度・民族区域自治制度の絶対堅持と「国家安全法」に依拠したチベット統治を指示するとともに、「ダライ・ラマ集団」に対する揺るぎない闘争方針・政策の堅持を明示した。
このような強権的な少数民族弾圧政策は各少数民族の頑強な抵抗を受け続けており、これをテロと見做す中共中央の方針は、これら自治地域の共産党幹部にも動揺を与えている。
2015年11月24日、新疆ウイグル自治区の中国共産党規律検査委員会書記 徐海栄(Xu Hairong)は、公設ウェブ「中国共産党規律検査委員会便り」における報告で「一部の共産党幹部がテロリストを支援するだけでなくて、そのテロ攻撃にも参加している」旨述べ、その強硬な弾圧政策に対する地方共産党組織の内部対立が存在していることを明らかにした。
このような内部矛盾を抱えながら、習近平政権はさらなるテロ対策の強化(通信・ネット事業者の捜査協力義務、報道管制等)を目論み、2015年12月27日「全人代」常務委員会で「中華人民共和国反テロリズム法」を可決し、とりわけ中共中央の統制強化に激しく反発している新疆ウイグル自治区の少数民族ウイグルへの締め付けを強めている。
⑸ 中国の分裂を恐れる中国共産党
中国共産党機関紙「人民日報」のウェブサイト「人民網」(2014年9月24日版)は、その「理論」欄で、中国共産党理論誌「求是」系の「紅旗文稿」誌に寄稿した李満長・駐セルビア共和国大使の論文「西側諸国が進める多党制の本質は何か」を全文掲載した。
同論文は、西側諸国のとる多党制がアフリカや旧ユーゴに混乱をもたらしたとして、多党制の本質的欠陥を取り上げ批判した。
さらに論文は、多民族国家であった旧ユーゴ分裂での具体的数字から比例して、西側の多党制を中国で行った(中国共産党の一党独裁が崩壊する)場合、国内での武力衝突の勃発による一千万人を超える死者や一億人を超える難民の発生が危惧され、五千年の歴史を有する中国が三〇余の小国に分立する可能性も指摘した。
この論文は、中国国民の「中国共産党」一党独裁への不満の鬱積という現状認識を含意しつつ、西側世界の混乱を生み出す多党制の政体よりも、社会主義中国の方が「よりましな政体」であるとして、中国共産党の統治の優越性を強調したが、図らずも、いわゆる「中華民族」なるものが費孝通が主張した「各民族は互いが離れることのできない」一体構造ではない現実をも露呈し、その「内訌(内輪もめ、内戦等)」による中国の分裂の可能性を公に肯定した。
中国の「海洋進出」
⑴ 中国の「海防思想」の転換~膨張する「国家ナショナリズム」
近時、南シナ海・東シナ海等における中国の「海洋進出」は、周辺諸国との軋轢を無視して強引に進められている。
このような「海洋進出」の背景には、清朝末期に海上から進出してきた諸外国の侵略に敗北し、不平等条約による領土割譲、賠償金支払い等恥辱を受けたという歴史的な「トローマ(心的外傷)」があり、このような国辱を招来したのが、「鄭和艦隊」以後の明・清朝の海禁政策による脆弱な海防体制に起因しているという思いがある。
以下、毛沢東以後の中国の「海防思想」の変遷を敷衍してみるが、その底流に流れているインセンティブは「愛国主義運動」や「中華民族の偉大な復興」に象徴される「国家ナショナリズム」への固執であり、その「海洋進出」はまさしく「ナショナリズム」固有の「排他性」と「偏狭性」をもって際限なく繰り広げられていると言っても過言でない。
1949年中国共産革命により権力を掌握した毛沢東は、帝国主義の海上からの侵略という歴史的教訓から、中国の長大な海岸線における「海の長城」構築(沿岸防衛)の必要性を説き、以後中国海軍は「沿岸防御」という防御戦略の下に建設されていった。
このような「沿岸防御」戦略は、1978年の鄧小平「改革開放」以後の中国経済の発展に伴い、中国沿海東部に偏在する中国経済の中枢部都市群の防衛や中国経済を支える石油資源等の海上交通要路の確保、加えて、1982年に「国連海洋法会議」で採択された「海洋法に関する国際連合条約」による中国の「排他的経済水域(EEZ)」での海洋管理の重要性などを受けて、鄧小平の信任の厚い劉華清・海軍司令員が策定した「海洋進出」を図る「近海防御」戦略へと発展していった。
この「近海防御」概念は、1986年1月海軍党委員会拡大会議で劉華清・海軍司令員から提示され、台湾武力統一に加えて自国防衛及び天然資源確保のために、中国海軍が想定する主な作戦地域は「第一列島線とその外側の海域で、黄海、東シナ海、南シナ海」であることが明らかにされた(「中国安全保障レポート2011」から引用)。
1992年2月に、台湾、尖閣諸島、澎湖列島、東沙諸島、西沙諸島、中沙諸島、南沙諸島等を中国領土とした「中華人民共和国領海及び接続海域法(以下「領海法」)が公布され、同年10月に開催された第14回党大会・江沢民主席政治報告で、「領海法」に定めた「領土・領海・領空の主権」と「海洋権益」の防衛が中国海軍の新たな任務として宣明された。
2004年9月に党中央軍事委員会主席に就任した胡錦濤は中央軍事委員会の組織改編を行い、海軍・空軍・第二砲兵部隊(戦略ミサイル部隊)の各司令員を新たにメンバーとして加え「海洋進出」を重視した海軍・空軍・戦略ミサイル部隊の統合運用態勢を確立した。
「2004年中国的国防(中国国防白書)」は、このような改革を「中国の特色ある軍事変革」として積極的に推進すると説明した。
「2004年中国国防白書」に規定された「軍事変革方針」における「海軍、空軍、第2砲兵の建設を強化」の冒頭部分(人民解放軍の任務)の「制海権、制空権奪取と戦略的反撃の能力を高める。」とは、具体的には中国軍事力の「海洋進出」を図っていくための
○ 海軍・空軍力の充実強化とアメリカの空母打撃群をターゲットとした対艦弾道ミサイル(ASBM)の配備による東シナ海・南シナ海の「制海権・制空権奪取」
○ 米本土を射程内にする大陸間弾道ミサイル(SLBM)搭載戦略ミサイル原子力潜水艦(SSBN)の太平洋深海への配備や超音速ミサイル(HGV)の開発などの「戦略的反撃能力を高める」
を意味する。
以下に、この「海軍、空軍、第2砲兵の建設を強化」方針の全文を掲載する。
※ 中華人民共和国国務院報道弁公室刊「2004年の中国の国防」(日本語版)から引用:田治一基氏による中国語原本との照合済み
海軍、空軍、第2砲兵の建設を強化
人民解放軍は陸軍の建設を引き続き重視すると同時に、海軍、空軍、第2砲兵の建設を強化し、作戦力構造の協調的発展をはかり、制海権、制空権奪取と戦略的反撃の能力を高める。
海軍は国の海上の安全を守り、領海の主権と海洋の権益を保全する任務を担っている。海軍は近海の防御作戦空間と防御の深度を拡大し、海上戦場の建設を強化、整備し、近海で海上戦役を行う総合的作戦能力と核反撃能力を増強する。精鋭で役に立つ原則にしたがって、指導と指揮の段階を減らし、各種の作戦力を科学的に編制し、海上作戦兵力特に水陸両面作戦兵力の建設を突出させている。海軍の兵器・装備の更新を加速し、新型作戦艦艇および多種の専用機と附属装備を重点的に発展させ、兵器・装備の情報化レベルと長距離精確攻撃能力を高める。各軍・兵種の共同演習と訓練に参加し、共同作戦能力と海上総合保障能力を高める。
空軍は、国の領空の安全を守り、全国の防空の安定を保っている。空軍は情報化空中作戦の要求に適応し、国土防空型から攻撃・防衛一体化型への転換をちくじ実現している。新型戦闘機、防空・対ミサイル兵器、情報作戦手段、空軍指揮自動化システムを重点的に発展させ、情報化空中作戦に適応する複合型人材を育成し、多兵種と多機種の共同作戦訓練を強化し、空中打撃、防空作戦、情報対抗、警戒偵察、戦略機動、総合保障の能力を高め、総体的規模が適度で、編制構造が合理的で、兵器・装備が先進的で、システムを集成し、情報支援と作戦手段が完備する空中防衛作戦力の建設に努める。
第2砲兵は国の安全を防衛する重要な戦略的力であり、主に中国に対する敵の核兵器使用を制止し、核反撃と常規ミサイルによる精確打撃の任務を遂行する。第2砲兵はミサイル兵器の改良と開発の強化を通じて、ミサイル兵器および指揮、通信、偵察などの附属装備の情報化レベルを高め、核兵器と常規兵器を同時に保有し、威力と効果が明らかに大きくなった各種射程の兵器・装備システムを初歩的に形成している。工程院アカデミー会員とミサイル専門家を中堅とする人材陣を確立し、70%以上の将校は大学本科以上の学歴を持っている。ハイテクの手段を運用して訓練を改革し、新型兵器・装備が戦力を形成する周期を短縮している。作戦の実際に応じて、ミサイルの発射訓練および実戦条件に近い戦備の演習と訓練を行って、部隊の快速反応と精確打撃の能力がたえず向上している。
上記の「海軍、空軍、第2砲兵の建設を強化」方針は、以後の中国の「海洋進出」を希求していく国防と軍建設の基軸となっていると言ってよく、このような流れのもと、2014年11月に開催された「中央軍事委員会改革工作会議」で、対外からの侵略を想定した国土防御を目的とする従来の「軍管区制」から、「海洋進出」など対外戦略を見据え海軍、空軍、ロケット軍(第2砲兵)を主体にした統合運用を図る「戦略区制(5つの戦区で構成)」への転換を内容とする「軍制改革方案」を決定した。
この流れを受けて、党中央軍事委員会は2016年2月、東部・西部・南部・北部・中部の五つの戦区を発足させ、南シナ海を統括する「南部戦区」には海軍出身の司令官を就かせる(2017年1月)など、周辺海域での中国海軍のプレゼンスを強化し、域内海域の海洋支配を図ろうとしている。
⑵ 甦る「鄭和」の影 ~ 「海洋進出」の隠れ蓑
2012年11月に開催された中国共産党「第18回党大会」において、習近平総書記は大会報告「外交・安全保障に関わる政策方針」の中で「海洋強国建設」を表明し、党中央が海洋問題(「海洋進出」)を重視していることを示した。
中国は、明朝期の「鄭和の大航海」を引用して、中国大陸周辺の海域(黄海・東シナ海・南シナ海)は伝統的に中国歴代王朝が支配していた「中華世界」に属する「中国の海」であり、これら海域及びそれらの島嶼が清朝末期に欧米列強や日本により奪われたもので、その後の覇権主義国・アメリカによる海洋秩序を認めないとしている。
このような主張は、国内の貧富の格差や少数民族問題などの諸矛盾に対する中国国民の不満のエネルギーを「勿忘国恥(国の受けた恥辱を忘れるな)」をスローガンとした「国家ナショナリズム」の高揚に転化する有効な手段として「海洋進出」を図っていくもので、江沢民以来の中国共産党歴代指導部により踏襲されている。
しかし、東シナ海・南シナ海に位置する周辺諸国は中国の一方的な「懐古主義」的主張に強硬に反発し、中国の海洋進出(膨張する「国家ナショナリズム」)に対し警戒心を強めている。
中国の海洋における軍事的台頭を受けて東南アジア諸国では潜水艦を主体とした海軍力の増強の動きが見られる(THE DIPLOMAT:Southeast
Asian State Deploy Conventional Submarines january.03.2014から引用)。
ベトナム
2013年12月31日 ロシア製ヴァルシャヴャンカ級潜水艦の引き渡しを受け、2016年までに同級潜水艦6隻体制を構築。
インド政府が、これら潜水艦要員のインド海軍潜水艦要員訓練センターでの訓練を引き受けると発表
インドネシア
現在のウィスキー級潜水艦2隻体制を2020年までに12隻までに増強し、戦略的要衡(チョーク・ポイント)や島嶼間の狭隘な水路の確保に当たる。さらに、超音速巡航ミサイル搭載可能なロシア製キロ級潜水艦の購入や既存の港湾施設が利用可能な韓国製潜水艦の購入を企図。
シンガポール
2013年11月末に新型のドイツ製タイプ218SG通常型潜水艦2隻とドイツ国内でのメインテナンスと訓練を含めた契約に署名。218SG潜水艦2隻は2020年までに配備予定で改修したアーチャー級潜水艦(スエーデン製)2隻と隊伍を組む。
ミャンマー
2013年6月、2隻のキロ級潜水艦の購入についてロシア当局と協議。
タイ
タイ海軍の次期調達計画(10年)に3隻の潜水艦購入を含める。チョン・ブリの海軍基地に潜水艦訓練センター関係施設を建設。
中国は、これら周辺諸国の警戒心を懐柔するために、様々なチャンネルを通じて、明朝期の「鄭和の大航海」を引き合いに出し、鄭和が示した友好と生産技術の伝授等文化の伝播は中国の歴史的伝統であり、中国は有益で脅威とならない強国だと喧伝している。
しかし、その鄭和の艦隊(armada)の実態は、友好的にはほど遠い"wide-bellied ships by the hundred,rigged
fore and aft,soldiers massed at their bulwarks.Strange warlike banners
snapped from the topgallants.( 帆を満帆に張って、甲板の両舷側に多数の兵士を蝟集させ、三番マストに異様な軍旗をたなびかせた数百隻の軍艦)"で、その狙いは"Wonder
attended its sails,followed by capitulation and obeisance(その艦隊の勢威によって驚愕させ、降伏と服従を求める)〔CHARLES
C. MANN:1493~UNCOVERING THE NEW WORLD COLUMBUS CREATED〕"ものであった。
そして、艦隊の遠征司令官の鄭和についても、明朝期に紅毛碧眼のムスリム少年であった鄭和が雲南を拠点とするムスリムに対する漢族の侵攻により捕らえられ、少数民族ムスリムの根絶を目的とした断種・去勢を施され宦官に貶められたという史実に籠められた中国の少数民族への弾圧の歴史については一切触れられていない。
