「アラブの春」とは
「アラブの春」は、2010年末のチュニジアの「ジャスミン革命」に端を発した北アフリカ、中東諸国のアラブ世界で起きた長期独裁政権打倒などの若者たちによる体制変革運動を言う。
この運動は、エジプト、イエメン、リビアにおける独裁体制の打倒に大きな役割を果たしたほか、アルジェリア、モロッコ、シリア、サウジアラビア、ヨルダン、クウェートなどでの一連の改革要求の波につながっていった。
また、シリアのアサド政権の独裁体制に立ち向かう武装闘争の中で台頭してきた、極端なイスラム原理主義を唱える「ISIS(イラク・シリア・イスラム国)」は、イラク・シリア・リビアの国境を越えた武装闘争を活発に展開しており、アラブ世界の混迷の様相を深めている。
「アラブの春の真実」~イスラム化の波
しかし,この「アラブの春」の状況を見ると、アラブ世界における若者たちの体制変革の動きには、「プラハの春」に代表される中東欧社会の民主化に見られた「自由と民主化」を要求し、「民主主義体制」を確立する運動との決定的な位相差があることに気づく。
今次「アラブの春」の動きの中で、閉塞した社会情勢への不満を契機に、長期独裁政権の打倒により新しい政体を求めたチュニジア・リビア・エジプトの各国での
チュニジア:2011年10月制憲議会選挙でイスラム政党・アンナハダ90議席を獲得し第1党に躍進
リビア:2012年国民議会選挙でムスリム同胞団系の公正建設党が投票獲得数で第2党となり17議席を獲得
エジプト:2012年6月大統領選挙でムスリム同胞団系のムルシー大統領が当選
という事象に示されたとおり、これらの国々の多数のムスリム(イスラム信徒)が求めようとしたのは、キリスト教圏で編み出された「民主主義体制」という政体ではなく、イスラム教圏で普遍的に信奉されている「ムハンマドのウンマ(イスラム共同体)」なのである。
この「イスラム共同体」は宗教共同体であるとともに社会的組織でもあり、共同体におけるイスラム教の最高指導者は必然的に政治的支配者となる(イスラム法学者の統治)。
その最高指導者は「シャリーア(イスラム法典)」により「イスラム共同体」を紀律し、ムスリムとその社会にとって,日常生活から国家の政治に至るまで,「イスラム法典」に示される神の意志が絶対のものとされている。
「イスラム法典」も、19世紀に欧州からアラブ世界に近世法体系が伝播するにつれ、アラブ各国の憲法にいろいろな形で規定されたが、戒律の厳しい国(イラン・サウジアラビアなど)から戒律を私的生活に限定する緩やかな国(トルコなど)まで態様はさまざまである。
現代アラブ世界では、「イスラム法典」に基づく国家・社会への回帰を求める「イスラム原理主義運動(イスラム復興運動)」が一つの大きな流れになっている。
このようなイスラムの思潮の中で起きた「アラブの春」において、ムハンマド(マホメット)の末裔達が究極的に「イスラム共同体」を目指していこうとするのは、当然といえば当然である。
ただ、この「アラブの春」がアラーの啓示を受けた宗教闘争でないことは万人の認めるところであり、アラブの世界に吹き荒れた砂嵐が奈辺に行くか、まだまだ予断を許さない状況が引き続いている。
欧米の論調の中には、この動きを「民主主義の後退」や「民主的制度が未成熟」などとして「アラブの春は失敗」だと声高に主張する向きもある。
これら主張は、西欧文明の先進性・優位性を背景とする「普遍主義(universalism)」を論拠としているが、このようなキリスト教圏文明の価値観を先進的かつ絶対優位としてイスラム教圏文明の価値観を揶揄(やゆ)する姿勢は、異教徒文明を断固拒絶する「イスラム共同体」の先鋭化にもつながり、ムスリムの反発と軋轢(あつれき)を生む以外に何も得るものはないだろう。
サミュエル. P.ハンチントンはその著書「文明の衝突(The Clash of Civilizations and the Remaking
of World Order)」で、世界を睥睨した「西側世界(The West)」の勝利について、「優れた理想や価値観、宗教によってではなく、どちらかと言えば組織だった暴力の行使における優位性によるものだ。西欧の人々はしばしばこの事実を忘れるが、非西欧の人々は決して忘れることはない。(The
West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion
but rather by its superiority in applying organized violence.Westerners
often forget this fact;non-Westerners never do.)」と喝破している。
「アラブの春」の真実~人口学からのアプローチ
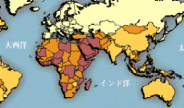
しかし、それにしてもなぜ「アラブの春」がこの時期に起こり、そして「アラブの春」の波が同時多発的にアラブ世界に波及したのだろうか?
そのような背景を説明する基礎資料として、図「世界の人口増加率」を参照して欲しい。 図に示された国々のうち褐色(■)は人口増加率が2.0から2.9%で、茶色(■)は人口増加率が3.0%以上を示している。
人口増加率が高いのはアフリカおよび中東地域の国々であり、とりわけアラブ世界(中東および北アフリカ)の人口は2020年代には世界の4分の1になると予測されている。
そして、この様な人口増加は、人口統計上「youth bulge(膨張した若年層=30歳未満)」の顕在化として発現する。
英・guardian紙(14.February.2011)掲載の「Arab youth:the tipping point」記事中の統計データによれば、アラブ主要各国の総人口に占める「youth
bulge」の割合は、チュニジア50%、エジプト61%、リビア60%、イエメン72%、シリア66%、アルジェリア57%、モロッコ56%、ヨルダン64%、サウジアラビア61%と今次「アラブの春」の波を受けた国々の全てが異常な「youth
bulge」状態を示している。
さらに、きわめて重要なことであるが、これらアラブ主要国の「youth bulge」の中の就労適齢期の若者たち(15~24歳)の失業率の数値を見ると、チュニジア27.3%、エジプト21.7%、リビア27.4%、イエメン18.7%、シリア16.5%、アルジェリア45.6%、モロッコ21.9%、ヨルダン27.0%、サウジアラビア16.3%と高い数値を示している。
この「guardian」紙の統計データから見えてくるのは、アラブ各国においてその総人口の過半以上を占める若年層に失業者が溢れているということだ。
思うに、「アラブの春」は、2010年12月にチュニジア中部の都市シディブジドの市場の路上で果物と野菜を売っていた青年モハメッド・ブウアジジ(26歳)が当局の不当な取り扱いに抗議して「貧困を終わらせろ、失業を終わらせろ!」と叫びながら焼身自殺した事件を発端としているが、この青年は大学卒業後職を得られず、その後、職を得られない同世代の若者たちと同じく市場の路上で果物と野菜を売りながらかろうじて生活を維持していた。
この青年ブウアジジこそ苦悩するアラブ世界の「youth bulge」の象徴なのだ。
「アラブの春」が青年ブウアジジの叫びから始まり、その波が同時多発的にアラブ世界に波及したのは当然の帰結であったと言える。
「アラブの春」~「自爆する若者たち」
このような「youth bulge」の現象に着目したのが、「アラブの春」から七年前の2003年にドイツ語で出版されたグナル・ハインゾーン著「Sohne
undo Weltmacht:Terror im Aufstieg undFall der Nationen(帝国とその息子たちー列国の興廃におけるテロ:直訳)」であった。
ハインゾーンはその著書で、世界の各地で勃発しているテロ、内戦、ジェノサイドなどはイデオロギー・宗教・民族問題に由来するものでなく、その要因は人口の爆発的増加にあるとし、人口爆発によって生じる若者たちの閉塞した状況(「youth
bulge」)に国家が対処しきれなくなったとき、暴力(テロ・ジェノサイド・内戦など)となって現れるとした。
英国「the guardian」紙のweb site(30.October.2014)は、同紙が入手した国連安保理報告を引用して、「ISIS(イラク・シリア・イスラム国)」の台頭により政情が不安定なシリアとイラクにアラブ世界の多数の若者たちが戦闘員として流入しているほか、80ヵ国以上の国々からイスラム改宗者約15,000人が「ISIS」側になって戦うために入国した旨報じているが、その後のアラブ世界の混乱を見ると、ハインゾーンの指摘にある部分首肯せざるを得ないところである。
「youth bulge」を生む人口の爆発的増加は、アフガニスタンを例にとれば、2012年統計の男女の平均寿命(男47歳、女50歳)や2010年統計の新生児・乳児死亡率(148%)という信じられない抑制因子があるにもかかわらず、2005~2010年合計特殊出生比率(一人の女性が15~49歳の間に産む子供の数)係数は6.63と高い数値を示し、最近の概ね十年をグラフ化すると、2002年2千万人弱の人口が2013年現在3千万弱とほぼ40度の右肩上がりで急増している。
このような状況は、合計特殊出生率係数が落ち着くと見られる2020年までは続くと言われている。
ハインゾーンは2008年の「日本語版(『自爆する若者たち』)に寄せて」の中で、この「youth bulge」に残された道としての六つのオプション(・国外への移住 ・犯罪に走る ・クーデターを起こす ・内戦または革命を起こす ・集団殺害等で少数派のポストを奪う ・越境戦争で植民地を獲得する)ならびに六つのオプションに関わる国々を示す三つのリスト(「各国の『軍備人口』状況」、「1950~2050年に係数9~26で増加する人口50万以上の国々」、「アフガニスタン、イラク、チュニジアの人口」)を掲載し、近い将来における世界の混乱を警告していた。
「自爆する若者たち」でハインゾーンが、スタディー・ケースとして挙げているのが、アフガニスタンである。アフガニスタンは「軍備人口(40~44歳の男性1,000人に対する0~4歳の男子の割合)」から言えば、世界第6位の大国(1,000人<4,040人)で、2020年までに戦闘年齢に達する少年が毎年50万人動員できるとしている。そのような若者たちが六つのオプションのいずれかの行動をとるのは現実的な選択肢の一つとなるとし、このアフガニスタンの潜在的な戦闘能力を極めて危険視している。
ただ、ハインゾーンが「自爆する若者たち」で主張する見解は、有史以来の帝国の興廃や戦争などが全て「youth bulge」に起因するという牽強付会の論理やリスト「1950~2050年に係数9~26で増加する人口50万以上の国々」の中での精度の低い統計数値の取り扱い(ある程度のレンジでは許容される「人口モメンタム」の範囲を超えた2050年という将来について予測不能な「合計特殊出生率」により数値計算している。)などから、そのクレデビリティー係数は高いとは言い難い。
この「自爆する若者たち」はマルサスの「人口論」の流れを汲むup-to-date版に類するもので新しい理論の展開ではないが、読者の耳目を引きつけようとする軽佻浮薄な邦題の「自爆する若者たち―人口学が警告する驚愕の未来」とは若干ニュアンスの異なる原題「帝国とその息子たち―列国の興廃におけるテロ(直訳)」の趣旨を踏まえながら紐解けば、「アラブの春」の展開を理解する一助にもなるだろう。
「アラブの春」の徒花~「ISIS(イラク・シリア・イスラム国=イスラム国)」の行方
英国「the guardian」紙のweb site(30.October.2014)が報じるとおり、「ISIS(イラク・シリア・イスラム国=イスラム国)」の台頭により政情が不安定なシリアとイラクにアラブ各地域や欧米の若者たち15,000人が、サイクス・ピコ体制(1916年、英仏露による「大シリア」分割秘密協定による国境画定)およびその後のアメリカナイズされたアラブ世界秩序の打倒を掲げる「ISIS」側になって戦うために入国した旨報じているが、彼ら若きムスリム達の大義も宗教的狂信(religious
fanaticism)に基づいて異教徒・裏切り者(シーア派など)の大量処刑を図る「ISIS(イラク・シリア・イスラム国=イスラム国)」という国家的規模の暴力装置の中に組み込まれてしまった。
「大シリア」国としての国家的擬制をもくろむ「ISIS(イラク・シリア・イスラム国=イスラム国)」であるが、占拠した地域の油田地帯の多くを掌中にしたものの、生産資源や人的資源等国家として成り立つための基本的要素が欠漏したその存在は何れ砂漠の蜃気楼として跡形もなくなるのは必定と言える。
ただ、「ISIS(イラク・シリア・イスラム国=イスラム国)」が「アラブの春」の徒花として消え去っても、「ISIS(イラク・シリア・イスラム国=イスラム国)」も掲げたサイクス・ピコ体制およびその後のアメリカナイズされたアラブ世界秩序を認めないという「アラブの大義」が消え去ることはなく、その旗の下に参集する若きムスリムたちが途絶えることもない。「クルディスタン国」独立問題も絡めて、アラブの砂嵐の行方は定まらない。
